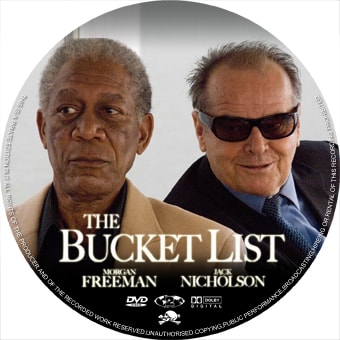先日このブログで『ジャンパー』を取りあげて「あんまり出来の良い映画とは云えない」ってなことを書きました。
しかし昨日、大学生の次男坊と話しているうちに、少し印象が変わりました。
せがれは実は映画のほうは未見ですが、原作となった小説の方を日本語訳で読んでいて、「面白かったから続編も買って読んだ」というのです。奴さんは小さい頃から読書が好きで、今も同年代の学生の中では比較的熱心に本を読む方です。作品の善し悪しを判断する目は信頼して良いでしょう。ですから映画を観てイマイチだったという私の感想と食い違うのが意外でした。
「あれだけの能力を泥棒に使って、稼いだ金はガールフレンドにええ恰好するために無駄遣いするような奴の話が面白かったってえの?」
「テロリストを捕まえて海上に放置したりとか、ヒーローみたいなこともするでしょ」
「ええっ? 映画ではそんなシーン無かったぞ」
「テレポートの能力がないと入れない炭坑の奥みたいなところに基地をつくったりして、結構頭良いじゃん」
「いや、映画ではかなりのヘタレにしか見えなかった」
話してみればみるほど、彼の持っている物語観と、私の映画観には大きなギャップがありました。
無論、私の生半可な英語力ですから、映画の持っているメッセージ性を読み違えている可能性は捨て切れませんが、息子の話を総合してみると、どうやら映画の方に問題があることが分って来ました。
エンディングで暗示されているように、この映画は最初から続編ありきでつくられていて、物語の進行が大胆に改編されているのです。ですからわざと1話完結の流れにはされていないため、私のように小説版の原作を知らない目には、とんだ駄作映画に見えてしまうらしい。
次男坊と話す事で、物語としての『ジャンパー』には少し興味が湧いて来ました。奴から借りて来て読んでみようと思います。
そんな訳でこの作品に関しては少しだけ印象が変わりました。
ただし、1本の完結した映画という見地から観た場合、必ずしも成功しているとは思えない演出であることには変わりありませんが…。
しかし昨日、大学生の次男坊と話しているうちに、少し印象が変わりました。

せがれは実は映画のほうは未見ですが、原作となった小説の方を日本語訳で読んでいて、「面白かったから続編も買って読んだ」というのです。奴さんは小さい頃から読書が好きで、今も同年代の学生の中では比較的熱心に本を読む方です。作品の善し悪しを判断する目は信頼して良いでしょう。ですから映画を観てイマイチだったという私の感想と食い違うのが意外でした。
「あれだけの能力を泥棒に使って、稼いだ金はガールフレンドにええ恰好するために無駄遣いするような奴の話が面白かったってえの?」
「テロリストを捕まえて海上に放置したりとか、ヒーローみたいなこともするでしょ」
「ええっ? 映画ではそんなシーン無かったぞ」
「テレポートの能力がないと入れない炭坑の奥みたいなところに基地をつくったりして、結構頭良いじゃん」
「いや、映画ではかなりのヘタレにしか見えなかった」
話してみればみるほど、彼の持っている物語観と、私の映画観には大きなギャップがありました。
無論、私の生半可な英語力ですから、映画の持っているメッセージ性を読み違えている可能性は捨て切れませんが、息子の話を総合してみると、どうやら映画の方に問題があることが分って来ました。
エンディングで暗示されているように、この映画は最初から続編ありきでつくられていて、物語の進行が大胆に改編されているのです。ですからわざと1話完結の流れにはされていないため、私のように小説版の原作を知らない目には、とんだ駄作映画に見えてしまうらしい。

次男坊と話す事で、物語としての『ジャンパー』には少し興味が湧いて来ました。奴から借りて来て読んでみようと思います。
そんな訳でこの作品に関しては少しだけ印象が変わりました。
ただし、1本の完結した映画という見地から観た場合、必ずしも成功しているとは思えない演出であることには変わりありませんが…。