今年最後の追加クエストもどき。クリスマスネタなのに当日に間に合わず残念。文中のキャンディは実際は女の子の親が入れた物ですが自分だと敢えて言うサンタや女主たちの優しい嘘も含むタイトル。
クリスマスの朝。ミミが枕元に下げていた白いふわふわ飾りつき赤い靴下の中には、プラチナ鉱石を使って一から作った、繊細なデザインの腕輪が入っていた。踊りの時に上腕に着けるタイプのものだ。
奇しくもミミの方は、ミスリル鉱石で作った格闘家向けの、頑丈だが洗練されたデザインのリストバンドをイザヤールに贈っていた。相談も無いのに互いに腕の装備物をクリスマスプレゼントに贈り合った偶然が何だかおかしくて、ちょっとだけ行儀悪く二人で一緒にシーツの中に戻ると、じゃれあうように抱き合いながら、声をひそめて笑った。
それからイザヤールは、冷たくないようにと自分の手に包んで腕輪を温めてから、ミミのむき出しの二の腕にそれを着けてくれた。白く滑らかな肌の上に、月のように光る銀色が映えて、なんとも美しく艶かしい。彼女によく似合うのを見て、満足そうに目を細めた彼は、その装飾品の近くの肩口に、あたたかな唇をそっと当てた。
ミミはそんな彼の頭を胸元にきゅうと引き寄せて抱きしめて、頬を薔薇色に染めて囁いた。
「イザヤールサンタさんも、もらっていいの?」
イザヤールは抱かれている極上の感触に陶酔しつつも、自らもしっかりミミを腕に抱えて引き寄せて、いたずらっぽい笑みを口元に浮かべて返答した。
「もちろん。・・・私はこの可愛いサンタガールをもらうからな、おあいこだ」
こうして朝っぱらから二人にとって申し分ない甘さのクリスマスが始まった。為すべきことも全て済ませてあるので、今日はのんびり過ごせる筈だった・・・が、しかし。のんびりという訳にはいかないことが起こってしまうのが、この二人の常である。その予感もあってか、いつもよりちょっとだけ長く、二人は自室でぐずぐずしていたのであった。
クリスマスの午前中。セントシュタイン城下町の教会では、厳かな聖なる日の為の礼拝が行われていた。オルガンの音と神の恵みへの感謝を歌った聖歌は、華やかに装飾された町にも流れて、盛大な宴会の賑わいの中にも、しみじみとした安息の気配を醸し出していた。
しかし、教会のすぐ近くの通りの一角の、子供たちの集まる場所は、そんな静粛なる雰囲気とは全く無縁だった。家族全員でじっとおとなしく座り「神父さまの長い退屈なお話」を聞く時間からようやく解放された彼らは、今朝方それぞれの家のクリスマスツリーの下や、枕元に吊るした靴下の中に入っていたサンタさんのプレゼントの話題に夢中になっていた。
「ボク、サンタさんから、カッコいい毛織りのマントをもらったんだ!青くてボクの名前が刺繍されてて、お話の中の勇者様が着ているのとそっくりなやつ!」
「あたしはオレンジリボンもらったんだ♪将来スーパースターになりたいからくださいって毎日お空に向かっていっしょーけんめいお願いしてたから!」
「アタシはラッキーペンダントよ♪もうさっそく着けてるの、キレイでしょ?」
「オレは十分の一スケールのガチャコッコを再現したニューモデルのおもちゃさあ!ぜんまいを巻くと、ちゃんと羽を動かして飛ぶんだぜ!」
などなど、サンタクロースからもらったプレゼントについて話したり見せたりして盛り上がっていたが、中で一人だけ、沈んだ顔をして黙っている女の子が居た。この子の家庭は、決して暮らしに困っているわけではなかったが、家族が多忙すぎて、子供のプレゼントにまで気を回す余裕がなく、クリスマスツリーや枕元に下げる靴下を用意することはなかった。
そんな訳で彼女は自分で小さな木の枝に手作りのクリスマス飾りをし、自分で靴下を枕元に下げた。そして今朝その靴下に入っていたのは、まるで誰かが急いで用意したかのような、いつのシーズンでもそこらへんで売っている、大きく派手な棒付きキャンディ一本だけだった。そのキャンディももちろん好きではあったし、だからサンタさんはこれをくれたんだと納得しようとしていたものの、友達のもらったプレゼントの話を聞いているうちに、羨ましいという気持ちが強くなって、だんだん表情が曇るのを抑えられなかった。
「で、おまえは何をもらったんだよ?」
一人だけ黙っていた彼女に、みんなが尋ねてきた。
「えっと・・・わたしは・・・」
女の子が口ごもっていると、子供たちの中で口の悪い男の子が、はやし立てるように言ってきた。
「あー!おまえさあ、悪い子だから、サンタさん来なかったんだろー!」
「ち、違うもん、ちゃんと来たもん・・・」
「じゃあ何をもらったんだよ?」
「そ、それは・・・」普段は好物の、もらって嬉しい棒付きキャンディ。でも、今は、それしか靴下に入ってなかったと、何だか言いたくなかった。それで、思わずこんなことが口をついた。「もらったもん!可愛いふかふかの、モーモンのぬいぐるみ!」
「へー」男の子をはじめ、みんなニヤニヤしていた。信じていない顔だ。「じゃあ見せろよ~、モーモンぬいぐるみ」
「い、今持ってないもん・・・」
「じゃあ家まで取りに行けよー」
みんな嘘だとわかっているのだ。ゴメンと謝ればそれで終わるだろう。でもそれが何だか悔しかった。
「み、見せられないの!す、すっごい盗賊に取られちゃったから!」
「へー。じゃあさ、取り返してもらえよー。ルイーダの酒場に居る冒険者に頼んでさー。行こうぜルイーダの酒場!」
「えっ、あ・・・その」
子供たちは、女の子を押すようにして、いっせいにルイーダの酒場が入っているリッカの宿屋へと向かった。
ミミとイザヤールがルイーダの酒場のカウンター席で遅めの朝食兼昼食を摂っていると、突然子供たちがどやどやとリッカの宿屋のロビーに入ってきて、酒場の女主人のルイーダに向かって口々に言った。
「ねーねー、冒険者紹介してー」
「この子が、サンタさんにもらったモーモンぬいぐるみを大ドロボーに取られちゃったのー」
「すっごいドロボーなんだってさー」
ルイーダはいささか戸惑っていたが、やがて事情がわかると、ほんの少し首を傾げて考えた。ぬいぐるみを盗られたという女の子が、暗い表情でうつむいているのが気になったのだ。プレゼントを盗られた小さな子供は、普通大泣きするかしょんぼりしているかで、こんな困ったような顔になるのは不自然だ。カウンター席で子供たちとルイーダのやり取りに耳を傾けていたミミとイザヤールも、その不自然さに気付いて小さく首を傾げた。
ルイーダは、城下町の商工会でときどき会うこの女の子の両親が、殊にこの時期忙しくて娘にあまり構ってやれないことを思い出した。その事情と彼女の表情から真相を何となく察して、ルイーダはミミとイザヤールに推測したことをこっそり耳打ちし、助けてあげるよう頼んだ。それから彼女は、子供たちに言った。
「じゃあ、この二人を紹介するわね。すごい冒険者だから、きっとなんとかしてくれるわよ」
ミミとイザヤールは頷き、クエスト「罪なき嘘」を引き受けた!
他の子供たちを帰し、ぬいぐるみを盗まれたという女の子だけを残して、ミミは優しく質問を始めた。イザヤールはその前にミミに何か囁くと、スッと立ち上がってどこかに行った。
「どんなドロボーさんに、モーモンのぬいぐるみを盗られたか、わかる?」
「ええ・・・えっと・・・。すごい盗賊なの・・・覆面してて、すばやくて、びゅーんって・・・」
答えながらも女の子はしどろもどろで、泣きそうになっていた。まさかこんなことになるなんて、と言いたげな表情だった。
「どっちの方に行ったか、わかる?」
「・・・わかんない」
「そう、わかったわ。じゃあ、一緒に探しに行きましょう」
「一緒に?!」
おろおろする女の子の手を優しく引いて、ミミは外に出て、町外れに向かった。
女の子は、泣きそうになるのを我慢して、ちらちら後ろを振り返った。一回帰った筈のみんなが、こっそり着いてきているのがわかる。ちょっとしたウソが、大人たちまで巻き込んで、とんでもないことになってしまった、どうしたらいいのだろうと、彼女は途方にくれていた。
町外れまで来ると、ミミは、立ち止まって女の子に囁いた。
「あの人が、もしかして、あなたのモーモンぬいぐるみを連れて行っちゃった盗賊じゃない?私、捕まえてくるわ」
塀の上に、かげのターバンで頭と顔のほとんどを覆った盗賊衣装の精悍な男が座っていた。腕には、似つかわしくない可愛いモーモンのぬいぐるみを持っている。ミミが駆け寄ると、その男は、塀の上を軽やかに走って逃げ出した。その後を追うように、ミミは塀の下を走る。
「盗賊・・・ホントに居たのかよ・・・」
こっそり着いてきていた子供たちの一人が呟き、みんなで目を丸くしてミミと盗賊の追いかけっこを見つめた。女の子は、信じられない思いで、呆然と立っていた。ウソがホントになるなんて・・・。
やがて、盗賊衣装の男は、ミミに追いつかれかけた。すると彼は、モーモンのぬいぐるみを放り出すと、建物の屋根の上に鮮やかに飛び上がり、逃げてしまった。放り出されたモーモンぬいぐるみは、なんとかミミが受け止めた。
ミミは女の子のところに戻り、モーモンぬいぐるみを差し出した。
「ドロボーさんは捕まえられなかったけれど、はい、これ。ぬいぐるみは無事よ」
「あ・・・ありがと・・・」
モーモンぬいぐるみは、つぶらな目で女の子を見つめている。とても可愛くて、これを抱っこして眠れたらどんなにいいだろうと、彼女は思った。・・・でも、これは、本当は自分の物ではないのだ。偶然ホントに盗賊に盗られてしまった、他の子のものだろう。だから・・・。もらっちゃうわけには、いかない・・・。
「これ、わたしのじゃない!」
やっとそれだけ言うと、女の子は駆け出した。ミミは、追いかけようか迷って少しの間立ち尽くした。
女の子は、家に帰ってきた。相変わらず親は帰っていなくて、一人で泣いていると、かすかな、だが楽しげな鈴の音が聞こえてきた。そして、玄関の扉が開くと、赤い帽子に赤い服の、優しそうな顔のおじいさんが入ってきた。
「プレゼントを配っている途中で橇が壊れてしまってね、お嬢ちゃんのところに持って来るのが遅くなってしまったよ。本当に済まなかったね」
おじいさんはそう言うと、大きな袋からラッピングのリボンがかかったモーモンのぬいぐるみを取り出し、差し出した。
「サンタさん・・・?サンタさんなの?来てくれたの?」女の子は目を丸くして呟いたが、みるみる再び泣き顔になって首を振った。「でも、サンタさん・・・わたし、もうキャンディもらったし、それに・・・せっかくキャンディもらったのに、モーモンのぬいぐるみをもらったってウソついちゃったの。ウソつきは悪い子だから、もらえないよ・・・サンタさんは、いい子にだけ、プレゼントをくれるんでしょう?」
するとおじいさんは、優しく微笑んで、女の子に言った。
「ぬいぐるみを靴下に入れる筈だったのに、間違えてキャンディを入れた私も悪かったからね。お嬢ちゃんも、ウソをついて悪かったと思っているんだろう?もうウソをついたりなんかしないと思っているよね?ならお嬢ちゃんはいい子だよ、安心して受け取っておくれ」
「ありがとう、サンタさん・・・」女の子はモーモンぬいぐるみをぎゅっと抱きしめ、泣きながら笑った。「わたし、友達や冒険者のおねえさんたちに、ほんとのこと言って、謝ってくるね」
おじいさんはにっこり笑ってうんうんと頷き、帰っていった。二頭の馬が引く橇に乗って。
ミミは、女の子が正直に打ち明けて謝ってきたことを嬉しく思い、クエストの報酬に棒付きキャンディをもらった。
「我々は、余計なことをしたかな。だが、あの子のところに本物のサンタクロースが来てよかったな」
かげのターバンを脱ぎながら、イザヤールも微笑む。彼が用意したモーモンぬいぐるみは、宿屋の子連れ客が使う部屋に置くことにした。甘いだけでなく、思いがけず心温まるクリスマスになった。〈了〉
クリスマスの朝。ミミが枕元に下げていた白いふわふわ飾りつき赤い靴下の中には、プラチナ鉱石を使って一から作った、繊細なデザインの腕輪が入っていた。踊りの時に上腕に着けるタイプのものだ。
奇しくもミミの方は、ミスリル鉱石で作った格闘家向けの、頑丈だが洗練されたデザインのリストバンドをイザヤールに贈っていた。相談も無いのに互いに腕の装備物をクリスマスプレゼントに贈り合った偶然が何だかおかしくて、ちょっとだけ行儀悪く二人で一緒にシーツの中に戻ると、じゃれあうように抱き合いながら、声をひそめて笑った。
それからイザヤールは、冷たくないようにと自分の手に包んで腕輪を温めてから、ミミのむき出しの二の腕にそれを着けてくれた。白く滑らかな肌の上に、月のように光る銀色が映えて、なんとも美しく艶かしい。彼女によく似合うのを見て、満足そうに目を細めた彼は、その装飾品の近くの肩口に、あたたかな唇をそっと当てた。
ミミはそんな彼の頭を胸元にきゅうと引き寄せて抱きしめて、頬を薔薇色に染めて囁いた。
「イザヤールサンタさんも、もらっていいの?」
イザヤールは抱かれている極上の感触に陶酔しつつも、自らもしっかりミミを腕に抱えて引き寄せて、いたずらっぽい笑みを口元に浮かべて返答した。
「もちろん。・・・私はこの可愛いサンタガールをもらうからな、おあいこだ」
こうして朝っぱらから二人にとって申し分ない甘さのクリスマスが始まった。為すべきことも全て済ませてあるので、今日はのんびり過ごせる筈だった・・・が、しかし。のんびりという訳にはいかないことが起こってしまうのが、この二人の常である。その予感もあってか、いつもよりちょっとだけ長く、二人は自室でぐずぐずしていたのであった。
クリスマスの午前中。セントシュタイン城下町の教会では、厳かな聖なる日の為の礼拝が行われていた。オルガンの音と神の恵みへの感謝を歌った聖歌は、華やかに装飾された町にも流れて、盛大な宴会の賑わいの中にも、しみじみとした安息の気配を醸し出していた。
しかし、教会のすぐ近くの通りの一角の、子供たちの集まる場所は、そんな静粛なる雰囲気とは全く無縁だった。家族全員でじっとおとなしく座り「神父さまの長い退屈なお話」を聞く時間からようやく解放された彼らは、今朝方それぞれの家のクリスマスツリーの下や、枕元に吊るした靴下の中に入っていたサンタさんのプレゼントの話題に夢中になっていた。
「ボク、サンタさんから、カッコいい毛織りのマントをもらったんだ!青くてボクの名前が刺繍されてて、お話の中の勇者様が着ているのとそっくりなやつ!」
「あたしはオレンジリボンもらったんだ♪将来スーパースターになりたいからくださいって毎日お空に向かっていっしょーけんめいお願いしてたから!」
「アタシはラッキーペンダントよ♪もうさっそく着けてるの、キレイでしょ?」
「オレは十分の一スケールのガチャコッコを再現したニューモデルのおもちゃさあ!ぜんまいを巻くと、ちゃんと羽を動かして飛ぶんだぜ!」
などなど、サンタクロースからもらったプレゼントについて話したり見せたりして盛り上がっていたが、中で一人だけ、沈んだ顔をして黙っている女の子が居た。この子の家庭は、決して暮らしに困っているわけではなかったが、家族が多忙すぎて、子供のプレゼントにまで気を回す余裕がなく、クリスマスツリーや枕元に下げる靴下を用意することはなかった。
そんな訳で彼女は自分で小さな木の枝に手作りのクリスマス飾りをし、自分で靴下を枕元に下げた。そして今朝その靴下に入っていたのは、まるで誰かが急いで用意したかのような、いつのシーズンでもそこらへんで売っている、大きく派手な棒付きキャンディ一本だけだった。そのキャンディももちろん好きではあったし、だからサンタさんはこれをくれたんだと納得しようとしていたものの、友達のもらったプレゼントの話を聞いているうちに、羨ましいという気持ちが強くなって、だんだん表情が曇るのを抑えられなかった。
「で、おまえは何をもらったんだよ?」
一人だけ黙っていた彼女に、みんなが尋ねてきた。
「えっと・・・わたしは・・・」
女の子が口ごもっていると、子供たちの中で口の悪い男の子が、はやし立てるように言ってきた。
「あー!おまえさあ、悪い子だから、サンタさん来なかったんだろー!」
「ち、違うもん、ちゃんと来たもん・・・」
「じゃあ何をもらったんだよ?」
「そ、それは・・・」普段は好物の、もらって嬉しい棒付きキャンディ。でも、今は、それしか靴下に入ってなかったと、何だか言いたくなかった。それで、思わずこんなことが口をついた。「もらったもん!可愛いふかふかの、モーモンのぬいぐるみ!」
「へー」男の子をはじめ、みんなニヤニヤしていた。信じていない顔だ。「じゃあ見せろよ~、モーモンぬいぐるみ」
「い、今持ってないもん・・・」
「じゃあ家まで取りに行けよー」
みんな嘘だとわかっているのだ。ゴメンと謝ればそれで終わるだろう。でもそれが何だか悔しかった。
「み、見せられないの!す、すっごい盗賊に取られちゃったから!」
「へー。じゃあさ、取り返してもらえよー。ルイーダの酒場に居る冒険者に頼んでさー。行こうぜルイーダの酒場!」
「えっ、あ・・・その」
子供たちは、女の子を押すようにして、いっせいにルイーダの酒場が入っているリッカの宿屋へと向かった。
ミミとイザヤールがルイーダの酒場のカウンター席で遅めの朝食兼昼食を摂っていると、突然子供たちがどやどやとリッカの宿屋のロビーに入ってきて、酒場の女主人のルイーダに向かって口々に言った。
「ねーねー、冒険者紹介してー」
「この子が、サンタさんにもらったモーモンぬいぐるみを大ドロボーに取られちゃったのー」
「すっごいドロボーなんだってさー」
ルイーダはいささか戸惑っていたが、やがて事情がわかると、ほんの少し首を傾げて考えた。ぬいぐるみを盗られたという女の子が、暗い表情でうつむいているのが気になったのだ。プレゼントを盗られた小さな子供は、普通大泣きするかしょんぼりしているかで、こんな困ったような顔になるのは不自然だ。カウンター席で子供たちとルイーダのやり取りに耳を傾けていたミミとイザヤールも、その不自然さに気付いて小さく首を傾げた。
ルイーダは、城下町の商工会でときどき会うこの女の子の両親が、殊にこの時期忙しくて娘にあまり構ってやれないことを思い出した。その事情と彼女の表情から真相を何となく察して、ルイーダはミミとイザヤールに推測したことをこっそり耳打ちし、助けてあげるよう頼んだ。それから彼女は、子供たちに言った。
「じゃあ、この二人を紹介するわね。すごい冒険者だから、きっとなんとかしてくれるわよ」
ミミとイザヤールは頷き、クエスト「罪なき嘘」を引き受けた!
他の子供たちを帰し、ぬいぐるみを盗まれたという女の子だけを残して、ミミは優しく質問を始めた。イザヤールはその前にミミに何か囁くと、スッと立ち上がってどこかに行った。
「どんなドロボーさんに、モーモンのぬいぐるみを盗られたか、わかる?」
「ええ・・・えっと・・・。すごい盗賊なの・・・覆面してて、すばやくて、びゅーんって・・・」
答えながらも女の子はしどろもどろで、泣きそうになっていた。まさかこんなことになるなんて、と言いたげな表情だった。
「どっちの方に行ったか、わかる?」
「・・・わかんない」
「そう、わかったわ。じゃあ、一緒に探しに行きましょう」
「一緒に?!」
おろおろする女の子の手を優しく引いて、ミミは外に出て、町外れに向かった。
女の子は、泣きそうになるのを我慢して、ちらちら後ろを振り返った。一回帰った筈のみんなが、こっそり着いてきているのがわかる。ちょっとしたウソが、大人たちまで巻き込んで、とんでもないことになってしまった、どうしたらいいのだろうと、彼女は途方にくれていた。
町外れまで来ると、ミミは、立ち止まって女の子に囁いた。
「あの人が、もしかして、あなたのモーモンぬいぐるみを連れて行っちゃった盗賊じゃない?私、捕まえてくるわ」
塀の上に、かげのターバンで頭と顔のほとんどを覆った盗賊衣装の精悍な男が座っていた。腕には、似つかわしくない可愛いモーモンのぬいぐるみを持っている。ミミが駆け寄ると、その男は、塀の上を軽やかに走って逃げ出した。その後を追うように、ミミは塀の下を走る。
「盗賊・・・ホントに居たのかよ・・・」
こっそり着いてきていた子供たちの一人が呟き、みんなで目を丸くしてミミと盗賊の追いかけっこを見つめた。女の子は、信じられない思いで、呆然と立っていた。ウソがホントになるなんて・・・。
やがて、盗賊衣装の男は、ミミに追いつかれかけた。すると彼は、モーモンのぬいぐるみを放り出すと、建物の屋根の上に鮮やかに飛び上がり、逃げてしまった。放り出されたモーモンぬいぐるみは、なんとかミミが受け止めた。
ミミは女の子のところに戻り、モーモンぬいぐるみを差し出した。
「ドロボーさんは捕まえられなかったけれど、はい、これ。ぬいぐるみは無事よ」
「あ・・・ありがと・・・」
モーモンぬいぐるみは、つぶらな目で女の子を見つめている。とても可愛くて、これを抱っこして眠れたらどんなにいいだろうと、彼女は思った。・・・でも、これは、本当は自分の物ではないのだ。偶然ホントに盗賊に盗られてしまった、他の子のものだろう。だから・・・。もらっちゃうわけには、いかない・・・。
「これ、わたしのじゃない!」
やっとそれだけ言うと、女の子は駆け出した。ミミは、追いかけようか迷って少しの間立ち尽くした。
女の子は、家に帰ってきた。相変わらず親は帰っていなくて、一人で泣いていると、かすかな、だが楽しげな鈴の音が聞こえてきた。そして、玄関の扉が開くと、赤い帽子に赤い服の、優しそうな顔のおじいさんが入ってきた。
「プレゼントを配っている途中で橇が壊れてしまってね、お嬢ちゃんのところに持って来るのが遅くなってしまったよ。本当に済まなかったね」
おじいさんはそう言うと、大きな袋からラッピングのリボンがかかったモーモンのぬいぐるみを取り出し、差し出した。
「サンタさん・・・?サンタさんなの?来てくれたの?」女の子は目を丸くして呟いたが、みるみる再び泣き顔になって首を振った。「でも、サンタさん・・・わたし、もうキャンディもらったし、それに・・・せっかくキャンディもらったのに、モーモンのぬいぐるみをもらったってウソついちゃったの。ウソつきは悪い子だから、もらえないよ・・・サンタさんは、いい子にだけ、プレゼントをくれるんでしょう?」
するとおじいさんは、優しく微笑んで、女の子に言った。
「ぬいぐるみを靴下に入れる筈だったのに、間違えてキャンディを入れた私も悪かったからね。お嬢ちゃんも、ウソをついて悪かったと思っているんだろう?もうウソをついたりなんかしないと思っているよね?ならお嬢ちゃんはいい子だよ、安心して受け取っておくれ」
「ありがとう、サンタさん・・・」女の子はモーモンぬいぐるみをぎゅっと抱きしめ、泣きながら笑った。「わたし、友達や冒険者のおねえさんたちに、ほんとのこと言って、謝ってくるね」
おじいさんはにっこり笑ってうんうんと頷き、帰っていった。二頭の馬が引く橇に乗って。
ミミは、女の子が正直に打ち明けて謝ってきたことを嬉しく思い、クエストの報酬に棒付きキャンディをもらった。
「我々は、余計なことをしたかな。だが、あの子のところに本物のサンタクロースが来てよかったな」
かげのターバンを脱ぎながら、イザヤールも微笑む。彼が用意したモーモンぬいぐるみは、宿屋の子連れ客が使う部屋に置くことにした。甘いだけでなく、思いがけず心温まるクリスマスになった。〈了〉


















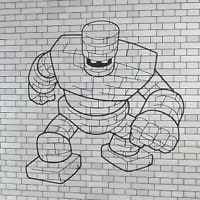







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます