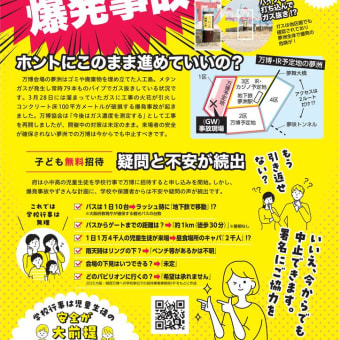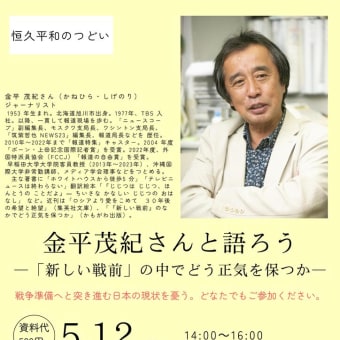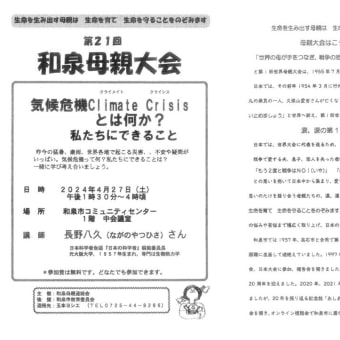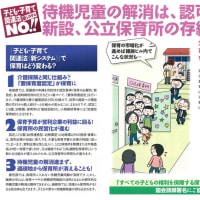政府が5日、国家公務員法「改正」法案を閣議決定したことに対して、日本国家公務員労働組合連合会(国公労連)が書記長談話を発表しましたので紹介します。
公務の中立・公正性の侵害、使用者権限の一方的強化に反対する
――国家公務員法「改正」法案の閣議決定にあたって(談話)
2013年11月5日
日本国家公務員労働組合連合会
書記長 鎌田 一
本日(5日)政府は、国家公務員法等の一部を改正する法律案(以下、法案)を閣議決定し、国会に提出した。
法案は、2008年に施行された国家公務員制度改革基本法(以下、基本法)にもとづいて検討が進められていた課題の内、①国家戦略スタッフ・政務スタッフの設置、②幹部職員の一元管理、③内閣人事局の設置などを盛り込んだ2009年法案(同年に廃案となった国家公務員法等の一部を改正する法律案)をベースにしており、公務の公正・中立な運営や国家公務員労働者の権利にとって重大な問題を抱えている。
1、法案では、国家戦略スタッフにあたる官職として、内閣総理大臣補佐官(首相補佐官)の所掌事務を現行の「内閣の重要政策に関して首相の特命事項の担当」から「首相の命を受け国家戦略などの施策の企画・立案の補佐」に改め、定数を5人以内と定めた。政務スタッフにあたる官職としては、大臣補佐官を新設。「各大臣の企画・立案・政務の補佐」を職務として、各府省が特に必要がある場合に1人以内(内閣府6人以内)の設置を可能とした。
いずれもその職務が抽象的であり、第一線の定員を減らし続けながら大臣政務官級の幹部公務員を増員する必要性に疑問が残る。さらに問題なのは、大臣補佐官の任用について「大臣の申出により、内閣がこれを行う」(国家行政組織法17条の2)とされ、政治任用が可能であり、運用によっては、行政運営の公正・中立性が大きく歪められかねないことである。
2、幹部人事の一元管理についても同様の問題がある。幹部職員(本府省の部局長以上)の人事について、最終的には従前通り各大臣が任命するとしているものの、任命までの課程で、官房長官(内閣総理大臣が委任)が適格性審査(人事評価を基本に官職の標準職務遂行能力の有無を確認)を実施した上で幹部候補者名簿を作成するという、人事配置に官邸の意向が強く反映できる仕組が盛り込まれた。法案協議の過程で「(政令の作成にあたって)人事院の意見を聴いて定める」(61条の2第6項)ことが加筆されたものの、運用の枠組には修正が加えられていない。
したがってこれまでも指摘してきたように、適材適所の人事ではなく、時の政権による恣意的な人事を許すこととなり、「全体の奉仕者」という公務の公正・中立性が損なわれ、行政の専門性の確保さえも困難となりかねない。
3、内閣人事局の設置についても多くの問題を含んでいる。
法案では、内閣人事局の役割について、①総務省の人事行政(国家公務員制度の企画・立案、人事評価、服務、退職手当等)と機構・定員管理等、②人事院の級別定数の設定・改定、任用(2009年法案ではすべて移管としていたが、人材の養成・活用を移管。公正確保は人事院)、試験・研修の企画等、③その他新設される幹部人事の一元管理や総人件費の基本方針を含めて多くの権限を内閣人事局に移管・集中し、強大な使用者機関を構成するとしている。
基本法では、内閣人事局について「政府全体を通ずる国家公務員の人事管理」を所掌するとして「国家公務員の人事行政に関して担っている機能について…中略…必要な範囲で、内閣官房に移管する」とされ、2009法案では重要な労働条件である級別定数に関する権限を人事院から移管するとしていた。そのため基本法では、自律的労使関係制度の措置を謳い、2009年法案の提出に先駆けて公務員制度改革にかかる「工程表」(推進本部決定)で、自律的労使関係制度への改革は「不可欠」と位置づけるなど、十分とはいえないまでも労働基本権制約を改める方向性は示していた。
しかし政府は、この間、ILO勧告を無視し続けたように、今回の法案提出にあたっても、労働基本権問題を棚上げして、検討する姿勢さえ示さない。そればかりか、「級別定数はそもそも勤務条件ではないけれども、長年ずっと人事院が掌握をしていた関係で、勤務条件的に運用されていた」(10月18日、稲田大臣)などと、労働条件性を否定する認識を示し、批判をかわそうとしている。
4、憲法で保障されている労働基本権が不当に制約されている国家公務員労働者にとって、給与などの労働条件決定に関わる人事院の代償機能は、重要な意味を持つ。人事院から移管するとしている級別定数は、昇格基準や職務評価とも密接に関わるとともに、給与の配分に関わる問題であり、官民給与比較の重要な要素である「役職別給与」に反映して給与勧告にも直接影響するもので、給与とは切り離すことができない明確な労働条件である。
この問題に関わって人事院は、「級別定数は、俸給表と一体の職員の給与処遇に関する重要な勤務条件であり、若手職員を含めた職員全体の昇格枠として機能するものである。…中略…労働基本権制約の下では、級別定数に関する機能は、使用者機関ではなく、中立・第三者機関が代償機能として担う必要がある」(8月8日、国家公務員制度改革等に関する報告)とまっとうな見解を示していた。しかし最終版で「(級別定数の設定・改定にあたって)職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については十分尊重するものとする」(給与法第8条)という修正が加えられたことを受け、「人事院の中立性と労働基本権の代償措置はある程度、確保できた」(人事院幹部のコメント。10月16日付日経新聞)などと自らの見解を翻したかのように報じられた。
人事院の関与の範囲については、曖昧な部分が残されてはいるものの、級別定数決定の権限が内閣人事局に移管されることに変わりはなく、その意味で法案は、国家公務員労働者の労働基本権制約の代償機能を奪うものである。
5、国公労連は、政府の法案の検討に対して、労働基本権の全面回復を先送りしたままで、級別定数管理をはじめとした労働条件関連の権限を内閣人事局に移管するなど、使用者権限を強化する公務員制度改革を行わないこと、合意と納得のうえで検討を行うことを求めてきた。
しかし政府は、今国会への法案の提出・成立にこだわり、私たちの要求に基本的に答えず、十分な交渉・協議を尽くさないまま、法案を閣議決定した。我々はこうした政府の姿勢に厳しく抗議する。
以上述べたとおり法案は、憲法15条(全体の奉仕者)に基づく公務員の中立・公平性の確保を困難とする危険性があり、国家公務員労働者の権利を奪いかねないものであることから、権利の回復なき法案の撤回を求める。また、労働者・国民の権利を保障する公務・公共サービス拡充をめざし、民主的な公務員制度改革を推進する立場から、法案の廃案に向けて奮闘するものである。
以 上