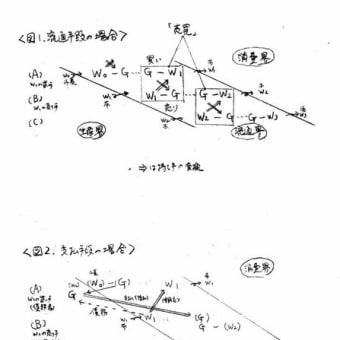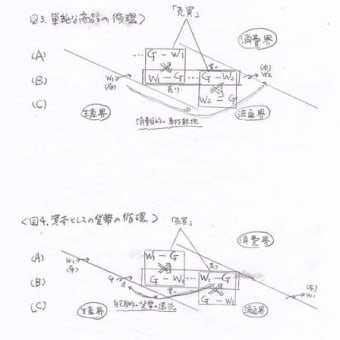「読む会」だより(24年12月用)文責IZ
(11月の議論など)
11月の「読む会」は17日に開催されました。
(10月の議論)の所では、マルクスが「資本主義」という言葉を使い始めたのは何時頃からか、という質問が出ました。チューターは、エンゲルスと二人でまとめた草稿『ドイツ・イデオロギー』ではまだ使っていないと思うが、少し調べたいと答えました。
チューターも少し驚いたのですが、マルクスが「資本主義」と明確に書いているのは資本論の第4部にあたる『剰余価値学説史』(1862~)からのようです。『ド・イデ』(46年)や、『哲学の貧困』(47年)では、ヘーゲルに倣ってまだ「ブルジョア社会」と言われています。48年の『共産党宣言』でも「近代ブルジョア社会」としか言われていないようですし、57年の『経済学批判要綱』では「ブルジョア的経済的形態」、59年の『経済学批判・序言』では「近代ブルジョア的生産様式」などと言われています。(チューターは訳文しか知らないので、文献的なことは、“学者”の方にお任せなのですが。)
ですから、マルクスがブルジョア的な生産様式(「序言」によれば、アジア的、古代的、封建的、に継ぐ経済的社会構成)のことを「資本主義」と名付けたのは、資本論の検討を始めてからということのようです。但しチューターは、「資本主義」の内容が明確化してきたのは47年の『哲学の貧困』の後に、労働者向け講演草稿として書かれた『賃労働と資本』の頃からではないかと理解します。というのは、その冒頭に次のように書かれているからです。
「わが読者諸君は……ブルジョアジーの存立と彼らの階級支配との基礎をなしており、また労働者の奴隷状態の基礎ともなっている経済的諸関係そのものに、今や詳しく立ち入るべき時である。われわれは次の三つの大きな部分に分けて叙述しよう。(1)賃労働の資本に対する関係、労働者の奴隷状態、資本家の支配。(2)……」(国民文庫版、P26、太字は原文)
ブルジョア社会であれ、ブルジョア的経済的形態であれ、ブルジョア的生産様式であれ、そして資本主義であれ、すべてその本質的な内容は賃労働と資本との関係に尽きるのですから。
また、参加者のOさんが訳して出版された、ルビンシュテインの著作への書評に対して、参加者から「共産主義と自由が注目されている折り」とあるがどういう意味か、という質問が出ました。ただこれは、書評を書いた人の問題意識だということで議論にはなりませんでした。
(説明)のところでは、たよりの3項の末尾に、「労賃という現象形態も単に需給関係で決まるのではなくて、その大きさが決まるための客観的な背景(本質的関係としての労働力の価値)をもつ」とあるが、労賃の大きさには文化的・歴史的な要素も含まれるのではないか、という意見が出ました。チューターはそれはその通りだが、ここでは労賃の具体的な決定要因を述べようとしたのではない。労働力の価値に規定されて、労賃は一定の変動幅の中に”規制される”ということを言ったつもりだ、と答えました。
関連して別の参加者から、労賃が労働力の価値で決まると言われると賃金闘争不要論にならないのか、という質問が出ました。これには参加者から、資本と労働者との力関係といったものも文化的・歴史的要素に含まれるだろう。日本の実質賃金の長年の低落は、労働運動の停滞が招いている面も大きい。賃金闘争がたとえ資本の搾取率を一時的に引き下げるだけのものであっても、賃金闘争抜きには生活は守れない、といった意見が出ました。
労賃が労働力の価値に規定されるという点について、必ずしも意見が一致しなかったので、20章の「労賃の国民的相違」のところでもう一度これらの点について取り上げることになりました。
また、4項では(3項が二つありますので、4項5項に訂正願います)、資本家は本当に労賃の中に不払労働が含まれているということを知らないのだろうか、分かった上で低賃金を押し付けているのではないか、という意見が出ました。これについては労働者もまた科学的な理解がなければ労働の価格という現象に囚われてしまう、など色々な実情が話題になりました。チューターは、マルクスが「資本の神秘化」という言葉で語っている、社会的なあるいは結合された労働の生産力が資本の力として現われるところに、問題の根底があると考えています。参考までに『直接的生産過程の諸結果』の一部分を引用しておきます。(太字は原文、下線は引用者)
・「生きている労働は──生産過程のなかでは──すでに資本に合体されているので、労働の社会的生産力は、すべて、資本に固有な属性としての生産力として現われるのであって、ちょうど、貨幣にあっては価値を形成する限りでの労働の一般的性格が物の属性として現われたのと同様である。それは次のような事情によってますます甚だしくなる。
(1)確かに、労働は、生産物に対象化されたものとしては資本家のものであるとはいえ、労働能力の発揮としては、努力としては、個々の労働者のものである(それは、彼が現実に資本家に支払うもの、資本家に与えるものである)。これに反して、そのなかでは個々の労働能力はただ工場全体を形成する総労働能力の特殊な諸器官として機能するにすぎない社会的な結合は、個々の労働能力のものではなくて、むしろ資本による編成としてそれらに対立し、それらに押しつけられる。
(2)このような、労働の社会的生産力、または社会的労働の生産力は、歴史的には独自に資本主義的な生産様式とともに初めて発展し、したがって、資本関係に内在するもの、資本関係とは不可分なものとして現われる。
(3)客体的な労働条件<すなわち生産手段(労働対象と労働手段)>は、資本主義的生産様式の発展につれて、それが充用される規模と節約とによって、変化した姿をとるようになる(機械の形態などはまったく別としても)。そのような<客体的な>労働条件は、社会的な富を表わす集積された生産手段として、また、本来全体をひっくるめてのことであるが、社会的に結合された労働の生産条件の規模や効果において、ますます発展したものとなる。労働そのものの結合を別とすれば、このような、労働条件の社会的な性格──この労働条件にはなかんづく機械や各種の固定資本としてのそれらの形態が属している──は、全く独立なもの、労働者から独立に存在するものとして、資本の一つの存在様式として、したがってまた労働者から独立に資本家によって編成されたものとして、現れる。労働者自身の労働の社会的な性格よりも、生産条件が結合労働の共同的生産条件として受け取る社会的な性格の方が、はるかにより以上に、労働者たちから独立にこれらの生産条件そのものに属する資本主義的な性格として現われるのである。」(国民文庫版、P131~)
(説明)第6篇労賃第19章出来高賃金
(1.時間払いか出来高払いかといった支払いの形態が違っても、労賃(労働の価格)が労働力の価値または価格の現象形態であるという、その本質は変えられるものではない)
・「出来高賃金は時間賃金の転化形態にすぎないのであって、<それは>ちょうど時間賃金が労働力の価値または価格の転化形態に他ならないようなものである。
出来高賃金では、一見したところ、労働者が売る使用価値は彼の労働力の機能である生きている労働ではなくて既に生産物に対象化されている労働であるかのように見え、また、この労働の価格は、時間賃金の場合のように 労働力の日価値/与えられた時間数の労働日 という分数<を尺度にして計られるの>ではなくて、生産者の作業能力によって規定されているかのように見える。
この外観を正しいと信ずる確信は、まず第一に、労賃のこの二つの形態<出来高賃金と時間賃金>が同じ時に同じ産業部門で相並んで存立するという事実によっても、すでに激しく動揺せざるを得ないであろう。たとえば、<ある著者は>次のように言う。
「ロンドンの植字工は通例は出来高賃金で働いていて、時間賃金は彼らの間では例外である。地方の植字工の場合はこれと反対で、地方では時間賃金が通例で出来高賃金が例外である。船大工はロンドン港では出来高賃金で支払われ、その他のイギリスの港ではどこでも時間賃金で支払われる。」
同じロンドンの馬具製造工場では同じ作業にフランス人なら出来高賃金で支払われ、イギリス人ならば時間賃金で支払われるということもよくある。……しかし、<時間払いか出来高払いかという>労賃の支払いの形が違ってもそのために労賃の本質<労働力の価値または価格が転化した現象形態であるということ>は少しも変えられるものではないということは、それ自体として明らかなことである。といっても、資本主義的生産の発展<すなわち資本の蓄積>にとっては一方の形態が他方の形態よりも好都合だということはあるであろうが。」(全集版、P715~)
最後の部分で、「労賃の支払いの形が違ってもそのために労賃の本質は少しも変えられるものではないということは、それ自体として明らかなこと」と述べられています。これは要するに、労賃がどのような仕方で支払われるのかということによって、労賃が何であるのかということが変わるわけではない、ということは自明なのだが、という意味と思われます。
述べられている通り、出来高賃金においては時間賃金の場合と異なって、労働者は彼の労働力を売るのではなくて、生産物に対象化された彼の労働自身を売るように見えますし、またその「労働の価格」(すなわち支出総労働時間の貨幣表現ではなくて、不払部分を除いた支払労働だけの大きさの貨幣表現)は、労働力の日価値の大きさによってではなくて、労働者の作業能力の大きさによって規定されるように見えます。しかし、両者のこの「外観」上の相違の真実性は、労賃のこの二つの形態が同じ産業部門の同じ作業においてすら同時に存在する(全くの別物なら同時に存在しえないはずなのに)という事実だけから見ても、危ういものではないか、ととりあえずマルクスは指摘します。
そして続いて次項のように具体的な例を挙げながら、出来高賃金とはただ時間賃金が変形したものであって、それもまた賃労働と資本(すなわち必要労働とそれを超過する剰余労働)という搾取関係の基礎をなす、労働力の価値または価格を越える労働力の使用という、資本の価値増殖過程の表現=現象形態でしかないことを明らかにします。
(2.出来高賃金は時間賃金の一つの変形でしかない)
・「通例の1労働日は12時間で、そのうち6時間は支払われ、6時間は支払われないとしよう。1労働日の価値生産物は6シリング、したがって1労働時間の価値生産物は6ペンスだとしよう<したがって時間賃金の場合、労働者は12時間で3シリング、1時間当たり3ペンスを受け取る>。@
<他方、出来高賃金の下で>平均的な強度と熟練度とをもって労働する、つまり、実際に、1物品の生産に社会的に必要な労働時間だけを費やす1人の労働者は、12時間に、不連続製品を24個、または一つの連続製品の計量可能部分を24個供給することが、経験によって分かっている<経験的に与えられている>としよう。そうすれば、この24個の<製品の>価値は、それに含まれている不変資本部分を引き去れば、6シリングであり、各1個の価値は<6/24=1/4シリング=1/4×12ペンス=>3ペンスである。労働者は1個につき1・1/2ペンスを受け取り、したがって12時間では<3/2×24=3×12ペンス=>3シリングを稼ぐ。@
<12時間の>時間賃金の場合には、労働者が6時間は自分のために、6時間は資本家のために労働すると見なしても、各1時間の半分は自分のために、残りは資本家のために労働すると見なしても、どちらでもよいのであるが、それと同じに、この<出来高賃金>場合にも、各1個の半分は支払われ半分は支払われない、と言ってよいし、12個の価格は労働力の価値だけを補填し、残りの12個には剰余価値が具体化されている、と言ってもよいのである。
出来高賃金という形態も時間賃金という形態と同じように<価値=支出労働量の表現としては>不合理である。例えば、2個の商品は、それに消費された生産手段の価値を引き去れば、1労働時間の生産物として6ペンスの価値がある<すなわち6ペンスの価値生産物である>のに、労働者はそれに対して3ペンスという<労働の>価格を受け取る。<このように>出来高賃金は、直接には実際少しも<製品の価値と支出労働量との>価値関係を表わしていないのである。ここで行われるのは、1個の<生産物の>価値をそれに具体化されている労働時間で計ることではなくて、逆に、労働者の支出した労働<量>を彼の生産した<生産物の>個数で計ることである。時間賃金の場合には<支出された>労働<量>がその直接的持続時間によって計られ、出来高賃金の場合には一定の持続時間中に労働が凝固する生産物量で<支出された>労働<の量>が計られるのである。@
<支出される>労働時間そのものの価格<つまり労働の価格>は、結局は、 日労働日の価値=労働力の日価値 という等式によって規定されている。だから、出来高賃金はただ時間賃金の一つの変形でしかないのである。」(同、P717~)
出来高賃金において行われているのは、「労働者の支出した労働<量>を彼の生産した<生産物の>個数で計ること」であり、つまり「一定の持続時間中に労働が凝固する生産物量で<支出された>労働<量>が計られる」ことにすぎません。そしてこの労賃の支払い方法においても、その基礎になるのは労働力の日価値または日価格なのですから、「出来高賃金は時間賃金の一つの変形でしかない」と、ここでは分かりやすく説明されています。
要は、賃金の理解のためには、支払労働と不払労働との区別が、したがってまた必要労働と剰余労働との区別が肝心であって、賃金(=労働の価格)を労働力の価値または価格に還元することで、はじめて賃金の諸形態も説明できる(そのためにはあらかじめ価値とは何か、等々の理解が必要になりますが)、と言われているように思われます。
(3.出来高賃金の第一の特徴ここでは労働の質や強度が製品の質や量を通じて規制されるので、労働監督の大きな部分が不要となる。このために出来高賃金は、近代的家内労働の基礎をなすと同時に、中間寄生者による追加収奪を可能にする)
・「そこで、出来高賃金の特徴をもう少し詳しく考察してみよう。
この場合には労働の質が製品そのものによって左右されるのであって、各個の価格が完全に支払われるためには製品は平均的な品質をもっていなければならない。出来高賃金は、この面から見れば、賃金の削減や資本家的なごまかしの最も豊かな源泉になる。
出来高賃金は、資本家に、労働の強度を計るためのまったく明瞭な尺度を提供する。ただ、前もって確定され経験的に固定されている商品量に具体化される労働時間だけが、社会的に必要な労働時間として認められ、そういうものとして支払いを受ける。@
それだから、ロンドンのやや大きい裁縫工場では、1時間を6ペンスとして、たとえば1枚のチョッキというような或る出来高の労働が1時間とか半時間とか呼ばれるのである。どれだけが1時間の平均生産物であるかは、経験によって知られているのである。新型や修理などの場合には、一定の出来高が何時間に相当するかについて雇い主と労働者との間に争いが起きるが、このような場合にも最後には経験が決着をつける。ロンドンの家具製造場などでも同様である。もし労働者が平均的な作業能力をもっていなければ、つまり彼が一定の最小限の1日仕事を供給することが出来なければ、彼は解雇されるのである。
この場合には労働の質や強度が<出来高賃金という>労賃の形態そのものによって制御されるのだから、この形態は労働監督の大きな部分を不要にする。したがって、この形態は、前に述べた近代的家内労働の基礎をなすと同時に、搾取と抑圧との階層制的に編成された制度の基礎をなすのである。@
この<階層制的>制度には二つの基本形態がある。出来高賃金は一方では資本家と賃金労働者との間に寄生者が介入すること、すなわち仕事の下請けを容易にする。仲介人たちの利得は、ただ、資本家が支払う労働の価格と、この価格のうちから仲介人たちが実際に労働者に渡す部分との差額だけから生ずる。この制度はイギリスではその特色を生かして(苦汁制度)と呼ばれている。他方では、出来高賃金は、資本家が主要な労働者──マニュファクチュアでは組長、鉱山では採炭夫など、工場では本来の機械工──と出来高当たり幾らという価格で契約を結び、その価格で主要な労働者自身が自分の補助労働者の募集や賃金支払いを引き受けるということを可能にする。資本による労働者の搾取がこの場合には労働者による労働者の搾取を媒介として実現されるのである。」(同、P718~)
特に説明は不要と思われます。
(4.出来高賃金の第二の特徴出来高賃金は当該の産業部門の総賃金の範囲内で、個人的な能力による収入の大きな差異を許す。このためここでは労働日の延長や労働の強化が労働者自身によって行われるとともに、労働者間の競争が高まり全体の平均賃金を低落させる傾向を持つ)
・「出来高賃金が与えられたもの<条件>であれば、労働者が自分の労働力をできるだけ集約的に緊張させるということは、もちろん労働者の個人的利益ではあるが、それが資本家にとっては労働の標準強度を高くすることを容易にするのである。同様に、労働日を延長することも労働者の個人的利益である。というのは、それにつれて彼の日賃金や週賃金が高くなるからである。それとともに、時間賃金の所ですでに述べたような反動<時間給制度による過少就業など>が現われる。労働日の延長は、出来高賃金が変わらなくても、それ自体として労働の価格の低下を含んでいるということは別にしても、である。
時間賃金の場合には、僅かな例外を別とすれば、同じ機能には同じ労賃というのは一般的であるが、出来高賃金の場合には、労働時間の価格<労働の価格>は一定の生産物量によって計られるとはいえ、日賃金や週賃金は、それとは反対に、労働者たちの個人差、すなわち一人は与えられた時間内に最小限の生産物しか供給せず、別の一人は平均量を、第三の一人は平均量より多くを供給するというような個人差につれて、違ってくる。だから、この<出来高賃金の>場合には現実の収入については、個々の労働者の技能や体力や精力や耐久力などの相違にしたがって、大きな差が生ずるのである。@
もちろん、このようなことは、資本と賃労働との一般的な関係を少しも変えるものではない。第一に、一つの作業場全体としては個人差は相殺されるので、作業場全体は一定の労働時間では平均生産物を供給するのであって、支払われる総賃金はその産業部門の平均賃金になるであろう。第二に、労賃と剰余価値<支払労働と不払労働>との割合は元のままで変わらない。というのは、各個の労働者の個別的賃金には彼によって個別的に供給される剰余価値量が対応するからである。しかし、出来高賃金のほうが個性により大きい活動の余地を与えるということは、一方では労働者たちの個性を、したがってまた彼らの自由感や独立心や自制心を発達させ、他方では労働者どうしの間の競争を発達させるという傾向がある。それゆえ、出来高賃金は、個々人の労賃を平均水準よりも高くすると同時にこの水準そのものを低くする傾向があるのである。……@
最後に、出来高賃金は、前に述べた時間給制度<労働者を時間単位で雇ったり雇わなかったりできる>の一大支柱である。」(同、P719~)
ここも特に説明は不要と思われます。
(5.出来高賃金は、今でもいわゆる“内職”などにおいて労働者家族全体としての労働時間の延長と労働強化をもたらす労賃形態として用いられるが、機械ならびに結合労働の大きな発展のなかでは比重を小さくしている)
以下の引用のようにマルクスは「出来高賃金は資本主義的生産様式に最もふさわしい労賃形態だ」と語っています。確かに出来高賃金は現代でも労働の強度を高め、労働者自身の個人的な活動によって労働時間の延長と賃金引下げの手段となりますが、しかしそれが「資本主義的生産様式に最もふさわしい形態」として広範囲に行われているとは言えません<いわゆる途上国を除けば>。この理由は言うまでもなく、機械ならびに結合労働の大きな発展によって、生産された製品が誰これの個人的な労働の結果だと認められることができなくなったことに起因しているでしょう。
「当時の工場は、今日のそれに比して小規模であった。1850年代のイギリスでは雇用労働者数300人の工場はなお極めて大規模なものと見なされていた。1871年においても、綿工場の平均雇用者数は180人、機械製造工場のそれは86人にすぎなかった。」(松尾太郎、『経済学史と資本論』、プロメテウス63号より重引。)現代では、近年の情報工学の発展も相まって、各企業、工場内の労働者ばかりではなくて、まさにグローバルな形での協業・分業がなされており、ここでは労賃の基本形態である時間賃金が主要な形態になるほかない(時間給制度を含めて)と思われます。
・「これまでに述べたところから、出来高賃金は資本主義的生産様式に最もふさわしい労賃形態だということが分かる。出来高賃金は決して新しいものではない──それは殊に14世紀のフランスやイギリスの労働者法規では時間賃金と並んで公式に現われる──とはいえ、それが初めて幾らか大きな部面を占めるようになるのは、本来のマニュファクチュア時代のことである。大工業の疾風怒濤時代、殊に1797年から1815年までは、出来高賃金は労働時間の延長と労賃引き下げとのための槓杆として役立っている。……
工場法の適用を受ける作業場では出来高賃金が通例のことになる。なぜならば、そこでは資本は労働日をもはや<労働の強度を高めることで>内包的に拡大するよりほかはないからである。
労働の生産性の変動につれて、同じ生産物量が表わす労働時間も変動する。したがってまた出来高賃金も変動する。というのは、出来高賃金は<やはり>一定の労働時間の価格表現だからである。……言い換えれば同じ時間で生産される個数が増加し、したがって同じ1個に充用される労働時間が減少するのと同じ割合で、出来高賃金は引き下げられるのである。……。」(同、P722~)