宮沢賢治〈雨ニモマケズ〉に新解釈の玄侑宗久氏 (28)最終回
――――――――――ヒドリの解釈について(3)――――――――――
昭和八年(1933年)九月十九日、賢治は朝から気分が良かった。賢治は病床からおきあがり、遠くから聞えてくる鉦や太鼓の音、神輿を担ぐわっしょい、わっしょいの掛け声に耳を傾けた。
窓から差し込む光は一輪挿しの花を照らしていた。青い花びら。賢治は机の前へゆき正座をした。詠んだばかりの短歌を今一度吟味し反芻した。青色が好きであるが、この頃はやけにアカ色に惹かれる。身を灼き尽くして赤色に、朱色に、緋色に燃えて燃えて、身を百ぺんでも灼きつくそうとも・・・・献身したい・・・・。
硯を引き寄せ墨をゆっくりゆっくり磨った。半紙に向き合い深呼吸をした。三十七年めの産土の祭り・・・・豊作を祝う花巻の祭りの、賑わいの風が頬にやさしい。・・・筆を執った。書き終えたら、門口へでてお神輿を御迎えしよう・・・。
賢治は歌を二首したためた。
この二首は後世、賢治の絶筆と評される。
方十里 稗貫のみかも 稲熟れて み祭三日 そらはれわたる
病(いたつき)のゆゑにもくちんいのちなり みのりに棄てば うれしからまし
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
辞世の一首には、多義性があると解読されている。
賢治のカラダは衰弱こそしているが、知能を働かせて辞世の歌に多義性をもたせた。
賢治は短歌文化の伝統にのっとり、修辞技法を駆使、本音を秘匿させた。
この秘匿に賢治の用意周到ぶりが窺えるのではなかろうか。
病(いたつき)のゆゑにもくちんいのちなり みのりに棄てばうれしからまし
この短歌は和歌のように平仮名を多用していた。詩雨ニモマケズではカタカナ文字を多用した。
どちらも表音文字の多用である。表意文字の漢字よりは本音を秘すには好都合な表音文字である。
賢治は病の漢字に丁寧に「いたつき」とルビを振った。よほど歌道を探究しておらなければ、いたつきとは読めない。賢治はいたつきと読んでほしくてルビをふった。あたかも病床を着けられたような二年に及ぶ日々。それで「いたつき」なのだ。
この思いをこめて漢字のいたつきで始める短歌とした。
万葉集でよく見かける枕詞のように、いたつきを枕詞にしたかったのであろうか。
いたつきとして挽歌としたかったのであろうか。
漢字は「病」と「棄」のふた文字のみ使用の歌。その漢字の二文字を並べると、病棄(びょうき)となる。
「病棄」の思いを強調したかった賢治であったのであろう。
賢治は病気がなければ、健康体であったならば、これほどまでに此の世、あの世を追究をしてはこなかったであろう。健康であったならば、別の職業に就いてたかもしれない。そうなると、詩雨ニモマケズは生まれることはなかった。いたつきに苦しめられたからこそ法華経のお教えを深く共感していった賢治。永遠の生命を求めてきたのではなかったか。此の世の幸せを追求してきたのではなかったか。童話作家になったのではなかったか。
東へ西へ南へ北へ行ッテ、行ッテ、手を差しのべる生き方。
書斎の学問ではなく実践の学問を追求してきた賢治。
そのような賢治は病床に臥し実践が出来難い独りのときは、ヒドリノトキハナミダヲナガシ、涙が零れてきたのであろう。
東北は寒いことから、口を大きくあげね。「独り」を「ヒドリ」と濁って聞えんか。
ヒドリノトキハナミダヲナガシ、
そのような解釈も実は、してほしいことからヒドリとしたのではないだろうか。弱気にもなってもいた賢治は「ヒドリ」にいろいろと托していたようにも思えてならない。
辞世の短歌に「病のゆゑにもくちん・・・」と詠んでいることを吟味したい。
吾がいのちは、病だけではなく自己献身で「も」くちん、と詠んだ。私は、このことに注目してほしいと思う。
・・・・のゆゑにも・・・と、「も」を詠みこんでいることを見落とされないでほしい。
強気の自己犠牲精神と病で弱気になってナミダを流す賢治の短歌。
ご両親には、「死」と明言するようなことをせずに「朽ちる」、と表現する優しさを持つ賢治。朽ちることは、他の生物の肥やしになり、循環してゆく姿も滲ませて作歌された。
さて、辞世の短歌いたつきのゆゑにもくちん・・・を解釈しておきたい。多義に詠まれていた。以下。
解釈1:私は病で間もなく樹木が朽ちるようになるが、今年の秋は“稔り” “実り”であったと伝え聞く。農民のお役に立てたかと思うと嬉しいことです。
解釈2: ミノリとは“御法”と漢字で表す。「ミノリ」と表記した賢治の拘りが秘められた歌と観る。
御法とは法華経を指す。自分は病でまもなく朽ち果てるだろうが、
法華経に吾がイノチを棄てる(捧げる)ことでもあり、本望でうれしいことです。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
賢治は、自分の亡き後の作品始末について、父、母、弟の清六に頼みこんでいた。
その内容は三人三様で驚くばかりである。以下にしめす。
『新文芸読本 宮澤賢治』平成2年(1990)9月20日、河出書房新社刊には「宮沢賢治と音楽・・・・林光・山口昌男 」対談が特集されてあった。引用する。
《 林―――晩年、賢治が死に際に父親には「自分の書いたものは何の価値もないの だから、捨てるなり焼くなりどうでもしてくれ」と言って、お母さんには「これは仏様の教えを書いた大事なものだからしまっておいてくれ」と言って、弟には「これはお前にやるから、どこかで出版したいと言ってきたら、出版させてやってくれ」と言ったと云う。このふりわけというか、それはやっぱり大変な人だ。
山口――近代日本の芸術家の中で、パフォーマンス能力が抜群にあった人じゃないかと思うね。国柱会で奉仕しながら、書きためた五千枚をトランクに詰めて東京市中を走り回っているんですからね。これは想像を絶する。 》
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
賢治は、単刀直入に本音を語ることを躊躇う人であったのであろうか。己が命を削って創作した文学作品を「棄てるなり焼くなりどうでもしてくれ」といわずにはいられない父との相克の歴史・・・自暴的にすら見える。賢治は本音を父に伝えたかったであろうに、肉親全員に同様の胸のうちを打ち明けられなかったのはなぜなのだろう。
東北砕石工場の技師で営業マンでもあった賢治はいつのまにか「処世術」を身に帯びてしまい、相手の気持ちに合わせてお話をしたのであろうか。それとも、賢治のシャイな性格が、ここに至っても出たのであろうか。それとも、父には謙っていわれたのでしょうか。それとも気弱になっていて、三様の云い方になってしまったのでしょうか。
父には蟠りが影響していたのではないか・・・と私は思う。
賢治の死後、発見された御遺書(東京の駿河台八幡旅館で1931年の書)から、なにかヒントが得られないか、
再度、引用させていただきます。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
『死を想う』宇治土公(うじとこ)三津子編 2003年初版 二玄社版によると、
《 賢治が肥料の販売のために上京したとき、賢治の大トランクの中の裏蓋のポケットに二通の遺書と「雨ニモマケズ」の書かれた手帳が残されていた。
遺書の一通は両親宛で、もう一通は弟や妹たちに宛てたものであった。
そのうち両親宛のものは次のようであった。
《
この一生の間どこのどんな子供も受けないような厚いご恩を
いただきながら、いつも我慢(ママ)でお心に背きとうとうこんなことになりました。
今生で万分一もついにお返しできませんでした。
ご恩はきっと次の生又その次の生でご報じいたしたいとそれのみを念願いたします。
どうかご信仰というのではなくてもお題目で私をお呼びだしください。そのお題目で絶えずおわび申しあげお答えいたします。
九月廿一日
賢治
父上様
母上様
》1931年(昭和6年9月21日付け 宮澤政次郎様・イチさま) 宛である。
弟妹への御遺書は以下の内容であった。
《
とうとう一生、何一つお役に立たず、ご心配、ご迷惑ばかり掛けてしまいました。
どうかこの我儘者をお赦しください。
賢治
清六様
しげ様
主計様
くに様
》
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
この御遺書から、賢治は輪廻のおもいを抱いていたことが窺える。また、ご両親宛では誤字(わがまま→我慢)が観られることで私は賢治の本心が窺えるのではないか、と考察する。
弟妹宛御遺書では、「我儘」と正確に書き記した賢治であるので、ワガママの漢字を知らなぬわけでは無い筈。ではなぜ、御両親宛では誤字を書いてしまったのであろうか。
ご両親宛として書きだした賢治は、「どんな子供も受けないような厚いご恩を・・・」としたためた途端に、親御さまと対座をしたことで、込上げてくる気持ちから滂沱の涙となったのではなかったか。
賢治の脳裏には緊張もはしり当時が蘇る。蘇るままに漢字のワガママを単純に間違えた説が考察されよう。
もうひとつの説は、慢心の慢を書いてしまったことは、賢治の深層心理には日ごろから御両親に対して増上慢、慢心で接してきたことを深く詫びるおもい、申し訳なかったとの情念が意識下があったのではなかろうか。その気持ちが遺書を書き出した途端に働いての誤字としてしまった説である。つまり賢治はご両親に対して反省の思念が心を占めていたこと。増上慢・慢心の「慢」と書いてしまったとみる説である。
賢治は創作品の始末依頼のときに、父には、宗教対峙時の増長慢ぶりであったことから侘びようとしても詫びきれずにきてしまい、「棄てるなり燃やすなり・・・」、との台詞がでてしまい、詫びたい気持ちが反語的にでてしまったのではなかったか?
我慢となっているのは、誤字ではあるが誤字ではないと考察する。
この増上慢、慢心の慢を当ててしまった賢治の誠意・猛省心は、賢治自身が書いた詩「病相」からも類推できるかと思う。
『宮沢賢治詩集』1997.2月・岩波書店刊、「肺炎詩篇」より引用。
病相
われのみみちにたゞしきと
ちちのいかりをあざわらひ
ははのなげきをさげずみて
さこそは得つるやまひゆゑ
こゑはむなしく息あへぎ
春は来れども日に三たび
あせうちながしのたうてば
すがたばかりは録されし
下品(げほん)ざんげのさまなせり
―――――――――――――――――――――――――――
※下品ざんげ・・・・意味を以下にしめす。インターネットの『釈迦弥陀は慈悲の父母 www.biwa.ne.jp/~takahara/kousan08Z.htm 』さまから引用させていただきました。感謝。
《 (語句)
真心=真実信心
三品=上品・中品・下品
功徳をどれだけ積んでいるか、あるいは仏教的な能力・素質によって、人を三
段階にわけて上品・中品・下品という。
三品の懺悔=善導大師は「懺悔に三品ある。上品の懺悔は、毛穴から血が流れ、眼か
ら血が出るほどに深く懺悔する。中品の懺悔は、全身の毛穴から熱い汗が流れ
だし、眼から血が流れる。下品の懺悔は、全身が熱くなり、眼から涙が出る。 これら三品の人たちは涅槃に導びかれる善根をそなえた人たちである。しかし、
心の底から懺悔もできない凡夫であっても、真実信心が徹底している者は、三
品の懺悔する人と同じである」といわれている。
宗師=善導大師 》
※私が上記の引用文を一部ゴジック体文字にした。そのゴジックに注目を頂きたいと思う。
賢治はヒドリノトキハナミダヲナガシ・・の「泪を流し」、と関係していると読み解けないでしょうか?
葬儀のヒドリノトキ、別れのときに、ご両親におわびを申し上げたい気持ち。永訣の時に、下品のざんげをしてお別れしたい。涙を流してしまうのであるという解釈である。
※さて、私は、「下品のざんげ」が理解ができずに、調べていると、浄土真宗の経文であることをしった。賢治は幼い時分から浄土宗のお教えに浸ってきたことであり、改宗はしたが、浄土真宗の影響下にあることをうれしくおもった。これは厳父との繋がりの証でもある。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^善導大師とは:善導(ぜんどう、ピンイン:sh`an-d~ao)は、中国浄土教(中国浄土宗)の僧である。「称名念仏」を中心とする浄土思想を確立する。姓は朱氏。「終南大師」、「光明寺の和尚」とも呼ばれる。浄土宗では、「浄土五祖[6]」の第三祖とされる。
浄土真宗では、七高僧の第五祖とされ「善導大師」・「善導和尚」と尊称される。・・・・・・・法然上人の師。 (出典:フリー百科事典『ウィキペディア』より)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ヒドリの解釈で取材
私は岩手県出身の都教職員に、ヒドリ、とだけ言われた場合、何をイメージしますか、と質問した。以下はその回答。
(イ)、ヒドリといわれたら、結婚式の日。・・・ナミダヲナガシ。
(ロ)、ヒドリといわれたら、田植えの日。・・・ナミダヲナガシ。
(ハ)、ヒドリといわれたら、葬儀の日。・・・・ナミダヲナガシ。
※回答ののちに、ヒデリvsヒドリの説があることをお伝えした。すると先生は子供時代「ヒデリ」で教わりました。そのヒドリのことは初耳ですと、驚いておられた。
私は、詩雨ニモマケズの文脈から、どのヒドリ説がピッタリかを考慮して拝聴した。
(イ)の結婚式のナミダは、嬉しナミダ。感激のナミダ。
(ロ)の田植えのヒドリは、農村での助け合い互助作業の「結」制度であろう。今日、その結が存続しているかは疑問はあるが、賢治が詩創作時は昭和のはじめ頃であり、「結」制度は存続していたと思われる。田植え時のナミダヲナガシは、考えられなくもないかも・・・嬉しいナミダに分類できよう。
(ハ)の葬儀(はふり)の日のヒドリ=日取り。飢饉頻発の岩手において、
ヒドリノトキハナミダヲナガシた日は多かったと思われる。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
玄侑宗久氏のヒドリ説を『慈悲をめぐる心象スケッチ』の190頁から引用する。
《 ヒドリノトキハナミダヲナガシの「ヒドリ」について、次の「サムサ」との関連で「ヒデリ」の間違いではないか、という説もあるようだが、賢治がそんな間違いを起こすと思うのは大間違いである。私の手元には手帳そのものを復刻したものがあるのだが、文字の修正にも賢治のじつに厳密な性格が窺われる。当然「ヒドリ」は「日取り」、つまり人が亡くなったときに山伏が、当家とお寺を往復して葬儀の日取りを決める行為を指すと思える。
ひいては、人が亡くなったあとに山伏が来ることそのものを意味したのではないだろうか。「日取り」のために山伏がやってくると、家人の死がもはや確実という実感をもち、「ナミダヲナガシ」てしまうものなのである。 》
玄侑宗久氏は山伏を登場させてのヒドリ説である。
明治維新の廃仏稀釈(通称:神仏分離令)では、お寺様は存続があやうくなった。それで山伏はほぼ壊滅させられた。全国で30万人とも云われる山伏たちではなかったか。
日本人が培ってきた信仰の、すべてに生命が霊魂が宿る敬う心、大切にするこころ、日本天台の「山川草木悉有佛性」または「草木國土悉皆成佛」ではなかろうか。
欧米人にならアニミズムの思想で説明できるかもしれないが、もっと奥の深い信仰心である。岩にも、滝にも、樹木にも、胡瓜にも、蛇にも、宮沢賢治がかつて石ころ賢ちゃんとよばれ集めてきた石ころの一つ一つにも、いのちが宿っている信仰。天地万物に霊魂がやどるとみる日本の庶民信仰ではないだろうか。
それらは弾圧されて壊滅か、とおもってきた現代人にとっては、山伏の介在でヒドリを解釈する発想は浮かび難いことである。
賢治の生きた時代なら、地方では、まだまだ山伏はおられたということか。それらの習俗や伝承は、柳田國男の『遠野物語』を読んでみると、いろいろ息づいていたことが知れようが、玄侑宗久氏の山伏の登場で解釈されたことは想定外であり驚愕であった。
ブログ宮沢賢治〈雨ニモマケズ〉に新解釈の玄侑宗久氏(1)でお伝えしましたように玄侑宗久氏の《その新説・解説・洞察力には度肝を抜かされた。特に〈雨ニモマケズ〉には、革命がおきたかとおもったほどに驚いた。》
私は、松尾芭蕉の『おくのほそ道』行では、フクシマの三春藩を「箕張」と表記していたことから洞察し、「隠密?説」を述べたつもりであるが、主に竹製の箕はその時代も、農民の必需品であり、日々使用し身近に置いて大切に使った農具であり民具であった。身近な道具の箕を芭蕉は藩名に代用したことで意表を衝かれた思いがした。
当時の人は箕を家の門口に裏向きで立てることで「不幸」「忌引」を告知したと伝えられる。現代人からは想像もできぬ箕の使い方であるが、松尾芭蕉は三春藩に降って沸くであろう不幸に思いを馳せ、「箕張」と表記したのかもしれぬ。芭蕉は嫌疑をかけられることを避けるために箕張としただけではなく、三春藩(藩主は秋田公なので秋田さまとも呼ばれた・・・三春町歴史民俗資料館回答)への同情も手伝って使用したのであろうか、との見方もできるのかもしれない。否、「張」の漢字を用いたことには理由がある。張の文字は引っ張りの弓篇。弓をひっぱり・返せば、秋田公の命は長(永)らえよう、故に「張」の漢字を当てたことに留意されよ、と芭蕉は伝えてたかったのかもしれない。「張」の文字を左右に解体すると、芭蕉の暗号が読み解けるのかも。宮澤賢治の「ヒドリ」も謎解き的ではある。ゲーム感覚での解釈も必要なのかもしれない。
箕が各家庭にあった時代の日本では、大衆的な箕の利用の方法のひとつであろう。箕を裏向きにして、葬儀のヒドリを告知する仕方である。此の考察は、農業社会をしらなければ、解釈は出来にくいことである。玄侑宗久氏の着眼された山伏同様に、日本の歴史をしらなければ、山伏でヒドリを読み解くことは出来ないことである。
日本人のご先祖さまの習俗を、玄侑宗久氏は、時代を遡って、ヒドリを分析された。
玄侑宗久氏のもうひとつのヒドリ解釈がある。以下。
《・・・・あるいは葬儀のあとに、やはり山伏が、死者を出した家は火も汚れたことからと、竈の灰をきれいに持ち去る「火取り」のことかもしれない。そうして決定的な処置がなされるとき、人はもっと深く「ナミダヲナガシ」てしまうものだろうか。いずれにしてもここに書かれた言葉は、賢治が心の奥底から絞り出した言葉である。》と、玄侑宗久氏は多義に解釈されたと思う。このことは、賢治の狙った複数の解釈をしてほしいことに叶うことになると思う。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
私は、賢治が「ヒドリ」に托した多義性を考察してきたなかで、やはり、玄侑宗久氏の解釈は説得性がある、と深い感銘を受けているのである。
私の取材からも「葬儀のヒドリ(日取り)」が一番妥当性があるのでは、と思う。
以下に私のヒデリの解釈を陳述します。
(1)説・・・絵『無題「赤玉」』のヒドリ説である。
赤玉は自己犠牲を描いた絵、と解釈し、それは、はふりの日取りでヒドリ・・・・と解釈。
僭越なことですが、玄侑宗久氏は山伏の登場によるヒデリ解釈をされておられる。
ヒデリ=葬儀の日取り。
私の場合は賢治が描いた絵『無題「赤玉」』とヒドリガモ から、ハフリの日と解釈し、結論だけは、おなじになったかと、思います。
2013年の夏、東京の世田谷文学館で賢治展が開かれた。そこで、展示解説書『宮沢賢治・詩と絵の宇宙 雨ニモマケズ』を求めてきたが、そこに収められた絵からもインスピレーションを得た。もっとも、原画を見させていただいての収穫であり、原画に対面が出来なかったならば得られない解釈であった。
展示解説書は
監修:天沢退二郎。アート・ベンチャー・オフィスショウの発行である。絵は林風舎代表取締役宮沢和樹氏のご協力で展示され掲載がされていた。
本物の絵を見させていただいたことに感謝を申し上げます。
賢治の詩の多義性を陳述してゆく上で、賢治の描いた絵『無題(赤玉)』に触れさせていただきます。展示解説書に掲載された絵のページを、見開きで見て頂きたい。その絵をみつつ、ヒドリの解釈をさせていただきたいと思います。
どうか、宮沢和樹さま、お許しねがいます。
以下は展示解説書の見開きページです。▼

展示解説書の38と39ページの見開頁の左側は『日輪と山』と呼ばれる絵。
右側頁の左上部には絵『無題(赤玉)』、右下には絵『無題(ケミカル)ガーデン』。
私は、『無題(赤玉)』の絵に強く惹きつけられた。
原画でないと感得できないかもしれないが、この絵には賢治が大循環の彼方へ微塵に砕け散る姿を描いたように見える。「大循環の風の中に溶けこんでしまいたい」と、賢治がつぶやいた心象風景ではなかろうか、との思いがしてくる。
或いは、絵『無題(赤玉)』は、 サムサノナツハオロオロアルキとうたわれたように渇望の太陽にもみえる。が、そうすると太陽は三つとなる。太陽は、左隣頁に絵『日輪と山』が紹介されている。その日輪の絵はひとつの太陽が描かれている。ゆえに賢治は三つも太陽を描いたとは思えない。太陽が三つでは、今度はヒデリで飢饉となろうから、火雲がおこり、農民にとっては凶雲で受け入れられないこととなる。
(※宮沢清六著『兄のトランク』の220ページの詩「老農」に 火雲・・とある。これは日照の雲とのこと。)
飢饉ともなると、やはり、賢治と妹のトシはそれぞれが自己献身するおもいを強めて灼かれこともいとわぬこおではなかったか。その象徴の赤玉三つを描いたと見てとれないだろうか。「みんなの幸せのためなら僕の体なんか百ぺん灼いてもかまわない・・・」と作品『銀河鉄道の夜』にあることから、百には足りないが三ケの赤玉として、多い回数を表現したのかもしれない。赤玉の絵の背景には大循環の宇宙の彼方へ微塵に砕け散る細々した透明性のある物が浮遊しているようにみてとれる・・・。
ここで、谷川徹三著「宮沢賢治」から以下に引用する。
《 辺遠に居ても常に一地方の存在から脱却する内にコスモスを持たない者はどんな文化の中心に居ても常に一地方的存在として存在する。岩手県花巻の詩人宮沢賢治は稀に見る此のコスモスの所持者であった。彼の謂ふところのイーハトヴは即ち彼の内の一宇宙を通しての世界全般の事であった。》(出典:文芸読本『宮沢賢治』 昭和55年5月20日・河出書房新社刊)。
哲学者谷川徹三の言辞をかりるなら、絵『無題(赤玉)』は、まさにコスモス(宇宙)を描いたのである。
「僕のからだなんか、百ぺん灼いてもかまわない。」。此の世を幸せにしようとして百ぺんでも身を灼きつくす熱情の賢治。ついには赤玉になって法華経の教えを実践する純粋な生き様の賢治とトシの姿ではないだろうか。
私は原画を暫く拝見していると、そのような思いに至った。
賢治の作品にでてくる「みんなの幸いのためならば僕のからだなんか、百ぺん灼いてもかまわない。・・・」、賢治の願いであったと火の玉になる、と捉える。
私は絵『無題(赤玉)』からハフリの日=ヒドリと解釈した。その解釈になくてはならぬ絵と思っている。
はふり=自己犠牲の火=ヒドリ=日取り・・・・と解釈する。
玄侑宗久氏著『慈悲をめぐる心象スケッチ』の212ページには《 実際賢治にとって冷夏は、そうして命を賭けたくなるほど辛いことだったに違いない。岩手では特に初夏、稲の幼穂分化の時期に「やませ」と呼ばれる冷たい北東寄りの風が吹くことが多い。霧雨を含んだその冷たい風を浴びると、八月になって穂は出るもののまったく稔らない。凶作風とか餓死風と呼ばれる所以である。
賢治が終生追い続けたテーマの如き自己犠牲がここで顔をだす。・・・後略・・・・・》
玄侑氏は「賢治が終生追い続けたテーマの如き自己犠牲」と把握されておられた。私も、賢治は自己犠牲で此の世を幸せの地にしようと労力を惜しまぬ人であったと認識する。そのために、賢治はいのちさえも捧げ、宇宙へ微塵となって飛び散ろうと、法華経のお教えを遂行したのではなかったか。
そのイメージを描いた絵が『無題(赤玉)』ではなかったか、と思う。世田谷文学館に数度でかけて、食い入るように見詰めてきた結論である。
赤玉の絵の背景には微細な透明性のある物物が描かれていた。透明の物は何の片片であろうか。私はハリであろうと観た。これは原画を見ていただかないことには感じ取れないかと思う。印刷物ではこの細密に描かれたハリをシャープに写し取るのは難しいようだ。微塵に砕けた姿の片片。
私は、花巻の賢治記念館には岩手山登山の帰りに寄らしていただいたきりで、残念ながら1回しかお訪ねしていない。記念館には原画が展示されることがあろうから、花巻温泉に泊まってゆったりした時間で鑑賞したい絵ではないだろうか。
それらの片片は賢治のいうハリであろうとみた。ハリとは、《玻璃/玻瓈/頗梨》のことである。《(梵)sphaṭikāの音写》で 仏教では、七宝の一ともいわれている。
絵に描かれた赤玉は、賢治と妹トシの自己献身の姿を描いているとみる。百ぺん灼いて、の熱情が三ケの赤玉になったとイメージする。
その赤玉になる時が、自己犠牲の日でヒドリノトキであると考察する。
そのヒドリの時は、ご両親も弟妹も、ナミダヲナガシとなろう。
私は、肉親との別れで、ナミダヲナガスばかりを考察するのではない。
岩手を度々襲う飢饉で亡くなる人々のハフリ(葬儀)のとき、つまり、ヒドリノトキハナミダヲナガシたのではなかろうか。
葬儀のヒドリのトキとは、農民に尽くした賢治ならば、ナミダヲナガシと解釈するのである。ヒドリは誰の日取り、葬儀であるのであろうか。・・・賢治自身のヒドリ、トシの日取り、或いは農民の日取り・・・も考えられると思う。、
多義的に解釈をできるようにヒデリの文字に潜ませられているのではないでしょうか。
(2)説・・・ヒドリはヒドリガモの説。ヒドリガモの緋色は自己犠牲の色を表す。自己犠牲の象徴色と捉える。
ヒドリノトキハナミダヲナガシは、ヒドリはヒドリガモが飛来すると、連想すること。
ヒドリの頭は緋色である。探鳥会でヒドリガモを見つけた場合、あそこにヒドリがいるぞ、と「ガモ」は省略して指差すことが多い。
たとえば、「キンクロがいるぞ・・」といえば、キンクロハジロガモを指す。キンクロと略称で呼ぶようなことである。
ここでは、ヒドリガモをヒドリと呼ぶことを前提に(2)説を陳述したい。
ヒドリは頭部は緋色であることからヒドリガモと命名されたといわれるが、緋色は火の色ともみられよう。私たちは赤色と一口で言われるが、具体的にアカ色を指定するとなると、色のグラデーションを見れとお分かりのように、様々のアカ色がある。賢治は灼いてもかまわぬ犠牲精神旺盛。自己献身、自己犠牲の人。もし、灼かれた場合の色は火の色となる。燃焼温度でみてゆくなら、橙色や朱色や深紅色や暗赤色などに変化してゆく。そのときの炎の火の色であり、その迫真の魂が赤色にも緋色にもなるとみる。
▲写真は ヒドリガモ

写真は、今年、河口湖へ合宿ででかけたおりに湖畔で撮影。陳述のために使わせていただきます。感謝。
賢治はヒドリの色の如くに緋の色や火の色になり火の玉となって献身人生を選びとった。自己犠牲をモットーに生きた人ではなかっただろうか。
ついには大循環の風に乗る。宇宙へ微塵に飛び散る、死、別れを予想しておったのではなかったか。そのヒドリノトキハナミダヲナガシなのである、と解釈する。
永訣のトキノナミダヲナガシであったと解釈できるのではないだろうか。
賢治は自己犠牲精神で、「みんなの幸いのためならば僕のからだなんか、百ぺん灼いてもかまわない。」と、作品『銀河鉄道の夜』に記述している。その生き方、精神を持っていたのである。
ヒドリガモから、百ぺんも灼いてもかまわない、へと私は連想をしていった。灼ける色は火の色であり、火の玉になって自己犠牲のイメージを思う。火の色は緋の色であることを考えると、ヒドリノトキハナミダヲナガシとなるのではないだろうか。
賢治の御遺言を転載する。以下。
父に「『國譯妙法蓮華經』を千部印刷して、知己友人に頒けて下さい。 校正は北向さんにお願いして下さい。本の表紙は赤に・・・。お経のうしろには 『私の一生のしごとは、このお経をあなたのお手もとにお届けすることでした。 あなたが、仏さまの心にふれて、一番よい正しい道に入られますように』と いうことを書いて下さい。」と、花巻弁で言われたと伝えられる。
この御遺言によれば表紙の色は赤色に拘った賢治であることがしれましょう。
なぜ赤色か。この色はとても大事なポイントと思う。
「朱色」としてくださいとする御遺言も伝えられるのであるが、どちらが正しいのであろうか。私は火の色と解釈するので、アカ色、でも朱色でも、どちらも正しい色と私は観る。みんなの幸せのためなら、僕の体なんか百ぺん灼いてもかまわない、とする賢治の覚悟の色である。赤い色、緋の色、朱の色、真紅の色等々、火の色であれば、燃える色、灼ける色であるなら良いのではないかと思う。百ぺん灼かれて熱くて熱くて涙を流す、のではない。百ぺん灼かれようとも、とする自己犠牲の象徴がアカ色なのである。火の色で貢献したトキハナミダヲナガス・・・と解釈できるのである。
「邪教」の父に託した遺言。父は誠意をもって『國譯妙法蓮華經』を火の色の表紙で出版したのである。
(3)説・・・ヒドリは渡り鳥のヒドリガモの説、と解釈する。ヒドリガモが飛来する頃には、「白い大きな鳥」も飛来すると賢治は連想したに違いない。その白い鳥は妹トシの姿であった。故に、次のように解釈する。
ヒドリ(鴨)ノトキハナミダヲナガシ。
なぜ、ヒドリガモでナミダヲナガスのであろうか。
賢治のトシへの思いは、詩「松の針」に吐露されている。一部、引用する。以下
・・・前略・・・
鳥のやうに栗鼠(りす)のやうに
おまへは林をしたつてゐた
どんなにわたくしがうらやましかつたらう
ああけふのうちにとほくへさらうとするいもうとよ
ほんたうにおまへはひとりでいかうとするか
わたくしにいつしよに行けとたのんでくれ
泣いてわたくしにさう言つてくれ
おまへの頬の けれども
なんといふけふのうつくしさよ
わたくしは緑のかやのうへにも
この新鮮な松のえだをおかう
いまに雫もおちるだらうし
そら
さはやかな
terpentine (ターペンテイン)の匂もするだらう
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
トシは11月27日に亡くなった。トシは飛んで行って(逝って)しまったと、賢治は思ってもいたようだ。吾がもとへ戻ってきてほしい思いから、賢治は鳥になぞらえて詩「白い鳥」を創作した。一部、詩「白い鳥」から引用する。以下。
(日本絵巻のそらの群青や
天末のturquoisはめづらしくないが
あんな大きな心相の
光の環は風景の中にすくない)
二疋の大きな白い鳥が
鋭くかな〔しく〕啼きかはしながら
しめつた朝の日光を飛んでゐる
それはわたくしのいもうとだ
死んだわたくしのいもうとだ
兄が来たのであんなにかなしく啼いてゐる・・・・・
「白い鳥」の詩で、トシは「白い大きな鳥」になって悲しく啼いている、とうたわれた。詩の文脈から、白鳥ではないようだ。大きな鳥となると、私には白鳥がイメージされるのだが・・、文脈から無理と判断する。それでも、諦め切れずに考えて考えて、留鳥として考察してみると、文脈をクリアーできそうに思えた。それで解釈してゆくと、留鳥ではいつでも逢えることになり、不自然さが残る。ということから、傷ついて遠くへ飛べなくなった白い鳥なのかもしれないと考えた。傷が癒えて遥か遠くへ渡ってしまった野鳥の白い鳥と解釈をしてみた。それでも、その「大きな白い鳥」の名前を私は特定ができないでいる。が、北上川に飛んでくる渡り鳥の仲間かもしれない、と想像してみた。そうしてみると、ヒドリが解釈できる。
野鳥のヒドリガモがイギリス海岸に現れた時候には、その白い大きな鳥も渡ってくるとしよう。賢治はその白い鳥のトシと出逢えることになるのではなかろうか。
ヒドリノトキとは、妹トシに出逢える日としてみた。その白い鳥とはわずかの期間の出逢いであり、トシとの再会である。トシと再会のトキハナミダヲナガシとなろう。
賢治のいのちがまさに朽ち果てようとしている時、トシとの再会を、おもわなかったと断定できようか。トシと逢いたいと祈っていたのではなかろうか。大きな白い鳥の姿に変身してしまったトシと出逢いたならば、ナミダを流すだろう。ヒドリガモは白い大きな鳥の呼び水的な、案内役的な役割をもつ渡り鳥と考察する。再会のヒドリ説である。
(4)説・・・一人ノトキハナミダヲナガシ説。この解釈はすでに小倉豊文広島大学教授が解釈されておられる。私は捨てがたい解釈と思っている。ヒトリ=ヒドリと解釈しての一人のときはナミダヲナガシ・・・である。賢治がトをドと間違えたとは
思わない立場での私は
一人=独り=ヒドリ、と解釈できるのではないだろうか。
北国の人なら、独り=ヒドリ・・・で、通じ合えるのではなかろうか。小倉氏は、賢治の書き間違いのド説であったかと思われるが、私はドであっても一人・独りと、解釈ができるのである。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
奇しくもトシさんの御命日に、私は雨ニモマケズのヒドリ解釈最終回を発信する。半年ほど時間がかかった。お陰で再読の機会を頂いた。感謝もうしあげます。
賢治さん、トシさんのご冥福をお祈りし合掌いたします。
2013年11月27日
永訣の朝
けふのうちに
とほくへいつてしまふわたくしのいもうとよ
みぞれがふつておもてはへんにあかるいのだ
(あめゆじゆとてちてけんじゃ)
うすあかるくいっさう陰惨な雲から
みぞれはびちよびちよふつてくる
(あめゆじゆとてちてけんじゃ)
A/Mに捧げる・・・y o
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
考察時の資料は、後日、(29)で発信したいとおもっています。
ブログ宮沢賢治《雨ニモマケズ》に新解釈の玄侑宗久氏(29)資料考察編へ続く^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
――――――――――ヒドリの解釈について(3)――――――――――
昭和八年(1933年)九月十九日、賢治は朝から気分が良かった。賢治は病床からおきあがり、遠くから聞えてくる鉦や太鼓の音、神輿を担ぐわっしょい、わっしょいの掛け声に耳を傾けた。
窓から差し込む光は一輪挿しの花を照らしていた。青い花びら。賢治は机の前へゆき正座をした。詠んだばかりの短歌を今一度吟味し反芻した。青色が好きであるが、この頃はやけにアカ色に惹かれる。身を灼き尽くして赤色に、朱色に、緋色に燃えて燃えて、身を百ぺんでも灼きつくそうとも・・・・献身したい・・・・。
硯を引き寄せ墨をゆっくりゆっくり磨った。半紙に向き合い深呼吸をした。三十七年めの産土の祭り・・・・豊作を祝う花巻の祭りの、賑わいの風が頬にやさしい。・・・筆を執った。書き終えたら、門口へでてお神輿を御迎えしよう・・・。
賢治は歌を二首したためた。
この二首は後世、賢治の絶筆と評される。
方十里 稗貫のみかも 稲熟れて み祭三日 そらはれわたる
病(いたつき)のゆゑにもくちんいのちなり みのりに棄てば うれしからまし
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
辞世の一首には、多義性があると解読されている。
賢治のカラダは衰弱こそしているが、知能を働かせて辞世の歌に多義性をもたせた。
賢治は短歌文化の伝統にのっとり、修辞技法を駆使、本音を秘匿させた。
この秘匿に賢治の用意周到ぶりが窺えるのではなかろうか。
病(いたつき)のゆゑにもくちんいのちなり みのりに棄てばうれしからまし
この短歌は和歌のように平仮名を多用していた。詩雨ニモマケズではカタカナ文字を多用した。
どちらも表音文字の多用である。表意文字の漢字よりは本音を秘すには好都合な表音文字である。
賢治は病の漢字に丁寧に「いたつき」とルビを振った。よほど歌道を探究しておらなければ、いたつきとは読めない。賢治はいたつきと読んでほしくてルビをふった。あたかも病床を着けられたような二年に及ぶ日々。それで「いたつき」なのだ。
この思いをこめて漢字のいたつきで始める短歌とした。
万葉集でよく見かける枕詞のように、いたつきを枕詞にしたかったのであろうか。
いたつきとして挽歌としたかったのであろうか。
漢字は「病」と「棄」のふた文字のみ使用の歌。その漢字の二文字を並べると、病棄(びょうき)となる。
「病棄」の思いを強調したかった賢治であったのであろう。
賢治は病気がなければ、健康体であったならば、これほどまでに此の世、あの世を追究をしてはこなかったであろう。健康であったならば、別の職業に就いてたかもしれない。そうなると、詩雨ニモマケズは生まれることはなかった。いたつきに苦しめられたからこそ法華経のお教えを深く共感していった賢治。永遠の生命を求めてきたのではなかったか。此の世の幸せを追求してきたのではなかったか。童話作家になったのではなかったか。
東へ西へ南へ北へ行ッテ、行ッテ、手を差しのべる生き方。
書斎の学問ではなく実践の学問を追求してきた賢治。
そのような賢治は病床に臥し実践が出来難い独りのときは、ヒドリノトキハナミダヲナガシ、涙が零れてきたのであろう。
東北は寒いことから、口を大きくあげね。「独り」を「ヒドリ」と濁って聞えんか。
ヒドリノトキハナミダヲナガシ、
そのような解釈も実は、してほしいことからヒドリとしたのではないだろうか。弱気にもなってもいた賢治は「ヒドリ」にいろいろと托していたようにも思えてならない。
辞世の短歌に「病のゆゑにもくちん・・・」と詠んでいることを吟味したい。
吾がいのちは、病だけではなく自己献身で「も」くちん、と詠んだ。私は、このことに注目してほしいと思う。
・・・・のゆゑにも・・・と、「も」を詠みこんでいることを見落とされないでほしい。
強気の自己犠牲精神と病で弱気になってナミダを流す賢治の短歌。
ご両親には、「死」と明言するようなことをせずに「朽ちる」、と表現する優しさを持つ賢治。朽ちることは、他の生物の肥やしになり、循環してゆく姿も滲ませて作歌された。
さて、辞世の短歌いたつきのゆゑにもくちん・・・を解釈しておきたい。多義に詠まれていた。以下。
解釈1:私は病で間もなく樹木が朽ちるようになるが、今年の秋は“稔り” “実り”であったと伝え聞く。農民のお役に立てたかと思うと嬉しいことです。
解釈2: ミノリとは“御法”と漢字で表す。「ミノリ」と表記した賢治の拘りが秘められた歌と観る。
御法とは法華経を指す。自分は病でまもなく朽ち果てるだろうが、
法華経に吾がイノチを棄てる(捧げる)ことでもあり、本望でうれしいことです。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
賢治は、自分の亡き後の作品始末について、父、母、弟の清六に頼みこんでいた。
その内容は三人三様で驚くばかりである。以下にしめす。
『新文芸読本 宮澤賢治』平成2年(1990)9月20日、河出書房新社刊には「宮沢賢治と音楽・・・・林光・山口昌男 」対談が特集されてあった。引用する。
《 林―――晩年、賢治が死に際に父親には「自分の書いたものは何の価値もないの だから、捨てるなり焼くなりどうでもしてくれ」と言って、お母さんには「これは仏様の教えを書いた大事なものだからしまっておいてくれ」と言って、弟には「これはお前にやるから、どこかで出版したいと言ってきたら、出版させてやってくれ」と言ったと云う。このふりわけというか、それはやっぱり大変な人だ。
山口――近代日本の芸術家の中で、パフォーマンス能力が抜群にあった人じゃないかと思うね。国柱会で奉仕しながら、書きためた五千枚をトランクに詰めて東京市中を走り回っているんですからね。これは想像を絶する。 》
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
賢治は、単刀直入に本音を語ることを躊躇う人であったのであろうか。己が命を削って創作した文学作品を「棄てるなり焼くなりどうでもしてくれ」といわずにはいられない父との相克の歴史・・・自暴的にすら見える。賢治は本音を父に伝えたかったであろうに、肉親全員に同様の胸のうちを打ち明けられなかったのはなぜなのだろう。
東北砕石工場の技師で営業マンでもあった賢治はいつのまにか「処世術」を身に帯びてしまい、相手の気持ちに合わせてお話をしたのであろうか。それとも、賢治のシャイな性格が、ここに至っても出たのであろうか。それとも、父には謙っていわれたのでしょうか。それとも気弱になっていて、三様の云い方になってしまったのでしょうか。
父には蟠りが影響していたのではないか・・・と私は思う。
賢治の死後、発見された御遺書(東京の駿河台八幡旅館で1931年の書)から、なにかヒントが得られないか、
再度、引用させていただきます。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
『死を想う』宇治土公(うじとこ)三津子編 2003年初版 二玄社版によると、
《 賢治が肥料の販売のために上京したとき、賢治の大トランクの中の裏蓋のポケットに二通の遺書と「雨ニモマケズ」の書かれた手帳が残されていた。
遺書の一通は両親宛で、もう一通は弟や妹たちに宛てたものであった。
そのうち両親宛のものは次のようであった。
《
この一生の間どこのどんな子供も受けないような厚いご恩を
いただきながら、いつも我慢(ママ)でお心に背きとうとうこんなことになりました。
今生で万分一もついにお返しできませんでした。
ご恩はきっと次の生又その次の生でご報じいたしたいとそれのみを念願いたします。
どうかご信仰というのではなくてもお題目で私をお呼びだしください。そのお題目で絶えずおわび申しあげお答えいたします。
九月廿一日
賢治
父上様
母上様
》1931年(昭和6年9月21日付け 宮澤政次郎様・イチさま) 宛である。
弟妹への御遺書は以下の内容であった。
《
とうとう一生、何一つお役に立たず、ご心配、ご迷惑ばかり掛けてしまいました。
どうかこの我儘者をお赦しください。
賢治
清六様
しげ様
主計様
くに様
》
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
この御遺書から、賢治は輪廻のおもいを抱いていたことが窺える。また、ご両親宛では誤字(わがまま→我慢)が観られることで私は賢治の本心が窺えるのではないか、と考察する。
弟妹宛御遺書では、「我儘」と正確に書き記した賢治であるので、ワガママの漢字を知らなぬわけでは無い筈。ではなぜ、御両親宛では誤字を書いてしまったのであろうか。
ご両親宛として書きだした賢治は、「どんな子供も受けないような厚いご恩を・・・」としたためた途端に、親御さまと対座をしたことで、込上げてくる気持ちから滂沱の涙となったのではなかったか。
賢治の脳裏には緊張もはしり当時が蘇る。蘇るままに漢字のワガママを単純に間違えた説が考察されよう。
もうひとつの説は、慢心の慢を書いてしまったことは、賢治の深層心理には日ごろから御両親に対して増上慢、慢心で接してきたことを深く詫びるおもい、申し訳なかったとの情念が意識下があったのではなかろうか。その気持ちが遺書を書き出した途端に働いての誤字としてしまった説である。つまり賢治はご両親に対して反省の思念が心を占めていたこと。増上慢・慢心の「慢」と書いてしまったとみる説である。
賢治は創作品の始末依頼のときに、父には、宗教対峙時の増長慢ぶりであったことから侘びようとしても詫びきれずにきてしまい、「棄てるなり燃やすなり・・・」、との台詞がでてしまい、詫びたい気持ちが反語的にでてしまったのではなかったか?
我慢となっているのは、誤字ではあるが誤字ではないと考察する。
この増上慢、慢心の慢を当ててしまった賢治の誠意・猛省心は、賢治自身が書いた詩「病相」からも類推できるかと思う。
『宮沢賢治詩集』1997.2月・岩波書店刊、「肺炎詩篇」より引用。
病相
われのみみちにたゞしきと
ちちのいかりをあざわらひ
ははのなげきをさげずみて
さこそは得つるやまひゆゑ
こゑはむなしく息あへぎ
春は来れども日に三たび
あせうちながしのたうてば
すがたばかりは録されし
下品(げほん)ざんげのさまなせり
―――――――――――――――――――――――――――
※下品ざんげ・・・・意味を以下にしめす。インターネットの『釈迦弥陀は慈悲の父母 www.biwa.ne.jp/~takahara/kousan08Z.htm 』さまから引用させていただきました。感謝。
《 (語句)
真心=真実信心
三品=上品・中品・下品
功徳をどれだけ積んでいるか、あるいは仏教的な能力・素質によって、人を三
段階にわけて上品・中品・下品という。
三品の懺悔=善導大師は「懺悔に三品ある。上品の懺悔は、毛穴から血が流れ、眼か
ら血が出るほどに深く懺悔する。中品の懺悔は、全身の毛穴から熱い汗が流れ
だし、眼から血が流れる。下品の懺悔は、全身が熱くなり、眼から涙が出る。 これら三品の人たちは涅槃に導びかれる善根をそなえた人たちである。しかし、
心の底から懺悔もできない凡夫であっても、真実信心が徹底している者は、三
品の懺悔する人と同じである」といわれている。
宗師=善導大師 》
※私が上記の引用文を一部ゴジック体文字にした。そのゴジックに注目を頂きたいと思う。
賢治はヒドリノトキハナミダヲナガシ・・の「泪を流し」、と関係していると読み解けないでしょうか?
葬儀のヒドリノトキ、別れのときに、ご両親におわびを申し上げたい気持ち。永訣の時に、下品のざんげをしてお別れしたい。涙を流してしまうのであるという解釈である。
※さて、私は、「下品のざんげ」が理解ができずに、調べていると、浄土真宗の経文であることをしった。賢治は幼い時分から浄土宗のお教えに浸ってきたことであり、改宗はしたが、浄土真宗の影響下にあることをうれしくおもった。これは厳父との繋がりの証でもある。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^善導大師とは:善導(ぜんどう、ピンイン:sh`an-d~ao)は、中国浄土教(中国浄土宗)の僧である。「称名念仏」を中心とする浄土思想を確立する。姓は朱氏。「終南大師」、「光明寺の和尚」とも呼ばれる。浄土宗では、「浄土五祖[6]」の第三祖とされる。
浄土真宗では、七高僧の第五祖とされ「善導大師」・「善導和尚」と尊称される。・・・・・・・法然上人の師。 (出典:フリー百科事典『ウィキペディア』より)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ヒドリの解釈で取材
私は岩手県出身の都教職員に、ヒドリ、とだけ言われた場合、何をイメージしますか、と質問した。以下はその回答。
(イ)、ヒドリといわれたら、結婚式の日。・・・ナミダヲナガシ。
(ロ)、ヒドリといわれたら、田植えの日。・・・ナミダヲナガシ。
(ハ)、ヒドリといわれたら、葬儀の日。・・・・ナミダヲナガシ。
※回答ののちに、ヒデリvsヒドリの説があることをお伝えした。すると先生は子供時代「ヒデリ」で教わりました。そのヒドリのことは初耳ですと、驚いておられた。
私は、詩雨ニモマケズの文脈から、どのヒドリ説がピッタリかを考慮して拝聴した。
(イ)の結婚式のナミダは、嬉しナミダ。感激のナミダ。
(ロ)の田植えのヒドリは、農村での助け合い互助作業の「結」制度であろう。今日、その結が存続しているかは疑問はあるが、賢治が詩創作時は昭和のはじめ頃であり、「結」制度は存続していたと思われる。田植え時のナミダヲナガシは、考えられなくもないかも・・・嬉しいナミダに分類できよう。
(ハ)の葬儀(はふり)の日のヒドリ=日取り。飢饉頻発の岩手において、
ヒドリノトキハナミダヲナガシた日は多かったと思われる。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
玄侑宗久氏のヒドリ説を『慈悲をめぐる心象スケッチ』の190頁から引用する。
《 ヒドリノトキハナミダヲナガシの「ヒドリ」について、次の「サムサ」との関連で「ヒデリ」の間違いではないか、という説もあるようだが、賢治がそんな間違いを起こすと思うのは大間違いである。私の手元には手帳そのものを復刻したものがあるのだが、文字の修正にも賢治のじつに厳密な性格が窺われる。当然「ヒドリ」は「日取り」、つまり人が亡くなったときに山伏が、当家とお寺を往復して葬儀の日取りを決める行為を指すと思える。
ひいては、人が亡くなったあとに山伏が来ることそのものを意味したのではないだろうか。「日取り」のために山伏がやってくると、家人の死がもはや確実という実感をもち、「ナミダヲナガシ」てしまうものなのである。 》
玄侑宗久氏は山伏を登場させてのヒドリ説である。
明治維新の廃仏稀釈(通称:神仏分離令)では、お寺様は存続があやうくなった。それで山伏はほぼ壊滅させられた。全国で30万人とも云われる山伏たちではなかったか。
日本人が培ってきた信仰の、すべてに生命が霊魂が宿る敬う心、大切にするこころ、日本天台の「山川草木悉有佛性」または「草木國土悉皆成佛」ではなかろうか。
欧米人にならアニミズムの思想で説明できるかもしれないが、もっと奥の深い信仰心である。岩にも、滝にも、樹木にも、胡瓜にも、蛇にも、宮沢賢治がかつて石ころ賢ちゃんとよばれ集めてきた石ころの一つ一つにも、いのちが宿っている信仰。天地万物に霊魂がやどるとみる日本の庶民信仰ではないだろうか。
それらは弾圧されて壊滅か、とおもってきた現代人にとっては、山伏の介在でヒドリを解釈する発想は浮かび難いことである。
賢治の生きた時代なら、地方では、まだまだ山伏はおられたということか。それらの習俗や伝承は、柳田國男の『遠野物語』を読んでみると、いろいろ息づいていたことが知れようが、玄侑宗久氏の山伏の登場で解釈されたことは想定外であり驚愕であった。
ブログ宮沢賢治〈雨ニモマケズ〉に新解釈の玄侑宗久氏(1)でお伝えしましたように玄侑宗久氏の《その新説・解説・洞察力には度肝を抜かされた。特に〈雨ニモマケズ〉には、革命がおきたかとおもったほどに驚いた。》
私は、松尾芭蕉の『おくのほそ道』行では、フクシマの三春藩を「箕張」と表記していたことから洞察し、「隠密?説」を述べたつもりであるが、主に竹製の箕はその時代も、農民の必需品であり、日々使用し身近に置いて大切に使った農具であり民具であった。身近な道具の箕を芭蕉は藩名に代用したことで意表を衝かれた思いがした。
当時の人は箕を家の門口に裏向きで立てることで「不幸」「忌引」を告知したと伝えられる。現代人からは想像もできぬ箕の使い方であるが、松尾芭蕉は三春藩に降って沸くであろう不幸に思いを馳せ、「箕張」と表記したのかもしれぬ。芭蕉は嫌疑をかけられることを避けるために箕張としただけではなく、三春藩(藩主は秋田公なので秋田さまとも呼ばれた・・・三春町歴史民俗資料館回答)への同情も手伝って使用したのであろうか、との見方もできるのかもしれない。否、「張」の漢字を用いたことには理由がある。張の文字は引っ張りの弓篇。弓をひっぱり・返せば、秋田公の命は長(永)らえよう、故に「張」の漢字を当てたことに留意されよ、と芭蕉は伝えてたかったのかもしれない。「張」の文字を左右に解体すると、芭蕉の暗号が読み解けるのかも。宮澤賢治の「ヒドリ」も謎解き的ではある。ゲーム感覚での解釈も必要なのかもしれない。
箕が各家庭にあった時代の日本では、大衆的な箕の利用の方法のひとつであろう。箕を裏向きにして、葬儀のヒドリを告知する仕方である。此の考察は、農業社会をしらなければ、解釈は出来にくいことである。玄侑宗久氏の着眼された山伏同様に、日本の歴史をしらなければ、山伏でヒドリを読み解くことは出来ないことである。
日本人のご先祖さまの習俗を、玄侑宗久氏は、時代を遡って、ヒドリを分析された。
玄侑宗久氏のもうひとつのヒドリ解釈がある。以下。
《・・・・あるいは葬儀のあとに、やはり山伏が、死者を出した家は火も汚れたことからと、竈の灰をきれいに持ち去る「火取り」のことかもしれない。そうして決定的な処置がなされるとき、人はもっと深く「ナミダヲナガシ」てしまうものだろうか。いずれにしてもここに書かれた言葉は、賢治が心の奥底から絞り出した言葉である。》と、玄侑宗久氏は多義に解釈されたと思う。このことは、賢治の狙った複数の解釈をしてほしいことに叶うことになると思う。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
私は、賢治が「ヒドリ」に托した多義性を考察してきたなかで、やはり、玄侑宗久氏の解釈は説得性がある、と深い感銘を受けているのである。
私の取材からも「葬儀のヒドリ(日取り)」が一番妥当性があるのでは、と思う。
以下に私のヒデリの解釈を陳述します。
(1)説・・・絵『無題「赤玉」』のヒドリ説である。
赤玉は自己犠牲を描いた絵、と解釈し、それは、はふりの日取りでヒドリ・・・・と解釈。
僭越なことですが、玄侑宗久氏は山伏の登場によるヒデリ解釈をされておられる。
ヒデリ=葬儀の日取り。
私の場合は賢治が描いた絵『無題「赤玉」』とヒドリガモ から、ハフリの日と解釈し、結論だけは、おなじになったかと、思います。
2013年の夏、東京の世田谷文学館で賢治展が開かれた。そこで、展示解説書『宮沢賢治・詩と絵の宇宙 雨ニモマケズ』を求めてきたが、そこに収められた絵からもインスピレーションを得た。もっとも、原画を見させていただいての収穫であり、原画に対面が出来なかったならば得られない解釈であった。
展示解説書は
監修:天沢退二郎。アート・ベンチャー・オフィスショウの発行である。絵は林風舎代表取締役宮沢和樹氏のご協力で展示され掲載がされていた。
本物の絵を見させていただいたことに感謝を申し上げます。
賢治の詩の多義性を陳述してゆく上で、賢治の描いた絵『無題(赤玉)』に触れさせていただきます。展示解説書に掲載された絵のページを、見開きで見て頂きたい。その絵をみつつ、ヒドリの解釈をさせていただきたいと思います。
どうか、宮沢和樹さま、お許しねがいます。
以下は展示解説書の見開きページです。▼

展示解説書の38と39ページの見開頁の左側は『日輪と山』と呼ばれる絵。
右側頁の左上部には絵『無題(赤玉)』、右下には絵『無題(ケミカル)ガーデン』。
私は、『無題(赤玉)』の絵に強く惹きつけられた。
原画でないと感得できないかもしれないが、この絵には賢治が大循環の彼方へ微塵に砕け散る姿を描いたように見える。「大循環の風の中に溶けこんでしまいたい」と、賢治がつぶやいた心象風景ではなかろうか、との思いがしてくる。
或いは、絵『無題(赤玉)』は、 サムサノナツハオロオロアルキとうたわれたように渇望の太陽にもみえる。が、そうすると太陽は三つとなる。太陽は、左隣頁に絵『日輪と山』が紹介されている。その日輪の絵はひとつの太陽が描かれている。ゆえに賢治は三つも太陽を描いたとは思えない。太陽が三つでは、今度はヒデリで飢饉となろうから、火雲がおこり、農民にとっては凶雲で受け入れられないこととなる。
(※宮沢清六著『兄のトランク』の220ページの詩「老農」に 火雲・・とある。これは日照の雲とのこと。)
飢饉ともなると、やはり、賢治と妹のトシはそれぞれが自己献身するおもいを強めて灼かれこともいとわぬこおではなかったか。その象徴の赤玉三つを描いたと見てとれないだろうか。「みんなの幸せのためなら僕の体なんか百ぺん灼いてもかまわない・・・」と作品『銀河鉄道の夜』にあることから、百には足りないが三ケの赤玉として、多い回数を表現したのかもしれない。赤玉の絵の背景には大循環の宇宙の彼方へ微塵に砕け散る細々した透明性のある物が浮遊しているようにみてとれる・・・。
ここで、谷川徹三著「宮沢賢治」から以下に引用する。
《 辺遠に居ても常に一地方の存在から脱却する内にコスモスを持たない者はどんな文化の中心に居ても常に一地方的存在として存在する。岩手県花巻の詩人宮沢賢治は稀に見る此のコスモスの所持者であった。彼の謂ふところのイーハトヴは即ち彼の内の一宇宙を通しての世界全般の事であった。》(出典:文芸読本『宮沢賢治』 昭和55年5月20日・河出書房新社刊)。
哲学者谷川徹三の言辞をかりるなら、絵『無題(赤玉)』は、まさにコスモス(宇宙)を描いたのである。
「僕のからだなんか、百ぺん灼いてもかまわない。」。此の世を幸せにしようとして百ぺんでも身を灼きつくす熱情の賢治。ついには赤玉になって法華経の教えを実践する純粋な生き様の賢治とトシの姿ではないだろうか。
私は原画を暫く拝見していると、そのような思いに至った。
賢治の作品にでてくる「みんなの幸いのためならば僕のからだなんか、百ぺん灼いてもかまわない。・・・」、賢治の願いであったと火の玉になる、と捉える。
私は絵『無題(赤玉)』からハフリの日=ヒドリと解釈した。その解釈になくてはならぬ絵と思っている。
はふり=自己犠牲の火=ヒドリ=日取り・・・・と解釈する。
玄侑宗久氏著『慈悲をめぐる心象スケッチ』の212ページには《 実際賢治にとって冷夏は、そうして命を賭けたくなるほど辛いことだったに違いない。岩手では特に初夏、稲の幼穂分化の時期に「やませ」と呼ばれる冷たい北東寄りの風が吹くことが多い。霧雨を含んだその冷たい風を浴びると、八月になって穂は出るもののまったく稔らない。凶作風とか餓死風と呼ばれる所以である。
賢治が終生追い続けたテーマの如き自己犠牲がここで顔をだす。・・・後略・・・・・》
玄侑氏は「賢治が終生追い続けたテーマの如き自己犠牲」と把握されておられた。私も、賢治は自己犠牲で此の世を幸せの地にしようと労力を惜しまぬ人であったと認識する。そのために、賢治はいのちさえも捧げ、宇宙へ微塵となって飛び散ろうと、法華経のお教えを遂行したのではなかったか。
そのイメージを描いた絵が『無題(赤玉)』ではなかったか、と思う。世田谷文学館に数度でかけて、食い入るように見詰めてきた結論である。
赤玉の絵の背景には微細な透明性のある物物が描かれていた。透明の物は何の片片であろうか。私はハリであろうと観た。これは原画を見ていただかないことには感じ取れないかと思う。印刷物ではこの細密に描かれたハリをシャープに写し取るのは難しいようだ。微塵に砕けた姿の片片。
私は、花巻の賢治記念館には岩手山登山の帰りに寄らしていただいたきりで、残念ながら1回しかお訪ねしていない。記念館には原画が展示されることがあろうから、花巻温泉に泊まってゆったりした時間で鑑賞したい絵ではないだろうか。
それらの片片は賢治のいうハリであろうとみた。ハリとは、《玻璃/玻瓈/頗梨》のことである。《(梵)sphaṭikāの音写》で 仏教では、七宝の一ともいわれている。
絵に描かれた赤玉は、賢治と妹トシの自己献身の姿を描いているとみる。百ぺん灼いて、の熱情が三ケの赤玉になったとイメージする。
その赤玉になる時が、自己犠牲の日でヒドリノトキであると考察する。
そのヒドリの時は、ご両親も弟妹も、ナミダヲナガシとなろう。
私は、肉親との別れで、ナミダヲナガスばかりを考察するのではない。
岩手を度々襲う飢饉で亡くなる人々のハフリ(葬儀)のとき、つまり、ヒドリノトキハナミダヲナガシたのではなかろうか。
葬儀のヒドリのトキとは、農民に尽くした賢治ならば、ナミダヲナガシと解釈するのである。ヒドリは誰の日取り、葬儀であるのであろうか。・・・賢治自身のヒドリ、トシの日取り、或いは農民の日取り・・・も考えられると思う。、
多義的に解釈をできるようにヒデリの文字に潜ませられているのではないでしょうか。
(2)説・・・ヒドリはヒドリガモの説。ヒドリガモの緋色は自己犠牲の色を表す。自己犠牲の象徴色と捉える。
ヒドリノトキハナミダヲナガシは、ヒドリはヒドリガモが飛来すると、連想すること。
ヒドリの頭は緋色である。探鳥会でヒドリガモを見つけた場合、あそこにヒドリがいるぞ、と「ガモ」は省略して指差すことが多い。
たとえば、「キンクロがいるぞ・・」といえば、キンクロハジロガモを指す。キンクロと略称で呼ぶようなことである。
ここでは、ヒドリガモをヒドリと呼ぶことを前提に(2)説を陳述したい。
ヒドリは頭部は緋色であることからヒドリガモと命名されたといわれるが、緋色は火の色ともみられよう。私たちは赤色と一口で言われるが、具体的にアカ色を指定するとなると、色のグラデーションを見れとお分かりのように、様々のアカ色がある。賢治は灼いてもかまわぬ犠牲精神旺盛。自己献身、自己犠牲の人。もし、灼かれた場合の色は火の色となる。燃焼温度でみてゆくなら、橙色や朱色や深紅色や暗赤色などに変化してゆく。そのときの炎の火の色であり、その迫真の魂が赤色にも緋色にもなるとみる。
▲写真は ヒドリガモ

写真は、今年、河口湖へ合宿ででかけたおりに湖畔で撮影。陳述のために使わせていただきます。感謝。
賢治はヒドリの色の如くに緋の色や火の色になり火の玉となって献身人生を選びとった。自己犠牲をモットーに生きた人ではなかっただろうか。
ついには大循環の風に乗る。宇宙へ微塵に飛び散る、死、別れを予想しておったのではなかったか。そのヒドリノトキハナミダヲナガシなのである、と解釈する。
永訣のトキノナミダヲナガシであったと解釈できるのではないだろうか。
賢治は自己犠牲精神で、「みんなの幸いのためならば僕のからだなんか、百ぺん灼いてもかまわない。」と、作品『銀河鉄道の夜』に記述している。その生き方、精神を持っていたのである。
ヒドリガモから、百ぺんも灼いてもかまわない、へと私は連想をしていった。灼ける色は火の色であり、火の玉になって自己犠牲のイメージを思う。火の色は緋の色であることを考えると、ヒドリノトキハナミダヲナガシとなるのではないだろうか。
賢治の御遺言を転載する。以下。
父に「『國譯妙法蓮華經』を千部印刷して、知己友人に頒けて下さい。 校正は北向さんにお願いして下さい。本の表紙は赤に・・・。お経のうしろには 『私の一生のしごとは、このお経をあなたのお手もとにお届けすることでした。 あなたが、仏さまの心にふれて、一番よい正しい道に入られますように』と いうことを書いて下さい。」と、花巻弁で言われたと伝えられる。
この御遺言によれば表紙の色は赤色に拘った賢治であることがしれましょう。
なぜ赤色か。この色はとても大事なポイントと思う。
「朱色」としてくださいとする御遺言も伝えられるのであるが、どちらが正しいのであろうか。私は火の色と解釈するので、アカ色、でも朱色でも、どちらも正しい色と私は観る。みんなの幸せのためなら、僕の体なんか百ぺん灼いてもかまわない、とする賢治の覚悟の色である。赤い色、緋の色、朱の色、真紅の色等々、火の色であれば、燃える色、灼ける色であるなら良いのではないかと思う。百ぺん灼かれて熱くて熱くて涙を流す、のではない。百ぺん灼かれようとも、とする自己犠牲の象徴がアカ色なのである。火の色で貢献したトキハナミダヲナガス・・・と解釈できるのである。
「邪教」の父に託した遺言。父は誠意をもって『國譯妙法蓮華經』を火の色の表紙で出版したのである。
(3)説・・・ヒドリは渡り鳥のヒドリガモの説、と解釈する。ヒドリガモが飛来する頃には、「白い大きな鳥」も飛来すると賢治は連想したに違いない。その白い鳥は妹トシの姿であった。故に、次のように解釈する。
ヒドリ(鴨)ノトキハナミダヲナガシ。
なぜ、ヒドリガモでナミダヲナガスのであろうか。
賢治のトシへの思いは、詩「松の針」に吐露されている。一部、引用する。以下
・・・前略・・・
鳥のやうに栗鼠(りす)のやうに
おまへは林をしたつてゐた
どんなにわたくしがうらやましかつたらう
ああけふのうちにとほくへさらうとするいもうとよ
ほんたうにおまへはひとりでいかうとするか
わたくしにいつしよに行けとたのんでくれ
泣いてわたくしにさう言つてくれ
おまへの頬の けれども
なんといふけふのうつくしさよ
わたくしは緑のかやのうへにも
この新鮮な松のえだをおかう
いまに雫もおちるだらうし
そら
さはやかな
terpentine (ターペンテイン)の匂もするだらう
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
トシは11月27日に亡くなった。トシは飛んで行って(逝って)しまったと、賢治は思ってもいたようだ。吾がもとへ戻ってきてほしい思いから、賢治は鳥になぞらえて詩「白い鳥」を創作した。一部、詩「白い鳥」から引用する。以下。
(日本絵巻のそらの群青や
天末のturquoisはめづらしくないが
あんな大きな心相の
光の環は風景の中にすくない)
二疋の大きな白い鳥が
鋭くかな〔しく〕啼きかはしながら
しめつた朝の日光を飛んでゐる
それはわたくしのいもうとだ
死んだわたくしのいもうとだ
兄が来たのであんなにかなしく啼いてゐる・・・・・
「白い鳥」の詩で、トシは「白い大きな鳥」になって悲しく啼いている、とうたわれた。詩の文脈から、白鳥ではないようだ。大きな鳥となると、私には白鳥がイメージされるのだが・・、文脈から無理と判断する。それでも、諦め切れずに考えて考えて、留鳥として考察してみると、文脈をクリアーできそうに思えた。それで解釈してゆくと、留鳥ではいつでも逢えることになり、不自然さが残る。ということから、傷ついて遠くへ飛べなくなった白い鳥なのかもしれないと考えた。傷が癒えて遥か遠くへ渡ってしまった野鳥の白い鳥と解釈をしてみた。それでも、その「大きな白い鳥」の名前を私は特定ができないでいる。が、北上川に飛んでくる渡り鳥の仲間かもしれない、と想像してみた。そうしてみると、ヒドリが解釈できる。
野鳥のヒドリガモがイギリス海岸に現れた時候には、その白い大きな鳥も渡ってくるとしよう。賢治はその白い鳥のトシと出逢えることになるのではなかろうか。
ヒドリノトキとは、妹トシに出逢える日としてみた。その白い鳥とはわずかの期間の出逢いであり、トシとの再会である。トシと再会のトキハナミダヲナガシとなろう。
賢治のいのちがまさに朽ち果てようとしている時、トシとの再会を、おもわなかったと断定できようか。トシと逢いたいと祈っていたのではなかろうか。大きな白い鳥の姿に変身してしまったトシと出逢いたならば、ナミダを流すだろう。ヒドリガモは白い大きな鳥の呼び水的な、案内役的な役割をもつ渡り鳥と考察する。再会のヒドリ説である。
(4)説・・・一人ノトキハナミダヲナガシ説。この解釈はすでに小倉豊文広島大学教授が解釈されておられる。私は捨てがたい解釈と思っている。ヒトリ=ヒドリと解釈しての一人のときはナミダヲナガシ・・・である。賢治がトをドと間違えたとは
思わない立場での私は
一人=独り=ヒドリ、と解釈できるのではないだろうか。
北国の人なら、独り=ヒドリ・・・で、通じ合えるのではなかろうか。小倉氏は、賢治の書き間違いのド説であったかと思われるが、私はドであっても一人・独りと、解釈ができるのである。
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
奇しくもトシさんの御命日に、私は雨ニモマケズのヒドリ解釈最終回を発信する。半年ほど時間がかかった。お陰で再読の機会を頂いた。感謝もうしあげます。
賢治さん、トシさんのご冥福をお祈りし合掌いたします。
2013年11月27日
永訣の朝
けふのうちに
とほくへいつてしまふわたくしのいもうとよ
みぞれがふつておもてはへんにあかるいのだ
(あめゆじゆとてちてけんじゃ)
うすあかるくいっさう陰惨な雲から
みぞれはびちよびちよふつてくる
(あめゆじゆとてちてけんじゃ)
A/Mに捧げる・・・y o
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
考察時の資料は、後日、(29)で発信したいとおもっています。
ブログ宮沢賢治《雨ニモマケズ》に新解釈の玄侑宗久氏(29)資料考察編へ続く^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^












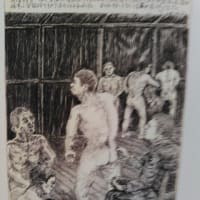
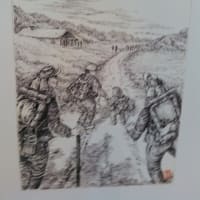
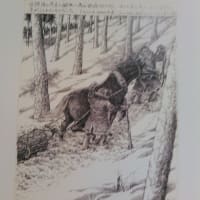
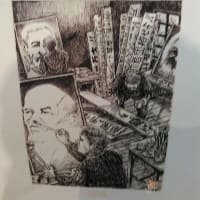
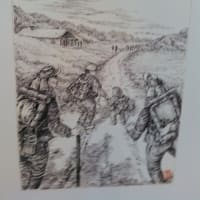

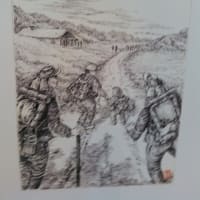
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます