古墳には、亡くなった人と一緒に鏡が埋葬されていることがあります。
大切なものだから一緒に埋めているという考えもあります。
ところが、不思議なことに、鏡の多くは細かく割られています。
故人に大切なものなら、割ることはないでしょう。
むしろ割れないように、布でくるんでおくでしょうね。
福岡県の糸島半島には日本で最大の鏡が出土していますが、この鏡もバラバラでした。
鏡だから簡単に割れてしまうと思われるかもしれませんが、古代の鏡はガラスではなくて、青銅でできています。
十円硬貨と同じですね。十円玉のほうが純銅に近いので曲がりやすいです。
この十円玉は簡単には割れませんよ。
1980年代に念力の使い手として有名になったユリゲラーは知っていますか。
彼は十円玉を曲げることはできましたが、十円玉を割るところは観たことがありません。
ついでにスプーン曲げはできても、スプーン割れはできませんでしたね。
念力で曲げるだけではぜんぜん面白くないです。手で曲げられますからね。
ところが、スプーンを割ったら、これは違いますよ。私はオーッと声を上げます。
金属を割るには、温度をぐっと下げて凍らせるか、熱を加えて脆くしないとだめなんです。
ドライアイスの中にバナナやバラを入れて凍らせて粉々にする場面をテレビで見たことがあるでしょう?
ドライアイスが無かった古代では、熱する方法しかありません。
ですから鏡が細かく割られているのは、割る目的のために、わざと熱を加えたのに違いないです。
だいたい、割った鏡を死者と一緒に埋葬していることに、これはちょっとおかしいなと疑問に思わないといけませんね。
では、なぜ割ったのか。
専門家は、この疑問に全くすっきりした答えを言ってません。
鏡を埋納した時には割れておらず後で盗掘した者が割ったという説や、青銅は貴重な材料だから再利用するために割ったとか、盗掘するものが誤って踏みつけて壊したなどという説もあります。
どれも、私は違うように思います。
古墳に死者と一緒に埋めるのは、宗教的な意味があると思います。古代に仏教は無いので神道ですね。
神道は生活の中に馴染んでいますし、正確には宗教ではありません。私も詳しいわけではありませんが、その意味するところは理解できます。
埋葬者があの世に行って戻って来られないようにという意味が考えられそうです。
これは葬送と鎮魂であって、この世に未練を残さないよう成仏祈願するとともに冥界から戻ってこないように怨念を封じる両方の意味を持つのだと思いますよ。
これはほかよりは納得できる考えではないでしょうか。
どうでしょう。
頭の固い学者ですと、こういう発想がきっとできないです。
大切なものだから一緒に埋めているという考えもあります。
ところが、不思議なことに、鏡の多くは細かく割られています。
故人に大切なものなら、割ることはないでしょう。
むしろ割れないように、布でくるんでおくでしょうね。
福岡県の糸島半島には日本で最大の鏡が出土していますが、この鏡もバラバラでした。
鏡だから簡単に割れてしまうと思われるかもしれませんが、古代の鏡はガラスではなくて、青銅でできています。
十円硬貨と同じですね。十円玉のほうが純銅に近いので曲がりやすいです。
この十円玉は簡単には割れませんよ。
1980年代に念力の使い手として有名になったユリゲラーは知っていますか。
彼は十円玉を曲げることはできましたが、十円玉を割るところは観たことがありません。
ついでにスプーン曲げはできても、スプーン割れはできませんでしたね。
念力で曲げるだけではぜんぜん面白くないです。手で曲げられますからね。
ところが、スプーンを割ったら、これは違いますよ。私はオーッと声を上げます。
金属を割るには、温度をぐっと下げて凍らせるか、熱を加えて脆くしないとだめなんです。
ドライアイスの中にバナナやバラを入れて凍らせて粉々にする場面をテレビで見たことがあるでしょう?
ドライアイスが無かった古代では、熱する方法しかありません。
ですから鏡が細かく割られているのは、割る目的のために、わざと熱を加えたのに違いないです。
だいたい、割った鏡を死者と一緒に埋葬していることに、これはちょっとおかしいなと疑問に思わないといけませんね。
では、なぜ割ったのか。
専門家は、この疑問に全くすっきりした答えを言ってません。
鏡を埋納した時には割れておらず後で盗掘した者が割ったという説や、青銅は貴重な材料だから再利用するために割ったとか、盗掘するものが誤って踏みつけて壊したなどという説もあります。
どれも、私は違うように思います。
古墳に死者と一緒に埋めるのは、宗教的な意味があると思います。古代に仏教は無いので神道ですね。
神道は生活の中に馴染んでいますし、正確には宗教ではありません。私も詳しいわけではありませんが、その意味するところは理解できます。
埋葬者があの世に行って戻って来られないようにという意味が考えられそうです。
これは葬送と鎮魂であって、この世に未練を残さないよう成仏祈願するとともに冥界から戻ってこないように怨念を封じる両方の意味を持つのだと思いますよ。
これはほかよりは納得できる考えではないでしょうか。
どうでしょう。
頭の固い学者ですと、こういう発想がきっとできないです。










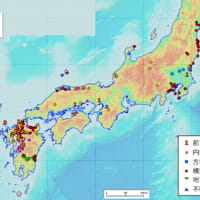









ただ、割られていない銅鏡もあるということは、全ての死者に対する等しい儀式として行っていたのではないということでしょうか。
と書くつもりでした。
参考まで
割られていない銅鏡:
https://www.sagas.co.jp/articles/-/158122
割った銅鏡を副葬したのだと思います。
いずれにしても、完品の方が少ないですね。
ですから、ほぼ故意に割ったのは間違いないです。
さて、これ以降は根拠はなく、ただ私の全くの推測です。
鏡割りは原則行われたもので成仏祈願と怨念封じであったと思いますが、鏡が割られていない場合には、埋葬した側の事情によるのではないかと思います。
被葬者にこの世に戻ってきてほしいという願いが強い場合には、鏡をわざと割らなかったのではないかと思います。
たとえば、割られていない鏡については、初期古墳の那珂八幡古墳の例があります。後円部には神社の社殿が立地しており2基ともその真下にあり1基については調査できない状況です。うち1基は、石室の中ではなく古墳に直接埋葬されており、そこから三角縁神獣鏡が1枚が割られず副葬されていることが判明しています。
したがって、埋葬した者が被葬者によみがえってほしいという未練があったので、石室に入れず鏡も割らなかったのではないかと思います。
その点はちょっと使いにくいところです。
興味深い疑問点のコメントをありがとうございます。
https://www.sagas.co.jp/articles/-/158122
は残念ながら現在ヒットしないです。
何が書いてるあるのか読んでみたい気持ちがあります。
お手数をかけました。
記事を見ることができました。
今、仲島遺跡の調査報告書を読んでいるところです。
仲島遺跡は、福岡市博多区と大野城市にまたがる弥生時代から奈良時代にかけての集落遺跡で、この完形の鏡は、溝に土器などと一緒に捨てられたものですね。
その出土については、集落であって墳墓ではありませんので、成仏祈願や怨念封じとは違ったケースと言えるでしょう。ですから割られていなくても不思議ではないように思います。
なお、福岡市教委では、博多区側から出土した完形の鏡を取り上げていますが、ここに隣接した大野城市側では、漢鏡の小さな破片が出土しています。出土状況が埋葬地であったかどうかなどの詳細は不明です。
今のところ、割られていない銅鏡は、墳墓の副葬品ではなく成仏などの葬送に使用されたものではないと考えると筋が通るように思います。
新聞記事は、完形の銅鏡がでたことに注目しているということでしょう。11cmほどの小さめの銅鏡でとてもきれいであったということですので、生活の中で大切に使用されていたものかもしれません。記事では専門家が祭祀に使ったと述べられています。