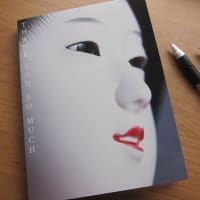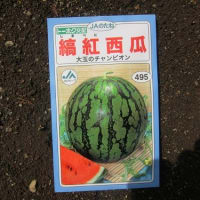2022年度大根成長記録のスタートです。
成長する過程を節目毎に追記していきます。
今回は、「第7回沢庵漬け編」です😁
今後の節目予定は
1⃣8/20種まき編・・・済み
2⃣9/4除草・土寄せ編・・・済み
3⃣9/11害虫駆除・・・済み
4⃣9/17間引き作業編・・・済み
5⃣10/8防虫対策のネットを外す作業編・・・済み
6⃣11/19収穫・沢庵用に干す作業・・・済み
7⃣12/10干し大根収穫・・・今回報告
大根を蒔くとなると秋を感じますね!
毎年、まき時をずらして2回に分けて蒔いています。2回に分ける理由は、沢庵を2回に分けて漬けて、漬けの浅い漬け物を長く食べるためです。蒔く時期を3週間ずらしているので、2回目は成長が遅くなるため漬ける時期は1ヶ月ほどずれます。
それでは、
【第7回12/10干し大根収穫編】
予想以上に干す日数が掛かってしまいました。小屋の軒下裏に暑さ対策としてよしずを付けたのが遅延の原因だと思います。干し大根が日陰になってしまい約3週間干しました。
本日の作業工程
①収穫作業
作業ポイントの説明
強めに干すと沢庵が堅くなるので、毎年弱め傾向ですが今年は意識して弱めの弱めで行きました。
➀収穫作業
よく言われる大根の干し加減は、「Uの字まで曲がるまで」とか「への字まで曲がるまで」とか言われます。今年は弱めの弱めなので「への字程度」で行きました。

曲げた感じがこんなもん

以上で本日の作業は終了です。
沢庵漬け作業は別途ブログで記述する予定です。
以下は、前回の記事で参考まで
【第6回11/19収穫・沢庵用に干す作業編】
2週間前から収穫していましたが、今回は沢庵用に収穫します。

本日の作業工程
①収穫作業
②沢庵用に干す作業
作業ポイントの説明
今年の出来映えは「良」といったところです。
①収穫作業
沢庵用に43本収穫しました。
②沢庵用に干す作業
昨年までは洗った大根を干していましたが、畑の仲間が「地元では洗わないままで干している」というので……
「本当かいな????」
洗わない理由を聞いたところ
・洗うと腐りやすい(表面に傷が付く)
・洗わない方が細菌に強い
と、申しておりました?(真実かどうかは不明です)
今年は洗わないで干す事としました。(砂の塊はスポンジで払い落としました)
《洗わなかった理由》
・ゴシゴシこすった大根よりも自然のままの大根の方が「沢庵表面が素敵に」漬けあがるのでは(優しい表面になるのでは)
・大根を引き抜いた段階で土がこびりついた状態でない → 干している過程での埃などの汚れと変わらないのでは
・ぬか床の中で水分を出して細っていく段階で大根表面の汚れがなくなると推定
・食べる前に必ず洗う作業があるので
こんな感じで干しました。里山の私の拠点である小屋の軒下に干したので空気はとても綺麗です。
2重紐を垂らして、大根を挟み込んだだけです。太い大根だと柔らかな美味しい沢庵となります

広角で見るとこんな感じ
10日前後で干し上がりますが、今週は雨模様なので少し時間掛かるかな?

以上で本日の作業は終了です。
次回は、収穫作業です。(購入した沢庵とは別物ですから自家製沢庵は造る価値あり)
以下は、前回の記事で参考まで
【第4回10/8防虫対策のネットを外す作業編】
今の所順調に育っており、大根の太さは直径30mm程です。2回目に蒔いた大根の間引きを同時に本日行いました。(写真奥3列目ネット掛かって居るのが該当畝です。ネットで密閉されているのにダイコンシンクイムシが一匹居ました。不思議ですね????)
《肝心の何故ネットを外すかですが!》
私の過去の経験でネットを被せたままで居ると、中でアブラムシは苗から苗に伝染して大繁殖し大根の苗を壊滅状態にします。(成長が止まり物になりません)
何故アブラムシが大繁殖するか私なりに推察した結果、天敵のテントウムシなどからネットによりアブラムシが保護されているためと推測しました。以上の理由によりできるだけ早い段階でネットを外しています。(以上、個人的な見解です)
本日の作業工程
①防虫対策のためネットを外す作業
作業ポイントの説明
①防虫対策のためネットを外す作業
アブラムシが繁殖しないためにネットを外すタイミングは
・ダイコンシンクイムシが付いても成長できる大きさになっていること
・ダイコンシンクイムシの産卵のピークが過ぎていること
この2点が条件です。
以下の写真ぐらいに育っていればダイコンシンクイムシに対して対応力ありと判断しています。
また、産卵ピークですが神奈川では10月に入れば過ぎていると判断しています。
従って、本日ネットを外しました。
アブラムシ対策として「銀色テープ」を園芸ポールに取り付けて数カ所に挿しています。写真参照

以上で本日の作業は終了です。
以下は、前回の記事で参考まで
【第4回9/17間引き作業編】
本日の作業工程
①間引き作業
作業ポイントの説明
種を蒔いて一月が経ち大分大きくなったので間引き作業に取りかかります。

①間引き作業
種を2粒蒔きしていますので、1株を間引く形となります。毎年同じ種を購入しているのですが、物価高騰の影響で今年の種は容量が減量されており、今年は3粒蒔きから2粒蒔きに変更していますので、間引き作業も楽です。大根の発芽率は相変わらず良くて、2粒蒔きでも十分でした。
下の写真は、2株の内の1株を抜いたところです。優劣がはっきりしている株については躊躇無く間引くことが出来ますが、優劣が同じ株については…… 悩みますね!
間引いた株が、下の写真のように「真っ直ぐな大根の形」になっていると、失敗したかなと想い、残した株は、又割れになっていないだろうかと不安になります。(逆に、間引いた株が又割れになっていると…… しめしめと思います。)

間引き作業と同時に
・除草作業
・害虫チェック
を行います。
除草作業は、先日行ったばかりなので2mm位の草しか生えていません。従って、土の表面全体を道具によりかき回せるだけです。
害虫チェックは、どちらの株を間引くか悩んでいるときに害虫チェックをします。不思議なことに、3mm程のダイコンシンクイムシを一匹だけ見つけて退治しました。
・何で1匹だけなの?
・何処から入ってくるの?
産卵するには親の蛾がネットに侵入するしかないが、ネットは隙間無く塞いであります。3mmの幼虫がネットに侵入してくるのは無理だし
何時も不思議に思います。ネットを外して作業している間しか隙は無いので、作業中に侵入してくる???
永遠の疑問を抱えながら……
本日の作業は終了です。
次回は、害虫除けのネットを外す作業になりますが、このタイミングが凄く重要で上手くいくことを願います。何故かは「害虫」と「益虫」との関係です。詳しくは、次回に記述します。
以下は、前回の記事で参考まで
【第3回9/11害虫駆除編】
本日の作業工程
①害虫駆除
作業ポイントの説明
先週、ダイコンシンクイムシが一匹いたので注意深く害虫のチェックをしてみました。
①害虫駆除
葉が食べられていたので、周辺をチェックしたところハスモンヨトウが2匹地べたを張っていました。虫を分かりやすくするために葉の上に載せて写真を撮りました。

これは、ネキリムシの被害で、根元から茎が切断されていました。株の周囲10cm位を深さ10mm程度ほじくると出てきました。葉の上に載せて撮影です。

以上で終了です。今回は気になっていたダイコンシンクイムシはいなくてホットしました。捕獲した害虫は、1週間でこれだけ大きくならないので……
先週防虫ネットを土で塞ぐ前に侵入した物と考えられます。
以上で本日の作業は終了です。(今回、2回目の種まきを1畝行いました。)
以下は、前回の記事で参考まで
【第2回9/4除草・土寄せ編】
本日の作業工程
①除草作業・土寄せ
②未発芽箇所の追加種まき
③ネットを被せる
作業ポイントの説明
種を蒔いて2週間経ち順調に育っています。
①除草作業・土寄せ
前回の作業から2週間しか経っていないので除草作業は楽です。畝全体の表面を引っかき回すことが重要です。なぜならば、発芽しようとしている草たちも一網打尽となるからです。
そして、さらさらの土となっているので、土寄せもスムーズです。
土寄せした後の写真となります。
土寄せ前は、根元が露出していてぐらぐら状態ですが、根元を覆うように土を被せます。大根の芯(中央部)には、決して土が入らないように土寄せするのがポイントです。

土寄せ作業をしながら害虫のチェックも同時に行います。大根の幼少期の大敵は、ダイコンシンクイムシとなります。ネットを被せていないと必ず居ます。(自然に囲まれた私の畑だけかな…… )
大根の芯を食べ尽くしますので、大根が生長できなくなり物になりません。本日もネットを被せていたにもかかわらず一匹発見して駆除しました。
②未発芽箇所の追加種まき
発芽していない箇所が数箇所あったので、種を蒔きました。
③ネットを被せる
最後にネットを被せます。ネットの端(土と接触している部分)に隙間が出来ないように、鍬で土を被せる作業をして本日の作業は終了です。
ダイコンシンクイムシが一匹居たことが後ろ髪を引かれるんだよね……
次回は、害虫対応にならないことを祈って……😴
以下は、前回の記事で参考まで
【第1回8/20種まき編】
本日の作業工程
①畝を作る
②種をまく
③土を被せ、水をまく
④ネットを被せる
作業ポイントの説明
沢庵を毎年漬けるので、定番の品種「本漬け大根一番」となります。当初は、神奈川県名産「三浦大根」でしたが、先端が丸太りするので均一に成長する本品種に替えています。
種まき時期としては、この地域としては10日間ぐらい早めかな?
煮物にも使えるので、作る品種はこれだけで、青首大根も作りません。

①畝を作る
幅1mの畝を作ります。何時もは、腐葉土を必ず入れていますが、大根が大きくなりすぎてしまうため、大根だけは収穫まで肥料を一切入れません。
幅1mの畝が完成です。(2畝造りました。3週間後に右側に1畝追加します)

②種をまく
2列/畝、蒔きます。30cm間隔2粒セットで種を落としていきます。最後に親指(人差し指)を使って、種の上から1cm位押し込んで、周りの土を軽く被せて軽く手のひらで叩いて終了です。
例年、3粒セットで蒔いていましたが、今年は種の1袋の容量が少なく足りなくなりそうだったので今年は2粒に急遽変更しました。(インフレの影響が出ていますね!) 大根の発芽率は良いので大丈夫と判断しました。ただ、発芽率の良さは、発芽までに雨が降ることなので、天気予報を見ながら蒔くタイミングを計ることが重要です。
下の写真の「白いひも」は、まっすぐな畝を作るために使っている物ですが、30cm間隔でこぶ結びを付けています。種を蒔くときに目安になるので、蒔くときにも畝の中央に置いています。45cm、60cmにも応用できます。(マーカーだと、色あせてしまうのでこぶ結びなら永久に存在します)

③土を被せ、水をまく
蒔いたところの軽く手のひらで叩いた部分に、水をまきます。
2日以内に雨が降ることを祈って、たっぷりと水をまきます。勿論、かんかん照りになるような天気は4日間だめです。(毎日、畑に来ることが出来る人は天気を気にすることはないのかな…… 水まきができるので!)
何故そんなに天候に過敏になるかと申しますと……
・週末にしか畑に来ないので、水くれが出来ません。
・直まきなので、日よけをしなければならない面積が大きすぎて日よけ材料がたりません。
④ネットを被せる
最後に、防虫対策のためネットを被せます。
下の写真は、仮のネットかぶせといった感じです。自然に囲まれた畑なので、ダイコンシンクイムシ対策にネットは必需品となります。ちょっとの隙間からでも侵入して成虫が卵を産みますので、ネットの端は土で目張りが必要です。
発芽して、土寄せが済んだ時点で土の目張りを行います。今週末かな……

以上で、本日の作業は終了です。
次回は、発芽後の土寄せを紹介する予定です😁