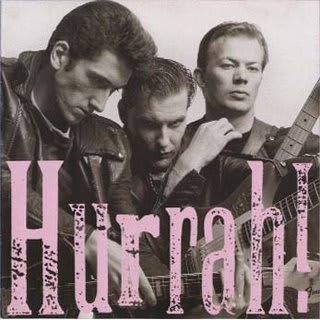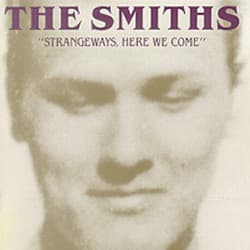
Strangeways,here we come
当時のモリッシーの心境を端的によく表していると思う。
鬱屈した日々を過ごしていた彼が、あれよあれよという間にスターダムにのし上がった。
恐らく自身でも身辺で起きていることを上手く理解できないことも多々あっただろうと思う。
先の記事で英米文学の原題に心を打たれた経験を書いたが、ひとかどの文学的素養を持ち、且つ言葉を紡ぐ才能のある方が書いたものには、それがポップ・ミュージックの歌詞であろうと僕は同様の感銘を受けた。
80年代のUKで活躍したThe Smiths の楽曲たちは、その中でも群を抜いて僕の心を打ったものが多くある。
冒頭の一文をタイトルに冠した The Smiths のスタジオ録音盤4枚目に当たるアルバム。
そこに収録されている曲の歌詞の一節に、僕は一抹の寂しさを抱きながらもぐっと胸に迫るものを感じた。
Stop me, oh, stop me
Stop me if you think that you've
Heard this one before
Stop me, oh, stop me
Stop me if you think that you've heard this one before
Nothing's changed
I still love you, oh, I still love you
...Only slightly, only slightly less than I used to, my love
とても簡単な単語の羅列で読み解くのも何ら困難は伴わない。
受験英語で習う文法を知っていれば充分に理解できる。
A面の5曲目に当たる"Stop me if you think that you've heard this one before" の冒頭かつサビの一節だが、特に後半の"Nothing's changed..." 以降に、僕は言葉には出来ない寂しさを感じた。
「何も変わってないよ、僕は今もきみのことが好きさ。
でもね、ほんのちょっと、ほんのちょっとだけ、前より好きじゃなくなっちゃたなあ・・・」
「何も変わらないのよ、私は今もあなたのことを愛しているわ。
ただね、ほんの少し、ほんの少しだけ、愛は薄れたわ」
一人称を僕にするか私にするか、二人称をあなたにするかきみにするか、そして文体をどのような調子にするのか、どういう訳を当てるのが最適なのか僕にはわからない。
訳し方によっては若者が発する軽い恋愛のような印象にもなるし、重い感じの大人の恋愛のようにもなる。
でも、いずれにしろ日本語を宛てるとたいした感銘も受けない。
それが英文のままだとぐっと胸に突き刺さる。
"only slightly" を二度繰り返している。
このことにより、迷いながら、ためらいながら、そして言葉を慎重に選びながら心情を吐露している様子が伝わってくる。
"less than I used to"
「嘗て自分がそうであったよりも少し」というのが直訳だ。
この人の中に何かがあって、以前よりも愛の気持ちが薄れて行ったのだろう。
でもそれを英語であれ日本語であれ、直截的な表現をしたのでは相手を傷つけてしまう。
以前よりも愛は薄れたとはいえ、今尚愛している存在 "my love" なのだ。
その相手を気遣いながら躊躇して発している様が思い浮かぶ。
もしかしたら、その言葉を発したことによって、相手から自分への愛も薄まるかもしれないと不安を感じているのかもしれない。
そういうことを僕は上手に日本語で伝えられるだろうか。
いやそれは非常に難しい。
そんな僕が、もしこのモリッシーの書いた一節を翻訳した上で理解しても感銘は受けなかったように思う。
そもそも"than I used to" を上手に日本語にすることが困難なのだ。
だからこそ、ここは原文のまま理解したい。鑑賞したい。
僕は自分自身でそれが出来たと思っている。
出来たからこそこれほどまで感銘を受けたのだ。
このような感銘を与えてくれる歌詞がモリッシーが書いたThe Smiths の曲中には随所にある。
メロディに載せた言葉だから文字を宛てるなら「詞」なのだろうが、モリッシーが書いたものには僕は寧ろ「詩」の文字を宛てたくなる。
純粋に言葉だけ取り出して「詩」として鑑賞することも可能だとさえ思う。
僕は幼い頃より読書が好きだったし、文章を書くことも好きだった。
同様に音楽を聴くのも好きだったが、聴くときは常に歌われる言葉を気にしていた。
僕も次第に成長していくと、その言葉が耳触りになってきた。
日常の会話で使う言葉と同じ種類の言語がメロディにも載っている。
とうことは直ちにそれが理解できるということだ。
そうなると、これは高慢な感じでとても言い難いことなのだが、言葉を綴った方々の文学的なセンスがなさ過ぎて聴くに堪えない。
しょうもない言葉遊びや無理やり踏んだこじつけの韻、何処かで覚えてきた難解語を敢えて用いる、そもそも「詩」でも「詞」でもなく単なる文章やんかと思わせるものも多数。
いやでもそれは仕方ないことなのだ。
あくまでそれは音楽なのだから。
そのメロディラインの修飾のようなものなのだ。
あまり小難しい言葉を並べても逆に聴かれなくなることの方が多いのだろう。
作り手だってそれで商売しているわけだから、その辺りのことはよく考えて分かっているだろう。
やはり言葉の鑑賞のためには読書なのだ。
音楽は音楽として楽しめばよいことなのだ。
そう思い始めると、僕は国産の音楽は殆ど聴かなくなった。
それでもやはり僕は言葉が気になる。
英詞の曲を聴いてもそこで歌われている言葉は必ず確認する。
その作業をしてく中で、モリッシーは特別だと感じた。
他のアーティストの詞にも感銘を受けることはある。
しかし、モリッシーのそれに受ける感銘は、質も量も比較にならない。
I don't owe you anything, no
But you owe me something
Repay me now
Too freely on your lips
Words prematurely sad
Life is never kind
Life is never kind
Oh, but I know what will make you smile tonight
(I Don't Owe You Anything の一節)
Coyness is nice, and
Coyness can stop you
From saying all the things in
Life you'd like to
(Ask の一節)
Askのこの一節で"coyness"を用いるところなど心の底から敬服します。
特にこの曲はサウンドも美しいし、詞の中に文学少女らしき人物も登場するのでリンクを貼っておきます。
Ask / The Smiths (you tubeへ)
Ask Shyness is nice, and
Shyness can stop you
From doing all the things in life
You'd like to
Shyness is nice, and
Shyness can stop you
From doing all the things in life
You'd like to
So, if there's something you'd like to try
If there's something you'd like to try
ASK ME - I WON'T SAY "NO" - HOW COULD I ?
Coyness is nice, and
Coyness can stop you
From saying all the things in
Life you'd like to
So, if there's something you'd like to try
If there's something you'd like to try
ASK ME - I WON'T SAY "NO" - HOW COULD I ?
Spending warm Summer days indoors
Writing frightening verse
To a buck-toothed girl in Luxembourg
ASK ME, ASK ME, ASK ME
ASK ME, ASK ME, ASK ME
Because if it's not Love
Then it's the Bomb, the Bomb, the Bomb
the Bomb, the Bomb, the Bomb, the Bomb
That will bring us together
Nature is a language - can't you read ?
Nature is a language - can't you read ?
SO ... ASK ME, ASK ME, ASK ME
ASK ME, ASK ME, ASK ME
Because if it's not Love
Then it's the Bomb, the Bomb, the Bomb
the Bomb, the Bomb, the Bomb, the Bomb
That will bring us together
If it's not Love
Then it's the Bomb
Then it's the Bomb
That will bring us together
SO ... ASK ME, ASK ME, ASK ME
ASK ME, ASK ME, ASK ME
Oh, la ...
 にほんブログ村
にほんブログ村