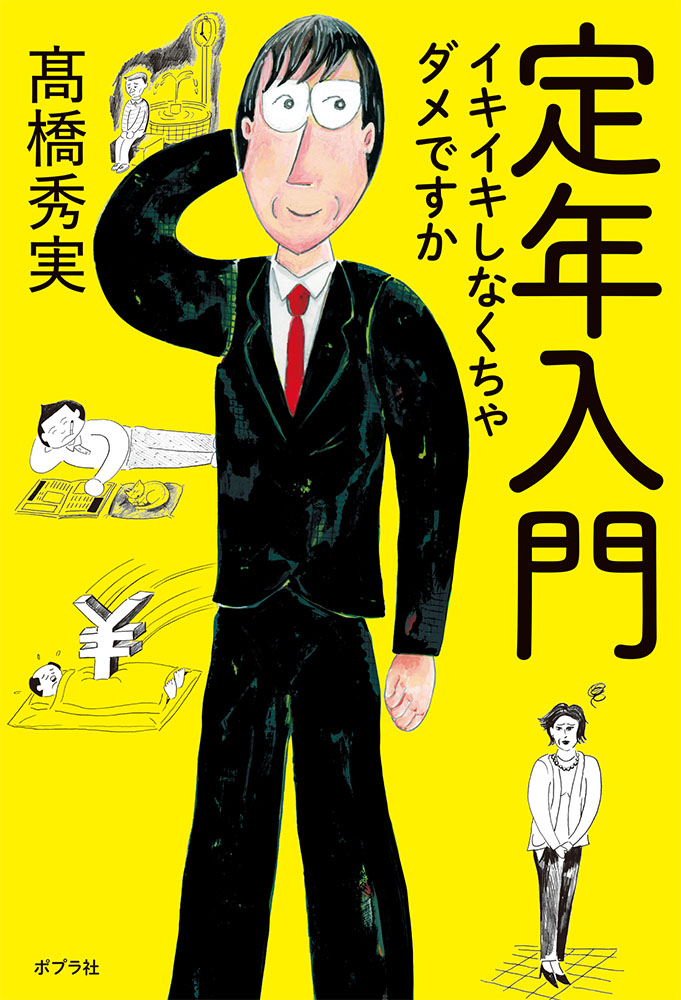朝日新聞出版の「病院のやめどき 」です。
「どんな人にも「快適に生きる権利」があるはずだ。
ところがほとんどの病院は、それを無視している。
あなたの身体を診ようとはせず、検診結果の数値だけを見て、ほぼ機械的に薬を処方する。
薬の副作用に関する説明はナシ。
たとえば血圧の数値が「標準」より高ければ、降圧剤を処方する。
だが、「過降圧」となって、頭がふらふらしたとしても、
医者はあなたの訴えに耳を貸そうとしない。
「数値を標準にする」という医療の信奉者だからだ。
しかも、日本の病院で出される薬は、
日本人に有効であるというエビデンス(科学的根拠)が欠如していると言わざるを得ない。
また、日本ほど集団検診が大規模に行われている国も珍しいが、
国民の健康に役立っているか、はなはだ疑わしい。
ほかにも医療界が隠したがる問題はやまほどある。
患者は情報弱者になってはいけない!
自分の健康な生活を守れるのは自分自身だからだ。
病院から言われるままに治療して、
副作用に悩みつつ少しだけ長生きしたら幸福だろうか?
生活の質(QOL)を下げない生活を守れるかどうかはあなた次第。
「医療の自己決定」が重要なのだ。
日本の医療界の正体を明らかにし、快適に生きるためのヒントを紹介する。」とのことです。

日経BP社の「アフターデジタル 」です。
「現在、多くの日本企業は「デジタルテクノロジー」に取り組んでいますが、そのアプローチは「オフラインを軸にしてオンラインを活用する」ではないでしょうか。
世界的なトップランナーは、そのようなアプローチを採っていません。
まず、来るべき未来を考えたとき、「すべてがオンラインになる」と捉えています。考えて見れば、モバイル決済などが主流となれば、すべての購買行動はオンライン化され、個人を特定するIDにひも付きます。IoTやカメラをはじめとする様々なセンサーが実世界に置かれると、人のあらゆる行動がオンラインデータ化します。つまり、オフラインはもう存在しなくなるとさえ言えるのです。
そう考えると、「オフラインを軸にオンラインをアドオンするというアプローチは間違っている」とさえ言えるでしょう。筆者らはオフラインがなくなる世界を「アフターデジタル」と呼んでいます。その世界を理解し、その世界で生き残る術を本書で解説しています。」とのことです。

日経BP社の「China 2049 」です。
「1990年代後半のクリントン政権時代、著者のマイケル・ピルズベリーは国防総省とCIAから、中国のアメリカを欺く能力と、それに該当する行動を調査せよ、と命じられた。諜報機関の資料、未発表の書類、中国の反体制派や学者へのインタビュー、中国語で書かれた文献をもとに、中国が隠していた秘密を調べはじめた。やがて見えてきたのは、中国のタカ派が、北京の指導者を通じてアメリカの政策決定者を操作し、情報や軍事的、技術的、経済的支援を得てきたというシナリオだった。これらのタカ派は、毛沢東以降の指導者の耳に、ある計画を吹き込んだ。それは、「過去100年に及ぶ屈辱に復讐すべく、中国共産党革命100周年に当たる2049年までに、世界の経済・軍事・政治のリーダーの地位をアメリカから奪取する」というものだ。この計画は「100年マラソン」と呼ばれるようになった。共産党の指導者は、アメリカとの関係が始まった時から、この計画を推し進めてきたのだ。そのゴールは復讐、つまり外国が中国に味わわせた過去の屈辱を「清算」することだった。
本書は、ニクソン政権からオバマ政権にいたるまで、米国の対中政策の中心的な立場にいた著者が、自分も今まで中国の巧みな情報戦略に騙されつづけてきたと認めたうえで、中国の知られざる秘密戦略「100年マラソン(The Hundred-Year Marathon)」の全貌を描いたものだ。日本に関する言及も随所にあり、これからの数十年先の世界情勢、日中関係、そしてビジネスや日常生活を見通すうえで、職種や年齢を問わず興味をそそる内容となっている。」とのことです。