古代から水は神聖視されていて、汚れを祓い清める意味で、何らかの形で水を使ってきていた。現在でも神社で手水を使い、擬似清祓行為をした経験があると思う。折口信夫の古代研究によると、さらに湯は常世から来る水のことで、普通の水より温かいため、やはり禊ぎに使われていたそうだ。また湯が豊富に出る、その地域をも禊ぎの地としていた。斎戒沐浴(ゆかはあみ)がだんだん短くなって「ゆ」となったと考えられるが、この斎(ゆ)の文字は、人の生死と関わりがある。おそらく、湯浴みして生命の再生力を湯から取り込めると考えていたのかもしれない。いずれにしろ、私たちが湯につかるのは、汚れを祓い落とし、清める意味がありそうだ。古代には、体を洗うといっても川の水や海水といった冷水しかなかった。湯浴み自体は中国から仏教の伝来と共に移入され、まず寺を中心に湯につかることが次第に普及していった。それを利用していた信徒の中の豪族達が自前で風呂を作り始め、やがて村民がそれを利用させてもらう。やがて宗教性と離れ、入浴が次第に大衆に普及していくという経過を辿っている。岩風呂や岩盤浴は当時からも使われていたようだ。やがて、鎌倉時代頃からさらに普及し、湯治場もできてきた。これらの知識があるとないでは、湯浴みのありがたさや、効果も大きく違ってくるかもしれない。私も温泉に入るときは、温泉の湯にゆっくりとつかり、世俗の汚れを洗い落とし、また俗世間で頑張ろうと思う。
最新の画像[もっと見る]
-
 市長就任式
17年前
市長就任式
17年前
-
 胎動
17年前
胎動
17年前
-
 恩師との会話
17年前
恩師との会話
17年前
-
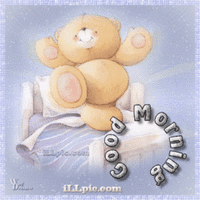 新市長誕生
17年前
新市長誕生
17年前
-
 Hello
17年前
Hello
17年前
-
 毎日新聞 全国版に!
18年前
毎日新聞 全国版に!
18年前
-
 ダルタニウスの苦悩・・・原作者による解説
18年前
ダルタニウスの苦悩・・・原作者による解説
18年前
-
 セリーヌディオン
18年前
セリーヌディオン
18年前
-
 謹賀新年
18年前
謹賀新年
18年前
-
 ドキュメント番組「泣きながら生きて」を見て。
19年前
ドキュメント番組「泣きながら生きて」を見て。
19年前









