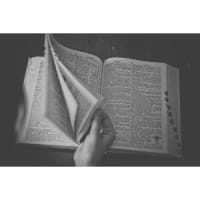国内版と共にサービスは終了している。
(記事タイトルのナンバリングの意味や、この記事の目標、記事内の ‘Oxford’ の定義などが気になる方はコチラへ)
〈追記〉記事としてツギハギ感が出るのであまりしたくなかったことではあったが、
納得できない範疇だったので、日付を変えて。
inferno についての説明、使役動詞についての扱い、仮定法の扱いが些か雑過ぎたので修整。
以前以上に需要が謎なことしているので、誰も気にしていないかもしれないが、一応。
『塵も残さん!奥義、浄破滅焼闇!闇の炎に抱かれて消えろ!』
こちらの台詞、及び台詞が使用される秘奥義・浄破滅焼闇の初出は、
こちらの台詞、及び台詞が使用される秘奥義・浄破滅焼闇の初出は、
テイルズオブデスティニー2のジューダス。
短くも、黒と赤が入り混じる二色の炎の演出もさながら、もっぱら後半の台詞が有名になった技。
原作では、「闇の炎に〜」以降は通常の戦闘画面に戻って無防備状態で動けなくなる為、
そこを敵に狙われて「うはっうはっ馬鹿なッ!」と死んでいくのもネタにされる。
また、なぜか無断で他作品に使われることがあり、
「解離性ミリオンアーサー」のガチャの煽り文句に使われたり、
「中二病でも恋がしたい!」の主人公の決め台詞になっていたりする。
意外にも?シリーズ後発作品ではこの技どころか類似技すらあまり登場していない為、
シリーズ内というよりは、完全に外側で、
中二病の代名詞として、サブカルのトレンドを一時期形成してしまったような感じはする。
本題。
テイルズオブデスティニー2には、英語圏の海外版が存在しない
(韓国語版の存在は確認している。しかもボイス吹き替え済み)。
リメイク版デスティニーもローカライズされていない為、オリジナルタイトルでこの技が見られる機会は他にない。
そして、長らくこの技が登場しているクロスオーバータイトルがローカライズされることはほぼ無かった為、
自然と、その台詞もまた翻訳される機会がなかった。
しかし、リンクの英語版が登場したことにより、
ようやく日の目(?)を見ることとなった。
その気になる英訳は、
"Not even your ashes shall remain! Mystic arte! Cleansing Inferno! Let the flames deliver you to oblivion!"
となっている。
長いので、一先ず筆者の訳を載せておく。
『(貴様の身体の)塵すら残さん!奥義!浄破滅焼闇!この炎が貴様を虚無へと還さん!」
辺りになるはずである。
全体として日本語の語句からそれほどズレなく、丁寧に英訳されていると思う。
強いて言えば「闇の」が出力されていないが、そこは oblivion のニュアンスに取り込まれたといってもいいだろう。
というのも通常、ローカライズにおいて、こういった中二病というか
クドい表現の入った台詞は、あっさり目に処理されがちである。
そこを妥協せず、できる限り細かく訳す選択をした辺り、ファンへの配慮が伺える。
英訳文内の、気になる表現をピックアップ。
一文目の、平叙文での shall は、日本の教育で習う範囲や、日常会話のレベルではあまり使われない。
『〜しませんか?』を意味する “Shall we~?” 以外では見かけたことがない、という人もいるかもしれない。
今回のような shall は、ほぼほぼ日本語でいう「古典でしばしば使われる助動詞 む」の意味になっている。
つまり、基本的に意思を表してはいるが、古臭かったり仰々しかったりする印象を与える。
故に、口語で頻繁に使われるものでは無い。
英語における意思の助動詞といえば、他に will があると思う。しかし、
上記リンクの Usage の項に記載があるように、現代英語において、両者の意味に特に差別化があるわけではない。
伝統的には、shall は一人称 I と呼応し、will はそれ以外の人称詞と呼応していたようだが、
今では英米共にそのような使い分けをしない方が、通例となっているようだ。
さて前述の「む」は、現代日本語でも残っている。
この「む」は、終止形や連体形では「ん」に変化する。
そして、この「ん」は、「いざ行かん」「全てを滅ぼさん」そして「塵も残さん」といった形で使われている。
日本語においても、これらの表現は堅苦しく、よりカジュアルに発言する際は、
「さあ行こう」「全てを滅ぼしてやろう」「塵すらも残してはやらないぞ」といった表現になるだろう。
Mystic Arte は、ほぼシリーズを通して『奥義』の訳に当てられている。
ただし、日本語の「奥義」自体に当たる英訳というわけではない。
飽くまで、テイルズオブの用語の一つである『奥義』に当たる英訳だ、ということは注意しておきたい。
arte という英単語は存在しない。
恐らく、art(『芸術』の意味の方が有名だろうが、ここでは『技巧』)に e を敢えて余分につけて、
このシリーズ独自の『技』を意味する造語、という位置付けだと思われる。
一応、arte はイタリア語の art に相当する単語や、ラテン語の art に相当する単語の奪格でもあるようだが、
ラテン語ならともかく、イタリア語をいきなり持ち込んだ、とはあまり思えない。
浄破滅焼闇は Cleansing Inferno と訳されている。
cleanse は、日本語でクレンザーとなっているように、
『洗浄する』とか『(罪を)赦す、清める』とかと言った意味の単語。
inferno も、日本語で(イタリア語由来で)インフェルノとなっているものに相当する。
ただし英語での読みは、インファーノに近い。
この単語は、簡潔に言えば『地獄』を指しているわけだが、
上記 Oxford の定義にあるように、特にダンテ・アリギエーリの「神曲」に登場するそれを指しているようだ。
同部分には、英語で単に「地獄」というものを指すときは hell を用いる、とも書かれている。
この辺りは多分に感覚的な話でもあり、辞書を脳死で信じるのがイヤな人には納得が難しい部分かもしれない。
ただ、例えば “go to hell.” などを、”go to inferno.” と言い換える、と言ったことは聞いたことがないと思う。
何故ないかと言えば、ここでの地獄はともかく「死後、最悪な場所」を意味したいだけであり、
相手への強い侮蔑以外に、余計なニュアンスは含みたくない、ということだと思われる。
結局、早い話がこの表現は『クタバレ!』を意味しているだけであり、
「神曲」を念頭に発言する人は皆無だろう、と思われる発言だと思う。
辞書の信用度については、編纂者が何人もいる以上(特に、Oxford には歴史的な積み立てや、利用者の多さもある)、
少なくとも、そのあたりの(筆者含めた)個人サイトの見解よりは信用できると思う。
この辺りは、書き始めると無限にボロが出る話題ではあるが、また別記事にして自身の見解は出してみたいと思っている……。
上記リンクには、inferno は『地獄』の他に、
A large fire that is dangerously out of control.
のことも指すと書かれている。
日本語では『大規模火災』や『大火』と訳されると思うが、
inferno にはしっかり炎のイメージも含まれている、ということが分かるだろう。
この辺りを踏まえると cleansing inferno は、単に『敵を一掃する大火』とも訳せるし、
もう少し踏み込んで『邪悪なるもの達を浄化する、地獄の業火』とも訳せるだろう。
‘let the flames deliver you to oblivion’ という文は、全体的にネイティヴらしい仕上がりとなっていると思う。
第二言語話者には、即座に思いつかない表現が盛り込まれている。
‘let the flames (deliver ~)’ は、まだ分かりやすい方だろう。
‘let (something) (動詞の原型)’ で、『(何か)にほしいままに〜させる』を意味している。
「縦/恣/擅(ほしいまま)」というのが重要で、
この辺りは have や make などの、他の使役動詞(英:Causative verb)との使い分けになる部分だ。
正直参考書などに書いてある通りと言い切りたいので、深くは触れない
という理由で、逃げさせてほしい。)
let には常に「対象の自由に任せる・させる」というニュアンスが含まれている、というのは何となく感じることだと思う。
例えば、“Let It Be” や “Let It Go” といった有名な曲なども、そのニュアンスを活かしているのがよく分かると思う。
今回の flames『炎』を「自由にさせる」ことといえば、それは『(対象が)塵になるまで焼き尽くす』ということになるだろう。
しかし、実際の文章はそれで終わりではない。
ここで let が flames に自由にやらせるとしているのは、‘deliver you to oblivion’ という行為だ。
deliver は、
’deliver (something) to (someone)’
という形で、『(誰か)に(何か)を送る』の意味で使われるのが一般的だ。
ところが、今回の文章では、上記の something にあたる部分に you が入っている。
you は、この秘奥義を受ける相手のことだ。
つまり、『貴様』を何処かに送ってやる、と言っている。
その先が oblivion だ。
この単語、和英や英和の辞書では『忘却』という言葉が推されていると思う。
実際、普段はその認識で間違いない。
上記リンクはMTGのカード名に oblivion が含まれるものを検索した結果だが、
どれもその単語に相当する部分は『忘却』と訳されているのが分かるだろう。
しかし、ことさらローカライズにおいては、
上記の 1.2 に記載があるように、『破滅』とか『消滅』とかの意味の方で使われていることの方が多い。
ゆえに、’deliver you to oblivion’ をストレートに訳せば、
『貴様を消滅(の運命・未来・結末……)へと送る』という感じになる。
ここで let~ に立ち返れば、flames がほしいままに相手を消滅させる、という繋がり方になる。
ということは、つまり『この炎が、貴様が塵も残らぬ姿になるまで、焼き尽くし続ける』わけだ。
しかし、塵も残さず、と同じ表現を二度も使うのはあまりよくない。
ところでデスティニー2には、エクセキューションの詠唱文に
「裁きの時、来れり!還れ、虚無の彼方!」
というものがある。
後半部分がちょうど、deliver (you) to oblivion の表現に近いものとなっていると思う。
そこで、前述の筆者訳では『この炎が貴様を虚無へと還さん』としている。
以下、本題には無関係のこと。
有名な話だとは思うが、ジューダスの名前は
「イスカリオテのユダ」の英語圏での呼び名、Judas から来ている。
あのカイルが「じゃあ……ジューダス!」と、突然教養のあるネーミングセンスを見せたのも驚きだが、
よりにもよって裏切り者から名を取っているのが凄まじい。
メタな話をすれば開発スタッフ側のアイデアなのだが、
カイルが「こいつ裏切りそう」と思いながら名付けたと思うと、ゾッとしない話である。
とはいえ、エクシリアのアルヴィンは古英語由来で、『尊き友』とか『古くからの友』とかを意味しているらしい。
……これと比べれば、ストレートに裏切り者と呼んだカイルはまだ優しいのかもしれない。
まあ、そもそもジューダスは劇中では結局裏切らないのだが……。
前段で obilivion について、「ローカライズにおいては」と敢えて主語を大きく書いた。
というのもこの単語、どうやらローカライズする側としては実に使いやすいもののようで、
テイルズオブでも頻繁に登場している。
当然、日常会話では滅多に使われない単語である。
上記動画でも、エクシリア1のガイウスの秘奥義、闢・魔神王剣の台詞が、
“Awaken! The inferno cries out…… Into oblivion! Absolute Domination!”
となっている。
こちらをかなり大雑把に訳すと、
『醒めよ!地獄が叫ぶ…… 「虚無に消えよ」と!闢・魔神王剣!』
という感じになる。
実のところ、out と into の間に文として切れ目があるかは、ボイスだけでは判然としない。
かといって、そこを繋げると全く意味不明だ。
『地獄が破滅へ向かって叫ぶ』が、その場合の直訳になるだろうが、
それをどうやって意訳すればいいか、自分では分からない。
いずれにせよ、日本語の「黄昏の地より呼び寄せし、流転の狼王!」と全く違う文章になっていることは、明確にわかるはずだ。
それも仕方のないことで、「黄昏の地」や「流転の狼王」が具体的に何を指しているか、解説できる人がいるだろうか?
いないと思う。全く謎だ。
しかし、それは悪いことではないだろう。
こういった、意味深だが荒唐無稽な表現、つまり中二病的フレーズを創っても疑問に持たれないのが、日本語の良さの一つだ。
とはいえ、ローカライズする側としてはそうもいかない。直訳すれば
“Awaken, the king of wolves, who shall cometh from the twilight world!”
辺りになるだろうが、英語で見ると正直意味不明である。
こうするぐらいならば、「黄昏の地」はとりあえず「地獄」ということにして、
狼王の部分はもはや何であるか分からないので、とりあえず強い言葉にしておこう、となる。
そこでしばしば使われるのが、oblivion というわけだ。
なおガイウスに関しては、エクシリア2にて、共鳴術技の破邪七支星にも、
Star of Oblivion という訳があてられている。
「(ハイデリンの、光の使徒よ!)
闇に抱かれて消し飛べッ!!」
FF14において、とある人物が発する台詞。
なんとはなしに、本題のジューダスの台詞と似ている。
テイルズオブ以外のネタバレは極力控えたいのと、
スクショの為だけに自力でこのシーンに辿り着く場合、1時間近くかかるのが面倒なので、動画貼り付けで勘弁願いたい。
該当のシーンは再生時間が28分を過ぎた辺りとなり、その英訳は、
“It is past time your flame was extinguished… “Bringer of Light”.”
となっている。
……そう、確かにニュアンスとしては同じであるものの、
『闇に抱かれて消し飛べ』の表現が、ストレートに落とし込まれているとはいえない訳となっている。
このシーンはまだ新生エオルゼア、FF14において(リニューアルしてから)サービス開始初期の頃であり、
ローカライズチームの体制が、それほど整っていたわけではない可能性もある。
それを差し置いても、このやけにクサい台詞の英訳が見られなかったことは、少し残念だ。
ところで、英文そのものは面白い表現となっている。
‘was extinguished’ だ。何故過去形になっているのか?
簡潔に言えば、これは仮定法となっている。
‘it is past time (that) SV ~’ という表現は、『SがVするべき時はとうに過ぎている』といった意味を表している。
past time の部分は、high time の方が有名かもしれない。
これから転じて、『いい加減、SはVしろ』という、やや遠回しな命令や、話者の強い願望の表現になることもある。
“It is high time you went to bed!”(『もう寝る時間よ!』)などは、よく聞く表現だと思う。
「話者の強い願望」というのが大切だ。
実際のことではなく、かつ行為者の意思にかかわらず、話者がそうあって欲しいと願っている。
となれば、仮定法を使うことになる。
厳密に言えば、現在の事柄に対して、現在とは違う形を求めているので、仮定法過去になる。
……単に仮定法と言えば普通、それは仮定法過去なのだが、
that節以下の助動詞を述べない、仮定法現在と混同しないようにしたい、という戒め。
ところでこの際、「正しくは was ではなく were では?」と思うかもしれないが、
口語では素直に was の形でも使われる。
途中少し話が飛んでしまったが、以上を考慮すれば、まず直訳としては
『貴様の炎がいい加減に滅されるべき時が来た(、「光をもたらすもの」よ)』
という感じになる。
「炎」が何かは、少し考えれば『魂の炎』のことであることは分かるだろう。
ただ、例の発言者が「いい加減」なんて表現を使っているのは少しダサい。
というわけで、最終的な意訳としては、
『光の使徒よ、貴様の魂、ここで消し飛ばしてくれる!』
ぐらいが自然だろうか。
極めて今更だが、タイトルの画像の人物はジューダスという名前ではない、という指摘は受け付けない。
リメイク版で逆輸入してしまったからね。