5月21日(月) 「日高敏隆選集 Ⅰチョウはなぜ飛ぶか」 (ランダムハウス講談社)

研究とは「仮説」と「検証」の繰り返しであることを軽妙に伝えた傑作! 第30回毎日出版文化賞受賞作品が復刊
日高少年の素朴な疑問と好奇心が、20年の時を経て、世の中を驚かせるチョウの生態を明らかにしていく!
そういうことをしらべてゆくうちに、ぼくらはチョウの飛ぶルートを予言できるようになった。
あらかじめあちこちのLVを測っておき、チョウがあらわれると、「次はあそこへいく」「今度はそお」というように予言してゆくのである。
チョウはほとんど予言どおりに飛んでいった。ぼくらは大喜びであった。これほど正確に予言できるということは、チョウ道のしくみが完全にわかったということである。小学校のころから二〇年以上にもわたって頭にひかかっていた問題は、これで解決したのだ! とこどが、これはそれほどかんたんではなかった。(第一部「チョウの飛ぶ道」より)
日高敏隆の本は、「春のかぞえ方」も面白かった。
5月27日(日) 「おとなり」(まなべゆきこ著)

 映画のチラシ
映画のチラシ
映画『おと・な・り』のプレ・ストーリー。「音」で繋がったお隣同士の小さな絆を描く映画『おと・な・り』。映画のストーリーの一年前から始まりまでを、ひと月ごとに描く、脚本・まなべゆきこによる書き下ろし
岡田准一と麻生久美子の主演による、30歳の男女を描いた等身大のラブストーリー。監督は「ニライカナイからの手紙」の熊澤尚人。進むべき道に迷うカメラマンの聡と、フラワーデザイナーを目指しフランス留学を控える七緒は、都会の古アパートに暮らす隣人同士。お互いに顔を合わせたこともなかった2人だが、壁越しに聞こえる生活音で次第に心を通わすようになる。
6月12日(火) 「海うそ」(梨木 香歩著)

昭和の初め、人文地理学の研究者、秋野は南九州の遅島へ赴く。かつて修験道の霊山があったその島は、豊かで変化に富んだ自然の中に、無残にかき消された人びとの祈りの跡を抱いて、彼の心を捉えて離さない。そして、地図に残された「海うそ」ということば…。五十年後、再び遅島を訪れた秋野が見たものは―。
梨木香歩の不思議な世界にどっぷりと浸かる! 他の作品も読んでみたくなった。そして次 ↓
6月17日(日) 「家守綺譚」(梨木 香歩著)

これは、つい百年前の物語。庭・池・電燈つき二階屋と、文明の進歩とやらに棹さしかねてる「私」と、狐狸竹の花仔竜小鬼桜鬼人魚等等、四季折々の天地自然の「気」たちとの、のびやかな交歓の記録。
たとえばたとえば。サルスベリの木に惚れられたり。床の間の掛軸から亡友の訪問を受けたり。飼い犬は河瞳と懇意になったり。白木蓮がタツノオトシゴを孕んだり。庭のはずれにマリア様がお出ましになったり。散りぎわの桜が暇乞いに来たり。と、いった次第の本書は、四季おりおりの天地自然の「気」たちと、文明の進歩とやらに今ひとつ棹さしかねてる新米精神労働者の「私」と、庭つき池つき電燈つき二階屋との、のびやかな交歓の記録である。
6月28日(木) 「未必のマクべス」(早瀬 耕著)

IT企業Jプロトコルの中井優一は、東南アジアを中心に交通系ICカードの販売に携わっていた。同僚の伴浩輔とともにバンコクでの商談を成功させた優一は、帰国の途上、澳門の娼婦から予言めいた言葉を告げられるー「あなたは、王として旅を続けなくてはならない」。やがて香港の子会社の代表取締役として出向を命じられた優一だったが、そこには底知れぬ陥穽が待ち受けていた。異色の犯罪小説にして、痛切なる恋愛小説。
朝日新聞(6/9)の売れてる本で紹介されていた。しかも「中年くすぐる懐かしい香り」とも。
「この小説の魅了を語るのは難しい。経済小説であり、犯罪小説であり、ハードボイルド小説であり、恋愛小説でもあるのだが、そういうジャンルに押し込もうとすると、魅力がどんどんこぼれていく気がするからだ。文章が滑らかで気持ちいいこと。どこか甘く、懐かしい香りが漂っていること。遠い昔のことをどんどん思い出すこと。・・・」(北上次郎)で決定!
7月16日(月) 「陽炎の門」(葉室 麟著)

友を陥れてまで、己は出世を望んだのか――。若き執政がゆく道は、栄達か、修羅か。
職務において冷徹非情、若くして執政の座に昇った桐谷主水。かつて派閥抗争で親友を裏切り、いまの地位を得たと囁かれている。三十半ばにして娶った妻・由布は、己の手で介錯した親友の娘だった。あるとき、由布の弟・喬之助が仇討ちに現れる。友の死は己が咎か――主水の足元はにわかに崩れ、夫婦の安寧も破られていく。すべての糸口は、十年前、主水と親友を別った、ある〈事件〉にあった。
著者史上、最上の哀切と感動が押し寄せる。組織を生き抜く者たちへ--直木賞作家・葉室麟の最新作! 峻烈な筆で描き出す、渾身の時代長編!!
7月21日(土) 「殉教者」(加賀 乙彦著)

友を陥れてまで、己は出世を望んだのか――。若き執政がゆく道は、栄達か、修羅か。
職務において冷徹非情、若くして執政の座に昇った桐谷主水。かつて派閥抗争で親友を裏切り、いまの地位を得たと囁かれている。三十半ばにして娶った妻・由布は、己の手で介錯した親友の娘だった。あるとき、由布の弟・喬之助が仇討ちに現れる。友の死は己が咎か――主水の足元はにわかに崩れ、夫婦の安寧も破られていく。すべての糸口は、十年前、主水と親友を別った、ある〈事件〉にあった。
著者史上、最上の哀切と感動が押し寄せる。組織を生き抜く者たちへ--直木賞作家・葉室麟の最新作! 峻烈な筆で描き出す、渾身の時代長編!!
この本を読むきっかけとなったのが朝日新聞土曜連載の<みちのものがたり>(2018/6/30)でした。そのタイトルは「ペトロ岐部殉教への道」(大分県)です。<「司祭になる」一路ローマへ>や<決死の帰国、信徒支え続け>で読んでみることにした。小説として遠藤周作の「銃と十字架」もいづれ読みたい。
7月28日(土) 「柚子の花咲く」(葉室 麟著)

一人の武士の遺骸が河岸で見つかった。男は村塾の教師・梶与五郎。かつての教え子・日坂藩士の筒井恭平は、師が殺された真相を探るべく隣藩へ決死の潜入を試みる―。命がけで人を愛するとは、人生を切り拓く教育とは何かを問う、感動の長篇時代小説。
梶与五郎の口癖である「桃栗三年、柿八年、柚子は九年で花が咲く」が印象的。筒井恭平のまっすぐな生き方が魅力で、ぐいぐいと物語に引き込まれていく。「徳は孤ならず、必ず隣有り」という孔子の言葉を思い出した。まっすぐに生きてさえいれば、孤独ではない、支える人が現れるという意味だ。まさに恭平の生き方で、強く勇気をもらった。(解説<江上剛>より)
8月27日(月) 「奥のほそ道」(リチャード・フラナガン著)
 朝日新聞(7/21)で紹介されていた
朝日新聞(7/21)で紹介されていた
1943年、タスマニア出身のドリゴは、オーストラリア軍の軍医として太平洋戦争に従軍するが、日本軍の捕虜となり、タイとビルマを結ぶ「泰緬鉄道」(「死の鉄路」)建設の過酷な重労働につく。そこへ一通の手紙が届き、すべてが変わってしまう……。
本書は、ドリゴの戦前・戦中・戦後の生涯を中心に、俳句を吟じ斬首する日本人将校たち、泥の海を這う骨と皮ばかりのオーストラリア人捕虜たち、戦争で人生の歯車を狂わされた者たち……かれらの生き様を鮮烈に描き、2014年度ブッカー賞を受賞した長篇だ。
作家は、「泰緬鉄道」から生還した父親の捕虜経験を題材にして、12年の歳月をかけて書き上げたという。東西の詩人の言葉を刻みながら、人間性の複雑さ、戦争や世界の多層性を織り上げていく。時と場所を交差させ、登場人物の心情を丹念にたどり、読者の胸に強く迫ってくる。


















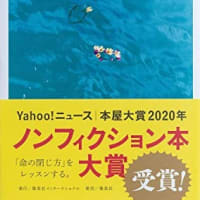

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます