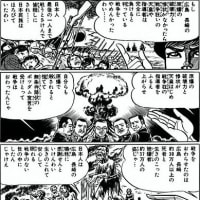ここに2枚の版画がある。どちらも町を背景とした雪景色、どちらも人物は傘をさして前かがみで、後ろに点々と足跡を残してそれぞれの目的地へ歩んでいる。薄明かりの雪の中、ほの暗いがしかし決して荒々しくは無いつつましい人々の暮らしが見えるようだ。
1枚目はフランスのアンリ・リヴィエールの「エッフェル塔三十六景の内、建築中のエッフェル塔」の図、1902年作。
2枚目は日本の歌川広重の「東海道五十三次の内、蒲原夜之雪」の図、1832年(天保3年)作。
パリの浮世絵師と言われるアンリ・リヴィエールは、北斎や広重など、浮世絵の風景画に心酔したパリの画家で、木版画を制作するための道具まで自ら考案し、絵師、彫師、摺師の仕事をひとりで行ったそうだ。
浮世絵といえば、日本の名品の多くが実は海外にあると聞く。明治維新の頃、われわれのひい祖父さんだかひいひい祖父さんたちは、文明開化と叫んで、東海道五十三次を売り飛ばして、鉄筋レンガ造りの洋館建物や蒸気機関車や蒸気船を買ったのだ。
当時も、また今に至る後世の者もそれを、明るい明治、若き力の明治、勝った勝ったと、大声でもてはやす者が多い。
しかし、浮世絵を異人さんに売り飛ばしたわれわれの祖父さんたちの多くも、喜んで売った人ばかりではなかろう。いや多くは、自分や身内の人の生活のために心ならずも手放したのであろう。
確かに幕末の頃の徳川幕府を頂点とする日本の社会体制は、長期権力の宿命として隅々まで腐りきっていて、有るものを泣く泣く売り飛ばしてでも政体を変えるしか国民の生残る道は無かっただろうと思う。
大切なことは、明治の先人たちのその維新前後の哀しみや先行きへの不安感から、目をそらさないことではないだろうか。
それをほったらかして、やれ明治の人は偉かった、やれ強かった、素晴らしい素晴らしい、などと大声でもてはやすドラマなどの横行する様子を見ていると、これは、やがてまた来るであろう体制の腐敗の病原菌なのではないか、とさえ思ってしまう。
もう一度「エッフェル塔三十六景の内、建築中のエッフェル塔」と「東海道五十三次の内、蒲原夜之雪」に戻って。
リヴィエールが浮世絵に出合ったのは、ロートレックも常連だったモンマルトルのカフェ「シャ・ノワール」だったという。彼は浮世絵を愛するあまり、北斎「富嶽三十六景」へのオマージュとしてリトグラフ集「エッフェル塔三十六景」を制作した。そのうちの一枚がこの「建築中のエッフェル塔」だそうだ。
かたやフランスかたや日本、かたや1900年製作かたや1830年、国も時代も大きく隔たるこの2枚の版画は、私にはまるで双子の兄弟のようにそっくりに見える。
どちらも「文明開化、勝った勝った」の雄たけびの風景ではない。
どちらにも、元帥や大臣や財閥創業者、英雄や成功者の姿は描かれていない。
描かれているのは、雪の街角と、雪の中のやさしい人々の姿である。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
上からは明治だなどというけれど 治まるめいと下からは読む
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++