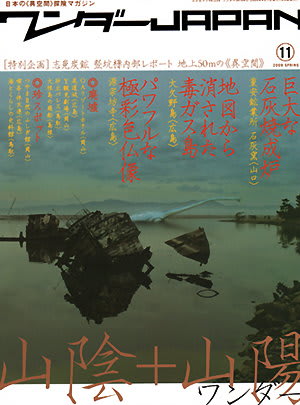長崎産業遺産視察勉強会~池島炭鉱編1~
前回の記事に引き続き、
今年の7月に行なわれたJ-ヘリテージ主催の、
『長崎産業遺産視察勉強会』に参加した時のリポートです。
J-ヘリテージは、現代社会が抱える様々な問題点を、
近代化遺産を振り返ることでその解決の糸口を模索しようとするNPO団体で、
様々な遺産の見学会を開催したりメディアで遺産の必要性を訴えている団体です。
そんなJ-ヘリテージが主催した『長崎産業遺産視察勉強会』は、
軍艦島の非見学エリアと池島特別見学コースの視察という、
とても内容の濃いものでした。
今回は池島炭鉱の視察のリポート前半です。

池島炭鉱は長崎県中部の外海側にある小島で、
かつて島内に大きな池があることから池島と呼ばれていましたが、
1950年代の後半、炭鉱の開発によって池は港に改築され、
島の多くが炭鉱とその住宅施設に変貌した島です。
約40年にわたって操業した池島は2001年に閉山し、
その後約10年、東南アジアの研修所として使われ、
現在では全ての操業が停止しています。
軍艦島の視察は昼過ぎからの約2時間で、その足で池島へ。
軍艦島の視察中は運良く晴れていたましたが、
池島へ向かう途中、雲行きは再び怪しくなり、
フェリーから見る池島の上空には、重たい雨雲が乗っていました。

しかし島に着く頃にはまたまた運良く晴れ出し、
以降2日に渡る池島視察中は、ずっと晴天に。
港にはいつものように沢山の猫がいます。
島民が減少の一途にある池島では、
もはや島民より猫の方が多いと言われる程、
猫島化している島でもあります。

この日は夕方遅くに島に到着したので、
特に見学とかはなかったので、ちょっと島内を散策。
島の奥に建つ8階建てのアパートが、
夕日に照らされたオレンジ色に染まっていました。
◆
夜は懇親会が開かれ、
約40人の参加者が自己紹介を兼ねて、
ご自分の活動等のPRをすることになったのですが、
みなさん、情熱的な方ばかりで話にも熱が入り、
結局それだけで終わってしまいました。
ご自分に関係のある地域活性化の活動をされている方や、
産業遺産の保存を考えている方等、
みなさん素晴らしい活動をされている方々でした。

翌朝の朝ご飯は、島内で唯一常営している食堂、
「かあちゃんの店」のまかないで合宿気分です。

午前中は坑外施設、つまり炭鉱の坑道以外の施設の見学です。
繰込所(あるいは発進所)は、
坑道へ仕事で入る前に待機して、装備の点検や準備をするところ。
正面には「あとでよりいまが大切 点検と確認」と、
いかにも炭鉱らしい標語が掲げられていますが、
実はこの掲示は、今年の夏池島でロケが行われた、
映画『池島譚歌』のロケ用に新しく設置されたものです。
※もしかしたら映画『信さん・炭坑町のセレナーデ』の時かも…
でも、本物より本物っぽいですね。

繰込所の建物の一階には、
操業時の写真が展示されたスペースがあります。
右側に写るのは上から三枚目の画像の8階建てのアパート。
もう今では灯りがともることのないアパート群に、
沢山のあかりが灯っています。
◆
この後、様々な坑外施設を見学するのですが、
多くは以前の記事で既に触れているので、
そちらをご覧になって頂ければと思います。
・繰込所のある建物内の炭鉱風呂や管理室(この記事の中頃)
・繰込所のある建物の隣の第二竪坑の捲座(この記事の終わり頃)

そんな中、
以前の見学時には外観だけを横目で見ていた画像の施設を、
今回はじっくりと説明して頂きました。
この施設は扇風機と言って、坑内の空気を循環する為の施設です。
下部に写る黒い筒の中に大型の扇風機が設置され、
坑道に繋がっている左側から右に写るラッパ状の吹出口の方向へ、
空気を排出する装置です。
炭鉱では、空気を送り込むのではなく、
排出することによって、別の坑口から自然に空気が入る様に作られています。

上画像の左側を見た所。2つの同じ構造物があります。
右は鉄の板があり左にはないように見えますが、
ないのではなく、下に降りています。
鉄の板が弁の役割を果たし、
今は右側の方が通気出来る状態にあることを示しています。
万が一右の扇風機が故障した際には、
即座に右の鉄の板を降ろし、左の鉄の板を引き上げて、
左側で通気を行なう仕組みになっています。
通気は坑道の中で働く炭鉱マンの命綱。
24時間、決して休むこと無く動き続ける必要があります。

坑外施設の見学の後は住宅棟エリアの見学です。
炭鉱アパートの中に一部屋だけ、
見学出来る様に解放された部屋があります。
内部はちょっと作り込みが多く、
あまり当時のリアルな生活を偲ぶことはできませんが、
それでも間取りやトイレ事情等、
炭鉱アパートがどのようなものだったかを知ることはできます。
それを見る限り、決して炭鉱アパートの部屋は広くはなく、
たとえ高給取りだったとしても、
その生活は派手なものではなかったんだと思います。

玄関のノブの下には、
「ヨシ!」と声をあげる炭鉱マンのイラストシールが貼られています。
このかけ声は炭鉱での仕事で、安全を確認する時のかけ声です。
後貼りかそれとも当時から貼ってあったものかはわかりませんが、
炭鉱アパートならではですね。

そのほか島内を周回する道も一回りし、
その周囲にある施設も一通り見学。
気になったのは画像の汚水処理施設。
汚水といってもいわゆるし尿処理。
果たしてこの装置がどう処理してくれるか想像もつきませんが、
島という環境は、
陸続きの生活以上の苦労がつきものなのだと実感します。
次回、池島炭鉱の後半は坑道内の見学です。
前回の記事に引き続き、
今年の7月に行なわれたJ-ヘリテージ主催の、
『長崎産業遺産視察勉強会』に参加した時のリポートです。
J-ヘリテージは、現代社会が抱える様々な問題点を、
近代化遺産を振り返ることでその解決の糸口を模索しようとするNPO団体で、
様々な遺産の見学会を開催したりメディアで遺産の必要性を訴えている団体です。
そんなJ-ヘリテージが主催した『長崎産業遺産視察勉強会』は、
軍艦島の非見学エリアと池島特別見学コースの視察という、
とても内容の濃いものでした。
今回は池島炭鉱の視察のリポート前半です。

池島炭鉱は長崎県中部の外海側にある小島で、
かつて島内に大きな池があることから池島と呼ばれていましたが、
1950年代の後半、炭鉱の開発によって池は港に改築され、
島の多くが炭鉱とその住宅施設に変貌した島です。
約40年にわたって操業した池島は2001年に閉山し、
その後約10年、東南アジアの研修所として使われ、
現在では全ての操業が停止しています。
軍艦島の視察は昼過ぎからの約2時間で、その足で池島へ。
軍艦島の視察中は運良く晴れていたましたが、
池島へ向かう途中、雲行きは再び怪しくなり、
フェリーから見る池島の上空には、重たい雨雲が乗っていました。

しかし島に着く頃にはまたまた運良く晴れ出し、
以降2日に渡る池島視察中は、ずっと晴天に。
港にはいつものように沢山の猫がいます。
島民が減少の一途にある池島では、
もはや島民より猫の方が多いと言われる程、
猫島化している島でもあります。

この日は夕方遅くに島に到着したので、
特に見学とかはなかったので、ちょっと島内を散策。
島の奥に建つ8階建てのアパートが、
夕日に照らされたオレンジ色に染まっていました。
◆
夜は懇親会が開かれ、
約40人の参加者が自己紹介を兼ねて、
ご自分の活動等のPRをすることになったのですが、
みなさん、情熱的な方ばかりで話にも熱が入り、
結局それだけで終わってしまいました。
ご自分に関係のある地域活性化の活動をされている方や、
産業遺産の保存を考えている方等、
みなさん素晴らしい活動をされている方々でした。

翌朝の朝ご飯は、島内で唯一常営している食堂、
「かあちゃんの店」のまかないで合宿気分です。

午前中は坑外施設、つまり炭鉱の坑道以外の施設の見学です。
繰込所(あるいは発進所)は、
坑道へ仕事で入る前に待機して、装備の点検や準備をするところ。
正面には「あとでよりいまが大切 点検と確認」と、
いかにも炭鉱らしい標語が掲げられていますが、
実はこの掲示は、今年の夏池島でロケが行われた、
映画『池島譚歌』のロケ用に新しく設置されたものです。
※もしかしたら映画『信さん・炭坑町のセレナーデ』の時かも…
でも、本物より本物っぽいですね。

繰込所の建物の一階には、
操業時の写真が展示されたスペースがあります。
右側に写るのは上から三枚目の画像の8階建てのアパート。
もう今では灯りがともることのないアパート群に、
沢山のあかりが灯っています。
◆
この後、様々な坑外施設を見学するのですが、
多くは以前の記事で既に触れているので、
そちらをご覧になって頂ければと思います。
・繰込所のある建物内の炭鉱風呂や管理室(この記事の中頃)
・繰込所のある建物の隣の第二竪坑の捲座(この記事の終わり頃)

そんな中、
以前の見学時には外観だけを横目で見ていた画像の施設を、
今回はじっくりと説明して頂きました。
この施設は扇風機と言って、坑内の空気を循環する為の施設です。
下部に写る黒い筒の中に大型の扇風機が設置され、
坑道に繋がっている左側から右に写るラッパ状の吹出口の方向へ、
空気を排出する装置です。
炭鉱では、空気を送り込むのではなく、
排出することによって、別の坑口から自然に空気が入る様に作られています。

上画像の左側を見た所。2つの同じ構造物があります。
右は鉄の板があり左にはないように見えますが、
ないのではなく、下に降りています。
鉄の板が弁の役割を果たし、
今は右側の方が通気出来る状態にあることを示しています。
万が一右の扇風機が故障した際には、
即座に右の鉄の板を降ろし、左の鉄の板を引き上げて、
左側で通気を行なう仕組みになっています。
通気は坑道の中で働く炭鉱マンの命綱。
24時間、決して休むこと無く動き続ける必要があります。

坑外施設の見学の後は住宅棟エリアの見学です。
炭鉱アパートの中に一部屋だけ、
見学出来る様に解放された部屋があります。
内部はちょっと作り込みが多く、
あまり当時のリアルな生活を偲ぶことはできませんが、
それでも間取りやトイレ事情等、
炭鉱アパートがどのようなものだったかを知ることはできます。
それを見る限り、決して炭鉱アパートの部屋は広くはなく、
たとえ高給取りだったとしても、
その生活は派手なものではなかったんだと思います。

玄関のノブの下には、
「ヨシ!」と声をあげる炭鉱マンのイラストシールが貼られています。
このかけ声は炭鉱での仕事で、安全を確認する時のかけ声です。
後貼りかそれとも当時から貼ってあったものかはわかりませんが、
炭鉱アパートならではですね。

そのほか島内を周回する道も一回りし、
その周囲にある施設も一通り見学。
気になったのは画像の汚水処理施設。
汚水といってもいわゆるし尿処理。
果たしてこの装置がどう処理してくれるか想像もつきませんが、
島という環境は、
陸続きの生活以上の苦労がつきものなのだと実感します。
次回、池島炭鉱の後半は坑道内の見学です。