平城遷都1300年祭の記念事業、秋の秘宝・秘仏特別開帳で、奈良市の「西大寺」を拝観してきました。
毎年1月、4月、10月に大茶盛式という行事があるお寺です。
奈良時代に創建された、東の東大寺に対する西の大寺でしたが、室町時代に兵火などによって多くの御堂や塔を焼失したそうです。
現在の境内も十分に広いのですが、それでも創建時の広さの1割にも満たないのだとか。
(※このブログの写真は全てクリックをすると拡大表示できます。)

 江戸時代建立の重要文化財・西大寺の本堂です。この本堂は、土壁でなく板壁になっています。
江戸時代建立の重要文化財・西大寺の本堂です。この本堂は、土壁でなく板壁になっています。
ご本尊の釈迦如来立象と、堂内に安置された文殊菩薩騎獅像・四侍者像も重要文化財です。
その四侍者像のひとつ善財童子像は、灰谷健次郎作「兎の眼」という小説に出てきます。この童子像の目を主人公が“兎の眼”に喩え、それが表題になっています。堂内の善財童子像の前に、この小説のことも書かれていました。
そして、本堂の前には、東塔の基壇跡があります。

 本堂の横にある愛染堂です。この堂内に祀られている重要文化財・愛染明王座像が秘仏特別開扉で拝観させていただくことが出来ました。
本堂の横にある愛染堂です。この堂内に祀られている重要文化財・愛染明王座像が秘仏特別開扉で拝観させていただくことが出来ました。

 境内の鐘楼です。右に少しだけ写っている光明殿というところで、大茶盛式が行われるそうです。
境内の鐘楼です。右に少しだけ写っている光明殿というところで、大茶盛式が行われるそうです。

 軒のところなど、朱色や金色が鮮やかに残っているので、最近の再建かと思ったら1674年建立の四天堂。
軒のところなど、朱色や金色が鮮やかに残っているので、最近の再建かと思ったら1674年建立の四天堂。
約6mもある十一面観音立象と、約2mの四天王立像(どちらも重要文化財)が安置されています。
四天王像は銅製で、兵火で焼け溶け、増長天像の足下の邪鬼のみが天平時代のもので、あとは後世の再鋳だそうす。そして多聞天像は、銅が足りなくなって、ひとつだけ木像なのだそうです。

 南門から見た本堂。本当はここが正門なんですって。日曜日に拝観に行ったので境内は大勢の参拝者が来られていましたが、ここは駅や駐車場と逆の方向にあるので、ひっそりとしていました。
南門から見た本堂。本当はここが正門なんですって。日曜日に拝観に行ったので境内は大勢の参拝者が来られていましたが、ここは駅や駐車場と逆の方向にあるので、ひっそりとしていました。

 南門からの参道ごしに見た東塔跡基壇と金堂。紅葉が色づいていました。
南門からの参道ごしに見た東塔跡基壇と金堂。紅葉が色づいていました。

 西大寺本坊。
西大寺本坊。
ここは宗務所なので、恐らく普段は参拝客は入れないのではないかと思われますが、この日は水墨画の展示会が開催されていて見学が出来ました。
また、境内では寺宝を展示している聚宝館という展示館も見学ができました。
なお、西大寺の秘宝・秘仏特別開帳は終了しています。
近鉄大和西大寺駅から南西へ徒歩5分ほど。
有料駐車場有り。
毎年1月、4月、10月に大茶盛式という行事があるお寺です。
奈良時代に創建された、東の東大寺に対する西の大寺でしたが、室町時代に兵火などによって多くの御堂や塔を焼失したそうです。
現在の境内も十分に広いのですが、それでも創建時の広さの1割にも満たないのだとか。
(※このブログの写真は全てクリックをすると拡大表示できます。)

 江戸時代建立の重要文化財・西大寺の本堂です。この本堂は、土壁でなく板壁になっています。
江戸時代建立の重要文化財・西大寺の本堂です。この本堂は、土壁でなく板壁になっています。ご本尊の釈迦如来立象と、堂内に安置された文殊菩薩騎獅像・四侍者像も重要文化財です。
その四侍者像のひとつ善財童子像は、灰谷健次郎作「兎の眼」という小説に出てきます。この童子像の目を主人公が“兎の眼”に喩え、それが表題になっています。堂内の善財童子像の前に、この小説のことも書かれていました。
そして、本堂の前には、東塔の基壇跡があります。

 本堂の横にある愛染堂です。この堂内に祀られている重要文化財・愛染明王座像が秘仏特別開扉で拝観させていただくことが出来ました。
本堂の横にある愛染堂です。この堂内に祀られている重要文化財・愛染明王座像が秘仏特別開扉で拝観させていただくことが出来ました。
 境内の鐘楼です。右に少しだけ写っている光明殿というところで、大茶盛式が行われるそうです。
境内の鐘楼です。右に少しだけ写っている光明殿というところで、大茶盛式が行われるそうです。
 軒のところなど、朱色や金色が鮮やかに残っているので、最近の再建かと思ったら1674年建立の四天堂。
軒のところなど、朱色や金色が鮮やかに残っているので、最近の再建かと思ったら1674年建立の四天堂。約6mもある十一面観音立象と、約2mの四天王立像(どちらも重要文化財)が安置されています。
四天王像は銅製で、兵火で焼け溶け、増長天像の足下の邪鬼のみが天平時代のもので、あとは後世の再鋳だそうす。そして多聞天像は、銅が足りなくなって、ひとつだけ木像なのだそうです。

 南門から見た本堂。本当はここが正門なんですって。日曜日に拝観に行ったので境内は大勢の参拝者が来られていましたが、ここは駅や駐車場と逆の方向にあるので、ひっそりとしていました。
南門から見た本堂。本当はここが正門なんですって。日曜日に拝観に行ったので境内は大勢の参拝者が来られていましたが、ここは駅や駐車場と逆の方向にあるので、ひっそりとしていました。
 南門からの参道ごしに見た東塔跡基壇と金堂。紅葉が色づいていました。
南門からの参道ごしに見た東塔跡基壇と金堂。紅葉が色づいていました。
 西大寺本坊。
西大寺本坊。ここは宗務所なので、恐らく普段は参拝客は入れないのではないかと思われますが、この日は水墨画の展示会が開催されていて見学が出来ました。
また、境内では寺宝を展示している聚宝館という展示館も見学ができました。
なお、西大寺の秘宝・秘仏特別開帳は終了しています。
近鉄大和西大寺駅から南西へ徒歩5分ほど。
有料駐車場有り。
















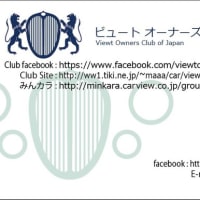


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます