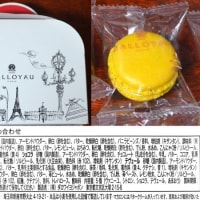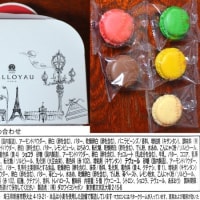竹取物語において1000年の謎になっている文章はいくつかあります。
そのうち『かまど』について解読できたので、論文にして投稿してみました。
残りの『十六そをかみにくとをあけて』の解読内容についての論文や
『我が名はうかんるり』の解読内容についての論文を書くには
『かまど』論文でまとめた内容を自分で引用しなければまとめられないため、
次を書く前に、かまどの論文だけはどうしても先に出す必要があります。
……が、採用はされません。
論文を改良するためのコメントすらつかないので、直しようもありません。
大学の恩師はこういうのをやってきて、その場所にいたんだなあと思うと、
ようやくいろいろなものが見えてきてため息をつくばかりです。
そこで、暑中お見舞いついでに近況報告として
そんなことを書いてみたところ、読んでみたいと言われたので、
ジャンルはまったく違うけれどと思いながら送ってみました。
すると、すぐに返事が来て、いろいろ書いてありました。
まずは、わたしの理論が一般的には微妙なこと。
これはわたしも書きながらうっすら思っていました。
わたしの解読は、埋蔵金探しのようなものです。
ほかの人は、よくわからない古文書の文章をそのまま追っていって、
論理的に埋蔵金に迫ろうとしています。
その結果、数百年かかっても埋蔵金にたどり着けてさえいません。
でもわたしは最初に埋蔵金を見つけてしまったので、
その埋蔵金が文章にかかれているそのものであることと、
古文書が間違いなくそこを示していたのだということを、
通常とは逆側から説明していかなくてはいけません。
でも、だれが何の目的で埋めたのか、それが本物かもわからないような
埋蔵金とは違い、わたしの見つけたものは文章の訳です。
周りの文章と比べても、文脈から見ても、
日本語がまともに読める人ならその答えを
決しておかしくないと思うはずです。
……が。そこにいたるまでの論理が、
一般的でないと認められないそうです。
一般的な説明で迫ろうとしていたから、
今までの少なくとも300年間の人は答えがわからなかったのです。
だからこそ一般的な方向からの説明では答えにたどりつけないのに、
答えにたどり着ける一般的でない説明は、
一般的でないからだめだとなっては、結局答えにたどりつけません。
ただし、国文学業界の大御所であれば、
真新しい説を真新しいまま発表しても、
驚きをもって受け入れられることは普通にあるそうです。
やっぱりそういうものなのかとがっかりしていたら、
とりあえず新訳を使って全部書いてみてもと言われたので、
やってみることにしました。
ひさしぶりに長文やりとりをしましたが、
先生の言葉の中には知性の光というか、何かの輝きが感じられて、
自分の目も開くような感じがあります。
論文を書くことだけに一生懸命で、
途中ですっかり忘れていたものも思い出すこともでき、
ああいうのが聡明というものかと、しみじみ感じ入りました。
実のところ、論文が雑誌に載ったら、
先生にそれを送って、すこしでも近づけましたと
調子に載るつもりだったのですが、まだまだ遠かったようです。