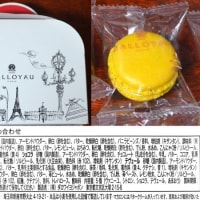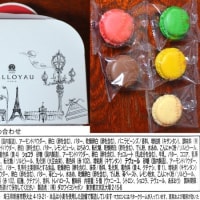ちょっと前、八坂神社を調べていて
スサノオに関連しそうな素桜神社あたりで見かけたアラハバキ。
正体不明の神様として考えられているそうなので、
その正体がわかるかどうかちらっと調べて考えてみました。
まず、アラハバキ、という名前。
意味で単語を分けると、『アラ』と『ハバキ』とにできそうです。
この『アラ』=『荒』は、戦争で敗北したことにより
勝者からつけられたものか、
あるいは、居留地系名称に見えます。
すると、名前の本体は『ハバキ』であると考えられます。
古い時代の知識からすると、
ハバキと言って思い浮かぶのはホウキです。
現代語で『ほうき』と言えば箒ですが、
これの古語は『はばき』。
この音は中古時代でも同様で、
『伯耆(ほうき)の国』の別名は『はばき』と言います。
これを思うと、アラハバキとは
『伯耆(ホウキ=ハバキ)』の神だったのではないか、
とひとまず仮定することができます。
ところで、伯耆のそばには出雲があります。
ここにはすごく大きな出雲大社があり、
今の祭り神は大穴持です。
……が。古い文献を調べると、現在の地は本来の出雲ではなく、
単に別の場所にあった本物の出雲の地の名前を持ってきただけの、
ニセ出雲だということがわかります。
これについては理屈だけはまとめましたので興味があれば参照を。
神道の話とからめたちゃんとした内容はまとめ中です。
参照:
[>神話の地 出雲という神話
https://blog.goo.ne.jp/nanmo-nanmosa/e/fd92b5a2b6c99cef0ea7761a228799b1
さて。
『ハバキからどこかへうつされた』
ということを思うと、連想されてくるものがあります。
『出雲から諏訪にうつされた』
という古事記の話です。
出雲あたりには、オオクニヌシと二人の子、コトシロヌシ、
タケミナカタがいて、幸せに国をおさめていたと言います。
でも、それを他国で知ったアマテラスはむかっとし、
「そんな素敵な国、オオクニヌシなんかにゃもったいない!
そこはあたしらの子にこそふさわしい。よこせ!」
と思って、ぶんどるためにタケミカヅチを派遣します。
いきなりやってきたタケミカヅチはオオクニヌシたちに、
「お前のものはおれのもの。おれのものはおれのもの。
なんか文句あるか!?」
と言いますが、タケミナカタが反発。武力衝突します。
タケミカヅチは圧倒的な戦力差で
タケミナカタのアームズを壊して無力化し、諏訪に追放しました。
……という内容は、名前や行為などから、
ハバキの伝説につながりそうではないでしょうか?
わたしは、古事記や日本書紀がまったくのでたらめを
書いているとは思っていません。
何かしらの古代史実を込めているのだと考えています。
ハバキの地から、難癖をつけられて
国を奪われて諏訪に追いやられた神……
もしかすると、古事記に言うタケミナカタが、
ハバキ神なのではないでしょうか。
アラハバキは伝説では、その音からも足腰の神様と言われています。
つまり、手ではないのです。
タケミナカタも、手を奪われています。
さらに、タケミナカタの名前を見ると、
建御名方、南方刀美、御名方富というものがあります。
タケミナカタ、ミナカタトビ、ミナカタトブ、もしくはミナカタトミ。
タケミナカタに関連する神様で、
こんな名前を持った神がいましたよね?
最初で述べた、素桜神社でも祭られていた、
八坂刀売(ヤサカトメ)です。
古くから、トジだのトメだのヒメだのは女性をあらわす単語です。
では、男のタケミナカタに、なぜ『刀美』、『富』がつくのでしょうか。
……本当は、タケミナカタは『ミナカタの女』ではないのでしょうか。
タケミナカタは八坂刀売と結婚したと言います。
でも、名前からするとタケミナカタは実は女性であって、
女性ゆえに女性と結婚はできないことから、
『八坂刀売と結婚した』、言い換えれば
『八坂刀売といっしょになった』タケミナカタは、
八坂刀売その人なのではないかと思えます。
ヤサカトベは、ヤサカがあることから、スサノオ系に見えます。
オオナムチもたしかスサノオ系統の養子になっていたはず。
場所と伝説を考えても異常はありません。
他にも、同じく古事記だと、
ハバキに近い言葉で『ハバカ』があります。
これは桜の類をあらわします。
桜といえばスサノオ系統のシンボルでもあります。
すると、素桜神社には、
・スサノオが植えたという桜があり、
・スサノオの『素』が名前にあり、
・スサノオと共通する『ヤサカ』をもつヤサカトベがおり、
・桜の『ハバカ』に近い音を持つアラハバキの地にあり、
・ハバキから追放されたタケミナカタの話が聞こえる、
という内容が見えます。
わたしにはこれは偶然とは思えないのです。
もっときちんと調べてみないとなんともいえませんが、
今のところの結論としては、
『アラハバキ』は、ハバキの地から追いやられた
『タケミナカタ』であって、女性です。
これが正しいとすると、スサノオ一派は、
出雲や九州などの大地域を支配していたものの、
アマテラス一派の生き残りに巻き返されて、
大戦争の末に負け、諏訪に飛ばされたということになります。
すると、スサノオを祀る神社の中にアラハバキがいるのも納得できます。
ハバキの神はスサノオの子孫で同族だからです。
素桜神社の伝説を見て、ひとまずわたしが考えるのはこんなところです。
こういうふうに仮説を立てたものは仮説としておいておき、
神道文書や神社の縁起、伝承などを調べている最中に出会う内容で
説が補強できるものがあれば補強して、
説を否定するものがあれば修正していくというのが
古代神道の研究です。
まだまだ途中ですが、
すでにいくつもの誤りを見つけている
現在の神道、明治神道の誤りの指摘や
神道文書の解読などやっていますので、
興味があれば自作本カテゴリをごらんください。