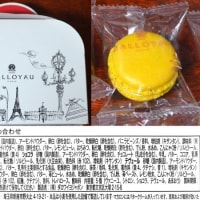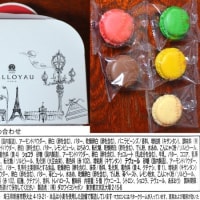最近、古い本を読んだりいろいろ見たりして、
昔のことを調べています。
その中で、ふと、ものすごくおかしなことに気づきました。
しめなわのことです。
しめなわ。注連縄とも七五三縄とも書かれ、
神社などにかけられるあれですが、
なぜ、あれをしめなわと呼ぶのでしょうか?
だれが、言い始めたのでしょうか?
神社の上にかかっているようなあれ、
腰に巻いたら『横綱』です。
どこかに張ったしめ『縄』を交換するのは、
『綱』替え、『綱』掛けなどと言ったりします。
みんな普通に、しめなわしめなわと呼んでいますが――
あれ、本当は『しめつな』じゃないんでしょうか?
なぜみんなあれをしめなわと呼んでいるのか、
どう見ても綱のものをしめなわとして飾っている神社の人は
あれに疑問を持たないのか、本当のところが知りたいです。
今の世の中には、失われてしまったものが多すぎます。