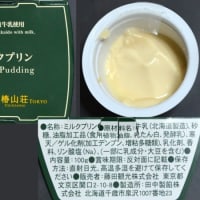●記録可能光学メディアの寿命?
昔焼いたCD-Rのデータ、読み出そうとしたら
エラーが出てなんにも取り出せなかったんだけど。
CD-Rって一回焼けばずっと使えるもんなんじゃないの?

回転式の記録メディアは
感熱紙みたいなものなんだからねっ!
★ポイント
CDやDVDなどの回転式メディアは
プラスティックの円盤に、金箔のようなものを
貼り付けて作られています。
それは、記録できないCDでも、CD-Rでも同じです。
(※これ以降、回転式光学メディアのことを
総括して『CD』と記述します)
CDを裏から見るときらきらして見えますが、
あれはCD表面のすぐ裏。
CD表面に貼り付けた、金箔のようなものを
裏から見ているだけにすぎません。
そのため、ただのレーベルだと思っている
表面に裏まで貫通する傷をつけると、
CDは読むことができなくなってしまいます。
一方、プラスティック面についた傷は、
読み込むときのレーザーを曲げてしまうために
読めなくなるだけで、
データ自体が壊れるわけではありません。
プラスティックディスクを傷がなくなるまで
平らに削りこんでいけば、データをまた
読み出すことは可能になるのです。
適当にたとえて言うなら、
CDのレーベル面は家。
CDのプラスティック面は道路です。
CDのプラスティック面を傷つけることは、
家へとたどり着く道を閉ざすことです。
そのために家、すなわちデータへと
たどりつけなくなってしまいます。
一方、CDのレーベル面を壊すことは
家自体を壊すことです。
たとえ道があったとしても、
家自体が壊れてしまえば
家にたどり着くことは二度とできません。
それほど重要なCDのレーベル面ですが、
実はとても貧弱なつくりをしています。
特に、記録可能なものはそうです。
本当に金箔のような、アルミホイルのようなものが
一枚、ぺたりと貼り付けてあるだけ。
切り傷をつけてガムテープをはれば、
そこから簡単にはがせてしまいます。
CDというもののプラスティック部分と
ぺらぺらのレーベル部分を人間で置き換えると、
プラスティック部分が肉体、
レーベル部分が魂と言えます。
CDの魂の座はレーベル部分にあります。
そして、CDの魂は直接的な傷にとても弱いのです。
すこしでも長持ちさせたいなら、
レーベル部分の扱いに特に気をつけましょう。
でも、どれだけ気をつけていても
CDのデータが読み出せなくなることがあります。
それが、CDの寿命です。
CD-RやDVD Rなど、R(Recordable、記録可能)
属性がついて売られているものは、
初めからデータを焼き付けてある
音楽CDなどのプレスCDよりも寿命が短いです。
でも、どちらにしても寿命があることには
変わりませんけれど。
……というのも、レコーダブル光学メディアの
記録方式は、基本的には感熱紙と同じだからです。
感熱紙とは、FAX用紙やレジのレシート用紙で
よく使われている、熱によって変色する
紙のことです。
CD-Rなどにデータを入れることを
『焼く』と表現しますが、
感熱紙に焼きいれるという意味からも
かなりイメージに近い言いまわしだと言えます。
たばこを畳に落として焼けてしまったら
畳を交換するまで焼け焦げは消えないので
焼いたCDのデータも消えないと思うかもしれませんが、
感熱紙にとっての『焼く』というのは
それほどはっきりしたものではありません。
むしろ、金属にとっての錆のようなものです。
錆は金属が酸素と結合してできるものですが、
このとき化学反応で微量ながら熱が出ます。
感熱紙は熱に反応して色を変える紙なので、
この熱にも敏感に反応してしまいます。
そのため、野ざらしにしていた鉄板が
錆びてぼろぼろになるように、
剥いておいたりんごが茶色くなるように、
買ったままにしておいた感熱紙が
使わない間に真っ黒、もしくは真っ白に
なってしまうように、
CD-Rの記録面でも変化が起こって、
データが読み出せなくなるということは
普通に起こるのです。
一般的には、CDの寿命は5年から10年と言われています。
ある日、必要になったCDが読めなくなっていたということを
避けるためにも、CD-Rなどに焼くデータは、
違うメーカーのメディアに複数補完しておき、
5年ごとくらいでデータの移し変えをするのが安心でしょう。
ただし、この寿命も、CDのメーカーにより
ずいぶん異なることがあります。
安さだけを目指した粗悪品は、
寿命が短い上に、寿命前でも
読み出せなくなることも頻発したりします。
また、実際には書き込めていても、読み出しドライブによって
そのデータを読み出せないということも起こります。
CD-Rが読めなくなるというのは、
光学メディア自体の問題以外にも、
焼くドライブ、読むドライブの問題などが関わってくるのです。
昔焼いたCD-Rのデータ、読み出そうとしたら
エラーが出てなんにも取り出せなかったんだけど。
CD-Rって一回焼けばずっと使えるもんなんじゃないの?

回転式の記録メディアは
感熱紙みたいなものなんだからねっ!
★ポイント
CDやDVDなどの回転式メディアは
プラスティックの円盤に、金箔のようなものを
貼り付けて作られています。
それは、記録できないCDでも、CD-Rでも同じです。
(※これ以降、回転式光学メディアのことを
総括して『CD』と記述します)
CDを裏から見るときらきらして見えますが、
あれはCD表面のすぐ裏。
CD表面に貼り付けた、金箔のようなものを
裏から見ているだけにすぎません。
そのため、ただのレーベルだと思っている
表面に裏まで貫通する傷をつけると、
CDは読むことができなくなってしまいます。
一方、プラスティック面についた傷は、
読み込むときのレーザーを曲げてしまうために
読めなくなるだけで、
データ自体が壊れるわけではありません。
プラスティックディスクを傷がなくなるまで
平らに削りこんでいけば、データをまた
読み出すことは可能になるのです。
適当にたとえて言うなら、
CDのレーベル面は家。
CDのプラスティック面は道路です。
CDのプラスティック面を傷つけることは、
家へとたどり着く道を閉ざすことです。
そのために家、すなわちデータへと
たどりつけなくなってしまいます。
一方、CDのレーベル面を壊すことは
家自体を壊すことです。
たとえ道があったとしても、
家自体が壊れてしまえば
家にたどり着くことは二度とできません。
それほど重要なCDのレーベル面ですが、
実はとても貧弱なつくりをしています。
特に、記録可能なものはそうです。
本当に金箔のような、アルミホイルのようなものが
一枚、ぺたりと貼り付けてあるだけ。
切り傷をつけてガムテープをはれば、
そこから簡単にはがせてしまいます。
CDというもののプラスティック部分と
ぺらぺらのレーベル部分を人間で置き換えると、
プラスティック部分が肉体、
レーベル部分が魂と言えます。
CDの魂の座はレーベル部分にあります。
そして、CDの魂は直接的な傷にとても弱いのです。
すこしでも長持ちさせたいなら、
レーベル部分の扱いに特に気をつけましょう。
でも、どれだけ気をつけていても
CDのデータが読み出せなくなることがあります。
それが、CDの寿命です。
CD-RやDVD Rなど、R(Recordable、記録可能)
属性がついて売られているものは、
初めからデータを焼き付けてある
音楽CDなどのプレスCDよりも寿命が短いです。
でも、どちらにしても寿命があることには
変わりませんけれど。
……というのも、レコーダブル光学メディアの
記録方式は、基本的には感熱紙と同じだからです。
感熱紙とは、FAX用紙やレジのレシート用紙で
よく使われている、熱によって変色する
紙のことです。
CD-Rなどにデータを入れることを
『焼く』と表現しますが、
感熱紙に焼きいれるという意味からも
かなりイメージに近い言いまわしだと言えます。
たばこを畳に落として焼けてしまったら
畳を交換するまで焼け焦げは消えないので
焼いたCDのデータも消えないと思うかもしれませんが、
感熱紙にとっての『焼く』というのは
それほどはっきりしたものではありません。
むしろ、金属にとっての錆のようなものです。
錆は金属が酸素と結合してできるものですが、
このとき化学反応で微量ながら熱が出ます。
感熱紙は熱に反応して色を変える紙なので、
この熱にも敏感に反応してしまいます。
そのため、野ざらしにしていた鉄板が
錆びてぼろぼろになるように、
剥いておいたりんごが茶色くなるように、
買ったままにしておいた感熱紙が
使わない間に真っ黒、もしくは真っ白に
なってしまうように、
CD-Rの記録面でも変化が起こって、
データが読み出せなくなるということは
普通に起こるのです。
一般的には、CDの寿命は5年から10年と言われています。
ある日、必要になったCDが読めなくなっていたということを
避けるためにも、CD-Rなどに焼くデータは、
違うメーカーのメディアに複数補完しておき、
5年ごとくらいでデータの移し変えをするのが安心でしょう。
ただし、この寿命も、CDのメーカーにより
ずいぶん異なることがあります。
安さだけを目指した粗悪品は、
寿命が短い上に、寿命前でも
読み出せなくなることも頻発したりします。
また、実際には書き込めていても、読み出しドライブによって
そのデータを読み出せないということも起こります。
CD-Rが読めなくなるというのは、
光学メディア自体の問題以外にも、
焼くドライブ、読むドライブの問題などが関わってくるのです。