古文解読をやっていると、
訳と称するとんでもない解釈を目にすることがたびたびあります。
たとえば、
・文章に書いてあるものを無視して訳す
・文章のどこにも書いていないものを勝手に付け加えて訳す
・文法を無視する
・常識で見れば誤りとわかるものを誤りとしない
といったような。
しかもそれを先行研究として提示し、
それをそのまま参照して、話を進める始末です。
——なんでそれ、文法の誤りを誰も指摘しないの?
なんでわたしでもわかる明らかな間違えを、
誰も無視して話進めるの?
……と、本当に意味がわからず、
すごく腹立たしい気持ちでいたのですが。
このまえ、ふと、思いついたのです。
わたしですら簡単に気づく異常、というのは、実は、
『わたしだから簡単に気づく異常』であって、
当たり前のものを当たり前に簡単にとらえられるというのは、
わたしのギフテッド能力によるものではないか、と。
考えたくありませんが、
ギフテッド能力を持っていない人は、
どんなにあからさまな異常がそこにあろうと、
どれだけ先行研究が文法や常識を無視したインチキだろうと、
その異常性を『知覚できない』あるいは
『認知できない』のかもしれません。
そう考えると、いろんなことに意味が通じるのです。
たとえば、竹取物語の千年の謎ともいえるもののひとつ。
『我が名ははうかんるり』
一般の研究者は、
「これは、はうかんるりか、うかんるりか、
どちらだろう……」
などと考え始めるようです。
……が、そんなことには意味がない、
ということがわかるでしょうか。
そんなこと考え始めるより先に、
目を奪われる、格別に大きな異常があるでしょう?
本当にそれが、わからないのでしょうか。
ここに言及する研究がないということは、
ほんとうに、知覚・認識できていないのでしょうか。
ここは、ばかばかしい異常さえ見つければ、
もう半分解読終わった、というところですが、
その異常、わかりますよね?
あるいは、本当にわからないのでしょうか。
ほかにも、
いわゆる魏志倭人伝には、
『張政等 因齎 詔書黄幢 拜假難升米 爲檄告喩之』
というような文字列があります。
みんなこの文の異常に気づかず解釈し、
訳を作っているようですが、
だから、いわゆる魏志倭人伝の解釈が狂っているのです。
ここにある、文章を破壊するほどの異常、
わかりますよね?
日本語の古文解読者のわたしが簡単にわかるようなものですから、
いわゆる魏志倭人伝の研究者や、
中国語古文の研究者であれば、
この文の大きな異常くらい、わかりますよね?
……それとも、こんな異常もまた、
知覚できないのでしょうか。
それから、
『根掘り葉掘り』という言葉なども。
今の一般的な人は、『葉掘り』には意味がない、
と言っているはずです。
おそらく辞書にもそう載っています。
でも、そんなわけないでしょう。
ほんとに世の中の人は、『根掘り葉掘り』の『葉掘り』には
意味がないと、本気で思っているのでしょうか。
『根掘り葉掘り』の『葉掘り』には意味がない、
単なる根掘りにあわせた口よごしだ、なんて見たら、
ぞわっとした気持ち悪さ、怒りのようなものを感じます。
なぜならわたしは、
『根掘り葉掘り』なんて文字列を見たら
その意味がわかるからです。
そして、
『葉掘り』には意味がない、
という概念は間違っている、と指摘できるからです。
この間違いがわかるというのが、
古文を学んできたからか、あるいは和歌をまなんできたから
だろうと思っていたのですが、
こういったものがすでに、ギフテッド能力なのかもしれません。
『根掘り葉掘り』の意味なんて、
あるいは『葉掘り』の意味なんて、
ちょっと考えればわかるでしょう?
『葉を掘ってどうするか』なんて疑問自体が、
考えるまでもない愚かな発想だと、
簡単にわかるでしょう?
というのをかつてまとめた話がこれ。
参照:
『根掘り葉掘り』の意味
わたしは、世の中のレベルがわかりません。
あんまりみんながわかっていないので、
わたしの考えがおかしいのかとも思っていましたが、
どう考えてもわたしの論理のほうが正しいのです。
なぜなら、他の人の既存研究の誤りが指摘できるからです。
たとえば、文法を無視して訳しているだとか、
別の本を踏まえて書かれているから参照しながら
訳さなきゃいけないのに参照できていないだとか、
前後の文脈から切り離して矛盾を作りながら訳しているだとか。
こんなものが古文解読の世界だというのなら、
本物の訳というものを、また、
本物の訳し方というものを、
わたしが見せてみせます。
いわゆる邪馬臺国の場所だろうが、
卑弥呼の読みだろうが、
天孫降臨の場所だろうが、
竹取物語の意味がわからない場所だろうが、
全部明快に示して見せますから、
わたしにまともな場所で語らせて欲しい。
……けど。わたしにはなんのコネも実績もありませんし。
わたしがまともに述べてみたところで、
文法や常識を無視して読むのに慣れている人間は
正しい読み方を理解できないかもしれません。
ただ悔しいです。
訳と称するとんでもない解釈を目にすることがたびたびあります。
たとえば、
・文章に書いてあるものを無視して訳す
・文章のどこにも書いていないものを勝手に付け加えて訳す
・文法を無視する
・常識で見れば誤りとわかるものを誤りとしない
といったような。
しかもそれを先行研究として提示し、
それをそのまま参照して、話を進める始末です。
——なんでそれ、文法の誤りを誰も指摘しないの?
なんでわたしでもわかる明らかな間違えを、
誰も無視して話進めるの?
……と、本当に意味がわからず、
すごく腹立たしい気持ちでいたのですが。
このまえ、ふと、思いついたのです。
わたしですら簡単に気づく異常、というのは、実は、
『わたしだから簡単に気づく異常』であって、
当たり前のものを当たり前に簡単にとらえられるというのは、
わたしのギフテッド能力によるものではないか、と。
考えたくありませんが、
ギフテッド能力を持っていない人は、
どんなにあからさまな異常がそこにあろうと、
どれだけ先行研究が文法や常識を無視したインチキだろうと、
その異常性を『知覚できない』あるいは
『認知できない』のかもしれません。
そう考えると、いろんなことに意味が通じるのです。
たとえば、竹取物語の千年の謎ともいえるもののひとつ。
『我が名ははうかんるり』
一般の研究者は、
「これは、はうかんるりか、うかんるりか、
どちらだろう……」
などと考え始めるようです。
……が、そんなことには意味がない、
ということがわかるでしょうか。
そんなこと考え始めるより先に、
目を奪われる、格別に大きな異常があるでしょう?
本当にそれが、わからないのでしょうか。
ここに言及する研究がないということは、
ほんとうに、知覚・認識できていないのでしょうか。
ここは、ばかばかしい異常さえ見つければ、
もう半分解読終わった、というところですが、
その異常、わかりますよね?
あるいは、本当にわからないのでしょうか。
ほかにも、
いわゆる魏志倭人伝には、
『張政等 因齎 詔書黄幢 拜假難升米 爲檄告喩之』
というような文字列があります。
みんなこの文の異常に気づかず解釈し、
訳を作っているようですが、
だから、いわゆる魏志倭人伝の解釈が狂っているのです。
ここにある、文章を破壊するほどの異常、
わかりますよね?
日本語の古文解読者のわたしが簡単にわかるようなものですから、
いわゆる魏志倭人伝の研究者や、
中国語古文の研究者であれば、
この文の大きな異常くらい、わかりますよね?
……それとも、こんな異常もまた、
知覚できないのでしょうか。
それから、
『根掘り葉掘り』という言葉なども。
今の一般的な人は、『葉掘り』には意味がない、
と言っているはずです。
おそらく辞書にもそう載っています。
でも、そんなわけないでしょう。
ほんとに世の中の人は、『根掘り葉掘り』の『葉掘り』には
意味がないと、本気で思っているのでしょうか。
『根掘り葉掘り』の『葉掘り』には意味がない、
単なる根掘りにあわせた口よごしだ、なんて見たら、
ぞわっとした気持ち悪さ、怒りのようなものを感じます。
なぜならわたしは、
『根掘り葉掘り』なんて文字列を見たら
その意味がわかるからです。
そして、
『葉掘り』には意味がない、
という概念は間違っている、と指摘できるからです。
この間違いがわかるというのが、
古文を学んできたからか、あるいは和歌をまなんできたから
だろうと思っていたのですが、
こういったものがすでに、ギフテッド能力なのかもしれません。
『根掘り葉掘り』の意味なんて、
あるいは『葉掘り』の意味なんて、
ちょっと考えればわかるでしょう?
『葉を掘ってどうするか』なんて疑問自体が、
考えるまでもない愚かな発想だと、
簡単にわかるでしょう?
というのをかつてまとめた話がこれ。
参照:
『根掘り葉掘り』の意味
わたしは、世の中のレベルがわかりません。
あんまりみんながわかっていないので、
わたしの考えがおかしいのかとも思っていましたが、
どう考えてもわたしの論理のほうが正しいのです。
なぜなら、他の人の既存研究の誤りが指摘できるからです。
たとえば、文法を無視して訳しているだとか、
別の本を踏まえて書かれているから参照しながら
訳さなきゃいけないのに参照できていないだとか、
前後の文脈から切り離して矛盾を作りながら訳しているだとか。
こんなものが古文解読の世界だというのなら、
本物の訳というものを、また、
本物の訳し方というものを、
わたしが見せてみせます。
いわゆる邪馬臺国の場所だろうが、
卑弥呼の読みだろうが、
天孫降臨の場所だろうが、
竹取物語の意味がわからない場所だろうが、
全部明快に示して見せますから、
わたしにまともな場所で語らせて欲しい。
……けど。わたしにはなんのコネも実績もありませんし。
わたしがまともに述べてみたところで、
文法や常識を無視して読むのに慣れている人間は
正しい読み方を理解できないかもしれません。
ただ悔しいです。
















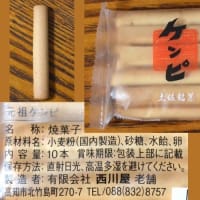
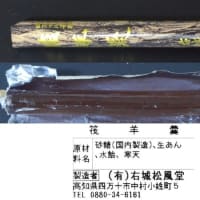

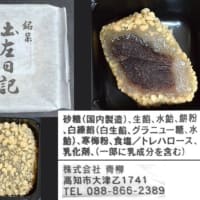






「我が名はうかんるり」は非常に興味深い箇所ですよね。仰るとおり、「はうかんるり」か「うかんるり」か、という議論はそもそも成り立たないのです(なお、「我が名ははう……」と「は」が重出する本文は末流なので考えなくてよいと思います)。
個人的にはこれは単純な誤写だと考えています(文献学的に検証可能です)。しかし、一箇所判断できていない箇所があるので、御説を拝見するのが楽しみです。
続刊お待ちしております。
むしろ、どうしてそれがもとの形なのか、という説明がめんどくさい箇所です。
判断できていない のがどんな感じなのか気になりますねえ
「判断できていない」というのは、私の仮説では、再建可能な祖本本文が2パターンあり、どちらか決めかねて困っているということです。そしてその判断できない箇所は、この作品内には現れない単語だと考えられるのです。
大体の誤写は、二系統(箇所によっては三系統)の本文と作品内の用例(なければ同時代作品における用例)を調べることで取り除くことが可能ですが、他に現れない単語となると難しいですね。ですから、この箇所にアプローチした様々な読解例を知りたいのですが、残念ながら多くは「はうかんるり」「うかんるり」の漢字表記をどうするか程度なので……。
さて。
ここは、文章で許される形は実は一つしかありません。
前からも、あとのほうからも、その箇所にかかっている文章があります。
よく考えてそこを見つけてください。
重要なのは、文章的解釈と……常識的解釈でしょうか。
文章を文章としてきちんと読んでいれば常識的に気づいてよいところなのですが
それに気づくか気づかないかがセンスなんですかねえ……