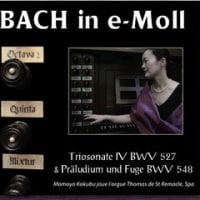女性のオルガン作曲家
は、世の中に実に少ないものです。
歴史的に、19世紀の終わり頃のヨーロッパで、ピアノが弾けるんだからオルガンも弾きたい!というお転婆な女性が現れ始めたにもかかわらず、
1。衣装が適していない(スカートがふくらんでいるし中にジュポンというフープまで入っていることもある)
2。教会のオルガン演奏台は聖なる場所なので女性は禁止
という二つの壁を乗り越えなければ演奏できませんでした。
メンデルスゾーンの妹、ファニーさんは貴族だったので、オルガンの演奏台に上る許可書をちゃんと書いてもらったか、一族のプライベートチャペルのオルガンを自由に使えたのかはわかりませんが、ふつうのドレスのままで演奏できる、ペダルは使用しないオルガン作品を残しています。
今でもオルガンのレッスンの時に、
うちのおばあちゃんは、(1930年代か?)教区からオルガン台にあがる許可書をいただいて奏楽していたそうですよ。
などと教えてくれる生徒がいて、よくきいてみれば、当時のミサはすべてラテン語。教会堂奥の祭壇で神父がミサをとり行う間、教会のなかほどにひざまずいている信徒にはミサの内容がはっきり聴こえる訳もないので、ロザリオをひとつひとつたどりながら、念仏のように暗記した連祷を口の中で繰り返し、ミサの終わるのを待つということも普通という時代。男性と女性は会堂の左右に分かれて座る、司式の補佐や歌い手は全て男性という中、オルガンを演奏する男性が不足していれば女性でも仕方ないので許可書を出して、女性がオルガン台に上がったということのようです。ちなみにオルガンはアカペラで歌われる男声の合唱といれちがいに、式の流れ、司祭の動きを伴奏しました。
実際的なことをいうと、一旦オルガン台にあがってしまえば弾いているのが男性か女性か、人々には見えなかったことも幸運だったのかもしれません。このころはパンツスタイルこそ浸透していなかったけれど、スカートは軽くなり、膝下丈であったと思われるので、これならパンプスでもちょっとペダルの音を弾いたりは出来たはず。マリー=クレール・アランはいつも膝丈スカートにヒール靴で演奏しますが、ヨーロッパで女性が演奏し始めたころのスタイルである、ということができます。もちろん彼女のペダルの技巧は、ちょこっとペダルで音を出す、というようなものではなく、若かりしころから群を抜いたものであったわけですが。
19世紀のフランスでは、盲目であったがために、女性だけど盲学校でオルガンを習う、というケースもありました。ピアノとは違い、鍵盤の音域が広くないので、両手を左右に遠く「飛ばす」必要も無く、複数の鍵盤を触って確かめながら上下動できるオルガンの分野は、多くの盲目の演奏家、作曲家を輩出しています。また、教会で演奏する場合、即興演奏が大きな比重を占めているため、作品を点字で勉強して演奏するだけではないという魅力もあるのでしょう。
そんなわけで、つい最近まで女性がオルガンを弾くという機会がとても限られていたために、女性のオルガン作品はまだまだ稀少な存在です。しかし戦後活躍した多くの女性オルガニストには、即興、作曲に優れた人たちも多く、フランスものを中心にレーパートリーは広がりつつあります。
しかしここで問題は、つまり、女性のオルガン作品はほぼ現代曲しかない、ということです。また、技術的に男性に負けないような難度の高いものだけが生き残り印刷され演奏され続ける可能性を勝ち取ったようなところがあって、結局、譜面のあまりの難しさに、滅多に演奏されない、という状況を呈しているのではないかと思います。
私の教会の毎週のランチタイムコンサートでは(オルガンの月曜日http://www.lundidorgue.be/)、無題のまま一年40回の演奏会を運営するのに無理があって、2002年ごろから月ごとのテーマを決めるようになりました。その中で、いろいろな楽器とオルガン、という9月のテーマのあと、オルガンリサイタル年3回をこなさなければいけないかわりに、このオルガンで通年無料で練習できる、という条件のオルガン奨学生のデビューがある10月、そして11月は聖セシルにちなんで女性オルガン作曲家の作品を4週にわたって演奏することになっています。
上の写真が聖セシル、ラテン語ではセシリア、またはチェチリア、を題材にした19世紀の絵です。歌ったり、いろいろな楽器を演奏する天使のひとり、というイメージですが(背中に羽はついていたりいなかったり。)常にたくさんのアンジェロ君たちに囲まれ、華やかな雰囲気の、有名(?)女性聖人のひとりです。11月22日の聖セシルの日前後には、この音楽のミューズにちなんだフェスティバルが、ヨーロッパ各地で行われます。
聖セシルシリーズをはじめてからというもの、じゃあどんな女性作曲家のオルガン作品を弾けばいいのか、という問題には、この月に登場するオルガニストが4人に4人とも頭を悩まされ、楽譜を取り寄せたり図書館に行って稀少な作品を掘り出したり、つぎに曲が決まれば決まったでなんとも難しい作品ばかりで練習に練習を重ねる、という感じで、各人、とても良い勉強の機会となっているのは確かです。
昨年の11月の演奏会では、偶然の出会いによって、はじめて日本人女性のオルガン作品を演奏する事ができました。実際にお目にかかったのは今年の6月で、それまでに録音や手紙、メールや電話でコンタクトをとりながら、演奏する楽器に合った音の選択に始まって音楽の「つくりかた(解釈のこと)」に至るまで、相談に乗っていただき、ひとりで勝手に解釈して弾くのではなく、共同作業で演奏会にもっていくという経験になりました。それも、ベルギー初演では納得の行く演奏にならず、このままで捨てておくのは忍びなかったので、さらに日本でも6月に演奏する機会が与えられて、そこでまたいろいろな不思議な出会いがありました。
この作曲家、斉木由美さんのオルガン曲、ファンファーレについて、次回お話したいと思います。
は、世の中に実に少ないものです。
歴史的に、19世紀の終わり頃のヨーロッパで、ピアノが弾けるんだからオルガンも弾きたい!というお転婆な女性が現れ始めたにもかかわらず、
1。衣装が適していない(スカートがふくらんでいるし中にジュポンというフープまで入っていることもある)
2。教会のオルガン演奏台は聖なる場所なので女性は禁止
という二つの壁を乗り越えなければ演奏できませんでした。
メンデルスゾーンの妹、ファニーさんは貴族だったので、オルガンの演奏台に上る許可書をちゃんと書いてもらったか、一族のプライベートチャペルのオルガンを自由に使えたのかはわかりませんが、ふつうのドレスのままで演奏できる、ペダルは使用しないオルガン作品を残しています。
今でもオルガンのレッスンの時に、
うちのおばあちゃんは、(1930年代か?)教区からオルガン台にあがる許可書をいただいて奏楽していたそうですよ。
などと教えてくれる生徒がいて、よくきいてみれば、当時のミサはすべてラテン語。教会堂奥の祭壇で神父がミサをとり行う間、教会のなかほどにひざまずいている信徒にはミサの内容がはっきり聴こえる訳もないので、ロザリオをひとつひとつたどりながら、念仏のように暗記した連祷を口の中で繰り返し、ミサの終わるのを待つということも普通という時代。男性と女性は会堂の左右に分かれて座る、司式の補佐や歌い手は全て男性という中、オルガンを演奏する男性が不足していれば女性でも仕方ないので許可書を出して、女性がオルガン台に上がったということのようです。ちなみにオルガンはアカペラで歌われる男声の合唱といれちがいに、式の流れ、司祭の動きを伴奏しました。
実際的なことをいうと、一旦オルガン台にあがってしまえば弾いているのが男性か女性か、人々には見えなかったことも幸運だったのかもしれません。このころはパンツスタイルこそ浸透していなかったけれど、スカートは軽くなり、膝下丈であったと思われるので、これならパンプスでもちょっとペダルの音を弾いたりは出来たはず。マリー=クレール・アランはいつも膝丈スカートにヒール靴で演奏しますが、ヨーロッパで女性が演奏し始めたころのスタイルである、ということができます。もちろん彼女のペダルの技巧は、ちょこっとペダルで音を出す、というようなものではなく、若かりしころから群を抜いたものであったわけですが。
19世紀のフランスでは、盲目であったがために、女性だけど盲学校でオルガンを習う、というケースもありました。ピアノとは違い、鍵盤の音域が広くないので、両手を左右に遠く「飛ばす」必要も無く、複数の鍵盤を触って確かめながら上下動できるオルガンの分野は、多くの盲目の演奏家、作曲家を輩出しています。また、教会で演奏する場合、即興演奏が大きな比重を占めているため、作品を点字で勉強して演奏するだけではないという魅力もあるのでしょう。
そんなわけで、つい最近まで女性がオルガンを弾くという機会がとても限られていたために、女性のオルガン作品はまだまだ稀少な存在です。しかし戦後活躍した多くの女性オルガニストには、即興、作曲に優れた人たちも多く、フランスものを中心にレーパートリーは広がりつつあります。
しかしここで問題は、つまり、女性のオルガン作品はほぼ現代曲しかない、ということです。また、技術的に男性に負けないような難度の高いものだけが生き残り印刷され演奏され続ける可能性を勝ち取ったようなところがあって、結局、譜面のあまりの難しさに、滅多に演奏されない、という状況を呈しているのではないかと思います。
私の教会の毎週のランチタイムコンサートでは(オルガンの月曜日http://www.lundidorgue.be/)、無題のまま一年40回の演奏会を運営するのに無理があって、2002年ごろから月ごとのテーマを決めるようになりました。その中で、いろいろな楽器とオルガン、という9月のテーマのあと、オルガンリサイタル年3回をこなさなければいけないかわりに、このオルガンで通年無料で練習できる、という条件のオルガン奨学生のデビューがある10月、そして11月は聖セシルにちなんで女性オルガン作曲家の作品を4週にわたって演奏することになっています。
上の写真が聖セシル、ラテン語ではセシリア、またはチェチリア、を題材にした19世紀の絵です。歌ったり、いろいろな楽器を演奏する天使のひとり、というイメージですが(背中に羽はついていたりいなかったり。)常にたくさんのアンジェロ君たちに囲まれ、華やかな雰囲気の、有名(?)女性聖人のひとりです。11月22日の聖セシルの日前後には、この音楽のミューズにちなんだフェスティバルが、ヨーロッパ各地で行われます。
聖セシルシリーズをはじめてからというもの、じゃあどんな女性作曲家のオルガン作品を弾けばいいのか、という問題には、この月に登場するオルガニストが4人に4人とも頭を悩まされ、楽譜を取り寄せたり図書館に行って稀少な作品を掘り出したり、つぎに曲が決まれば決まったでなんとも難しい作品ばかりで練習に練習を重ねる、という感じで、各人、とても良い勉強の機会となっているのは確かです。
昨年の11月の演奏会では、偶然の出会いによって、はじめて日本人女性のオルガン作品を演奏する事ができました。実際にお目にかかったのは今年の6月で、それまでに録音や手紙、メールや電話でコンタクトをとりながら、演奏する楽器に合った音の選択に始まって音楽の「つくりかた(解釈のこと)」に至るまで、相談に乗っていただき、ひとりで勝手に解釈して弾くのではなく、共同作業で演奏会にもっていくという経験になりました。それも、ベルギー初演では納得の行く演奏にならず、このままで捨てておくのは忍びなかったので、さらに日本でも6月に演奏する機会が与えられて、そこでまたいろいろな不思議な出会いがありました。
この作曲家、斉木由美さんのオルガン曲、ファンファーレについて、次回お話したいと思います。