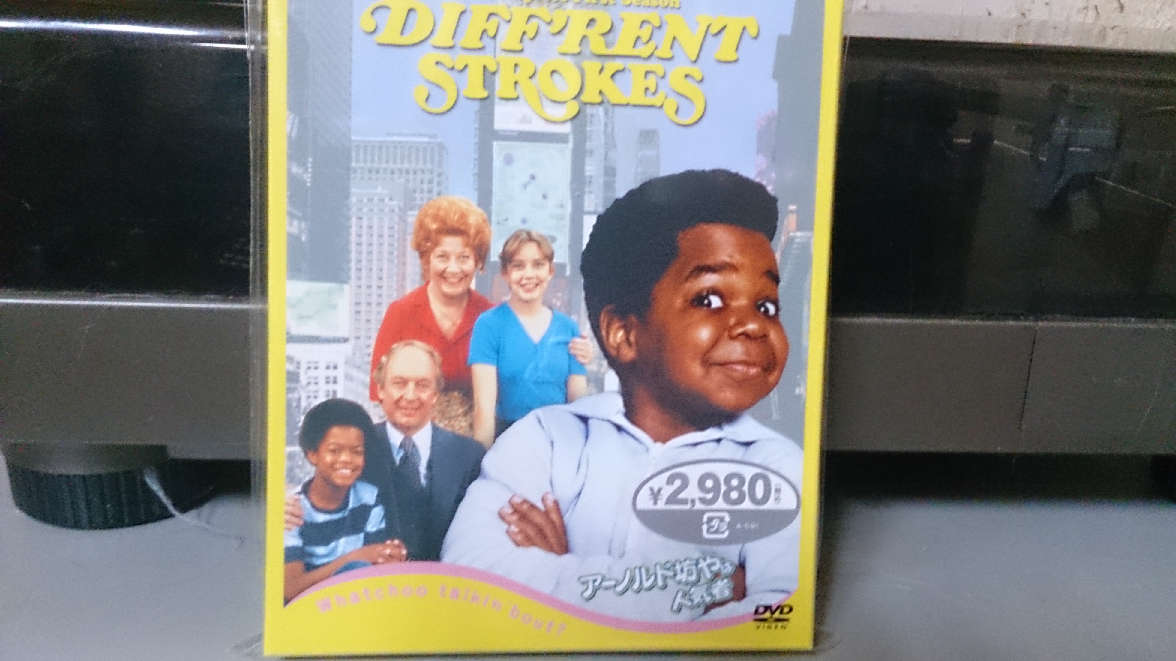ルー・リードが死んでしまった。
肝硬変が死因だが、6月に肝臓移植の手術を受けていただなんて知らなかった。
ラモン・デッカーや山口富士夫ほど衝撃的ではない。享年71歳、現在では早い部類ではあるものの、決して早すぎるわけではないし、ラモン・デッカーや山口富士夫のときのように絶句するような死に方というわけでもない。
最近はあまり聴いていなかったが、この人のレコード・CDはソロとヴェルヴェット・アンダーグラウンドを含めて大半は持っているから、かなり好きなアーティストだと言っていいだろう。
はじめて聴いたのは中学生のときだった。松風町の玉光堂で、ヴェルヴェッツのファーストを買った。LPで。当時既にヴェルヴェッツのファーストはCD化していたが、LPの1800円という値段に比べるとCDの3300円という価格は余りにも高額だった。まあ、ジャケットのシールもきちんと復刻されていたし、LPで買って大正解だったのだが(そういえば、俺が持っているポリドールから出たヴェルヴェッツのレコード・CDは全部松風町の玉光堂で買ったものだ)。
それから18,9ぐらいまでヴェルヴェッツは自分のなかで重要なグループのひとつであった。しかし、ルー・リードのソロはそれほどでも愛聴しなかった。名盤ガイドに筆頭として挙げられる「トランスフォーマー」と88年当時の最新作であった「ニューヨーク」、そしてLP2枚組ベストだった「ロックンロール・ダイアリー」の3枚に留まっていた。
当時、パンクの、そしてソニック・ユースやプッシー・ガロアなど一時期ジャンクなるカテゴライズされていたUSインディーのルーツとして神格化されていたヴェルヴェッツに対し、ソロ・アーティストとしてのルー・リードは当時、現役ベテランロッカーの第1人者として、どちらかといえばニール・ヤングやボブ・ディランに近いポジションにあったと思う。当時の俺は、そんな風潮に流されて(ブロガーなどを見るとむしろ今のほうがそうした傾向が強いかもしれない)、ソロのルー・リードは黙殺してもよいが、ヴェルヴェッツは盲目的に崇めなければならないと半ば自己暗示にかけてすらいた。
ソロのほうがよいと思うようになったのは実は函館に帰ってきてからだ。声だ。10代の頃は、あの声こそがルー・リードの魅力だと気づかなかった。
訃報を目にして、いや、ルー・リードといいえばいつも思い出すのは、中学生のときに読んだクロスビートでのインタビューだ。
「俺の曲を最初からずっと聴くと、ニューヨークで生まれ育った男の生き様がわかるはずだ」
既にその発言を収めたクロスビートが手元にないので正確だが、凡そこんな意味の発言だった。実を言うと、リアルタイムでは特に何らかの感銘を受けたわけではない。あたりまえだ。函館の中学生がこの言動により何か左右されたほうがおかしい。
この発言とルー・リードがイコールと化したのは、9・11のあとだった。
DVDにもなったコンサート・フォー・ニューヨークシティ。ポール・マッカートニーやミック・ジャガー&キース・リチャーズ、エリック・クラプトンなど、なぜかアメリカ人よりもイギリス人のビッグネームが大挙して出演した慈善イベントだ。
あのイベントについては、イベントそのものよりもむしろ、ずっとニューヨークを拠点としていたアーティストが全然出ていないことがすべてではないかと思ったし、今でもそう思う。主役はポールでもミックでもフーでもニューヨーク市民のUSAコールでもなく、パティ・スミスやボブ・ディラン、そしてルー・リードの不在こそだ。今確認したが、スプリングスティーンすら出ていないんだな。軍需産業がスポンサーだったという噂が事実だったのではないかと勘ぐってしまう。
ルー・リードにとってのニューヨークは、完全なるアナーキーでなければならかったのだろうと思う。世界で一番綺麗なものと、世界で何より醜いものとが対立することなく、同時に共存するカオス。その観念には、「ニューヨークの自由を侵した奴には天罰がくだる」とかなんとか、ポールの義憤とは最初から無関係だ。ゆえに、ニューヨークはテロリズムさえも許容しなければならない。9・11によって起こった悲劇の数々も、そしてまた、ポールの憤りをも、想像し得る悲喜劇のすべてをニューヨークは肥大化せねばならない。
いま、98年にリリースされたライブ・アルバムの「Perfect Night」を聴いている。97年のライブを収録したものだ。「ヴィシャス」など、過去曲の再演もこのヴァージョンが一番好きだ。バックの演奏も最高にいい。終盤に向うにつれてますます凄くなるこのグルーヴ。「Thank you,Good Night」でしめくくる最後も最高にクールでカッコいい。ルー・リードの声にマッチしたバックという点では、2003年のライブアルバム「Animal Serenade」(独自の緊張感はこのアルバムこそが至極か)と、このアルバムが双璧ではないだろうか。
今挙げた2枚のライブアルバムのほか、スタジオ・アルバムでは「New York」、ヴェルヴェッツ時代では「3」を自分のなかのベスト・アルバムとして挙げておく。
肝硬変が死因だが、6月に肝臓移植の手術を受けていただなんて知らなかった。
ラモン・デッカーや山口富士夫ほど衝撃的ではない。享年71歳、現在では早い部類ではあるものの、決して早すぎるわけではないし、ラモン・デッカーや山口富士夫のときのように絶句するような死に方というわけでもない。
最近はあまり聴いていなかったが、この人のレコード・CDはソロとヴェルヴェット・アンダーグラウンドを含めて大半は持っているから、かなり好きなアーティストだと言っていいだろう。
はじめて聴いたのは中学生のときだった。松風町の玉光堂で、ヴェルヴェッツのファーストを買った。LPで。当時既にヴェルヴェッツのファーストはCD化していたが、LPの1800円という値段に比べるとCDの3300円という価格は余りにも高額だった。まあ、ジャケットのシールもきちんと復刻されていたし、LPで買って大正解だったのだが(そういえば、俺が持っているポリドールから出たヴェルヴェッツのレコード・CDは全部松風町の玉光堂で買ったものだ)。
それから18,9ぐらいまでヴェルヴェッツは自分のなかで重要なグループのひとつであった。しかし、ルー・リードのソロはそれほどでも愛聴しなかった。名盤ガイドに筆頭として挙げられる「トランスフォーマー」と88年当時の最新作であった「ニューヨーク」、そしてLP2枚組ベストだった「ロックンロール・ダイアリー」の3枚に留まっていた。
当時、パンクの、そしてソニック・ユースやプッシー・ガロアなど一時期ジャンクなるカテゴライズされていたUSインディーのルーツとして神格化されていたヴェルヴェッツに対し、ソロ・アーティストとしてのルー・リードは当時、現役ベテランロッカーの第1人者として、どちらかといえばニール・ヤングやボブ・ディランに近いポジションにあったと思う。当時の俺は、そんな風潮に流されて(ブロガーなどを見るとむしろ今のほうがそうした傾向が強いかもしれない)、ソロのルー・リードは黙殺してもよいが、ヴェルヴェッツは盲目的に崇めなければならないと半ば自己暗示にかけてすらいた。
ソロのほうがよいと思うようになったのは実は函館に帰ってきてからだ。声だ。10代の頃は、あの声こそがルー・リードの魅力だと気づかなかった。
訃報を目にして、いや、ルー・リードといいえばいつも思い出すのは、中学生のときに読んだクロスビートでのインタビューだ。
「俺の曲を最初からずっと聴くと、ニューヨークで生まれ育った男の生き様がわかるはずだ」
既にその発言を収めたクロスビートが手元にないので正確だが、凡そこんな意味の発言だった。実を言うと、リアルタイムでは特に何らかの感銘を受けたわけではない。あたりまえだ。函館の中学生がこの言動により何か左右されたほうがおかしい。
この発言とルー・リードがイコールと化したのは、9・11のあとだった。
DVDにもなったコンサート・フォー・ニューヨークシティ。ポール・マッカートニーやミック・ジャガー&キース・リチャーズ、エリック・クラプトンなど、なぜかアメリカ人よりもイギリス人のビッグネームが大挙して出演した慈善イベントだ。
あのイベントについては、イベントそのものよりもむしろ、ずっとニューヨークを拠点としていたアーティストが全然出ていないことがすべてではないかと思ったし、今でもそう思う。主役はポールでもミックでもフーでもニューヨーク市民のUSAコールでもなく、パティ・スミスやボブ・ディラン、そしてルー・リードの不在こそだ。今確認したが、スプリングスティーンすら出ていないんだな。軍需産業がスポンサーだったという噂が事実だったのではないかと勘ぐってしまう。
ルー・リードにとってのニューヨークは、完全なるアナーキーでなければならかったのだろうと思う。世界で一番綺麗なものと、世界で何より醜いものとが対立することなく、同時に共存するカオス。その観念には、「ニューヨークの自由を侵した奴には天罰がくだる」とかなんとか、ポールの義憤とは最初から無関係だ。ゆえに、ニューヨークはテロリズムさえも許容しなければならない。9・11によって起こった悲劇の数々も、そしてまた、ポールの憤りをも、想像し得る悲喜劇のすべてをニューヨークは肥大化せねばならない。
いま、98年にリリースされたライブ・アルバムの「Perfect Night」を聴いている。97年のライブを収録したものだ。「ヴィシャス」など、過去曲の再演もこのヴァージョンが一番好きだ。バックの演奏も最高にいい。終盤に向うにつれてますます凄くなるこのグルーヴ。「Thank you,Good Night」でしめくくる最後も最高にクールでカッコいい。ルー・リードの声にマッチしたバックという点では、2003年のライブアルバム「Animal Serenade」(独自の緊張感はこのアルバムこそが至極か)と、このアルバムが双璧ではないだろうか。
今挙げた2枚のライブアルバムのほか、スタジオ・アルバムでは「New York」、ヴェルヴェッツ時代では「3」を自分のなかのベスト・アルバムとして挙げておく。