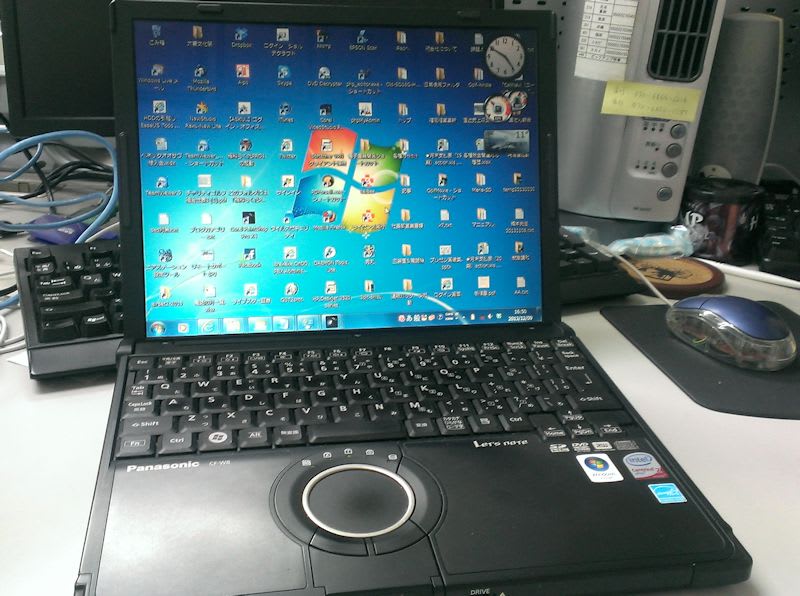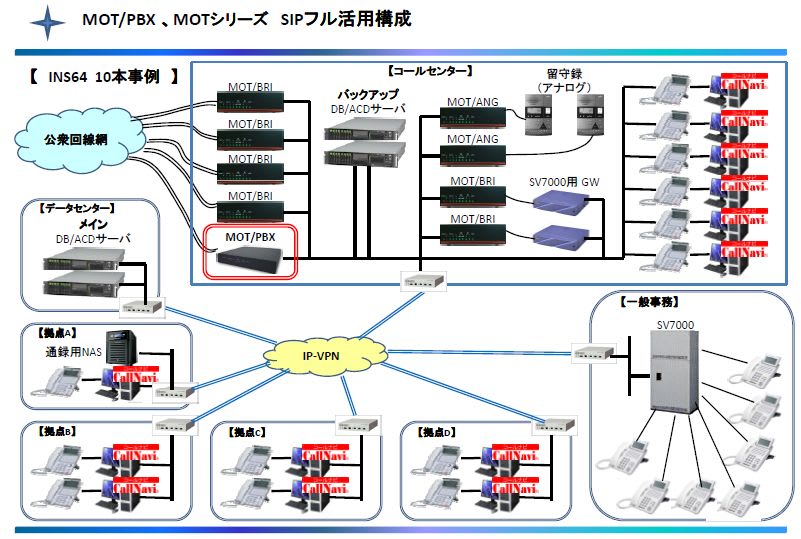手頃で使い勝手の良いSIPサーバ!
ここ最近小型のコールセンターの導入が増えてきています。
コールセンターシステムの構築費用が下がって来ているのもあってインハウス化が進んでいます。
弊社のCTIパッケージ「CallNavi(コールナビ)」&「DirectNavi(ダイレクトナビ)」との連携導入が非常に増えてきています。
何しろ構築がしやすい上に、「VC-SIP C2」は 20C、50C、100Cと3タイプがあります。
20Cは20内線、50Cは50内線、100Cは100内線です。
ここ最近での弊社からの導入実績は、50C、100Cがあります。
価格が手ごろなのと、動きの軽さを考えると近い将来を見込んで50内線or100内線を選ぶのが賢い導入です。
単純に内線電話の数ではなく、ACDグループの数も加わりますので、多い方がいろいろなことができます。
弊社の「CallNavi」と連携してしまうと、本格的なコンタクトセンタが実現出来てしまいます。
小規模なのにここまでは大げさかもしれない機能が実現出来てしまいます。
回線は、光ネクストを直収出来ます。小規模であるとひかり電話のオフィスA(エース)を入れるケースが多くあります。
それと標準でINS64を2回線4chを収容できます。
INSボード追加で、4回線8chの収容が可能です。
つい先日はNTT西日本限定の光プレミアムオフィスタイプでしたがVG830iを経由してINSに変換し、
8ch32番号での回線のコンタクトセンターに導入しました。
導入間近の動作検証!
小規模コンタクトセンターへの導入に向けての動作検証中です。
 写真
写真
右奥に置いてあるのが、ナカヨ製「VC-SIP 100CⅡ」電話機は5台で動作検証、とりあえず回線は
INS64を2本接続しての検証、サーバー機には検証用なので、DBサーバ、CTIサーバ、ACDサーバ、IVRサーバ、通話録音サーバを同居しての動作検証です。
この構成、これがまた良く動く、今までのかなりの数を導入していますが、本当に止まらず動きます。
心配であれば、サーバは冗長化すればいいのです。
SIPサーバは?
これがこのナカヨ製「VC-SIP CⅡ」の優れているところです。
旧型製品では冗長化が組めなかったものの、この現行バージョンホットスタンバイでの冗長ができます。
このようなワンボックスタイプでのSIPサーバには珍しい機能が付いています。
正直、旧型の「SIP-30」では不安だった部分がいくつかあったのですが、完全に改善されています。
インハウスのコンタクトセンターでの導入には、間違いない選択です。
30席、50席もできますが、5席程度でシンプルにまとめるならこんな構成で十分です。

この構成、自信ありです。お勧めです。
ここ最近小型のコールセンターの導入が増えてきています。
コールセンターシステムの構築費用が下がって来ているのもあってインハウス化が進んでいます。
弊社のCTIパッケージ「CallNavi(コールナビ)」&「DirectNavi(ダイレクトナビ)」との連携導入が非常に増えてきています。
何しろ構築がしやすい上に、「VC-SIP C2」は 20C、50C、100Cと3タイプがあります。
20Cは20内線、50Cは50内線、100Cは100内線です。
ここ最近での弊社からの導入実績は、50C、100Cがあります。
価格が手ごろなのと、動きの軽さを考えると近い将来を見込んで50内線or100内線を選ぶのが賢い導入です。
単純に内線電話の数ではなく、ACDグループの数も加わりますので、多い方がいろいろなことができます。
弊社の「CallNavi」と連携してしまうと、本格的なコンタクトセンタが実現出来てしまいます。
小規模なのにここまでは大げさかもしれない機能が実現出来てしまいます。
回線は、光ネクストを直収出来ます。小規模であるとひかり電話のオフィスA(エース)を入れるケースが多くあります。
それと標準でINS64を2回線4chを収容できます。
INSボード追加で、4回線8chの収容が可能です。
つい先日はNTT西日本限定の光プレミアムオフィスタイプでしたがVG830iを経由してINSに変換し、
8ch32番号での回線のコンタクトセンターに導入しました。
導入間近の動作検証!
小規模コンタクトセンターへの導入に向けての動作検証中です。
 写真
写真右奥に置いてあるのが、ナカヨ製「VC-SIP 100CⅡ」電話機は5台で動作検証、とりあえず回線は
INS64を2本接続しての検証、サーバー機には検証用なので、DBサーバ、CTIサーバ、ACDサーバ、IVRサーバ、通話録音サーバを同居しての動作検証です。
この構成、これがまた良く動く、今までのかなりの数を導入していますが、本当に止まらず動きます。
心配であれば、サーバは冗長化すればいいのです。
SIPサーバは?
これがこのナカヨ製「VC-SIP CⅡ」の優れているところです。
旧型製品では冗長化が組めなかったものの、この現行バージョンホットスタンバイでの冗長ができます。
このようなワンボックスタイプでのSIPサーバには珍しい機能が付いています。
正直、旧型の「SIP-30」では不安だった部分がいくつかあったのですが、完全に改善されています。
インハウスのコンタクトセンターでの導入には、間違いない選択です。
30席、50席もできますが、5席程度でシンプルにまとめるならこんな構成で十分です。

この構成、自信ありです。お勧めです。