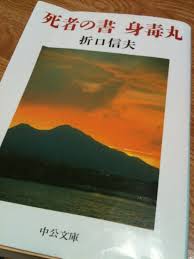
時間が無いから読めないと思っていたのだが
単に心に余裕がなかったのだろう。
読んでみると短い小説だった。ただし余韻は深い。
大阪に住んでいた2年間に、同期の古典好きから勧められた
小説が「猿丸幻視行」。これは面白かった。
その物語の主人公が若き日の折口信夫(歌人 釈超空)
ということになっている。
折口は民俗学者で柳田國男の弟子。
明日香村の古社、飛鳥坐神社(あすかにいますじんじゃ)
の縁者であった、と猿丸幻視行の後書きで知り
週末ごとに飛鳥や大和盆地をうろついた。
「おとう、またお寺?神社?」
と就学前の子供たちはぶーぶー言ったが
飛鳥、奈良時代の遺跡は、現存する建物などが少ない分
想像を膨らませることができ、空間も京都よりのびやかで
好きだった。
常陸国の片田舎に寓居する今となれば、
日本で最も有名な里山「天の香具山」に
登らせたのは、不徳の父としては
まあまあの出来であったと思う。
閑話休題。
そのうろうろの一環で、やはりオタクの後輩に
教えられたのが当麻寺(たいまでら)であった。
名前がいいでしょ。いえいえ古典的な響きのする読み方がです。
謀反の疑いをかけられ非業の死を遂げた天武天皇の子、大津皇子が
葬られた二上山(ふたかみやま)の麓なる古刹の本尊は
蓮の糸で織られた曼荼羅。
藤原氏の薄幸の姫が仏の来臨を織り込んだと伝えられるが
見たときは「ふーん」という感じ。
ただ東塔、西塔が現存するお寺はここ位だそう。
穏やかでずいぶん長居しました。
それから5年たった今、なんとなく手に取った
その本の内容が、当麻寺で謹慎する姫を訪れて恍惚とさせる貴人は
仏に見えて実は、わが念を残そうという大津皇子の亡霊、
というもの。
二上山、登って詣でるべきだった。
蛇足ながら飛鳥坐神社は陰陽石、天狗とおかめの目合いの奇祭でも有名です。
単に心に余裕がなかったのだろう。
読んでみると短い小説だった。ただし余韻は深い。
大阪に住んでいた2年間に、同期の古典好きから勧められた
小説が「猿丸幻視行」。これは面白かった。
その物語の主人公が若き日の折口信夫(歌人 釈超空)
ということになっている。
折口は民俗学者で柳田國男の弟子。
明日香村の古社、飛鳥坐神社(あすかにいますじんじゃ)
の縁者であった、と猿丸幻視行の後書きで知り
週末ごとに飛鳥や大和盆地をうろついた。
「おとう、またお寺?神社?」
と就学前の子供たちはぶーぶー言ったが
飛鳥、奈良時代の遺跡は、現存する建物などが少ない分
想像を膨らませることができ、空間も京都よりのびやかで
好きだった。
常陸国の片田舎に寓居する今となれば、
日本で最も有名な里山「天の香具山」に
登らせたのは、不徳の父としては
まあまあの出来であったと思う。
閑話休題。
そのうろうろの一環で、やはりオタクの後輩に
教えられたのが当麻寺(たいまでら)であった。
名前がいいでしょ。いえいえ古典的な響きのする読み方がです。
謀反の疑いをかけられ非業の死を遂げた天武天皇の子、大津皇子が
葬られた二上山(ふたかみやま)の麓なる古刹の本尊は
蓮の糸で織られた曼荼羅。
藤原氏の薄幸の姫が仏の来臨を織り込んだと伝えられるが
見たときは「ふーん」という感じ。
ただ東塔、西塔が現存するお寺はここ位だそう。
穏やかでずいぶん長居しました。
それから5年たった今、なんとなく手に取った
その本の内容が、当麻寺で謹慎する姫を訪れて恍惚とさせる貴人は
仏に見えて実は、わが念を残そうという大津皇子の亡霊、
というもの。
二上山、登って詣でるべきだった。
蛇足ながら飛鳥坐神社は陰陽石、天狗とおかめの目合いの奇祭でも有名です。











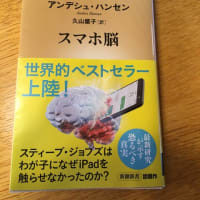



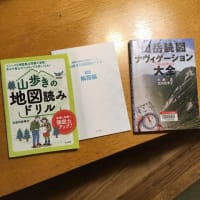




※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます