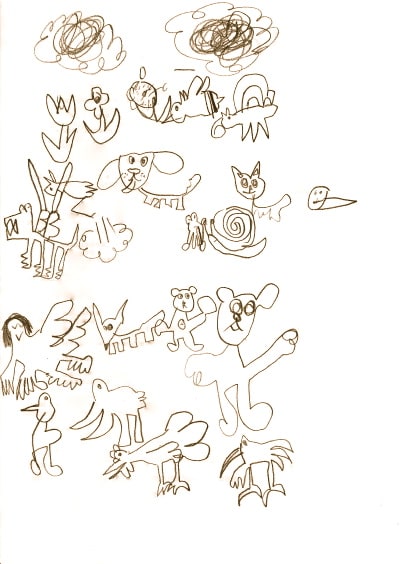photo by Cotomono
photo by Cotomono
雨がふったから 虹もかかる
9月に訪ねた、仙台の”
まちの工房まどか”のカレンダー表紙のことば。
No Rain, No Rainbow (雨が降らなければ 虹も出ない)
という言葉を知って、いい言葉だと思ったけど
Noではない、より肯定的な言葉を使いたかったので
Only Rainbows After Rain
にしたのだ、と
スタッフのTさんが教えてくれた。
”まどか”は、知的障害のある人たちが働いているところ。
太陽の光が、さしこむというよりは、やわらかくつつみこむような、
全体がぽかぽかあかるい場所だった。
そこにいるひとたちの笑顔も、さいこうにまぶしかった。
お茶もできるパンやさんがあって、ギャラリーがあって、
作業をする場所があって、ぜんぶぐるりとつながっているので、
作業する人たちと訪れる人たちはまざりあうようだ。
これは、震災後にあたらしく生まれ変わった、”まどか”。
震災前は荒浜地区にあった。
(”荒浜”と聞くと、震災直後に衝撃的なニュースを繰り返し聞いていたので、
わたしもその地名はよく覚えていた。)
当時の”まどか”は崩れ、そこにいた人たちはみな避難したけれど、
職員の方がひとり津波に巻き込まれて亡くなった。
後日、その時の恐怖を思い出すから”まどか”には行けない、
という方もいたそうで、心の傷は計り知れない。
カレンダー6月は、青い色。
絵の具で一面、ただ、青で塗られている。
「なみ」だそうだ。
描いた方は、津波を目の当たりにして、吐き続けていたと、
その介抱をしたTさんが、涙ぐみながら話してくれた。
澄んだ青のなかに、1年半の歳月がつまっている。
Tさんが、カレンダーの絵を描いた人たちのことを「画家さん」とよんでいるのが、
わたしはとても気に入った。
よく施設で言われるように「利用者さん」でもなく、
かっこよさげな「アーティスト」という横文字でもなくて、
「画家さん」「画家さんたち」とよんでいる。
それ以外の部分でも、
障害者の就労・自立支援のためだから、ということではなく、いいものをつくる。
健常者と障害者、もしくはスタッフと利用者の目線の高さは同じ。
そしてそのことをたのしんでいるという様子が、さまざま細部からよく伝わってきた。
たとえば、カレンダーのデザインは、お金がかかってもちゃんとプロに任せる。
商品のまゆ玉細工は、一定の品質をクリアできるよう、ひとりひとりテストがある。
それでいて、指先の細かい作業がニガテな方にでもきれいにできるよう、
使う道具などに工夫がこらしてある。
荒浜にいたときとは、お客さんの層がちがうので、それに合わせた商品開発をする。
などなど。
やわらかくあたたかくつつみこみ、ひとりひとりのほっぺたを明るく照らしているものは、
太陽の光だけではないんだな。
 photo by やまちゃん@いっしょに歩こう!プロジェクト
photo by やまちゃん@いっしょに歩こう!プロジェクト
ここに連れてきてくれたやまちゃんが、
ほかの地から東北へ来た人を案内するとき、たいてい、さいごにここを案内するのだ、
と言っていた。
ここには希望があるから、と。
たしかに、4泊5日の間、津波になめられた沿岸部を車で走り続け、
暮らしを壊された場所をたずねてまわって、どこか気持ちは沈んでいた。
たしか3日目の朝、車窓の外につづく光景に、ふいに
「もうイヤだってば!」と心が悲鳴をあげた瞬間があった。
すぐに、理性をとりもどしたけれど、これが自分のすむまちだったらどうだろう。
わたしには、帰る場所があるけれど。
逃げることのできないくるしさを思った。
そして、”まどか”に出会った。
虹は出るのだと知った。
ひとりひとりの雨は、どうやったらひとりひとりの虹になるのか、に、思いを馳せる。
逃げることのできないくるしみは。
震災発生の何日後だったかおぼえてないけれど、
病院から帰りの車の中で、ラジオから聞こえた言葉にはっとしたのを覚えている。
復興支援のイベントか何かで、チャラっとしてると思い込んでいた、イケメン俳優が言ったのだった。
「つらい目にあった方たちは、これから、今まで以上にしあわせになる権利があるのです。」
というような内容だった。
もっと、うまい言葉で言っていたと思うけど、わすれてしまった。
それを聞いて、復旧復興なんてことを、遠くに居るわたしたちが言うのは、おこがましいな、と思ったのだ。
これから、被災した方たちは、当然、わたしたちよりもずっとずっとしあわせになるのだ。
3月11日、あらためて誓う。
わたしは、わたしの手に責任を持つ。
All you need is love.
にじ
カレンダーは、まだ
ここで手に入るのかな?