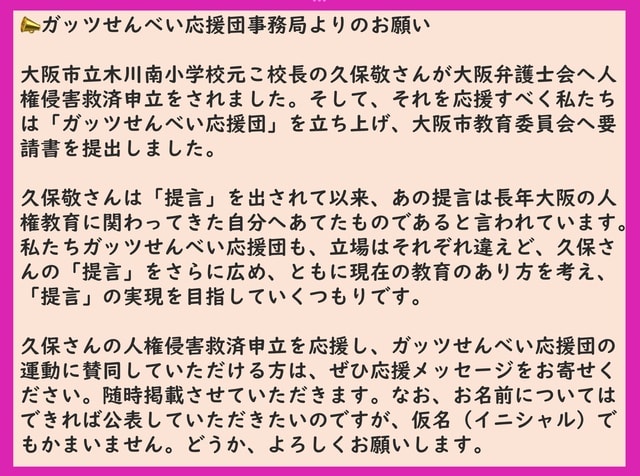久保さんと応援団へのメッセージ
◆池田直樹
久保先生、応援します。私は大阪弁護士会所属弁護士なので、申立人代理人に弁護士がついているのなら、私も参加します。よろしく。海月書店にも行かせてもらいました。
◆Takeshi Ogawa
日本中から応援をしている者たちの一人です。表現の自由を規制すると、前の戦争の時みたいになって自滅します。文書訓告の取り消しを求めます。そして世界の人類・生物にとって必要な教育を共に考えましょう。
◆ K
久保さんの提言書に感動し、勇気づけられました。維新の教育基本条例は、学校の先生を委縮させる、まさに、教育治安維持法です。本当の豊かさとは何か、一人ひとりが大事にされる社会について、学び考えていきたいと思っています。ありがとうございました。
◆ I
学校がブラック企業のような状態になり、教育を志す若い人が教員になることを諦めるような現状があると耳にします。とても残念で子ども達にとっても大きな損失に思います。現場から見ておかしいと思った意見を表明した為に訓告処分。現場の意見を聞いて事を進めるのが本来の行政や教育委員のあり方なのに、本当に「もの言えば唇寒し」が今の大阪の姿なのでしょうか。大勢の心ある人が久保さんの勇気ある行動を応援していると思います。
◆HIROSHI YAMAGUCHI
教え子を再び戦場に送らない!」が戦後の教職員組合運動の根本的スローガンでした。私はそのスローガンにあこがれて、そのための教員でありたいと思って教員になったように思います。退職した今、振り返って、そのスローガンに恥じない教員生活を送ってきたとは全く思えません。しかし今、そのスローガンが完全に踏みにじられようとしているときに、教壇に立てないことが歯がゆい思いです。そんなとき、久保先生が一人一人の子どもたちの思いに寄りそい、暖かく見守り育てる教育実践をしてこられて、その立場から、維新の競争を煽り子どもたちをずたずたに切り裂くような教育政策に異議を申し立てられたということは、私自身にとっても大いに勇気を与えてくださいました。なので久保先生にはもちろん頑張ってほしいし、今の教育状況を打ち破るたたかいをささやかですがともに進めていけたらと思っています。
◆大分県 高橋
社会の不合理や学校現場のおかしさを感じながらも、やり過ごして暮らしてしまう自分がいます。久保さんの本を読んで、声をあげても変わらないことも多いけれど、それでも、権力に抗う生き方を選びたいと思っています。現在60歳。流されず、歩み続けたいと思います。久保さん、応援しています!
◆赤嶺恵子
今の学校現場、働き方改革と言いながら、多忙化にますます拍車がかかっています。仕事量は、増え、教員を志す人は、減っているのに、在校時間を計るというアリバイを作るだけです。教員は、疲弊しています。隣にいる仲間に話しかけてもいいのだろうか?と躊躇するそうです。職場が分断され、物言わぬ雰囲気が広がっているようです。そして、学力テスト。特に様々な特性をもつ子どもにとっては、学校は、とても生きにくい場所になりつつあります。学校以外にそんな子どもたちの居場所を作る取り組みが行われています。そのこと自体は、素晴らしいのですが、そもそも、そんな子どもたちが居られない場所に学校がなっているということにも、目を向けてほしいと思います。久保さんと私たちの闘いが、そんな教育界に警鐘を鳴らす一歩になることを願います。久保さん、応援してます。
◆宮部
久保敬様
久保さんの提言書を読むたびに胸がいっぱいになります。
久保さんの思いは正に私も願っている教育、そして社会の姿です。
処分を受けるような内容ではありません。
学校現場の先生方が伸びやかに子ども達に向き合える学校であってほしいと思います。
久保さんや支援の方々のこれからの活躍を応援しています。
◆寺脇巧
教育現場での混乱はニュースや親御さん達が考えている以上にあったと感じています。机上の空論ではなく、ちゃんと現場を見てもらって、生徒たちと触れていただいて、教育現場に必要な物は何なのかを改めて考えて欲しいし、自分達も考えていきたいです。
久保さんの勇気のある行動を、自分もできればと思います。
◆N
私は、38年間、大阪で教員として働き、その後2018年まで非常勤の講師として学校現場を見てきました。久保敬さんの提言を読んだとき「その通りや!よう言ってくれはった!」とほんとうにありがたく思ったのを覚えています。子どもたちにむきあって仕事をされてきた人ならではの提言です。どこが地方公務員法の信用失墜行為にあたるのでしょうか。久保敬さん、応援しています。まわりの人にも知らせていきたいです。
◆谷口絵里子
勇気ある行動をありがとうございます。
現場の先生の声が活かされ、子どもたちの人権と学ぶ意欲、笑顔溢れる公教育が広がることを願います。
教育委員会が目を覚ましてくれることを願います。
◆小山優子
長野から久保敬さんへ応援メッセージを送ることができることを光栄に思いますし、誇りに思います。
なぜなら、私たち大人がモヤモヤした気持ちでいること 学校が、なんだか子どもたちを追い詰めているような気がする…… 。そのわけと原因を鮮明に指摘した『大阪教育行政への提言』は、すなわち全国の教育行政への提言だからです。
私は『人材』という言葉が大嫌いです。
子どもたちも私たちも一人ひとり、「愛されるために生まれてきてしあわせに生きていく」かけがえのない命と人生と未来を豊かに生きる権利をもった『人間』です。
比べるまなざし、評価されるまなざし、値踏みされるまなざしの中、子どもたちも、教員も、大人たちも生きづらさを抱えて生きています。
中村哲さんの映画のタイトル「荒野に希望の灯(あかり)をともす」のように、久保敬さんの提言は「教育に希望の灯(あかり) をともす」ものです。
先人が「教育は百年の計」と言ったように、「教えるとは 希望をともに語ること、学ぶとは 誠実(まこと)を胸にきざむこと」ルイ• アラゴンが言ったようにインディアンが七代先の子孫が幸せに生きることを考えて今を生きるように
久保敬さんの大阪行政への提言は活かされるべきもので、文書訓告を受けるべきものではありません。
◆佐々木実
久保元校長の「提言」を再読しました。やはり、「提言」には全く同感です。同意します。
そもそも久保さんをして、この「提言」を書かせたのは何か。それは、一言でいえば、現状の「競争」教育の実態です。教育は「競争」でないのは明らかなことです。「競争」教育は、子どもたちの関係性を分断し、多様な「問題」を引き起こしています。先生たちも教育の本質から離され、目的を見失って、いっそう疲弊しています。そこにいきなり全小中学校でのオンライン授業実施の通知です。まったくの場当たり的な対応。教育や学校現場に対しての無理解さ。その混乱のしわ寄せは、児童たちに向かいます。久保先生はやむにやまれぬ思いで、「提言」書を送られたのです。
さらに現在、新自由主義と国家主義の波が、教育現場にも押し寄せているのが実情です。「提言」は、現状の「公教育のあり方」を見直すことを真剣に訴え、問うています。「生き抜く」世の中ではなく、「生き合う」世の中でなくてはならない。この信念のもと、「提言」の根幹にあるのは、子どもたちの将来を思い、幸せを真摯に願う教育的愛情です。
しかし、それに対する教育委員会の姿勢はどうでしょう。
ただ「文書訓告」をもって応じたのです。「提言」の真意、主旨を捉えて対応しようとはしません。ですから、処分の理由とする「信用失墜」についても、何が該当するのかを明確に回答できないのです。また、「商品」という箇所を過剰に言い立てるなど、不当なものです。この姿勢こそ、教育行政に対する「信用失墜」を招くと言わざるを得ません。教育委員会として、子どもたちの将来を考慮するなら、誠実に対応すべきです。
今回の事象を冷静に検討し、まず、久保さんに対する処分を撤回することです。謙虚にいまの教育のあり方と向き合うことです。それこそが「信用回復」の契機となります。
子どもたちのために、また私たちのためにも、共に住みよい社会をつくっていきましょう。
◆長澤民衣
教育は権力から独立したものでないといけません。権力者は教育を通じて、子どもの個性を伸ばすのではなく、自分の思い通りになる人間を作ろうとするからです。1945年に敗戦した戦争で、軍国少年少女が作りだされました。二度とあのようなことがあってはいけないと思います。君が代、日の丸が強制され、橋下元市長が、卒業式、入学式で君が代の曲が流れたとき生徒の口が開いているか、教師の口が開いているかチェックしたと聞きました。ぞっとしました。いじめが横行しているのも今の大阪の教育に市長が口出しするからです。久保校長の提言は正しいです。よく言ってくださったと心から喝采を送りました。応援しています。
◆S.A
久保元校長先生は市長を批判したのではなく、教師として当然の使命感を表明しただけだと思います。先生の勇気のおかげで、先生方を信じようと思った保護者はたくさんいるはずです。
◆信谷 清
勇気を持って後輩のために闘う先生を尊敬いたします。
◆坂本一彦
大阪の教員希望者は、減少傾向が続いている現状を見ても教員の置かれた立場が予測出来る。それに小中校生の不登校生は、18000人を越え、全国でも五,六番目だ。子供に寄り添った教育が行われているとは思えない。権力を笠に門外漢が、教育に口出しは禁止すべきだ。
◆井上眞理子
先生の提言中の「あらゆるものを数値化して評価することで、人と人との信頼や信用をズタズタにし、温かな繋がり奪っただけではないか」という痛烈な批判に深く感銘を受けました。微力ながら応援させて戴きます。
◆松岡泰夫
頑張りましょう👍️久保先生🍀
◆山本幸子
私の孫は教室に入れません。不登校です。変質していく教育行政、学校を楽しく自由な場所に、どんな子も通いたい学校に変えたいです。地域で受けの入れられたいです。大阪がそんな学校を造ってきたのはたくさんの久保先生がおられたからだと思います。久保先生と共に皆の教育を受ける権利を守りたいです。
◆荒井喜一
応援します。志しの輪が広がりますように。
◆近藤ゆり子
非常に真っ当なことをおっしゃっています。押しつけたモノサシで子どもを測る点数主義・競争主義では、子どもは育まれません。そういう押しつけ教育をさせられる教員も疲弊します。社会全体が壊れていきます。多くの人がそれに気づいているのに『もの言えば唇寒し」になってしまっているときに言うべきことをおっしゃった。それがケシカランから訓告だということに対しては、やはり「訓告するほうが間違っている」と敢然と言い切り、闘わなければ、後輩の教師は萎縮してしまうでしょう。教師が萎縮した学校では、子ども達が生き生きと伸びていくことはできません。後輩教師のために、ひいては子ども達のために、背筋を伸ばした「背中」を見せ続けて下さい。
◆東口友子
子どもが子どもらしく人としての尊厳をもって生きていけるよう、自分が間違ったら子どもに謝り、いつも悩みながらも子どもたちとのふれあいの中で、まっすぐ生きてこられたのが、少ししか記事を読んでない身にもよくわかります。大阪市の子どもを一人一人の大切な人として育てようとしない、機械の一部として育てるような、目の前の利益しか考えないやり方に本当に腹が立ちます。まともな教育めざして、微力ながら、私もがんばりたいです。勇気が出ます。ありがとうございます。
◆クレイグ・キゾック(アメリカ・ミネソタ大学名誉教授)
タカシやあなたが他の方々と、人権救済の申し立てを提出することで公に行動を起こすことに最大限の賛辞を送ります。私は日本の法的手続きについて全く無知ですが、皆さんが教育と教育者の将来を考えて行動していることに、何よりも勇気づけられています。崇高でたぐい稀な努力であると同時に、極めて重要な行動だと考えます。
私はこのような行動を思いつかなかったのですが、教育者(と教育行政職員)が働く状況を改善するために、皆さんがリーダーシップを発揮されることを確信しており、そこに驚きはありません。
私は皆さんの応援団の一員でありますが、もし何か私にできることがあれば言ってください。
◆佐藤幸永
子どもたちを迎える学校生活の、ふれあいの楽しさを語る久保先生が、何よりうれしいのです。コロナ禍で、先生方との協働によって、子どもたちの学びと生活を守る実行を、次々されました。 子どもたちが「楽しい学校。先生、だいすき」と言える学校をつくっていってほしい。今を生きる、私たちの希望が始まります。大阪市に(府に)、上意下達ではない。育ちの場にかかわる人たちの提言が生まれてくるよう、血の通う行政をお願いしたい。久保先生への文書訓告は撤回です。
◆ハルシ・アドマワティ(インドネシア・ティダール大学講師)
久保先生、インドネシアからこんにちは。
私はジョイントセミナーでのグローバルなレベルでの経験に感謝しています。
これからの教育が、大阪だけでなく世界に向けて、人間の尊厳にもとづきその可能性を引き出す方向へと進んでほしいと願っています。教育の目的を実現するためには、できるだけ多くの人々(子ども、保護者、教職員、市民社会など)の声を聞き、お互いを理解し、教育現場で協力しあう必要があると学びました。今後、教育環境が改善されることを願っています。
2月初旬に、SEAMEO(東南アジア教育大臣機構)主催の東南アジア学生向けSTEM-EDコンペティション(https://seameo-stemed.org/news/149/STEM-Project-Competition-Winners-Announcement)で審査員を務める機会を得ました。久保先生とのジョイントセミナーでの経験が、この大イベントに臨む私に勇気を与えてくれています。教育分野でもっともっと学んでいきたいと実感しています。ありがとうございます。
◆松田幹雄
久保さんの提言には「社会の課題のしわ寄せが、どんどん子どもや学校に襲いかかっている。虐待も不登校もいじめも増えるばかり…10 代の自殺も増えており、コロナ禍の現在、中高生の女子の自殺 は急増…これほどまでに、子どもたちを生き辛くさせているものは、何であるのか。私 たち大人は、そのことに真剣に向き合わなければならない。」とあります。全く同感。こどもたちの置かれているこの状況に思いを寄せ、なんとかしたいと思うことが教育に携わる者の共通の基盤であるべきです。久保さんの提言を理由として文書訓告を出した大阪市教育員会はどうなんですか。提言が指摘した子どもたちの現状にまったく思いを寄せていないのだと思わざるを得ません。大阪市教委には、直ちに、文書訓告を取り消すこと、久保さんの「提言」内容について改めて検討することを求めます。久保さん、人権侵害救済申し立て、本当にありがとうございました。
◆和田幸子
是非、応援団員に入れてください。私は、久保さんの「提言書」には全面的に賛成です。松井市政や現行の教育委員会のやり方は、教育基本法改悪の時に危惧したとおりです。時の権力者が教育に出っ張ってきた過去に学ぼうとしない人たちが、この国を何処に連れて行こうとしているなか。子どもたちが主人公の教育行政を取り戻しましょう!
◆山田光一
ご苦労様です。可能な限り協力・参加したいと思いますので、よろしくお願いいたします