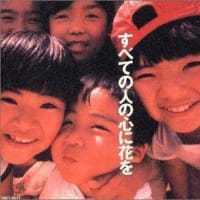子供のころ、誰しも親には自分のことを分かって欲しいと思ったことでしょう。
そして大きくなるにつれて、その対象は、親から友だち、先生、異性、配偶者、上司や同僚などへと
広がっていったと思います。
人はなぜ、自分のことを分かって欲しいと思うのでしょうか。
自分を分かって欲しいというのは、自分を受け入れて欲しいということに他なりません。
つまり、そこには自分は受け入れられていないという思いがあるわけです。
相手と心や気持ちが通うということは、目には見えない流動が生じている状態です。
そこに流れるのは、天地のエネルギーです。
天地に満ち満ちているご神気は、私たちの内にも外にも溢れており、それが停滞せず流れることで
私たちは生かされています。
他者との交流がない状態というのは、それがとどまった状態です。
密閉された部屋では、空気は濁っていきます。
流れのせき止められ川では、水は劣化して腐っていきます。
どちらもエネルギーが無くなった状態であるわけです。
流れが止まるとエネルギーは枯れていくのです。
「流動」というのはエネルギーそのものです。
万物流転や諸行無常というのは、この世のものは全てがエネルギー体であることを示しています。
「停止」というのはエネルギーがない状態です。
「止」は「死」に通じます。
それを避けるために、人はまわりの存在との関わりを本能的に求めるわけです。
そのために人は、あらゆる形で交流を生み出そうとします。
普通の交流が叶わない場合、たとえば攻撃でもって相手の反撃を引き出させて、流れを作り出そう
とすることもあります。
どのような形であれ、交流することがエネルギーを生むからです。
頭にきたりムカムカするのは、無意識のうちにその相手との交流を求めていることに他なりません。
本当に興味がなければ、何も引っかからないものです。
関わりたくないのに引っかかってしまうというのは、本質的には興味を持っているということです。
そのような場合、自分の中の雑味がその相手に投影されていることが多いと言えます。
つまり、鏡です。
それは、我が身を振り返るための交流となります。
この世界には、つまるところプラスアルファの交流しかありません。
交流の生み出したエネルギーが様々な物事を推し進める原動力となり、同時にまた、様々な物事
自体がそうしたエネルギーを生み出す素ともなるわけです。
さて、小さい子どもの頃は、純粋に自分を受け入れて欲しいと思っていたわけですが、成長するに
つれて自我が芽生えてきますと、どうしても親とのソリが合わなくなってきます。
交流は図りたい、しかし、自分の邪魔はされたくない。
すると、それが反抗期という形となって現れます。
反抗期になると、親にかぎらず自分以外のあらゆるものにムカムカしてしまいます。
世の中というのは、自分とソリが合わないものがほとんどです。
それら一つ一つにいちいち目くじら立ててイライラするのは、子供が成長する一つの過程です。
子供というのは、良くも悪くも、唯我独尊です。
この世に対して、決して受け身ではありません。
自分が中心であり、世界の全体です。
ただ、魂として正しいこの感覚に、新たに芽生え始めた自我がそのまま乗っかってしまうと大変な
ワガママへと拡大してしまいます。
一般的には、叱られたり失敗したり、高い鼻を折られたり、悲しい出来事を体験したりすることで、
増長した自我は徐々に抑えられていきます。
そして、そうした自我の縮小に合わせて、魂や心までも一緒に縮小させてしまったのが、今の私
たちであるとも言えます。
それは、自我が悪いものであるように捉えてしまっているところに一因があります。
自我はとても大切なものです。
自我というのは、意識のカーソルのようなものです。
標準を合わせるものです。
自我がなければ焦点は絞れません。
とはいえ、自我が暴走しても焦点は絞れません。
それが誤解を生む原因となっています。
自我は放っておくと際限なく暴走していくため、そこだけをとらまえてネガティヴな見方をされてしま
うわけです。
マイナスの捉え方では、マイナスの反発を招くだけです。
自我というのは抑えるものではなく、受け入れるものです。
押さえ込もうとしたりコントロールしようとすると余計に苦しくなります。
受け入れることによって自我は静まっていき、暴走熱は消えていきます。
そうして極限まで自我が研ぎ澄まされることで、焦点が無限小に極まるのです。
魂や心を縮小させずに自我の増長を無くすには、明るく伸び伸びと、しかし、慎ましく謙虚に生きる
ことが大切です。
成長とともに私たちは自我を見守れるようになっていきます。
それにつれて、まわりのことも受け入れられるようになります。
ソリが合わないと思っていたことにもイライラしなくなり、それはそういうものだとして受け入れられる
ようになっていくわけです。
子供の頃は、そうした自我が自由気ままな状態であるため、
「相手のことは分からなくてもいい。受け入れたくない。でも自分のことは分かって欲しい。受け入れ
て欲しい。」
となってしまいます。
どうしても「自分は全部わかっている。自分は正しい」と思ってしまうのです。
そして自分のまわりがソリの合わないことだらけになると孤立感が増してしまい、その不安な気持ち
から余計にイライラと当たり散らすわけです。
これは誰もが通ってきた道ですので、大なり小なりその因子が今もこの体に残っていると言えます。
とりわけ経験則から、自我を抑えることが得だとしてそれを積み重ねてきた場合は、見た目で影を
潜めていても、実際その因子は丸々そのまま残っていることでしょう。
それは、ただ比較と打算で押さえ込んでいるだけだからです。
ただ、まわりと交流したいという純粋な衝動からそれを重ねるのであれば、その因子は自然に昇華
されて霧散していきます。
「相手のことは受け入れたくない。でも自分のことは受け入れて欲しい」というのは、“交流”という
視点から見ると、明らかに条件が欠落しています。
ただの一方通行では、交流は生まれません。
循環して初めて、流動が保たれるのです。
ですから、もしも自分を受け入れて欲しいならば、まずは相手を受け入れることです。
受け入れない心では、受け入れない心しか返ってきません。
受け入れる心があって初めて、受け入れる心が返ってきます。
そこに天地の交流が生まれます。
反抗期の孤独感が薄れていったのも、結局は、自分がまわりのことを受け入れられるようになった
からだったのです。
そして相手を受け入れるためには、謙虚さが必要となります。
「自分はすべて分かっている」「自分の方が相手よりも上だ」と、自我が勝った状態では相手の心を
受け入れることはできません。
この場合の謙虚さというのは、意識して作るものではありません。
作為的な謙虚さには我欲のシコリが残ってしまい、それは我執と変わらなくなります。
自然な謙虚さというのは、たとえば、幼子を前にした時の感覚がそうです。
小さな子どもに相対した時、自分の方がまさっているという慢心を抱くようなことはありません。
「自分は何でも知っているが、こいつは何も分かっていない」とは思うはずもありません。
無意識のうちにそんなこだわりは捨てて、自然に優しく接するはずです。
そうであればこそ、幼子の方もこちらに心を開くわけです。
謙虚さというのは、それほど自然なものです。
決して、自身の自我を押さえ込んだり、着飾ったりするものではありません。
幼子を前にした時、純粋な思いが先行します。
純粋に相手と接したいと思った瞬間、すでに心はその相手に在ります。
つまり、心が相手のところまで広がっているわけです。
我を通したいという思いは、自分の中に引きこもっている状態のときに現れているということです。
「こだわりを手放したくないか」それとも「ただ純粋に相手と交流を図りたいか」。
その時の自分の心がどこに向いているかによって、結果として、謙虚になっていたり、意固地に
なっていたりするということです。
自分の心一つで、全ては自然に成るように成っているものなのです。
結果を求めようとするよりも、まずは自分の心に目を向ける方が先です。
私たちはそもそも、人と一緒に分かち合いたいという衝動を持っています。
その出どころは、遥か原初の状態にまでさかのぼります。
私たちは、今でも天地と一体ですが、原初は天地そのものでした。
自他の違いはなく、ただ一つでした。
このふるさとの感覚が、誰かと分かち合いたいという思いや、誰かと交流したいという思いに
繋がっていると感じます。
そうした思いを表面的なアプローチで押し進めようとすると、何も満たされずに余計に不満が
募ってしまいます。
そもそもが原初の感覚に端を発しているわけですから、見えるところを分かち合おうとしても
満たされるはずがありません。
外からのアプローチではなく、内からのアプローチが必要になってきます。
今も私たちは、目に見える世界に投影されているにすぎません。
そして、もとの大本では垣根なく、みんな繋がっています。
つまり、ラッセル車のように雪道を掘り進めようとするのではなく、最初から繋がっている部分に
心を向けるということです。
まさに、チェス盤の上部ではなく、その下の部分です。
それは降り積もったホコリを少しずつ掃いて、本当の地面へと立ち帰る作業です。
私たちは、最初からあらゆる全てのものと縦横無尽に交流していますし、あらゆる全てのもの
に受け入れられています。
それを阻害しているのは、自分自身に他なりません。
一方では、阻害する壁を絶えず造り続けながら、一方ではそこへ上書きするようにして交流を
図ろう(受け入れよう)という、正反対のことをしているわけです。
一人で綱引きをやっているのですから、大変に疲れてしまいます。
自分を顧みることなくただ交流を求めているうちは、それは決して叶わないものだと言えます。
上書きの交流を目指すよりも、まずは壁作りを諦めることです。
私たちというのは、そもそもの初発から交流している(=受け入れられている)からこそ、こうして
存在できています。
それを思い出すことで、自らの阻害行動は消えて、自ずと本来の交流が表面に現れてきます。
自分の世界にしがみついたまま交流を図ろうとするのは、まさしく自我の道を引くようなものです。
そうした一本道を行き交う流れというのは、イラスト的にも磁力線にそっくりですし、実際のところ
磁力が引き合うようにして人を引き寄せ合います。
文句ばかり言っている人間のところには、文句ばかり言っている人間が引き寄せられるわけです。
そもそも私たちは、天地に全面的に受け入れられています。
受け入れられるというのは、無条件に愛されているということです。
そこへフタをしているのは私たち自身です。
ひとたび天地の心を肌に感じれば、その温もりへ全身を投げ出しても大丈夫なのだと分かります。
いつでも安心しきって大丈夫だと理解します。
そして、自分だけではなく、世の中の全ての存在が同じく無条件に愛されている(受け入れられて
いる)ことが分かります。
そんな誰かに対して不満を持つのが、とても小さなことに思えてきます。
その相手もまた天地宇宙に全面的に受け入れられているというのに、なぜ人間風情の自分が文句
を言えるでしょう。
そのように考えますと、相手が何をしようともソレはソレとして、いい意味で放っておけるようになる
と思います。
そのとき、天地への感謝の思いが一気に溢れ出しているでしょう。
私たちは、何も分かっていませんし、誰よりも上ではありません。
天地の温もりを感じれば、増長する気持ちは決して起こりません。
ただ、感謝の思いで一杯になるだけです。
それが、天地に受け入れられている状態であり、同時に、天地を受け入れている状態です。
それは、天地に愛されているとともに、無条件に天地を愛しているということでもあります。
愛というのは、自ら出したり起こしたりするものではなく、結果としての「状態」です。
そして謙虚さというのもまた、自ら作るものではなく、自ずと辿り着く「状態」です。
私たちは、今こうしてこの世に存在しているということが、天地に受け入れられている何よりの証拠
です。
そうでなければ、そもそもが存在できないのです。
受け入れられている結果が、この世に「存在」として目に見える形で現われているのです。
愛されている結果が、この世に「存在」として目に見える形で現われているのです。
この世界はそうして成り立っています。
この世の全ての存在が、全面的に無条件に受け入れられ、全面的に無条件に愛されているのです。
自我を忌み嫌えば、自我は反発して余計に騒ぎ出します。
自我を受け入れれば、自我は暴走しなくなります。
ですから、まずは自分を受け入れることです。
そうして自分を受け入れれば、他人を受け入れられるようになります。
不満やストレスの心は血液をドロドロにしますが、素直な心は血液をサラサラにします。
天地に流れるエネルギーとは、まさに私たちを生かす血液です。
こだわりを捨てて、一つ一つを素直にそのまま受け入れることで、天地の心がサーッと流れ込んで
きます。
そして大きな優しい温もりが、私たちを包むように漂っていることを感じます。
天地宇宙は常にダイナミックに流動しています。
たとえ私たちが自分を受け入れられなくとも、そんなことに関係なく、私たちはすでに天地に受け入れ
られているのです。
不安に駆られて何かを求めようとしなくても、いいのです。
私たちは十二分なほどの全てに包まれています。
何も無いと不安に思うのは、目をつぶって両腕で身を固めてしまっているからです。
かたくなな心をほぐし、素直なままに、流れる風を感じましょう。
私たちにそそがれる天地の眼差しに耳を澄まし、心からの安らぎに浸ってみましょう。
透明にキラキラとプラチナ色に輝く幾千万もの無数の流れが、私たち自身や私たちのまわりの存在
すべてを包み込むように溢れています。
私たちは、絶対的に護られ、愛され、受け入れられています。
天地宇宙に満ち満ちるその流動こそが、私たちを生かしている命そのものなのです。
 にほんブログ村
にほんブログ村
そして大きくなるにつれて、その対象は、親から友だち、先生、異性、配偶者、上司や同僚などへと
広がっていったと思います。
人はなぜ、自分のことを分かって欲しいと思うのでしょうか。
自分を分かって欲しいというのは、自分を受け入れて欲しいということに他なりません。
つまり、そこには自分は受け入れられていないという思いがあるわけです。
相手と心や気持ちが通うということは、目には見えない流動が生じている状態です。
そこに流れるのは、天地のエネルギーです。
天地に満ち満ちているご神気は、私たちの内にも外にも溢れており、それが停滞せず流れることで
私たちは生かされています。
他者との交流がない状態というのは、それがとどまった状態です。
密閉された部屋では、空気は濁っていきます。
流れのせき止められ川では、水は劣化して腐っていきます。
どちらもエネルギーが無くなった状態であるわけです。
流れが止まるとエネルギーは枯れていくのです。
「流動」というのはエネルギーそのものです。
万物流転や諸行無常というのは、この世のものは全てがエネルギー体であることを示しています。
「停止」というのはエネルギーがない状態です。
「止」は「死」に通じます。
それを避けるために、人はまわりの存在との関わりを本能的に求めるわけです。
そのために人は、あらゆる形で交流を生み出そうとします。
普通の交流が叶わない場合、たとえば攻撃でもって相手の反撃を引き出させて、流れを作り出そう
とすることもあります。
どのような形であれ、交流することがエネルギーを生むからです。
頭にきたりムカムカするのは、無意識のうちにその相手との交流を求めていることに他なりません。
本当に興味がなければ、何も引っかからないものです。
関わりたくないのに引っかかってしまうというのは、本質的には興味を持っているということです。
そのような場合、自分の中の雑味がその相手に投影されていることが多いと言えます。
つまり、鏡です。
それは、我が身を振り返るための交流となります。
この世界には、つまるところプラスアルファの交流しかありません。
交流の生み出したエネルギーが様々な物事を推し進める原動力となり、同時にまた、様々な物事
自体がそうしたエネルギーを生み出す素ともなるわけです。
さて、小さい子どもの頃は、純粋に自分を受け入れて欲しいと思っていたわけですが、成長するに
つれて自我が芽生えてきますと、どうしても親とのソリが合わなくなってきます。
交流は図りたい、しかし、自分の邪魔はされたくない。
すると、それが反抗期という形となって現れます。
反抗期になると、親にかぎらず自分以外のあらゆるものにムカムカしてしまいます。
世の中というのは、自分とソリが合わないものがほとんどです。
それら一つ一つにいちいち目くじら立ててイライラするのは、子供が成長する一つの過程です。
子供というのは、良くも悪くも、唯我独尊です。
この世に対して、決して受け身ではありません。
自分が中心であり、世界の全体です。
ただ、魂として正しいこの感覚に、新たに芽生え始めた自我がそのまま乗っかってしまうと大変な
ワガママへと拡大してしまいます。
一般的には、叱られたり失敗したり、高い鼻を折られたり、悲しい出来事を体験したりすることで、
増長した自我は徐々に抑えられていきます。
そして、そうした自我の縮小に合わせて、魂や心までも一緒に縮小させてしまったのが、今の私
たちであるとも言えます。
それは、自我が悪いものであるように捉えてしまっているところに一因があります。
自我はとても大切なものです。
自我というのは、意識のカーソルのようなものです。
標準を合わせるものです。
自我がなければ焦点は絞れません。
とはいえ、自我が暴走しても焦点は絞れません。
それが誤解を生む原因となっています。
自我は放っておくと際限なく暴走していくため、そこだけをとらまえてネガティヴな見方をされてしま
うわけです。
マイナスの捉え方では、マイナスの反発を招くだけです。
自我というのは抑えるものではなく、受け入れるものです。
押さえ込もうとしたりコントロールしようとすると余計に苦しくなります。
受け入れることによって自我は静まっていき、暴走熱は消えていきます。
そうして極限まで自我が研ぎ澄まされることで、焦点が無限小に極まるのです。
魂や心を縮小させずに自我の増長を無くすには、明るく伸び伸びと、しかし、慎ましく謙虚に生きる
ことが大切です。
成長とともに私たちは自我を見守れるようになっていきます。
それにつれて、まわりのことも受け入れられるようになります。
ソリが合わないと思っていたことにもイライラしなくなり、それはそういうものだとして受け入れられる
ようになっていくわけです。
子供の頃は、そうした自我が自由気ままな状態であるため、
「相手のことは分からなくてもいい。受け入れたくない。でも自分のことは分かって欲しい。受け入れ
て欲しい。」
となってしまいます。
どうしても「自分は全部わかっている。自分は正しい」と思ってしまうのです。
そして自分のまわりがソリの合わないことだらけになると孤立感が増してしまい、その不安な気持ち
から余計にイライラと当たり散らすわけです。
これは誰もが通ってきた道ですので、大なり小なりその因子が今もこの体に残っていると言えます。
とりわけ経験則から、自我を抑えることが得だとしてそれを積み重ねてきた場合は、見た目で影を
潜めていても、実際その因子は丸々そのまま残っていることでしょう。
それは、ただ比較と打算で押さえ込んでいるだけだからです。
ただ、まわりと交流したいという純粋な衝動からそれを重ねるのであれば、その因子は自然に昇華
されて霧散していきます。
「相手のことは受け入れたくない。でも自分のことは受け入れて欲しい」というのは、“交流”という
視点から見ると、明らかに条件が欠落しています。
ただの一方通行では、交流は生まれません。
循環して初めて、流動が保たれるのです。
ですから、もしも自分を受け入れて欲しいならば、まずは相手を受け入れることです。
受け入れない心では、受け入れない心しか返ってきません。
受け入れる心があって初めて、受け入れる心が返ってきます。
そこに天地の交流が生まれます。
反抗期の孤独感が薄れていったのも、結局は、自分がまわりのことを受け入れられるようになった
からだったのです。
そして相手を受け入れるためには、謙虚さが必要となります。
「自分はすべて分かっている」「自分の方が相手よりも上だ」と、自我が勝った状態では相手の心を
受け入れることはできません。
この場合の謙虚さというのは、意識して作るものではありません。
作為的な謙虚さには我欲のシコリが残ってしまい、それは我執と変わらなくなります。
自然な謙虚さというのは、たとえば、幼子を前にした時の感覚がそうです。
小さな子どもに相対した時、自分の方がまさっているという慢心を抱くようなことはありません。
「自分は何でも知っているが、こいつは何も分かっていない」とは思うはずもありません。
無意識のうちにそんなこだわりは捨てて、自然に優しく接するはずです。
そうであればこそ、幼子の方もこちらに心を開くわけです。
謙虚さというのは、それほど自然なものです。
決して、自身の自我を押さえ込んだり、着飾ったりするものではありません。
幼子を前にした時、純粋な思いが先行します。
純粋に相手と接したいと思った瞬間、すでに心はその相手に在ります。
つまり、心が相手のところまで広がっているわけです。
我を通したいという思いは、自分の中に引きこもっている状態のときに現れているということです。
「こだわりを手放したくないか」それとも「ただ純粋に相手と交流を図りたいか」。
その時の自分の心がどこに向いているかによって、結果として、謙虚になっていたり、意固地に
なっていたりするということです。
自分の心一つで、全ては自然に成るように成っているものなのです。
結果を求めようとするよりも、まずは自分の心に目を向ける方が先です。
私たちはそもそも、人と一緒に分かち合いたいという衝動を持っています。
その出どころは、遥か原初の状態にまでさかのぼります。
私たちは、今でも天地と一体ですが、原初は天地そのものでした。
自他の違いはなく、ただ一つでした。
このふるさとの感覚が、誰かと分かち合いたいという思いや、誰かと交流したいという思いに
繋がっていると感じます。
そうした思いを表面的なアプローチで押し進めようとすると、何も満たされずに余計に不満が
募ってしまいます。
そもそもが原初の感覚に端を発しているわけですから、見えるところを分かち合おうとしても
満たされるはずがありません。
外からのアプローチではなく、内からのアプローチが必要になってきます。
今も私たちは、目に見える世界に投影されているにすぎません。
そして、もとの大本では垣根なく、みんな繋がっています。
つまり、ラッセル車のように雪道を掘り進めようとするのではなく、最初から繋がっている部分に
心を向けるということです。
まさに、チェス盤の上部ではなく、その下の部分です。
それは降り積もったホコリを少しずつ掃いて、本当の地面へと立ち帰る作業です。
私たちは、最初からあらゆる全てのものと縦横無尽に交流していますし、あらゆる全てのもの
に受け入れられています。
それを阻害しているのは、自分自身に他なりません。
一方では、阻害する壁を絶えず造り続けながら、一方ではそこへ上書きするようにして交流を
図ろう(受け入れよう)という、正反対のことをしているわけです。
一人で綱引きをやっているのですから、大変に疲れてしまいます。
自分を顧みることなくただ交流を求めているうちは、それは決して叶わないものだと言えます。
上書きの交流を目指すよりも、まずは壁作りを諦めることです。
私たちというのは、そもそもの初発から交流している(=受け入れられている)からこそ、こうして
存在できています。
それを思い出すことで、自らの阻害行動は消えて、自ずと本来の交流が表面に現れてきます。
自分の世界にしがみついたまま交流を図ろうとするのは、まさしく自我の道を引くようなものです。
そうした一本道を行き交う流れというのは、イラスト的にも磁力線にそっくりですし、実際のところ
磁力が引き合うようにして人を引き寄せ合います。
文句ばかり言っている人間のところには、文句ばかり言っている人間が引き寄せられるわけです。
そもそも私たちは、天地に全面的に受け入れられています。
受け入れられるというのは、無条件に愛されているということです。
そこへフタをしているのは私たち自身です。
ひとたび天地の心を肌に感じれば、その温もりへ全身を投げ出しても大丈夫なのだと分かります。
いつでも安心しきって大丈夫だと理解します。
そして、自分だけではなく、世の中の全ての存在が同じく無条件に愛されている(受け入れられて
いる)ことが分かります。
そんな誰かに対して不満を持つのが、とても小さなことに思えてきます。
その相手もまた天地宇宙に全面的に受け入れられているというのに、なぜ人間風情の自分が文句
を言えるでしょう。
そのように考えますと、相手が何をしようともソレはソレとして、いい意味で放っておけるようになる
と思います。
そのとき、天地への感謝の思いが一気に溢れ出しているでしょう。
私たちは、何も分かっていませんし、誰よりも上ではありません。
天地の温もりを感じれば、増長する気持ちは決して起こりません。
ただ、感謝の思いで一杯になるだけです。
それが、天地に受け入れられている状態であり、同時に、天地を受け入れている状態です。
それは、天地に愛されているとともに、無条件に天地を愛しているということでもあります。
愛というのは、自ら出したり起こしたりするものではなく、結果としての「状態」です。
そして謙虚さというのもまた、自ら作るものではなく、自ずと辿り着く「状態」です。
私たちは、今こうしてこの世に存在しているということが、天地に受け入れられている何よりの証拠
です。
そうでなければ、そもそもが存在できないのです。
受け入れられている結果が、この世に「存在」として目に見える形で現われているのです。
愛されている結果が、この世に「存在」として目に見える形で現われているのです。
この世界はそうして成り立っています。
この世の全ての存在が、全面的に無条件に受け入れられ、全面的に無条件に愛されているのです。
自我を忌み嫌えば、自我は反発して余計に騒ぎ出します。
自我を受け入れれば、自我は暴走しなくなります。
ですから、まずは自分を受け入れることです。
そうして自分を受け入れれば、他人を受け入れられるようになります。
不満やストレスの心は血液をドロドロにしますが、素直な心は血液をサラサラにします。
天地に流れるエネルギーとは、まさに私たちを生かす血液です。
こだわりを捨てて、一つ一つを素直にそのまま受け入れることで、天地の心がサーッと流れ込んで
きます。
そして大きな優しい温もりが、私たちを包むように漂っていることを感じます。
天地宇宙は常にダイナミックに流動しています。
たとえ私たちが自分を受け入れられなくとも、そんなことに関係なく、私たちはすでに天地に受け入れ
られているのです。
不安に駆られて何かを求めようとしなくても、いいのです。
私たちは十二分なほどの全てに包まれています。
何も無いと不安に思うのは、目をつぶって両腕で身を固めてしまっているからです。
かたくなな心をほぐし、素直なままに、流れる風を感じましょう。
私たちにそそがれる天地の眼差しに耳を澄まし、心からの安らぎに浸ってみましょう。
透明にキラキラとプラチナ色に輝く幾千万もの無数の流れが、私たち自身や私たちのまわりの存在
すべてを包み込むように溢れています。
私たちは、絶対的に護られ、愛され、受け入れられています。
天地宇宙に満ち満ちるその流動こそが、私たちを生かしている命そのものなのです。