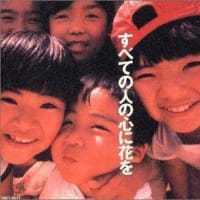人類の進化について特番が組まれてました。
進化の最後で二つに枝分かれしたネアンデルタール人とクロマニヨン人についての比較でした。
クロマニヨン人は我々と同じホモ・サピエンス。
DNAはほとんど同じですので見た目は全く変わりません。
一方、ネアンデルタール人は我々とは異なる亜種ということになります。
そのネアンデルタール人はこれまで知能が劣るとされていましたが、実は、最新の研究では極めて知能が高かったことが判明しているのだそうです。
いわゆる原始人というと、ウホウホやってるようなイメージでしたが、それは全くの間違い。
クロマニヨン人に全く引けを取らなかったと言います。
さらに身体能力の面では圧倒的に優っていたとも。
現代風に喩えるなら、非力なモヤシっ子に対して、IQの高いスーパーアスリートくらいの違いがあったようです。
しかし史実としてはそのスーパーアスリート集団が滅び、力の弱かったモヤシっ子軍団が生き残った。
それは何故かという内容でした。
結論は、スーパーアスリートのネアンデルタール人は小さな家族単位で暮らしていたのに対して、もやしっ子のクロマニヨン人は他の家族や仲間
と広く交流していたからというものでした。
それによって例えば、発見や発明を共有し、道具を進化させることができたとか、あるいは食糧不足に際しても相互扶助によって生き抜くことが
出来たということでした。

番組の内容は以上です。
ネットワークで可能性が広がり、集団力によって強さが増すというのはまさに理に適った話です。
とはいえ、助け合いは素晴らしい、みんな仲良くしましょう、などと薄っぺらい精神論で終わらしてしまうのはもったいない話です。
今さらそんなことは誰もが知っていることです。でも知っていながら、それがきちんと出来ないという事実がある。問題はそこです。
私たちはいま、様々なテクノロジーの発展により、超IQスーパーアスリートになっています。
助け合いの精神論は頭で分かっていても、テクノロジーの疑似能力によって大きな生存能力を獲得しているがために、本当の助け合いの必要性が
希薄になっています。
ですから、太古の二つの種から学ぶこととして、もっと根っこの部分に目を向ける必要があります。
つまり「何故クロマニヨン人は助け合いが出来たのか?」「何故ネアンデルタール人のように家族単位で暮らさなかったのか?」というところが
最大のポイントになってくるわけです。
結論を先に言ってしまうとそれは、彼らが自分たちは弱いということを自覚していたからに他なりません。
これは、それ以前の生物の歴史にも通じるところがあります。
強者は滅びて、弱い生き物の方が生き残ってきたという史実です。
強い存在というのは、今のままで十分生き抜いていけます。
ですからそれ以上の知恵を必要としません。
まさに日々安心のハッピーライフです。
しかし弱い存在は、そのままでは危ういので、生き抜こうと必死にもがいて、あらゆる知恵を使い続けます。
見ようによって、それは不安と苦しみ続きの日陰の人生と映るかもしれません。
でもそんなところに環境変化が訪れたら、後者の方が圧倒的有利となるのは明らかです。
弱い存在は、もがき苦しむ。
しかし、不断の努力をフルに発現し続ける。
それは謙虚や謙遜などではなく、己の現実をはっきりと自覚している状態であるということです。

このようにして見ると、いったい弱さとは何なのかという素朴な疑問が湧いてきます。
そして、もがき苦しむということも何なのかと。
弱さとなると、どうしてもマイナスのイメージを抱いてしまいます。
確かに「自分は強い」「自分は人より優ってる」というと、自信が湧いてくるものです。
でも、そのようにして得た自信というのは非常に脆い(もろい)ものだと言えます。
何より、弱さを排除することで自信を得ようとすると、謙虚さも失う恐れがあります。
そもそも、私たちが弱さをネガティヴなものに感じるのは「弱さによって自信を失うことを恐れているから」です。
その根っこには不安になりたくないという本能があります。
つまり、自信というのは安心感によって得られるものであるわけです。
その安心感を得るためにどのようなアプローチをするか。
その一つが、弱さを嫌い、強さを求めるというものです。
しかし「強い・弱い」という優劣意識によって得た安心感は仮りそめのものにしかなりません。
何故ならば、どこまでいってもそれは相対的なものでしかなく、鏡に映った虚像を追うようなものだからです。
鏡を挟んで分かれる虚と実。
鏡の向こうは観念の世界でしかありません。
つまり頭の中の世界でしかない。
鏡のこちら側こそが「実(じつ)」であるということです。
この場合の鏡とは何かといえば、優劣比較がそれに当たります。
比較という鏡によって優劣が映っているということです。
つまり本当の安心、本当の自信というのは、優劣比較(鏡)を手放すことで得られるのです。

「強さを求め、弱さを嫌う」
そうした優劣意識は、安心や自信を得たいがためのものでしたが、実は全く逆、追えば追うほど不安は尽きなくなるということなのでした。
ですから、まずは弱さを拒絶する心グセを捨てることが肝心要となります。
優劣比較という意味では、強さ弱さだけでなく、幸せと不幸、ラクと苦労というものについても同じことが言えます。
今の不幸は嫌だ、苦しい状況は嫌だ、幸せになりたい、ラクなりたい、と思っている間は、本当の安心を得ることはできないということです。
たとえば、病気になると誰でも弱気になります。
弱気になった時というのは、ネガティヴ思考に陥りやい反面、謙虚にもなります。
あるいは仕事でもプライベートでも、失敗をした時はガックリ落ち込みますが、同時に謙虚にもなります。
成功ばかり続いている人間は、自信家となって日陰が見えなくなります。
生きとし生けるものはすべて、日なたと日陰を有しています。
日陰を知るものは、己の本当の姿を認識することができるようになります。
日陰を知ればこそ、他の日陰もよく見えて、慈悲深くなります。
弱いからこそ、臆病になる。
弱いからこそ、もがき苦しむ。
弱いからこそ、努力を続ける。
弱いからこそ、謙虚になる。
弱いからこそ、他人を慈しめる。
これが人類の根源にあるわけです。
自分一人で生きていけると思う生物は滅びます。
「自分たちで何でも出来る」「他のことは知ったこっちゃない」という生物は滅ぶのです。
弱さを受け入れられないと、謙虚さが失われていきます。
自らの弱さを忌み嫌う人は、自己嫌悪に陥って卑屈になるか、あるいは己は強いと妄信して他の存在を軽視するようになります。
人を軽んじ、家族を軽んじ、国を軽んじ、天地を軽んじるようになります。
自尊心の強い人間ほど幼児性が際立っていきます。
己の弱さを認めたくないため、ひとたび弱みを指摘されると全身全霊で反撃を試みます。
己自身に関して全くの余裕がなくなり、安心感を得るため常に他人を責め立てるようになります。
つまり自分の弱さを受け入れないと、かえって打たれ脆い弱々しい存在になってしまうということです。
もとより、どれほど強い人間でも必ず弱さがあります。
強さを得たからといって弱さがなくなるわけではありません。
そもそも、私たちは弱さがあればこそ生き残ってこれた存在です。
そして、天地のあらゆる存在は日なたも日陰も有しているというのが真実です。
弱さを受け入れて地道に歩むか、弱さを忘れてラクさに溺れるか、そこが盛衰の分かれ目となります。
「強い弱い」というのは人間が決めた価値基準でしかありません。天地にそんなものは存在しません。
「押し引き」という言葉がありますが、押すのがプラスということではないですし、引くのがマイナスということでもありません。
押しては返す波がそうであるように、天地には自然な流れがあるだけです。
強さや押すことばかり求めるのは天地の理に反します。
一見強そうに思えても、それ一辺倒の人間は生物学的には最弱の存在ということになります。
本当に地獄を見た人、苦労人は、たとえ地位や名誉、金銭を得ようとも謙虚さを失うことはありません。
それは自分の弱さ、日陰の部分を嫌というほど知り、そしてそれを受け入れているからです。
もしもその弱さを毛嫌いしてフタしてしまうと、逆にイヤなタイプの傲慢な成金になってしまいます。
他人の弱さに寄り添うどころか、それをあげつらって非難するような輩に成り下がります。
長い人生を振り返って、常に順風満帆な人など居ないでしょう。
辛い経験というのは、日陰をしっかりと体験することに他なりません。
それによって、今の慈悲心や謙虚さが育まれたというわけです。
傷の深い人間は慈しみの深い人間と言えます。
それは日々の生活においても同じです。
ずっと晴れ続きであればハッピーかもしれませんが、現実はそうではありません。
苦労や失敗、あるいは病気というものは、私たちに弱さを思い出させてくれます。
そしてそれによって私たちは慎ましやかになり、謙虚さを取り戻します。
ほどほどの幸せと、ほどほどの不幸を繰り返すというのは、傷だらけにもならず傲慢にもならず丁度良い感じになるというわけです。
もとより、私たちは弱さを内含する存在であります。
そのことを思い出し、ありのままを受け入れる。
それは私たちが本当の私たちに合致する瞬間となります。
弱さを認めた瞬間、私たちは一番強い状態となるのです。
勝者という言葉を正しく使うなら、社会的な成功や現実的な勝ち負けなどは上っ面のものでしかなく、「己の弱さを知り、謙虚であるかどうか」
まさにそれに尽きます。
それこそが真の勝者です。
私たちの失敗や苦労や悲しみも、そのためにあると言えます。
弱さを知り謙虚になれたなら、それこそが勝者であるわけです。
日陰のありがたさ。
曇り雨のありがたさ。
人生において、雨を待ち望めとは言いませんが、晴れが少ないといって嘆く必要はないわけです。
雨模様になったら、そこであがき苦しむ。
それこそは私たちのご先祖様たちが繰り返してきた歴史そのものです。
苦しんでてイイ。
あがいててイイ。
「湿っぽいのは良くない」「ネガティヴは駄目」なんてのは幻想です。
日陰の湿っぽさこそは私たちの一部です。
青空ピーカン続きでは芽が開くことは無いのです。
晴れのち曇り、時々雨。
悲しみ、苦しみ、涙でグジュグジュ。
それが心の潤いとなって、慈愛の芽が開きます。
原始の人類が、家族単位を越えて他者と行動を共にできた最大の理由は、そこに他者を思う心が存在したからです。
弱き者、悲しみの深き者こそが他者を思いやることができた。
同じ悲しみを信じることができたわけです。
現代においても、日本というのは突き抜けて他者をおもんばかる民族と言われています。
それは、この狭い島国の中「俺が俺が」だけでは長くは続かなかったという理由もあるでしょう。
しかしそれ以上に、謙虚にならざるを得ない環境、自分たちの弱さを当たり前に受け入れざるを得ない環境だったからではないかと思います。
地震、噴火、台風、様々な自然災害を前にして、私たち人間が無力であるのは明らかです。
しかしその弱さというのは理不尽なことでも何でもなく、それが天地の当たり前の成り立ちだと私たちは理解しています。
己の弱さを悲しむでもなく卑下するでもなく、当たり前のものとして受け入れてきました。
だから、日本人は世界に類を見ない調和の民族と成ったわけです。
己の弱さを認めず天地自然に挑戦的な民族は、筋肉自慢になるだけで真の強さには程遠くなるということです。
私たちの人生は晴れっぱなしではありません。
しかし人類の歴史を見ても明らかなように、試練こそが私たちを生かしてきたわけです。
私たちは非力なモヤシっ子です。
今さら背伸びする必要などありません。
モヤシっ子だからこそ、強く生き抜いて来れたのです。
苦しみ、悲しみ、涙に暮れる日々にあろうと、己の弱さを知る者が、誰よりも強く逞ましく、優しさに満ち溢れた者になる。
遥か遠いご先祖様たちのDNAは、今この私たちにも刻まれています。

(おしまい)
進化の最後で二つに枝分かれしたネアンデルタール人とクロマニヨン人についての比較でした。
クロマニヨン人は我々と同じホモ・サピエンス。
DNAはほとんど同じですので見た目は全く変わりません。
一方、ネアンデルタール人は我々とは異なる亜種ということになります。
そのネアンデルタール人はこれまで知能が劣るとされていましたが、実は、最新の研究では極めて知能が高かったことが判明しているのだそうです。
いわゆる原始人というと、ウホウホやってるようなイメージでしたが、それは全くの間違い。
クロマニヨン人に全く引けを取らなかったと言います。
さらに身体能力の面では圧倒的に優っていたとも。
現代風に喩えるなら、非力なモヤシっ子に対して、IQの高いスーパーアスリートくらいの違いがあったようです。
しかし史実としてはそのスーパーアスリート集団が滅び、力の弱かったモヤシっ子軍団が生き残った。
それは何故かという内容でした。
結論は、スーパーアスリートのネアンデルタール人は小さな家族単位で暮らしていたのに対して、もやしっ子のクロマニヨン人は他の家族や仲間
と広く交流していたからというものでした。
それによって例えば、発見や発明を共有し、道具を進化させることができたとか、あるいは食糧不足に際しても相互扶助によって生き抜くことが
出来たということでした。

番組の内容は以上です。
ネットワークで可能性が広がり、集団力によって強さが増すというのはまさに理に適った話です。
とはいえ、助け合いは素晴らしい、みんな仲良くしましょう、などと薄っぺらい精神論で終わらしてしまうのはもったいない話です。
今さらそんなことは誰もが知っていることです。でも知っていながら、それがきちんと出来ないという事実がある。問題はそこです。
私たちはいま、様々なテクノロジーの発展により、超IQスーパーアスリートになっています。
助け合いの精神論は頭で分かっていても、テクノロジーの疑似能力によって大きな生存能力を獲得しているがために、本当の助け合いの必要性が
希薄になっています。
ですから、太古の二つの種から学ぶこととして、もっと根っこの部分に目を向ける必要があります。
つまり「何故クロマニヨン人は助け合いが出来たのか?」「何故ネアンデルタール人のように家族単位で暮らさなかったのか?」というところが
最大のポイントになってくるわけです。
結論を先に言ってしまうとそれは、彼らが自分たちは弱いということを自覚していたからに他なりません。
これは、それ以前の生物の歴史にも通じるところがあります。
強者は滅びて、弱い生き物の方が生き残ってきたという史実です。
強い存在というのは、今のままで十分生き抜いていけます。
ですからそれ以上の知恵を必要としません。
まさに日々安心のハッピーライフです。
しかし弱い存在は、そのままでは危ういので、生き抜こうと必死にもがいて、あらゆる知恵を使い続けます。
見ようによって、それは不安と苦しみ続きの日陰の人生と映るかもしれません。
でもそんなところに環境変化が訪れたら、後者の方が圧倒的有利となるのは明らかです。
弱い存在は、もがき苦しむ。
しかし、不断の努力をフルに発現し続ける。
それは謙虚や謙遜などではなく、己の現実をはっきりと自覚している状態であるということです。

このようにして見ると、いったい弱さとは何なのかという素朴な疑問が湧いてきます。
そして、もがき苦しむということも何なのかと。
弱さとなると、どうしてもマイナスのイメージを抱いてしまいます。
確かに「自分は強い」「自分は人より優ってる」というと、自信が湧いてくるものです。
でも、そのようにして得た自信というのは非常に脆い(もろい)ものだと言えます。
何より、弱さを排除することで自信を得ようとすると、謙虚さも失う恐れがあります。
そもそも、私たちが弱さをネガティヴなものに感じるのは「弱さによって自信を失うことを恐れているから」です。
その根っこには不安になりたくないという本能があります。
つまり、自信というのは安心感によって得られるものであるわけです。
その安心感を得るためにどのようなアプローチをするか。
その一つが、弱さを嫌い、強さを求めるというものです。
しかし「強い・弱い」という優劣意識によって得た安心感は仮りそめのものにしかなりません。
何故ならば、どこまでいってもそれは相対的なものでしかなく、鏡に映った虚像を追うようなものだからです。
鏡を挟んで分かれる虚と実。
鏡の向こうは観念の世界でしかありません。
つまり頭の中の世界でしかない。
鏡のこちら側こそが「実(じつ)」であるということです。
この場合の鏡とは何かといえば、優劣比較がそれに当たります。
比較という鏡によって優劣が映っているということです。
つまり本当の安心、本当の自信というのは、優劣比較(鏡)を手放すことで得られるのです。

「強さを求め、弱さを嫌う」
そうした優劣意識は、安心や自信を得たいがためのものでしたが、実は全く逆、追えば追うほど不安は尽きなくなるということなのでした。
ですから、まずは弱さを拒絶する心グセを捨てることが肝心要となります。
優劣比較という意味では、強さ弱さだけでなく、幸せと不幸、ラクと苦労というものについても同じことが言えます。
今の不幸は嫌だ、苦しい状況は嫌だ、幸せになりたい、ラクなりたい、と思っている間は、本当の安心を得ることはできないということです。
たとえば、病気になると誰でも弱気になります。
弱気になった時というのは、ネガティヴ思考に陥りやい反面、謙虚にもなります。
あるいは仕事でもプライベートでも、失敗をした時はガックリ落ち込みますが、同時に謙虚にもなります。
成功ばかり続いている人間は、自信家となって日陰が見えなくなります。
生きとし生けるものはすべて、日なたと日陰を有しています。
日陰を知るものは、己の本当の姿を認識することができるようになります。
日陰を知ればこそ、他の日陰もよく見えて、慈悲深くなります。
弱いからこそ、臆病になる。
弱いからこそ、もがき苦しむ。
弱いからこそ、努力を続ける。
弱いからこそ、謙虚になる。
弱いからこそ、他人を慈しめる。
これが人類の根源にあるわけです。
自分一人で生きていけると思う生物は滅びます。
「自分たちで何でも出来る」「他のことは知ったこっちゃない」という生物は滅ぶのです。
弱さを受け入れられないと、謙虚さが失われていきます。
自らの弱さを忌み嫌う人は、自己嫌悪に陥って卑屈になるか、あるいは己は強いと妄信して他の存在を軽視するようになります。
人を軽んじ、家族を軽んじ、国を軽んじ、天地を軽んじるようになります。
自尊心の強い人間ほど幼児性が際立っていきます。
己の弱さを認めたくないため、ひとたび弱みを指摘されると全身全霊で反撃を試みます。
己自身に関して全くの余裕がなくなり、安心感を得るため常に他人を責め立てるようになります。
つまり自分の弱さを受け入れないと、かえって打たれ脆い弱々しい存在になってしまうということです。
もとより、どれほど強い人間でも必ず弱さがあります。
強さを得たからといって弱さがなくなるわけではありません。
そもそも、私たちは弱さがあればこそ生き残ってこれた存在です。
そして、天地のあらゆる存在は日なたも日陰も有しているというのが真実です。
弱さを受け入れて地道に歩むか、弱さを忘れてラクさに溺れるか、そこが盛衰の分かれ目となります。
「強い弱い」というのは人間が決めた価値基準でしかありません。天地にそんなものは存在しません。
「押し引き」という言葉がありますが、押すのがプラスということではないですし、引くのがマイナスということでもありません。
押しては返す波がそうであるように、天地には自然な流れがあるだけです。
強さや押すことばかり求めるのは天地の理に反します。
一見強そうに思えても、それ一辺倒の人間は生物学的には最弱の存在ということになります。
本当に地獄を見た人、苦労人は、たとえ地位や名誉、金銭を得ようとも謙虚さを失うことはありません。
それは自分の弱さ、日陰の部分を嫌というほど知り、そしてそれを受け入れているからです。
もしもその弱さを毛嫌いしてフタしてしまうと、逆にイヤなタイプの傲慢な成金になってしまいます。
他人の弱さに寄り添うどころか、それをあげつらって非難するような輩に成り下がります。
長い人生を振り返って、常に順風満帆な人など居ないでしょう。
辛い経験というのは、日陰をしっかりと体験することに他なりません。
それによって、今の慈悲心や謙虚さが育まれたというわけです。
傷の深い人間は慈しみの深い人間と言えます。
それは日々の生活においても同じです。
ずっと晴れ続きであればハッピーかもしれませんが、現実はそうではありません。
苦労や失敗、あるいは病気というものは、私たちに弱さを思い出させてくれます。
そしてそれによって私たちは慎ましやかになり、謙虚さを取り戻します。
ほどほどの幸せと、ほどほどの不幸を繰り返すというのは、傷だらけにもならず傲慢にもならず丁度良い感じになるというわけです。
もとより、私たちは弱さを内含する存在であります。
そのことを思い出し、ありのままを受け入れる。
それは私たちが本当の私たちに合致する瞬間となります。
弱さを認めた瞬間、私たちは一番強い状態となるのです。
勝者という言葉を正しく使うなら、社会的な成功や現実的な勝ち負けなどは上っ面のものでしかなく、「己の弱さを知り、謙虚であるかどうか」
まさにそれに尽きます。
それこそが真の勝者です。
私たちの失敗や苦労や悲しみも、そのためにあると言えます。
弱さを知り謙虚になれたなら、それこそが勝者であるわけです。
日陰のありがたさ。
曇り雨のありがたさ。
人生において、雨を待ち望めとは言いませんが、晴れが少ないといって嘆く必要はないわけです。
雨模様になったら、そこであがき苦しむ。
それこそは私たちのご先祖様たちが繰り返してきた歴史そのものです。
苦しんでてイイ。
あがいててイイ。
「湿っぽいのは良くない」「ネガティヴは駄目」なんてのは幻想です。
日陰の湿っぽさこそは私たちの一部です。
青空ピーカン続きでは芽が開くことは無いのです。
晴れのち曇り、時々雨。
悲しみ、苦しみ、涙でグジュグジュ。
それが心の潤いとなって、慈愛の芽が開きます。
原始の人類が、家族単位を越えて他者と行動を共にできた最大の理由は、そこに他者を思う心が存在したからです。
弱き者、悲しみの深き者こそが他者を思いやることができた。
同じ悲しみを信じることができたわけです。
現代においても、日本というのは突き抜けて他者をおもんばかる民族と言われています。
それは、この狭い島国の中「俺が俺が」だけでは長くは続かなかったという理由もあるでしょう。
しかしそれ以上に、謙虚にならざるを得ない環境、自分たちの弱さを当たり前に受け入れざるを得ない環境だったからではないかと思います。
地震、噴火、台風、様々な自然災害を前にして、私たち人間が無力であるのは明らかです。
しかしその弱さというのは理不尽なことでも何でもなく、それが天地の当たり前の成り立ちだと私たちは理解しています。
己の弱さを悲しむでもなく卑下するでもなく、当たり前のものとして受け入れてきました。
だから、日本人は世界に類を見ない調和の民族と成ったわけです。
己の弱さを認めず天地自然に挑戦的な民族は、筋肉自慢になるだけで真の強さには程遠くなるということです。
私たちの人生は晴れっぱなしではありません。
しかし人類の歴史を見ても明らかなように、試練こそが私たちを生かしてきたわけです。
私たちは非力なモヤシっ子です。
今さら背伸びする必要などありません。
モヤシっ子だからこそ、強く生き抜いて来れたのです。
苦しみ、悲しみ、涙に暮れる日々にあろうと、己の弱さを知る者が、誰よりも強く逞ましく、優しさに満ち溢れた者になる。
遥か遠いご先祖様たちのDNAは、今この私たちにも刻まれています。

(おしまい)