嘉悦大学で行われた「空飛ぶ金魚と世界のひみつ」の映画とトークショウ、ワークショップに参加してきました。
内容は、副題にある「チガクテイイナ!」で、文化や宗教などが違っても、良い、いろいろな人が居るから世界は楽しい・・・というようなものです。
福岡で行われた世界の子供が集まる会議で、皆言葉は分からなくても、数日一緒にいると、知り合えて、友達になり、帰る頃には、離れるのが悲しくて皆泣くというのが一つのモチーフになっています。
ストーリーは、詳しくは、公式サイトをご覧ください。
過去、現在、未来が行ったり来たりしながら、
1.韓国からホームスティした男の子と受け入れ側の日本の男の子の友情。
2.絵本書きの父親に新しい中国人の妻がやってきて、このお母さんが「あきらめない」パワフルな人(普通ではない人)で、女の子との間で葛藤しながらも、あきらめない心を伝えていく。
3.空港地上員の新米の女性とバングラディッシュの親子の話。・・・・がオムニバスに進みます。
4.そして、人と人の関係がギクシャクすると「おもいやり泥棒」が現れて、人々の心から「おもいやり」を抜き去り、世界が色のない錆び色になってしまいます。でも、実は、「おもいやり泥棒」は、本当は、人と違う容姿なので、皆から疎外されており、寂しくてしょうがないので、世界を錆び色にしていたのです。だから、「おもいやり泥棒」をハグして、「チガクテイイナ!」と言ってあげると、心が融けて、世界に色が戻るのです。
絵本の中では、「空飛ぶ金魚」が色のない世界を色のある世界に変えていくという話。
キーワードとしては上記の「チガクテイイナ!」のほかに、「デアエテウレシイ」、「あきらめない」、「おもいやり」などが挙げられます。
後半は、4人に分かれて、このキーワードについて話し合うのを1回半くらいやりました。
+++++++++++
なかなか人が集まらなかったようですが、最後のラストスパートで40人くらい集まったのではないでしょうか。
中には、北海道から来られた方もおられましたし。2回目の方もおられました。千葉県の市役所で子どもの虐待のカウンセラーをされている方もおられました。
正直私は、話の内容がベタなのと、子ども向けだからかテンポがゆったりしているので、眠くなって、飽きてしまいました。
また、世界中で紛争が起きているなか、どうハグしたら、紛争が無くなるというのだろうとあまりのキレイごとに飽きれてしまいました。
でも、言われていることは、まったく正しいし、子ども達には、こういう気持ちを持ってもらい、いつか、本当に世界が一つになってもらいたいものと思います。
また、今回のストーリーとしては、多文化・多民族がテーマでしたが、現在、日常的に学校でのいじめや子どもの虐待が行われているなかで、こんな甘い話で良いのだろうかとも思いました。
+++++++++++
ワークショップでは、4人が4つのキーワードの1つを選んで5分話し、2分それに皆が意見を言い合うというのをやりました。
映画を見てグサッと来たという方もおられました。「あきらめない」を選んだ女性は、「自分は、親と喧嘩をして家を出てもう10年くらいになるが、これまでその現実を直視していなかった、でも、映画を観て、勇気をもって諦めずに現実と向きあわないとと思った」と言われていました。
「チガクテイイイナ!」を選んだ男性は、脚本家がどうして「チガクテイイヨ!」と直接的に呼びかけるのではない「チガクテイイナ!」という間接的な言葉を選んだんだろうと言われていました。言われてみればそうだなぁと思い、最後に質問しましたところ、この言葉が「合言葉、呪文??」のように、広く普及して欲しいと思ったからとのことでした。
私は、「おもいやり」というキーワードを選びましたが、「おもいやり」があるというのではなく、私自身が「おもいやり泥棒」のような気がすると言いました。
私は、良く人に、「このみさんの言葉は人を傷つける」と叱られたり、注意されたりします(親切心から)。
だから、気を付けるようにはしているのですが、「嫌いなもの」「我慢できないもの」「思いやれないもの」に蓋をして、良い顔をするのは、本当は嫌なのです。
私も67歳になって自身も高齢者ですが、高齢者を一律に弱者に見立てて大切にするということも嫌ですし、障害者など弱者を慮るというのが嫌なのです。弱い人を踏みにじろうとは思わないのですが、誰でも彼でもが、「いい子ぶる」というか「理解者」であるというような顔をしなくてはならないというのが気持ち悪い。障害者で素晴らしい色彩感覚を持つ子もいれば、人にやさしい子もいます。それぞれを良く見て、弱いところは弱いと知り、良いところは凄いなぁと感心すれば良いと思います。
気持ち悪いものを気持ち悪いと言えない社会は、却って色が無いような気がする。
そのうえで、「彼は、これこれこういう訳で、これが出来ないのだから、そこを理解してあげなければいけない」と言われて納得すれば、始めて、「思いやれば良い」と思います。
これは、私がいつも孤立していて、誰からも「チガクテイイ」と言われない寂しい人間だからなのかもしれません。
2回目のワークショップは、人を変えて、一人2分ずつ話し合うというものでした。その時一緒だった、中学生の女の子は、「知らない人とこんなに心を開いて話せるとは自分でも驚いている」と言われていました。
また、今学校では「喧嘩はしてはいけないことになっている」と教えてくれました。
おそらく、今の子供たちは、表面では、理解しあったように取り繕いながらも、でも気に入らない子がいれば、ネットなどで、こそこそといじめをするのではないかと思います。
口に出して、「あんたのこういうところが気に入らない」「あたしもあんたのこういうところが気に入らない」と喧嘩をして、誰かが仲裁をするなり、話し合いをすることによって、「じゃあこう直そう」とか「病気ならしかたないね」と理解し合う方が健全なのではないでしょうか。
内容は、副題にある「チガクテイイナ!」で、文化や宗教などが違っても、良い、いろいろな人が居るから世界は楽しい・・・というようなものです。
福岡で行われた世界の子供が集まる会議で、皆言葉は分からなくても、数日一緒にいると、知り合えて、友達になり、帰る頃には、離れるのが悲しくて皆泣くというのが一つのモチーフになっています。
ストーリーは、詳しくは、公式サイトをご覧ください。
過去、現在、未来が行ったり来たりしながら、
1.韓国からホームスティした男の子と受け入れ側の日本の男の子の友情。
2.絵本書きの父親に新しい中国人の妻がやってきて、このお母さんが「あきらめない」パワフルな人(普通ではない人)で、女の子との間で葛藤しながらも、あきらめない心を伝えていく。
3.空港地上員の新米の女性とバングラディッシュの親子の話。・・・・がオムニバスに進みます。
4.そして、人と人の関係がギクシャクすると「おもいやり泥棒」が現れて、人々の心から「おもいやり」を抜き去り、世界が色のない錆び色になってしまいます。でも、実は、「おもいやり泥棒」は、本当は、人と違う容姿なので、皆から疎外されており、寂しくてしょうがないので、世界を錆び色にしていたのです。だから、「おもいやり泥棒」をハグして、「チガクテイイナ!」と言ってあげると、心が融けて、世界に色が戻るのです。
絵本の中では、「空飛ぶ金魚」が色のない世界を色のある世界に変えていくという話。
キーワードとしては上記の「チガクテイイナ!」のほかに、「デアエテウレシイ」、「あきらめない」、「おもいやり」などが挙げられます。
後半は、4人に分かれて、このキーワードについて話し合うのを1回半くらいやりました。
+++++++++++
なかなか人が集まらなかったようですが、最後のラストスパートで40人くらい集まったのではないでしょうか。
中には、北海道から来られた方もおられましたし。2回目の方もおられました。千葉県の市役所で子どもの虐待のカウンセラーをされている方もおられました。
正直私は、話の内容がベタなのと、子ども向けだからかテンポがゆったりしているので、眠くなって、飽きてしまいました。
また、世界中で紛争が起きているなか、どうハグしたら、紛争が無くなるというのだろうとあまりのキレイごとに飽きれてしまいました。
でも、言われていることは、まったく正しいし、子ども達には、こういう気持ちを持ってもらい、いつか、本当に世界が一つになってもらいたいものと思います。
また、今回のストーリーとしては、多文化・多民族がテーマでしたが、現在、日常的に学校でのいじめや子どもの虐待が行われているなかで、こんな甘い話で良いのだろうかとも思いました。
+++++++++++
ワークショップでは、4人が4つのキーワードの1つを選んで5分話し、2分それに皆が意見を言い合うというのをやりました。
映画を見てグサッと来たという方もおられました。「あきらめない」を選んだ女性は、「自分は、親と喧嘩をして家を出てもう10年くらいになるが、これまでその現実を直視していなかった、でも、映画を観て、勇気をもって諦めずに現実と向きあわないとと思った」と言われていました。
「チガクテイイイナ!」を選んだ男性は、脚本家がどうして「チガクテイイヨ!」と直接的に呼びかけるのではない「チガクテイイナ!」という間接的な言葉を選んだんだろうと言われていました。言われてみればそうだなぁと思い、最後に質問しましたところ、この言葉が「合言葉、呪文??」のように、広く普及して欲しいと思ったからとのことでした。
私は、「おもいやり」というキーワードを選びましたが、「おもいやり」があるというのではなく、私自身が「おもいやり泥棒」のような気がすると言いました。
私は、良く人に、「このみさんの言葉は人を傷つける」と叱られたり、注意されたりします(親切心から)。
だから、気を付けるようにはしているのですが、「嫌いなもの」「我慢できないもの」「思いやれないもの」に蓋をして、良い顔をするのは、本当は嫌なのです。
私も67歳になって自身も高齢者ですが、高齢者を一律に弱者に見立てて大切にするということも嫌ですし、障害者など弱者を慮るというのが嫌なのです。弱い人を踏みにじろうとは思わないのですが、誰でも彼でもが、「いい子ぶる」というか「理解者」であるというような顔をしなくてはならないというのが気持ち悪い。障害者で素晴らしい色彩感覚を持つ子もいれば、人にやさしい子もいます。それぞれを良く見て、弱いところは弱いと知り、良いところは凄いなぁと感心すれば良いと思います。
気持ち悪いものを気持ち悪いと言えない社会は、却って色が無いような気がする。
そのうえで、「彼は、これこれこういう訳で、これが出来ないのだから、そこを理解してあげなければいけない」と言われて納得すれば、始めて、「思いやれば良い」と思います。
これは、私がいつも孤立していて、誰からも「チガクテイイ」と言われない寂しい人間だからなのかもしれません。
2回目のワークショップは、人を変えて、一人2分ずつ話し合うというものでした。その時一緒だった、中学生の女の子は、「知らない人とこんなに心を開いて話せるとは自分でも驚いている」と言われていました。
また、今学校では「喧嘩はしてはいけないことになっている」と教えてくれました。
おそらく、今の子供たちは、表面では、理解しあったように取り繕いながらも、でも気に入らない子がいれば、ネットなどで、こそこそといじめをするのではないかと思います。
口に出して、「あんたのこういうところが気に入らない」「あたしもあんたのこういうところが気に入らない」と喧嘩をして、誰かが仲裁をするなり、話し合いをすることによって、「じゃあこう直そう」とか「病気ならしかたないね」と理解し合う方が健全なのではないでしょうか。










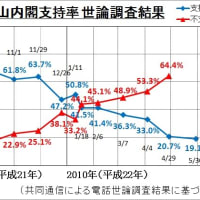
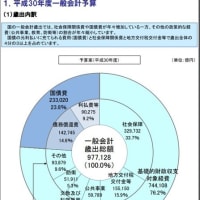
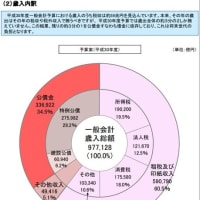
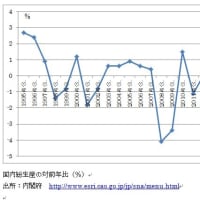
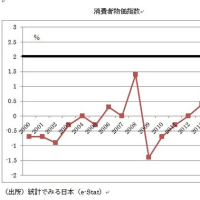



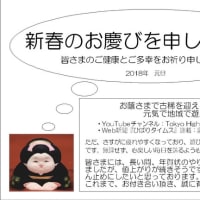

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます