
最近、高齢者を対象にした講座を実施した。
そこから3つのことを学んだ。
1.ついうっかりわすれる
3回シリーズの講座をやったのだが、毎回ごとでもOK。でも、第1回の講座を受講された方に、もしご希望があるなら、第2回とか第3回とかに丸をして、お名前を書いて頂いた。
ところが、第2回の講座に10名くらいの方が来られなかった。幸い、予約なしでこられた方が多かったので、それなりの人数になったのだが。
高齢者向け講座を長年やっておられる方によると、予約していても、「ついうっかり」忘れる方が多いのだとのこと。
このため、その方は、前日とかにお電話するようにしているという。
2.ゆっくり、繰り返してお話する
私は、どちらかといえば、早口の方かもしれない。第2回の講師の方は、ゆ・っ・く・りと、繰り返しながらお話されているので、私もはっと気が付き、そこからなるべくゆっくり話すようにした。
その折には、耳の不自由な方もおられたので。第1回の折には、耳の不自由な方が、遅くこられて後ろの席になり、あとで聞こえなかったと言われてしまった。
耳、足・・・いろいろなところが不自由なかたがおられるので、多様な配慮が必要。
3.紙媒体が強い
数年もすれば変わってくるのだろうが、ネットではごくわずかの方にしかリーチできない。
戸別配布される市報や公民館だよりの影響力は凄い。
もちろん、地元エリアを対象にした「タウン通信」や「アサココ」さんなどのメディアも大きな影響力を持つ。
チラシを印刷し、足を棒のようにして公共機関などに配布している。それを見てという方もおられるが、市報等や地元紙の効果には遠く及ばない。
市報は、同じ団体は、年3回まで、公民館だよりは年2回まで、戦略を上手く立てて使わないともったいない。
数年前、「おとぱ」(お父さんお帰りなさいパーティの略)を実施して、余りの反応の無さに嫌気がさしたのだが、お客を知ら無すぎたのかもしれない。












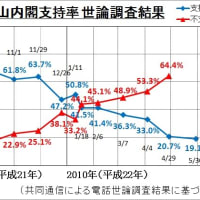
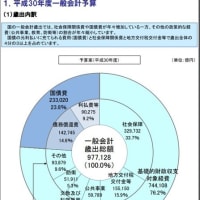
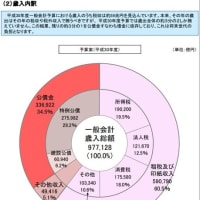
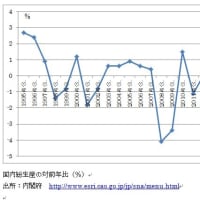
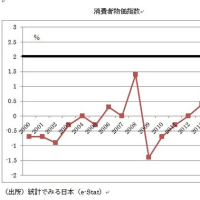



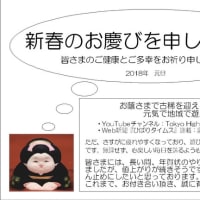

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます