「西東京まち探カレッジ」第4回 2015.7.6
「震災からの復興・避難先での暮らしを私たちはどう考えたらよいのか、私たちに出来ることは何だろうか」
★後藤恭子さん(浪江町から避難、縁あって西東京市で暮らす)からの「震災体験と防災について」のお話を伺いました。 以下は、富沢の備忘録です。
1. スライド(被災当時の写真、その後、汚染土壌をくるんだ黒い包みが山積みになっている)を見ながら、当時の体験談をお聞きしました。
(ア) その時々の決断が生死を分けるのだなぁと感じました。
(イ) 消防団員が自らの家族も被災しているなか、一生懸命救助してくれた。次が自衛隊の方々。
(ウ) 逃避行している途中で、山の方の別荘住まいの方々が炊き出ししてくれたり、ガス欠で止まっていた駐車場で、そこのラーメン屋の方がご馳走してくれた→人の暖かさを感じた。
(エ) 一方で、ポリバケツを5000円で売る人、1万円札で支払ったらおつりをくれない人など、品性が悪くなる人もいた。
(オ) 親戚と連絡を取って、なんとか逃げ延びたものの、親戚や子どもの家に居れるのは、せいぜい一ヶ月。
★福島の汚染土壌の様子(you tubeより)
2. 防災についてのお話は、役立つことも多かったので、メモしておきます。
(ア) 先ずは、自分の身を守ること(私は大丈夫だ!などと自信過剰な考えはやめましょう)持ち物には、名前を書いておくこと。似たようなものを持っている人が多く、避難所ではトラブルになりがち。
(イ) 室内にあるもの総てのモノが凶器になります。ピアノまで倒れます。日ごろから生活はシンプルにすることを心がける。
(ウ) 家族の落ち合う場所は、前もって2~3ケ所、決めておくこと。しかし、目印にしていた建物や木などは、全部流され、道はぐじゃぐじゃになるなど風景が一変する。伝言ダイヤルなどの活用。
(エ) 避難場所に行く道も前もって三通りくらい考えておかないと。目標としていた建物が倒壊すると方向が分からなくなる。
(オ) 他人のことは当てにしない。あの人が動かないからと他人の様子をうかがうのではなく、自ら判断しないと間に合わない。
(カ) 家を出る時は、火の元の確認とブレーカーを落とすこと(自分の家からは、絶対に火を出さないこと)
(キ) 足元は丈夫な靴を履く、軍手とマスクは必需品。帽子、ヘルメット、頭巾なども必需品。
(ク) 非常持ち出しと備品は分けて考える。前者は、1から2日必要なもの、身軽なもの。リュックや、釣りのベストのようにポケットの沢山ついたベストに入れるとよい。携帯、ラジオ、ポリ袋、防寒、水のストック、トイレ、懐中電灯、メガネ、薬、タオル、ティッシュ、飴、お金など。ホイッスルは、ガレキの下でまだ生きていることを知らせるのに有効。
(ケ) 備品は、災害がある程度落ち着き、家に戻った折、救助品が来るまで、2から3日凌げるもの。食品、衣類、毛布など。
(コ) 「防災、防災」と良く耳にするが、災害の形はさまざま、考えていた通りにはならない。臨機応変の対応が鍵!
(サ) そのうちにする予定では、永久にできない。行動があってこそ価値がある。後悔の無いように!
(シ) 人と人とのつながりこそ、災害時に生きると思う。
(ス) その時には、世の中が狂気になる!










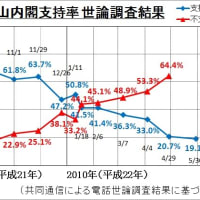
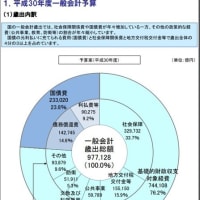
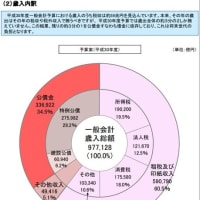
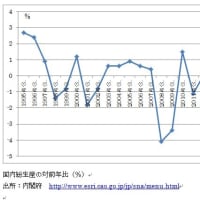
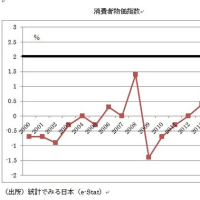



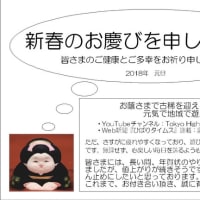

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます