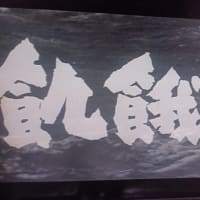さて先日5月20日に品川にある物流博物館に行ってきました。
こちらの鉄道ホビダスというページで、品川の物流博物館で貨物輸送に関する企画展をやっているのを見て、都心に出かけたついでに寄ってみることにしました。
品川駅の高輪口を降りて、プリンスホテルや旧パシフィックホテルの間の坂道を上がって行き、突き当りを左に曲がり狭い道に入る・・といったところで、品川駅から徒歩10分ほどで物流博物館に到着。

このシックな感じの小さい建物が「物流博物館」
入口の受付でチケット(大人200円)を買って入場します。

今回の目当てはこの企画展示「追憶・西関東の鉄道貨物輸送 ~鉄道貨物研究家・渡辺一策氏のフィールドノートから~」
この物流博物館は通常は常設展示で1階が「物流の歴史」地下1階が「現代の物流」となっているそうですが、企画展期間中は1階の「物流の歴史」はお休みで変わりに企画展示されるという構成のよう。
今回の企画展示は鉄道貨物研究家の渡辺一策氏が昭和30年代~昭和50年代頃にかけて、独自に調査した西関東地区の鉄道貨物輸送に関する展示。
写真だけでなく当時の調査データや資料、それらに基づき作られたパネル展示などで、当時の鉄道貨物輸送の状況を知る事が出来ます。
西関東という表現は聞きなれないですが、概ね当時の国鉄の東京西鉄道管理局の範囲を中心として「南は小田急線・相模線・相鉄線・北は東上線・西武線・秩父鉄道あたり」のエリアをさすよう。
企画展示は著作権の関係で撮影不可だそうで写真で紹介できないのは残念ですが・・・
第1章として主要路線ごとの概要。第2章として当時の主要な輸送品目(石灰・砂利・砕石・コンクリート・石油など)ごとに当時の輸送の状況やルートなどが解説されています。
私が子供の頃は地元の南武線でも奥多摩から臨海部に向けて石灰石貨物列車が頻繁に運転されていて、駅で電車を待っていると「電車がまいります」の表示が出た・・と思ったら貨物列車の通過。だったとか、貨物列車のお陰で踏切がなかなか開かなくて・・といった幼少期の記憶があるものです。
1960~1970年代当時はこの奥多摩からの石灰輸送が隆盛を極めていた時代。ただこの頃は南武線は単線区間があり線路容量が低く貨物列車の運転は少なく、中央線・山手貨物線経由での運転が基本だったよう。
南武・青梅線は奥多摩の石灰石を臨海部の浜川崎に運ぶ為の路線だと聞いていたので、これはちょっと意外な感が・・・。またこれが後述する新宿駅での衝突、大炎上事故の遠因にもなったそうで。
渡辺氏手作りの当時の貨物列車のダイヤも展示されていましたが、当時、奥多摩から立川方面の青梅線や秩父鉄道の一部では、貨物列車が24時間体制で運行されていたそうなのもビックり

以前に一度電車で奥多摩まで行ったことがありましたが、青梅から先は単線の線路が深い山の中を延々と走るような「東京都内」とは思えないようなローカルな路線だと思ったものですが、往時はそんな線路を24時間体制で貨物列車がひっきりなしで走っていた。というのは俄かにはイメージし難いものです。
また国鉄(現JR)路線だけでなく、東武や西武・小田急・相鉄など、現代では通勤電車が頻繁に行きかう通勤路線でも貨物輸送は頻繁に行われていたそうで、それらも紹介されていました。
小田急線も「昔は貨物列車があって、往時は砂利輸送の積み下ろし基地が東北沢にあった」という話や「足柄の専売公社(JT)工場までの貨物輸送が昭和50年代後半ぐらいまで行われていた」など、断片的な話は聞いていましたが、当時の写真なども含めもっと詳しく知ることが出来ました。
小田急線の場合、相模川の川砂利の採掘が1960年代末期に禁止されて貨物輸送が衰退するものの、その後も伊勢原駅が穀物輸送のターミナルとなり昭和40年代終わりごろまで伊勢原~小田原間で数往復の貨物列車が走っていたそうで・・・。伊勢原の話は初耳でした。
高度経済成長で郊外の開発が進み乗客が増える時代以前は、貨物輸送の収入が私鉄会社の経営を下支えし、現代の発展に至る基礎に。
またその高度経済成長期の開発や建設ラッシュで必要なコンクリートやその原料。鉄の原料になる石灰石輸送もまた鉄道貨物が支えていたということを実感しました。
1960年代は安保問題やベトナム戦争問題など、国際的にも揺れた時代だったと聞きますが、その中で、首都圏内各地の米軍基地への鉄道石油輸送がベトナム戦争の激化に比例して増大。当時の過密ダイヤの中で1967年には新宿駅で石油列車と石灰石列車が衝突大炎上するという負の側面も・・・。
当時の物流の主役であり、その時代を創っていたと表現しても過言ではなさそうな鉄道貨物輸送存在というものを詳しく知ることが出来て、行って良かったです。
この物流博物館自体が小さな博物館で展示スペースもそう大きくないので、展示のボリューム自体が限られてしまうのは残念ですね。もっと詳しく見たかった部分が多々・・・ですね

また鉄道貨物とはいえ、物流面にスポットを当てた紹介が主体なので、機関車や貨車など車両自体に関する展示解説は殆どなく、そういう面では車両ファンには物足りないかもですね。
鉄道貨物輸送は道路事情の向上と共に昭和50年代以降から段々と縮小、国鉄末期のスト連発などで荷主の信頼を失い滅亡への道を。その後JR移行や昨今の環境意識の高まりで幹線輸送を中心にいくらか盛り返し・・・という流れを辿るのは既出な話です。
昨今よく聞く、地方のローカル鉄道路線の多くが存続の危機に立たされているというのも、
「周辺の過疎化や人口減少、少子化で高校生の通学という手堅い需要が減り・・」という文言がテンプレの如く頻出ですが、実は「貨物輸送という大きな収入源を失った」という裏事情も忘れてはならなそうそうです。

地下1階の「現代の物流」のメイン展示の、巨大ジオラマ。鉄道・トラック・コンテナ船・航空の各貨物ターミナルが再現されていて、詳細な解説がタッチパネル画面で見れたり一部模型が動いてました。
またゲームで物流が学べるコーナーがあったりと、子供でも分かりやすいような展示になっています。

「現代の鉄道貨物」として2006年に運行が開始された「スーパーグリーンシャトル」が紹介されていました。CO2削減先の一環として、東京~大阪間で大型10トントラックと同じ31フィートコンテナで構成された列車で運行されていて、申し込めば誰でも手軽に利用出来るそう。
今回は企画展期間なので1階の常設展「物流の歴史」は見ることが出来ませんでしたが、またの機会に訪問して見学したいなと思います。
2014/5/22 3:18(JST)