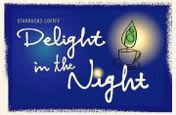5~6年ぐらい前から、関係者で検討と作業が行われていた海・空のNACCSの更改作業が2月21日のAirの新システムの稼動で一応終了し、順調に稼動しているとのこと。関係者のご苦労に、ひとまずお疲れ様ですと申します。
全国の輸出入申告の98%が、NACCSで申告し許可になっているとのこと、日本で唯一の貿易手続きシステムとして、港湾、空港の貨物処理のシステムとしてこれからも進化することを期待しています。
そこで、今回はこのNACCSの普及状況を企業統計から見てみます。
よく笑い話で、もっとも多い職業は、「社長さん」と言われます。
政府の事業所・企業統計調査によれば、わが国の会社企業(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社)の数は、2006年10月の調査では151万社ということです。すると成人日本人の、5~60人に一人は社長さんということになりそうで、盛り場を歩いている人をキャッチするのに「社長さん、社長さん」と呼ぶのは当たっている確率がそれなりにありそうで、「部長さん、部長さん」と声をかけるよりは、好感度もアップし営業用語としては良さそうです(笑)。
ついでに、同じ統計の事業所数は、609万ですので、社長さんと所長さんの名刺は、成人日本人の10人か15人に一人くらいは持っている計算になりそうです。
:::::::
脱線はさておき、NACCSの民間利用者は、輸出入・港湾関連情報処理センター(株)の資料によれば、2009年10月末現在で、海と空を合わせて2471社、5954事業所と発表されています。
先ほどの、日本中の会社や事業所の数から見れば微々たる比率ですが、日本のJRの駅の数が約4600で、
JR、私鉄、路面電車、地下鉄の数を全部合計すると約9800と言われていますから、NACCSを利用している事業場は、それなりの広がりと規模になっていることが明らかです。
:::::::::::::
NACCSの関連の話題をもう一つ取り上げると、昨24日の神戸税関のホームページで、「輸出入・港湾関連情報処理システム等に障害が生じた場合の税関手続について」というお知らせがアップされています。
NACCSの更改作業が上手くいったからといって、システムの突然の不調で長時間、利用できないということは、銀行や他のシステムや、外国の税関システムの例を持ち出すまでもなく有りうることです。
NACCSがシステムダウンしたからといって、24時間も輸出入が出来ないなんてことは許されません、不測の事態に備えての対応をあらかじめ示しておくというのは、適切な計らいのように感じています。

:::::::::::::
この2・3日、コートでは汗ばむような気温となっています。花粉が飛び出して、この季節には沖縄で生活したいという方もいらっしゃるのでは。お察しします。
数回前のブログでPCが不調と申しましたが、Windows7のノートを買いました。
サクサクではありますが、ユーザーインターフェイスがだいぶ変わり、目下習熟中です。
がんばれ、TOYOTA!! がんばれ NIPPON!!
全国の輸出入申告の98%が、NACCSで申告し許可になっているとのこと、日本で唯一の貿易手続きシステムとして、港湾、空港の貨物処理のシステムとしてこれからも進化することを期待しています。
そこで、今回はこのNACCSの普及状況を企業統計から見てみます。
よく笑い話で、もっとも多い職業は、「社長さん」と言われます。
政府の事業所・企業統計調査によれば、わが国の会社企業(株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社)の数は、2006年10月の調査では151万社ということです。すると成人日本人の、5~60人に一人は社長さんということになりそうで、盛り場を歩いている人をキャッチするのに「社長さん、社長さん」と呼ぶのは当たっている確率がそれなりにありそうで、「部長さん、部長さん」と声をかけるよりは、好感度もアップし営業用語としては良さそうです(笑)。
ついでに、同じ統計の事業所数は、609万ですので、社長さんと所長さんの名刺は、成人日本人の10人か15人に一人くらいは持っている計算になりそうです。
:::::::
脱線はさておき、NACCSの民間利用者は、輸出入・港湾関連情報処理センター(株)の資料によれば、2009年10月末現在で、海と空を合わせて2471社、5954事業所と発表されています。
先ほどの、日本中の会社や事業所の数から見れば微々たる比率ですが、日本のJRの駅の数が約4600で、
JR、私鉄、路面電車、地下鉄の数を全部合計すると約9800と言われていますから、NACCSを利用している事業場は、それなりの広がりと規模になっていることが明らかです。
:::::::::::::
NACCSの関連の話題をもう一つ取り上げると、昨24日の神戸税関のホームページで、「輸出入・港湾関連情報処理システム等に障害が生じた場合の税関手続について」というお知らせがアップされています。
NACCSの更改作業が上手くいったからといって、システムの突然の不調で長時間、利用できないということは、銀行や他のシステムや、外国の税関システムの例を持ち出すまでもなく有りうることです。
NACCSがシステムダウンしたからといって、24時間も輸出入が出来ないなんてことは許されません、不測の事態に備えての対応をあらかじめ示しておくというのは、適切な計らいのように感じています。

:::::::::::::
この2・3日、コートでは汗ばむような気温となっています。花粉が飛び出して、この季節には沖縄で生活したいという方もいらっしゃるのでは。お察しします。
数回前のブログでPCが不調と申しましたが、Windows7のノートを買いました。
サクサクではありますが、ユーザーインターフェイスがだいぶ変わり、目下習熟中です。
がんばれ、TOYOTA!! がんばれ NIPPON!!