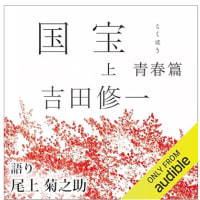多分に社会学の要素が入ってくる書籍の制作に煮詰まっている。
そんなときに、〝よりによって”

山崎方代の評伝にはまってしまった。
この歌人のことを少しでも知っている人なら
ダブルクォーテーションで区切らずにいられないほどの間の悪さに
共感してもらえると思うのですが……。
第二次大戦で視力をほとんど失い、
その後は終生、世捨て人のような暮らしをしていて、
歌を詠むも、どこの組織にも属さず、
ようやく世間に名前が知られてきた矢先、がんに冒されてしまう。
享年70。1985年没。
日本は高度経済成長を経て、バブル経済が始まったころ。
細かく見れば格差はあっても、日本全体が豊かになってきた時代だ。
そんなときに方代は
知人が自宅の庭先に建ててくれた4畳半ほどの小屋に住み、
気が向かないと1カ月も風呂に入らないような生活をしていて、
歯は一本もなく、
……と、この本には書かれている。
本の中のことだから、こんなでも人を惹きつけずにいられない
チャーミングなところがあった、という人柄に、惹かれる部分もあるけれど、
もし実際に本人が目の前にいたら、
ぜーったい近寄りたくない(スミマセン)と思う。
富とも名声とも、ついでに恋愛ともまったく無縁で
でも彼が詠む歌はのびのびと型にはまらず、かつ妙に共感をおぼえたり
核心をついているなあと感心したり。
なので、さぞ何か達観した、仙人のような人なのかしらと
この評伝を読む前は思っていたのだけど、
実はものすごく名誉を欲していて、愛情にも飢えていて、
それがために、やれ有名人と対談したとか、昔はもてたとか、
嘘ばかりついてしまう。
端的にいえばどう考えても、少なくとも当時の社会のシステムには
ひっかかりもしない(目が不自由だったのはお気の毒ですが)。
だからこそ尚更、
晩年になってしまうけれど歌集も出て、
故郷に碑も立って、
支援者もそれなりにいて、という実績に圧倒されてしまう。
この人は、本当に本当に、才能のあった方だったのではないだろうか。
いつまでも転んでゐるといつまでもそのまま転んで暮したくなる
------------------
おうおうにして評伝や歴史小説などを読んでいると、自分の知らない遠い昔の話と
錯覚してしまいそうだけれど、
1985年といえば、私はもう〝ばりばり”生きていた。
18歳、大学一年生だ。
そして1985年といえば、日航ジャンボ機墜落事故のあった年。
この本にもそのときのことが書かれていて、
既に死期が迫っていた方代が、病室で事故を知り
「そんなかに(犠牲者の中に)作家や詩人の名前はないの?」
間もなく校了する歌集の後記を書きなおすべきか、悩んでいる。
しかし方代にも、もう時間は残されていない。
1985年8月12日。私は大学近くに借りた部屋の中にいた。
入学したてで、遊ぶのが楽しくて、夏休みだったけれど故郷には帰らず、
一年生だったしまだ海外には出ず、バイトもしていなかったと思う。
小さな、14型だったか16型だったかのテレビで茫然と、映像を観ていた記憶だけ
残っている。
そのときの気持ちは幼稚園児のときやはり故郷で起こった
あさま山荘事件(機動隊が突入する前に、鉄の塊がアジトを破壊した場面)を
やはりテレビで観ていたときと同じような
「わけのわからなさ」だったような気がする。
遠い昔になりつつあるけれど、確かに生きていた時代。
この時代に、山崎方代も生きていたんだ、と思ったら、
何だか当時を確かめてみたくなって、
自分の大学時代の写真を探してみた。

85年の写真は手元になくて、こちらは86年。
下の写真は、ふいうちで撮られたのでしょう。
隣の男子は、卒業後NHKのアナになったS浦くん。クラスメートでした。

成人式を翌年に控え、髪がそこそこ長かったです。
服が……昭和すぎる!
海外を放浪していたときの写真も出てきたので、
続きは次回、アップしますね。