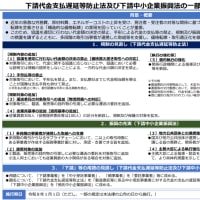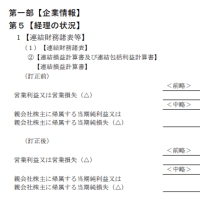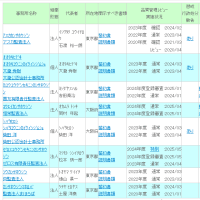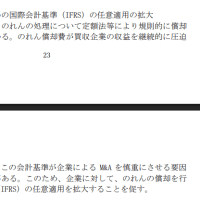訪問看護の最大手、過剰請求か 精神科「あやめ」が全社的に(共同通信配信)
「ファーストナース」という訪問看護事業者が、訪問回数を制度の上限である週3回にするよう全社的に指示していたという記事。
共同通信は証拠も入手しているようです。
「共同通信の取材に約10人の現・元社員が「3回は必要ない患者も多い」などと証言、過剰な診療報酬の請求に当たる可能性がある。社内のLINE(ライン)メッセージや内部資料も入手した。」
会社側は、利用者に訪問回数の増加を提案することはあるが、一律に指示などしていないと反論しているそうです。
記事でもふれているように、訪問看護を行った実績に基づいて、請求、売上計上していれば、架空請求・売上とまではいえないのかもしれませんが、正当な受注に基づくサービス提供でなければ、売上計上できないはずだという考え方もあるでしょう。
背景としては...
「同社はここ数年で急成長し、「あやめ」という名称で東北から中国地方まで18都県で約240カ所の訪問看護ステーションを運営。利用者は主に精神障害者で、1万人前後いるとみられる。」
精神科の「闇」を告白した医師が、差別の歴史を振り返った 世界と逆行する日本「昔も今も違憲状態」(東京新聞)
「いまだ続く虐待問題や安易な身体拘束、医師や看護師の配置基準が少ない精神科特例。日本の病床数の多さは、ナチスの精神疾患の患者殺害、旧ソ連の反体制運動家収容と並び、世界の三大精神科アビューズ(乱用)と語られる。
岡田さんは言う。「差別医療が徹底され、昔も今も違憲状態だ」とし、「精神科の病院運営はほとんどが民間任せ。民間の病院を擁護するつもりは全くないが、国は責任を持たなかった。その不作為を認めるところから全てが始まる」。」
こういう状況だとしたら、訪問看護自体はよいことだとは思うのですが...
他の会社の事例も取り上げています。
↓
「患者よりカネもうけ」ナースが見た訪問看護会社のあきれた実態 障害者を「食い物」に(Yahoo)(共同通信配信)
「女性は以前、障害者向けグループホームの大手運営会社「恵」(東京)が運営する訪問看護ステーションで働いていた。同社は主に精神、知的障害者を対象に各地で「ふわふわ」といった名前のホームを約100カ所運営。障害福祉や医療の報酬を不正に受け取っていた疑いや、食材費の過大徴収などが明らかになり、問題になっている会社だ。
女性や複数の元社員らによると、こんな手法が組織的に行われていたという。
(1)「健康管理」などの名目で、ホームの入居者に週3回の訪問看護をほぼ一律に契約させる
(2)1人5分程度の短時間で多数の入居者を巡回
(3)早朝・夜間に訪問したように虚偽の記録を作り、診療報酬の加算を不正請求する
女性は「障害者を食い物にしている」と我慢できず、精神科の訪問看護を手がける別の会社に転職。ところが、再びがくぜんとした。
ここでも、自社のグループホーム入居者にほぼ一律に週3回の訪問看護を、必要ない人まで利用させていたからだ。「こっちの会社は、高い報酬を取るため複数人での訪問にする手法でした」。失望し、1カ月ほどで辞めた。」
制度の説明や業界の現状。
「65歳以上の高齢者は、末期がんや難病などを除き、基本的に介護保険からお金が出る。医療的ケア児や現役世代は医療保険。精神科の訪問看護も医療保険が適用される。サービスを提供するのは主に訪問看護ステーションで、病院やクリニックもある。
訪問看護ステーションの参入ハードルは低い。医師などでなくても、法人を設立して看護師らを雇い、条件を満たせば事実上、誰でも開設できる。
高齢化などに伴い、利用者は年々増えていて、厚生労働省によると2023年現在、約122万人。そのうち医療保険の適用は約48万人で、主な傷病が「精神および行動の障害」という人が約21万人と半分近くを占める。10年間で7倍に増えた。
精神科の訪問看護ステーションは2022年までの5年間で倍増し、全国に約5300カ所。精神、知的障害者のケアには専門性が求められるが、事業者の中には「グループホームを巡回するだけ」「3年で年商8億円」などとうたい、広告でフランチャイズでの開業を促す例もある。」
専門家のコメント。
「訪問看護に詳しい国立看護大学校の萱間(かやま)真美学校長に話を聞くと、現状についてこう指摘した。
「訪問看護ステーションは、身体疾患のある人や高齢者を主な対象にするところと、精神科に特化したタイプで二極化している。精神、知的障害者の地域生活を支える上で精神科訪問看護は重要なサービスだが、一部の悪質な事業者では利用者を囲い込み、地域の関係機関と全く連携しないケースが見られる。それでは、長期入院で社会から隔離する従来の精神医療と同様、当事者は孤立してしまう」」