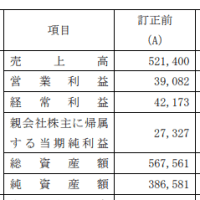公認会計士の監査法人離れ進む 形式的な作業に失望(記事冒頭のみ)
公認会計士登録者数は10年前と比べて38%も増えているのに、監査法人所属の会計士は7%増にすぎず、監査法人所属者比率は41%に下がってしまい、会計監査の担い手が不足しているという記事。
「財務諸表をチェックする会計監査の担い手不足が深刻になっている。監査法人で働く公認会計士の比率は10年で10ポイント下がった。上場企業数や監査業務量が増え続けるなか、やりがいに乏しい形式的な作業に失望し、スタートアップやコンサルティング企業に転身する動きが目立つ。資本市場の門番役を担う監査制度に、空洞化の危機が迫っている。」
数字は、先日、金融庁の公認会計士・監査審査会から公表されたモニタリング・レポートから取ってきているのでしょう。同レポートによれば、大手監査法人だけをみると、直近5年間で、増えるどころか、少し減っているぐらいです。
記事では、その背景などを述べています。
・会計士は、流動性の高い職種であり、監査法人でも入所10年程度で別の道を歩むのが典型だったが、近年は離職するのが若手スタッフからパートナーまで、全職階に広がっている。
・監査法人を退職した会計士約10人に聞いたところ、「監査基準委員会報告書」(カンキホウ)への不満がある。「形式的で膨大な作業が積み上がっている」
・監査法人も、規制当局から責められないよう、細かい文書化を会計士に求めており、形式化に拍車をかけている。
・全体の業務が増えているのに、若手スタッフの残業時間上限が管理されるため、マネジャーやシニアスタッフなど上の階層にしわ寄せが来て、全体の疲弊が進んでいる。
・監査法人以外の活躍のフィールドも拡がっており、一般企業の待遇も遜色なくなっている。
・監査報酬の時間あたり単価は、ここ10年ほど、1万2000円弱でいっこうに伸びない。
・新日本監査法人理事長コメント。値上げのためには「付加価値のある知見を提供する必要がある」
といった内容です。
結論としては、監査制度は「すでに崩壊の瀬戸際にあるのかもしれない」とのことです。
カンキホウに八つ当たりしても無駄でしょう。会計士協会のカンキホウは、国際監査基準を、ほぼそのまま翻訳しているだけのものです。それを、日本独自のものにしてしまうと、海外監査人と話が通じなくなって、かえって非効率になるでしょう。監査法人が提携しているネットワークファームも、国際監査基準をベースにしたマニュアルの遵守を求めています。また、会計士協会に、独自の監査基準を制定するだけのリソースはないでしょう。むしろ、不正対応監査基準のように、国際監査基準より、微妙にはみ出ている部分を整理する方が、よいでしょう。
監査法人は、10年ぐらいは務めてほしいのかもしれませんが、10年たった後の雇用を保障しているわけでもなく、厳しい選別が待っているのでしょうから、職員側が、先廻りして、新しい道を探るのは、止められないでしょう。大量採用大量離職という流動性の高さは、各監査法人が加盟している国際的ネットワークの傾向でもあります。監査法人からいったん離れた人を、再度、来てもらうなどしたほうがよいでしょう。活躍のフィールドが拡がっていること自体は、業界にとって、すばらしいことです。
会計監査自体が付加価値なのですから、それ以上の付加価値は、基本的には不要でしょう。新日本理事長のコメントは、会計監査に付加価値がないといっているようなものです。もちろん、監査の過程で、会社とコミュニケーションを十分に取り、必要な情報を提供することなどは必要でしょう。
監査報酬の値上げは、相手のあることですから、急に改善することは難しそうです。徐々に採算の合わない契約からは離脱していくという方法しかないでしょう。キーエンスの監査報酬を10倍とはいいませんが、5倍ぐらいにして1億円台に乗せることができれば、それだけで業界全体にプラスかもしれません。
公認会計士の監査法人離れ進む 形式的な作業に失望https://t.co/9blY0354ts pic.twitter.com/33XmhsFcqY
— 日本経済新聞 電子版(日経電子版) (@nikkei) July 24, 2023