蓮沼の歴史をさかのぼること11世紀後半、寿永二年(1183年)
村史にはこう記されている。
11世紀後半、上総の権介であった上総広常は、同時に上総・千葉氏系の武士団の棟梁であった。
古代末期の開発領主でもある広常は、上総・下総の一帯を担っていた。
本拠地は現在の御宿あたりと推定される。
しかし広常の不遜な言動が源頼朝の誤解を招き、寿永二年(1183年)12月鎌倉で誅殺(罪をとがめて殺すこと)された。
※後に頼朝は広常が謀反(裏切り)の気持ちがなく頼朝に忠誠を誓っていた事を知り、自分が広常を殺めてしまった事を非常に後悔する。
推測だが千葉の浜方面はとかく威勢が良く、口調も強くなる場面がある。広常も御宿を拠点としていた。言葉は荒いが気持ちは真っ直ぐだったのではなかろうか?と
頼朝の誤解を招いた、というのも広常の豪快さに加え、不器用さもあったのではないかと思われる。
蓮沼の伝承によると、鎌倉から大軍が来て一夜のうちに広常の城郭は落城し氏族、郎党が討ち死に。とある
さらに広常の孫「光宗」が9才の時、28人の武士を伴に連れて、武射郡へ(現東金市辺り)遁(のが)れた。と伝えられる。
その後、海辺近くの現在の(蓮沼)に隠れ住み、やがて成長した広常の孫「光宗」は「石橋丹後の守」(いしばしたんごのかみ)と称したとされる。
さらに一緒に移り住んだ28人の武士はそれぞれ低湿地の開墾につとめ、やがて(1238年~)一村を形成するに至ったとされる。
蓮沼の開発が12世紀以降、上総・千葉氏に連なる人々によって進められた事を物語り、さらに戦国末期、隠遁武士団の影響力を垣間見ることができる。
そして蓮沼には神社仏閣が面積の割に数多く現存しているが、それは何故か?
次回は、その謎について書き記したい。
村史にはこう記されている。
11世紀後半、上総の権介であった上総広常は、同時に上総・千葉氏系の武士団の棟梁であった。
古代末期の開発領主でもある広常は、上総・下総の一帯を担っていた。
本拠地は現在の御宿あたりと推定される。
しかし広常の不遜な言動が源頼朝の誤解を招き、寿永二年(1183年)12月鎌倉で誅殺(罪をとがめて殺すこと)された。
※後に頼朝は広常が謀反(裏切り)の気持ちがなく頼朝に忠誠を誓っていた事を知り、自分が広常を殺めてしまった事を非常に後悔する。
推測だが千葉の浜方面はとかく威勢が良く、口調も強くなる場面がある。広常も御宿を拠点としていた。言葉は荒いが気持ちは真っ直ぐだったのではなかろうか?と
頼朝の誤解を招いた、というのも広常の豪快さに加え、不器用さもあったのではないかと思われる。
蓮沼の伝承によると、鎌倉から大軍が来て一夜のうちに広常の城郭は落城し氏族、郎党が討ち死に。とある
さらに広常の孫「光宗」が9才の時、28人の武士を伴に連れて、武射郡へ(現東金市辺り)遁(のが)れた。と伝えられる。
その後、海辺近くの現在の(蓮沼)に隠れ住み、やがて成長した広常の孫「光宗」は「石橋丹後の守」(いしばしたんごのかみ)と称したとされる。
さらに一緒に移り住んだ28人の武士はそれぞれ低湿地の開墾につとめ、やがて(1238年~)一村を形成するに至ったとされる。
蓮沼の開発が12世紀以降、上総・千葉氏に連なる人々によって進められた事を物語り、さらに戦国末期、隠遁武士団の影響力を垣間見ることができる。
そして蓮沼には神社仏閣が面積の割に数多く現存しているが、それは何故か?
次回は、その謎について書き記したい。











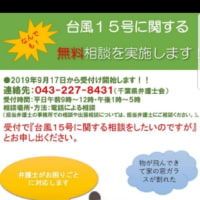
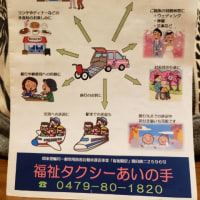

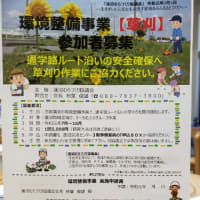
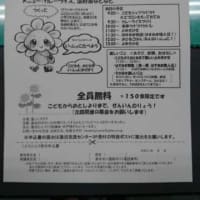
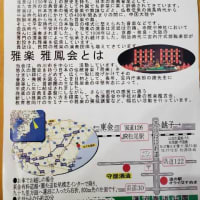
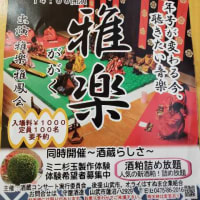







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます