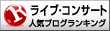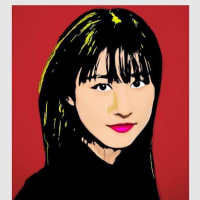次に記するのは、ほぼnuanceを知らない身勝手な立場からのテキスト。終演後は観賞したnuanceファンたちの感嘆の声がSNS上などに溢れていたが、そういった嬉々とした感情を共有するためにここに訪れたなら、今すぐにこのページから離れた方が賢明だ。ファンにとっては腹立たしく思う表現も出てくるかもしれない。nuanceの過去も現在もほぼ知らない一見からの刹那の感想に、なにも快い気分を害することはないだろう。それを承知した上で読む判断をしてもらえればと思う。
◇◇◇
おそらく日常が日常足り得ていたら観ることはなかったであろう、横浜発のローカル・アイドル、nuance(ヌュアンス)のワンマンツアーの最終公演〈nuance ONEMAN TOUR "OSU" TOUR FINAL「PEONY」〉のステージ。新型コロナウイルス感染症の影響により、スポーツやエンタテインメント、教育現場、職場でのテレワーク推奨などクラスター(感染者集団)の拡大防止策としての自粛ムードが蔓延るなか、エンタテインメント不足にもどかしさを感じていたこともある。とはいえ、アイドルというシーンへ取り立てて思い入れがある訳ではないし(かといって避けている訳でもない)、これまではnuanceというグループに感心を寄せるだけの“引っ掛かり”は芽生えなかった。以前、一度だけCDショップを訪れた際に偶然彼女らのインストアライヴに行き当たることがあったが、音楽的趣向を考えても、興味を示すほどの刺激が残らなかったというのが正直なところ。
ところが、ヒップホップやアーティスティックなカルチャーへの慧眼を持つnuanceのファンを公言する知人からの「(特別な印象を抱いていないだろうことを承知の上で)パブリックイメージを更新する気概と意欲を提示した昨年のワンマンを更新する可能性があるステージを観てもらいたい」という願いにも近い誘いに、天邪鬼な性分も幸い(災い?)して、「そこまで言うなら観てやろうじゃないか」という色気が薄っすらと沸いてきた。
ただ、実際に何も楽曲を聴かずには判断することは出来ない。取っ掛かりに『ongen』というミニ・アルバムを聴いてみたのだが、第一印象はAKB48や乃木坂46ほか“坂道”系にも似た歌謡ポップス路線のそれで、あまり琴線に触れるものではなかった。むしろ、こういった楽曲がほとんどを占めるとしたら「正直辛いかも」という思いが頭をもたげるなかで、知人からも「“乃木坂の下位互換”的にとらえられるのは重々理解します」との返答ももらった。
だが、その後に気まぐれに楽曲を数曲聴き進めてみると、リリカルスクール風なラップ・ヴァースで展開するエレクトロ要素も組み込んだジャジィ・ヒップホップ調の「ハーバームーン」や、セリフ&ナレーション導入や畳み掛けるクラップが走るオルタナティヴなダンス・チューン「タイムマジックロンリー」あたりが思いのほか耳を惹いたこともあり、まだ未知なる楽曲への期待も含めて、ギリギリのところでO-EASTへ向かう決断をした……というのが、nuanceのステージへ足を運ぶまでの顛末となる。
TSUTAYA O-EASTのキャパシティからするとお世辞にも大勢の観客で膨れ上がったという集客ではなかったが、それでもこの自粛ムードに足並みを揃えさせられているような感覚に陥る状況において、4名の一挙手一投足を目に脳裏に身体に焼き付けようという熱心なファンたちがフロアを埋めていく。ライヴ中止で莫大な損益を被ることからの回避、という経済的事情での開催に批判の声がないといったら嘘になるが、入場前の体温チェックやアルコール消毒、スタッフのマスク、手袋着用での対応、無料でペットボトル水の提供、開演中の場内換気など、可能な限りの対策を行なった。また、ライヴはYouTubeで無料配信され、残念ながら会場に来られなかった人たちへの配慮も整えていた。それだけ、このファイナル公演への思いが強かったのだろう。開演時刻の19時に時計の針が触れると、これまでに身に着けてきたドレスが飾られた4体のボディ(トルソー、胴体マネキン)がディスプレイされたステージと洋服の仕立て部屋を模したと思しきサイドステージに、それぞれ男女の仕立て人が現れ、ツアーファイナルの舞台の幕が上がった。

◇◇◇
混沌からのメタモルフォーゼを示した、4人の少女たちが紡ぐ感涙のソワレ。
“まってる”……nuanceが告知などに用いるキャッチフレーズと言ってもいいだろうか。その言葉に期待を寄せながらフロアを埋め尽くすファンたちの前で行なわれていたかもしれないステージも、コロナウィルス感染拡大の影響を鑑みた世間の自粛ムードの煽りを受けて、当初思い描いていたような集客はままならなかったのだろう。それでもさまざまな影響が懸念されるなか、nuanceの集大成の結晶となるべきステージを潰してはいけないという運営サイドとファンの思いが合致したのか、踊るには程よいスペースを保ちながらメインフロアが埋まっていく。メインステージには、バンドセットの前に4体のボディが置かれ、おそらくnuanceがこれまで身に着けてきただろう衣装がディスプレイされている。それらを眺め、満足げな顔をしながら、カウンター(手持ち型数取器)でフロアに集う観客の数を集計する仕立て屋の男。上手のサイドステージにはその衣装を仕立てた小部屋があり、衣装に囲まれながら、ミシンで裁縫をしている仕立て屋の女。
何の前触れもなく、期待を寄せる熱気に満ちたフロアを尻目に始まったのは、峰ゆとり、椙山さと美という劇団鹿殺しの美男・美女が演じる寸劇だ。肩にメジャーを掛けながら4体のボディのチェックを怠らない峰とサイドステージで裁縫に専念する椙山とが、nuanceのステージ衣装を仕立てるなかで掛け合いをしていく。ミシンの音が響くなかフロアに目を落とすと、既に観客で埋められた光景に慌てる二人。丁々発止の勢いでのコミカルな掛け合いが、4人の登場を待ち侘びるファンたちの期待と焦れた感情をヒートアップさせていく。その熱気が伝染したか、ステージ前面を覆う幕の下手側の一部が引っ掛かってしまい、幕が全部降りないというハプニングも。それでもさすがは舞台慣れしている役者ということか。そんなハプニングも観客の興奮を高める“アイテム”に変えてしまう(慌てふためいた椙山の口調がエドはるみを思わせたりも)。彼らはnuanceのステージへと導く案内人ならぬ“アヌュ内人”。ドタバタな寸劇を展開した最後に告げたのは、当公演のテーマと思われる言葉たちだ。
最終公演タイトルにある“PEONY”(ピオニー)とは牡丹のこと(nuanceの5thミニ・アルバム『botän』にもテクノポップ調の「ピオニー」という楽曲が収録されている)。洋服を紡いでくれた人たちの匂いを受け取り背負うことで、真の意味での感謝や恥じらいを知り、王者の風格が生まれると説くが、この“恥じらい”“王者のような風格”“富貴”“高貴”というのは牡丹の花言葉でもある。また、牡丹をミニ・アルバムにも冠している『botän』=ボタンにかけながら、少女たちとファンたちとの掛け違えていた“ボタン”(釦)がしっかりとハマってリンクしていくというダブルミーニングを用いて、これから始まるステージは“街を飛び出して転々としながら、新しい街や愛する人たちと出会いや別れを繰り返すことで紡がれた少女たちが、この先どのような人生を紡いでいくのかを探す物語”なのだと提示していく。

“ピオニー”という言葉から辿り着くのは、その名の由来。ギリシャ神話に登場する誰もが振り返る美貌の持ち主“妖精パエオニア”だ。同じくギリシャ神話に登場する詩歌・医術・芸術を司る太陽神アポロン(アポロ)が寵愛し、それに機嫌を損ねた誇り高き美神アフロディーテがアポロンをボタンの花に変えてしまった……という神話でも知られている。そのピオニー(牡丹)が持つ“思いやり、恥じらい、はにかみ、人見知り、風格、富貴、壮麗”などの花言葉に相応しい少女たちの物語が間近に迫っているという煽りも含めた寸劇なのだろうが、4人の登場まで20分強。初見の者にとってはやや冗長に感じたし、そこまで大仰なコンセプトに見合うものなのか、という疑念も沸いてきた。加えて、nuanceを登場させるギリギリまで集客を粘る、時間稼ぎの作戦なのかということも。
だが、おそらくnuanceというグループは、ツアーや作品において連続性を持った成育的ストーリーを展開してきたのだろう。その延長線上での集大成が当公演ということであれば、尺の長い寸劇を導入してきたことにも理解は出来る。一方で、そういった解釈をしづらい初見の者やファン歴が浅い者たちにとって、本編へすんなりと感情移入することの妨げにも思えてしまうという可能性は否定出来ない。俳優二人による寸劇とnuanceの歌唱パートに成熟の差が見られてしまえば、なおさらだ。
二人の“案内人(アニュ内人)”が舞台から退くと、ステージ前方を幕で覆われたまま歌唱パートがスタート。幕にオレンジ系のライトで細い楕円の模様が映し出される向こう側で、薄っすらと透けて見える4人が「wish」を歌い始める。ステージ前面を遮って張られた幕には、エンドロール風にキャスト、バンド、制作陣等が映し出され、次第に青白いライトが暗転してツアータイトル“PEONY”とうロゴが浮かび上がる。歓声とともに幕が落ちると、それぞれが微妙にデザインの異なるバーガンディのワンピースドレスを纏った4人が姿を現した。

ニュアンスではなく“ヌュアンス”。あどけなさと意志の強さを併せ持つマスコット役のようなポニーテール姿の(声優アーティストっぽさもある)misaki、パワフルな歌声で4人の歌唱の軸となる金髪ショートの(リトグリにいそうな感じの)わか、一心不乱に没頭するパフォーマンスで髪を掻き乱す姿が強く印象に残る(欅坂の平手あたりにも重なる?)みお、おっとりとしたお嬢さま風の容姿ながらどこかとぼけた感のある(横浜・石川町あたりのイメージに一番近そうな)巻きロングの珠理。“ヌュアンス”という響きや彼女らが纏うバーガンディのワンピースドレス姿からは、“ふんわり”“ゆるやか”といった印象を受ける。
その4人をサウンド面でバックアップするのが、9人のバンドメンバー。左からドラムのU、ベースの吉川衛、nuanceのサウンドプロデューサーでもあるギターの佐藤嘉風、キーボードの斎藤渉、パーカッションとトランペットの西岡ヒデロー、シンセの及川創介、ギターのしんいちろう、ベースの辻怜次、ドラムの鈴木敬という、パーカッションの西岡を境に左右対称風に2組のバンドが並ぶという変則編成だ。
彼女らの青春譚のような希望に満ちた作風による「wish」を終えるとガラリ一変。ラテン・ジャズ風のモダニズムが走る「tomodachi」を皮切りに、寸劇と「wish」で充溢させていた躍動の“タメ”を発破するように、ステージの景色には瞬時にさまざまな変化が伴っていく。“オイ!オイ!”とフロアを煽る叫びとジャズロック調のミスマッチが不穏な鼓動を速める「bye bye」、等間隔に並べられた椅子に立ってのゆらゆらしたダンスから忙しなく動き回りながら“回れ、回れ!”と歌う「cosmo」、流麗で軽快な鍵盤、哀愁を高めるトランペットなどが原曲とは異なるアダルトな彩色を施す「ハーバームーン」、「ハーバームーン」では抑え気味だったエレクトロ性を及川のシンセで強調しながらドラマティックなダンスとともに跳ねる「ヒューマノイズヒューマノイド」、フレアスカートの裾を持って揺れる振りでスイッチが入る“予兆”を匂わせつつ、性急で快活な鍵盤が止めどなく流れるこれまでのラテン・ジャズ・マナーを踏襲すると思いきや、ロック・アレンジへと転調してワイルドなスタンドマイク使いを見せる「which's wich」まで、一気呵成に攻め立てる。“スイッチ上げて”“叫び足りない”と去来する胸の内を吐露しながらギアを高め、アウトロの“消して!”の叫びと同時に暗転。集大成のステージに挑む興奮を、飾り気なくぶつけるようなステージを繰り広げていく。 
ここで、アニュ内人の二人が一脚ずつ運んだ椅子にメンバーを一人ずつ腰掛けて始まったのは、スクリーンに映し出された自撮り動画による独白のシーン。「臆病で自分を信じるのが苦手、そんな自分を変えて、信じられる人間になりたい」と語るmisaki、「誰かに嫌われるくらいなら自分の思いを我慢する方が楽だと自身を表現することから逃げてきたけれど、言葉とか行動で感情を表現出来るようになって、いつかそれが伝わった誰かの光になりたい」というわか、「挑戦する前に限界を決めて誰かに頼ってきたけれど、ステージに立つことで誰かの力になれるような、私が誰かを救えるような人間になりたい」と呟くみお、「個性も得意なこともない、失敗が怖くて挑戦することが苦手な自分が好きじゃない。失敗してもいいから挑戦して、自信をつけて自分を好きになりたい」という思いを話す珠理。4者4様の心境を語るシリアスなシーンは、これまでの彼女らを観てきたファンにとっても思いが高まる光景なのだろうが、そういった背景を知らずにいる自分にとってはやや唐突な感じも。ノンストップで畳み掛けてきた序盤を終えて、流れを転調させる意図もあるのだろうが、不意に喉元に拳を突き付けられる感じもして、ステージ構成という意味でもやや面を食らってしまった。
ただ、ファンにとってはこの演出が4人との共感濃度を高めたのか、ポップでラヴリーな音色の「Love chocolate?」からリスタートした後は、モノトーンのように淡々とした冷温の“tell me~”のリフレインが文字通りの切なさを漂わせる「セツナシンドローム」で、クラップとともにヴォルテージが上がり始める。青春歌謡曲風の「ナナイロナミダ」を挟んで、ファンキーなエレクトロ・ポップを配しながらもこれまでの辛苦が晴れ舞台で解放されるようなカタルシスをも感じた「sanzan」、本ツアーのタイトルにも冠した美しさと儚さを同居させたような表裏一体を表出した(Perfume「ワンルーム・ディスコ」っぽさも窺える)「ピオニー」と連なるなかで、フロアのテンションが鮮明に高ぶるのを実感。椅子に立って踊るアニュ内人の二人を従えて複雑変化な尖ったリズムで“愛のパワーです!”とコミカル&マジカルな詞世界を展開するマスロック調「I Know Power」、misakiがライオン、珠理がシロクマ、わかがキリン、みおがペンギンを名乗ってnuanceを表現するダンスロック「ミライサーカス」、さらに加速度を高めるようにダンスも激しさを増し、コール&レスポンスも駆使する「タイムマジックロンリー」と畳に畳み掛ける。鍵盤のアルペジオが耳を惹く、ピュアネスが煌めく「雨粒」でスローダウンするものの、ステージとフロアを繋ぐ熱気は冷めやらず。しっとりとした雰囲気の原曲の影が徐々にステージを這うなかで、内側に向かい合った4脚の椅子に花束を持って立って見つめ合う姿でブラックアウトした「tsukeru」は、跳ねる息遣いが残りながらも彼女らの清廉さを垣間見せる演出となった。
バンドメンバー紹介を経ての本編ラストは、misakiが「3年が経って、nuanceを好きでいてくれる皆、nuanceに関係する皆、メンバー全員が幸せであるという私の夢は(この光景を見ると)叶ったんじゃないかと思う」と告げてからの「きっといつか」。持っていた花をフロアに投げ込んで喜びを表現しつつ、ポジティヴでラヴリーな音色が響くなかで、微笑みが飛び交うエンディングに。加えて、6月にミニ・アルバム『brownie』のリリース、さらにメンバーも初めて知ることとなる同作のリリースワンマンツアー〈botawnie〉の開催決定が告知されるというサプライズ。メンバーの歓喜に沸く姿と彼女らを後押ししたいというファンの気持ちが渦巻くなかで一旦はステージアウトとなるも、フロアに宿る感情の蠢きは止められず。クラップとアンコールが響きわたるフロアに、当初はやる予定がなかったが、急遽4人とバンドメンバーが再び戻ってのアンコールへ。この日の冒頭で幕越しに演じた「wish」を、今度は幕という遮りを外したなかでパフォーマンス。“願い”を意味する「wish」を冒頭と結尾にパッケージして、高ぶるギターソロと清らかな鍵盤が映えるなかで集大成を演じ切って、熱い想いを届けていた。

ファンにとっては大団円なのだろう。それはステージを見つめる表情からもつぶさに窺えた。されど、個人的には、本音を言えば、首をやや傾げながらの観賞でもあった。その最大の要因はやはり歌唱力。もちろん歌唱の巧拙が全てではないものの、楽曲の質をストレートに伝えられる最たるところで不安定さを感じるのはストレスになる。個々の質を考え、ハーモニーでフォローアップしているという風でもないというのは、歌って踊るライヴステージでの歌唱とはいえ、耳を納得させるものではなかった。ダンスにおいても、フォーメーションやテクニカルな動きを用いる訳でもなく、統制がとれていたというほどまでは至らず。特にノンストップで駆け抜けていった序盤の終わり頃や、中盤の「sanzan」あたりでは、疲労感も重なってか、歌唱とともに動きがバラバラな印象もあった。
さらには、バンドセット。2組を揃えたスペシャルな編成は演者のスキルもあって非常に安定した音を供給していたが、それが楽曲性に特出すべきなにかを生み出していたかといえば、大きく首を縦に振れなかった。9名を揃え、音圧という意味では多大に貢献していたが、nuanceのパフォーマンスとのシンクロ性やバランスという意味では、人数的にやや過剰な気も。ホーンセクションやストリングスチームを擁した編成やブラスが乱れ飛ぶビッグバンド編成などといったスタイルでガラリとリアレンジするといったような、比較的大所帯にありがちなポピュラーな編成である必要性はないが、2バンド分だからこそ生み出される何かを感じられないと、その効果も薄かったのではという思いが頭の片隅からずっと離れず。西岡のトランペットや及川のシンセなどのアレンジには面白さも散見されたが、その他はあまり印象に残らず。もちろんそれは個々の巧拙などではなくて、全体的な音鳴りというバランスの意味でだが。

実はそんな思いが終始頭をもたげていたのだが、だからといって気持ちが乗れずにいたということもなかった。その不思議な感覚はどこからくるのか分からないまま終幕を迎えたのだが、振り返ってみるうちに頭を過ぎってきたのは、nuanceという良くも悪くも劇場風なストーリーとともに成長している彼女らの特性にあるのかもしれないということ。冗長に思えた冒頭の寸劇はじめ、大仰にも思えたバンドセットも、不揃いにも見える4人の振付や独創的なパフォーマンスもしかり。ステージアウトした後も座っていた椅子にスポットライト当たったままという演出には演劇っぽさも醸し出しているようだ。美しくて繊細、若さ特有の奔放と不安がないまぜになった“切なさ”を湛えたステージングには、若き乙女のピュアネスとその裏で蠢く欲との狭間に揺れる心を投影したような瞬間も。
これを音楽ライヴと見るのではなく、戯曲やオペラに寄せたシアトリカルな劇場風演出と捉えれば、物語へといざなうコンシェルジュとしてのキャストを配しての序幕、高い天井までも幅広く響かせるための2組分の演奏陣というのもそれなりに腑に落ちる。歌唱についての評価は変わらないが、一見不揃いに見えるパフォーマンスも、フォーメーションのような均衡や統一性は失われるものの、キャラクターの長所を活かすことを重視することでそれぞれの個性を発露させた……というのは解釈が過ぎるだろうか。アイドルらしくないと言えば語弊があるかもしれないが、ライヴという観念以上に人間としての成長の表現の場としてステージを捉えていたゆえ、劇場型のパフォーマンスに拘っていたとしたらどうだろう。緻密でテクニカルなダンススキル以上に、自己から発せられるさまざまな情感を重視したいという思いがあったのか、真意は知るところではないが、確かに統一感はなかったものの、それぞれが個々の色をもって活力に溢れたパフォーマンスをしていたのを目にしたのも事実。躍動する生命力に焦点を当てていたことが、前述の不思議な感覚に繋がっていたのではと問われたら、あながち否定は出来ない。
ここまで4人のストーリーに寄り添ってきたファンたちといわゆる一見の自分とでは、視点も感傷の度合いも大きく異なる。ステージを終え、歓喜や感涙、満ち足りたという感覚は、残念ながら持ち得ることはなかった。しかしながら、当初思い描いていたとは異なる、個性的で有機的な集合体という認識を感じ取ることも出来た。おそらく次のツアーでは、今回のコロナウィルスの影響で埋められなかったスペースを埋めるべく、これまで届かなかった領域へと手を伸ばし、掴み取れるかという試金石になるのだろう。歌唱面を含めてまだまだ課題は多いが、好奇をそそるような資質も見え隠れしている。その資質をどのように発芽させられるか、その伸びしろにも注目だ。
夜の渋谷の一角で繰り広げられた、ハプニングもあった不完全なソワレ。夜がさらに更ける頃合いに幕は閉じたが、次なるステージへのカウントダウンは刻まれているようだ。nuanceの語源は仏語の“陰”を意味するが、その陰が少しずつ顔を見せ始めれば……より微妙な色合いの差を生み出せたら、興味を抱かせる驚きや深化したオリジナリティをもたらすことにも繋がるはず。そのためにリスナーや観客にいかなるテクスチャ―、触れ心地をもたらしてくれるのか。その精度や着想が躍進へのカギになりそうな気がする。

◇◇◇
<SET LIST>
00 INTRODUCTION ~ skit by guides named“anunainin”~
01 wish (*o)
02 tomodachi (*t)
03 byebye (*g)
04 cosmo (*t)
05 ハーバームーン (*b)
06 ヒューマノイズヒューマノイド (*t)
07 Which's Witch (*b)
09 Love chocolate? (*g)
10 セツナシンドローム (*g)
11 ナナイロナミダ (*o)
12 sanzan (*o)
13 ピオニー (*b)
14 I Know Power (*b)
15 ミライサーカス (*m)
16 タイムマジックロンリー (*t)
17 雨粒 (*b)
18 tsukeru (*b)
19 BAND MEMBER INTRODUCTION&MC
20 きっといつか (*b)
<ENCORE>
21 wish (*o)
(*g): song from album“gachi choco!”
(*m): song from album“ミライサーカス”
(*o): song from album“ongen”
(*t): song from album“town”
(*b): song from album“botan”
<MEMBER>
nuance are:
misaki
わか
みお
珠理
band:
佐藤嘉風(g,cho)
斎藤渉(key,cho)
U(ds,cho)
吉川衛(b)
及川創介(syn)
鈴木敬(ds,cho / Bentham)
辻怜次(b,cho / Bentham)
しんいちろう(g)
西岡ヒデロー(perc,tp)
guest cast:
峰ゆとり(劇団鹿殺し)
椙山さと美(劇団鹿殺し)
◇◇◇