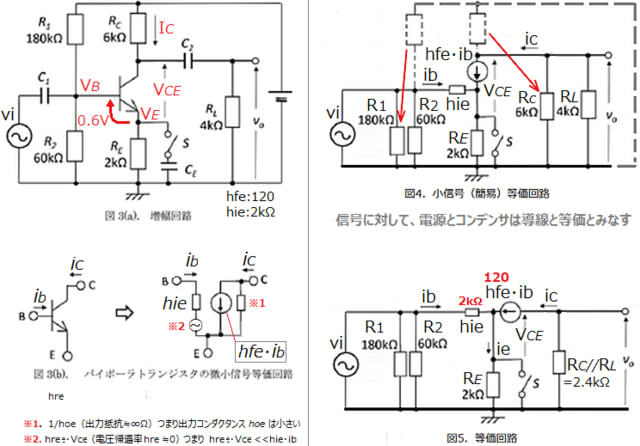知恵袋:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12232175392
(問い).各枝路の電流I1、I2、I3を求めよ!

答え:I1=0.5A、 I1=-0.5A、 I3=0A
解説:
1.ミルマンの定理:
「ミルマンの定理」より、ab間の電圧Vabは、
Vab = Io×Ro …(オームの法則)
= Io×{1/(1/ Ro)}
= Io/(1/Ro)
= Io/Go …(ミルマンの定理)
= (9V/2Ω +6V/4Ω +8V/3Ω) / (1/2Ω+1/4Ω+1/3Ω)
= {(54V+18V+32V) / 12Ω} / {(6+3+4) / 12Ω}
= (104V / 12Ω) / (13 / 12Ω)
= 104V/13
= 8[V]…(b点を基準0Vとしてa点が電位8Vと云う事です)
ここで、
上路よりVab=9V−(2Ω×I1)、この式よりI1を求めると
∴ I1 =(9V−Vab)/2Ω =(9−8)/2 =0.5[A] …(答え)
中路よりVab = 6V−(4Ω×I2)、この式よりI2を求めると
∴ I2 =(6V−Vab)/4Ω =(6−8)/4 =−0.5[A] …(答え)
下路よりVab = 8V−(3Ω×I3)、この式よりI3を求めると
∴ I3 =(8V−Vab)/3Ω =(8−8)/3 =0[A] …(答え)
2.キルヒホッフの法則(枝路電流法):
aにおいて第一法則より、I1 = I2+I3 = 0 …①
閉路(Ⅰ)において第二法則より、9−6 = 2I1−4I2 …②
閉路(Ⅱ)において第二法則より、6−8 = 4I2−3I3 …③
①よりI2 = −I1−I2を②,③に代入・整理
3 = 2I1−4(−I1−I3) = 6I1+4I3 …②’
-2 = 4(−I1−I3)−3I3 = −4I1−7I3 …③’
※.ここで網目電流法を使って、(ループ電流i1=I1)、(ループ電流i3=I3)とすると②,③を略して、いきなり②’,③’を立てる事ができるので時間短縮できるので、網目電流法の方が便利だと思います。
②’,③’よりI3を消去して、I1を求めるため
②’×7より、 21 = 42I1+28I3 …②”
③’×4より、−8 = −16I1−28I3 …③”
②”+③”より、13=26I1
∴ I1 = 13/26 = 0.5[A] …④(答え)
④を②に代入してI2を求める
3=(2×0.5)−4I2
∴ I2 = {(2×0.5)−3}/4 = −2/4 = −0.5[A] …⑤(答え)
④,⑤を①に代入してI3を求める
0.5−0.5 = I3 = 0
∴ I3 = 0[A] …(答え)
3.テブナンの定理:
要望があれば開示します
4.ノートンの定理:
要望があれば開示します
更新:2020/12/31