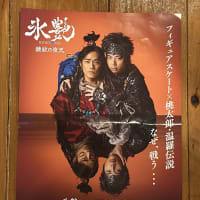ネットで見たら、9月に入ってからもの凄い混雑(180分待ち
 など)ということで、行くのやめようかとも思ったけれども、もう見られないかもと思って、旦那を説得して決行しました
など)ということで、行くのやめようかとも思ったけれども、もう見られないかもと思って、旦那を説得して決行しました (ちょっと大げさ?)
(ちょっと大げさ?)駐車場も混んでいるという情報だったので、早く着こうと、山口を6時半に出発したのですが、会場の前の8時半に着く予定が、高速道路が混んでいて、大宰府にある博物館に着いたのは10時頃になっていました。これは、駐車場に入れなくて、まずそこで待たされるなと悲しい気持ちになっていたら、駐車場はなんなくクリア
 。連休のため、返って皆さん違う観光地に分散したお陰かも。
。連休のため、返って皆さん違う観光地に分散したお陰かも。駐車場から気持ちのいい丘の道を登っていくと、やっぱり120分待ち
 の看板が・・・ チケット売り場も混むとあったので、前の日の夜にローソンで急遽買っておきましたよ。ということで、列の最後尾に付いてディズニーランド状態のくねくねに加わりました。予想された事態だったので、さっそく私も旦那も持参の文庫本を出して読みながら、徐々に前進すること約1時間で博物館の中に。中でさらに15分ほど並び、阿修羅展会場に入場しましたよ。(結局75分待ちでした) でも、本を読んでいたのと、気候がカラッとして気持ちがよかったので、あまり苦になりませんでした。ちなみに私はジェイン・オースティンの『ノーサンガー・アビー』の新訳、旦那は居眠り磐音シリーズを読んでいました。
の看板が・・・ チケット売り場も混むとあったので、前の日の夜にローソンで急遽買っておきましたよ。ということで、列の最後尾に付いてディズニーランド状態のくねくねに加わりました。予想された事態だったので、さっそく私も旦那も持参の文庫本を出して読みながら、徐々に前進すること約1時間で博物館の中に。中でさらに15分ほど並び、阿修羅展会場に入場しましたよ。(結局75分待ちでした) でも、本を読んでいたのと、気候がカラッとして気持ちがよかったので、あまり苦になりませんでした。ちなみに私はジェイン・オースティンの『ノーサンガー・アビー』の新訳、旦那は居眠り磐音シリーズを読んでいました。阿修羅展会場自体は、それほどの押し合い圧し合いという感じではなく、阿修羅像の周りには3から5周くらいの輪ができていましたが、誘導の声に従って左に15歩ずつずれながら、結構良く見ることができました
 。1300年も昔に造られたのねと思うと、やっぱり感動しましたね。お顔もなんとも言えないきりっとした良いお顔だし、側面のお顔はそれぞれ違った表情でこれも良かったですよ。お体は戦いの神としては、細身で少年のような体であるけれども、力はそれほどでもないが、しなやかな動きで戦いを制すという感じをうけました。(勝手な解釈ですが)
。1300年も昔に造られたのねと思うと、やっぱり感動しましたね。お顔もなんとも言えないきりっとした良いお顔だし、側面のお顔はそれぞれ違った表情でこれも良かったですよ。お体は戦いの神としては、細身で少年のような体であるけれども、力はそれほどでもないが、しなやかな動きで戦いを制すという感じをうけました。(勝手な解釈ですが)この阿修羅像を見て、光瀬 龍原作、萩尾望都の『百億の昼と千億の夜』の阿修羅を思いだしました。萩尾さんの阿修羅は女性として描かれていたけれども、やむにやまれぬ戦いを続ける阿修羅の哀しみを含んだ凛凛しさというようなものが、思いだされましたよ。スケールの大きい、哲学的な?インパクトのある漫画でした
 。
。阿修羅像以外にも、鳥の顔を持つ迦楼羅(かるら)、沙羯羅 (さから)、、乾闥婆(けんだつば)、などの 八部衆のなかの五像が展示されていて、それぞれなんともいえないいにしえの異形の少年像がよかったです。十大弟子像はこれらとは対照的に落ち着いた意志的な表情を浮かべていました。
とにかく、阿修羅展は1300年という時を経てきた阿修羅像をはじめとする八部衆の、後世の仏像にない何かが、見るものを感動させるのではないかな。その何かとは、ヒンズーの神々からの影響によると思われる異形の神、そして凛凛しい少年の姿で現されていること、それでいて自然な人間臭さのようなものも感じさせることなのではないかと、私は思いました。それぞれの人がそれぞれに感じればよいのでしょう。鎌倉時代に作られた四天王像も同時に見ることができて、その違いが良く解ります。四天王は四天王でその眼光するどく邪鬼を足にふんずけている様は、なかなかのものでした。
ということで、阿修羅展を堪能した後、隣接する大宰府天満宮に御参りし、娘の受験が成功した御礼を一応言って帰ってきました。(大宰府、防府、京都と様々な天満宮のお守りをいただいたので) お約束の梅が枝餅も食べ、一路山口へ。帰りの高速はいつもの様に空いていて、快適でした
 。
。