
長かった今年の雨の季節。
先週から、一気に夏の空になり先月仕込んだ梅を干さねばという日差しになってきました。
6月に梅を仕込んだ記事はこちらです。
先週あたまに、一気に夏空になってきて天気予報も晴れ続いていたので、ヨシ!と思い立ち梅をカメから出して干し始めちゃいました。
そのあと予報が外れてまさかの雨の2日になってしまいました…出した梅は、一度梅酢に戻すのがいいんだけど、カメも洗って片づけちゃったし、もう一度出し入れするのが大変だったので、だましだまし部屋で手拭いをかけてそのまま置いておきました。
先週半ばから晴れて来たので、ソレ!っとばかりに外に干して結局4日4晩出しっぱなしで今年もなんとか梅干し5キロが完成しました。
…ホッとしました。今年もなんとか無事に梅干しを仕上げることができました。
みなさんはどんな風に梅干し仕上げられていますか?
赤ジソと一緒に漬けこんで干して仕上げる方法もあるし、干した後に赤ジソを漬けこんで色をつけていく方法もあるし(赤ジソは特に干さなくても大丈夫です)、梅酢をつかわず仕上げてもいいし、梅酢にくぐらせたり、浸したりして仕上げる方法もありますよね。
赤ジソ(もみしそ)を入れるタイミングは何度も「ながくて風土」でも記載させてもらいましたが、意外に結構いつでもいいんですよね。
しまい方も、本当にお好みでという感じなんですよね。
梅干しをつくっているとなんとなく「本格的」なように思われることが多いかもしれませんが、一度実際に経験をされると、梅干しづくりってあっけなく簡単にこんなに「いいもの」がつくれてしまうことにお気づきになられると思います。
そして、こんな簡単にできるんだったら…と毎年続けてつくったり、量がだんだん増量されていったりしてゆくものなのかなと思います。
梅と塩と、時間とおひさまの光…たったこれだけでいいんだと、わたしははじめてつくったときにあっけない気持ちと感激が混ざったような気持ちになりました。
わたしは今年、畑の赤ジソの収穫期が梅雨明けに来たこともあり、梅を干し始めてからシソを収穫して、塩でもみこみ、梅酢に浸して「もみしそ」をつくりました。
なので梅干しが干せ上がってから、シソの色をつけていく手順となりました。

我が家の梅干しの仕上げです。今年はこんな風にしてみました。
一度写真の手前中央の白梅酢に梅をくぐらせ容器に入れて、その上にもみしそを散らして、梅、シソ、梅、シソ…と交互に重ねていき、最後に梅酢を浸して完了です。

赤ジソを加えた梅酢の色の比較です。
シソを入れることによってこんなにきれいな赤の色素がでます。
…実はわたしは赤ジソを入れた真っ赤な梅干しはあんまりつくらなくて、白梅干し(シソなし)をつくることが多いんです。
ただ、今年も自家栽培した赤ジソ(純赤ちりめん赤ジソという品種)がとってもいいできだったので、これは!と思って赤い梅干しにすることに決めました。
梅干しで使ってもまだまだ畑には赤ジソがあり、出荷するのがかなり大変なので(とても手間がかかります)自宅でシソジュースなどにして使えたらいいなあと思っています。
シソジュースの出がらしでは、シソの葉の佃煮も副産物として作れるので、よい保存食になってくれています。
過去のモミシソのつくり方を記載した記事はこちらです。
さてさて、もうひとつ。
いつも夏休みの畑にも公園にも出れないような猛暑日の昼下がりに「今こそ!」と思って作業するのが味噌の天地返しです。
わたしはかつて、天地返しの時期から新しい味噌を食べ始めていました。この時期まで手前味噌を切らしていて待ちわびて食べていたんです。早い時期の味噌は甘みが強くてこれはこれでとっても美味しいものなんですよね。
今は、1年分しっかり量をつくっているので、天地返しの時期にはまだ前年度に漬けた味噌が1カメ分残っているので、その必要がなくなりました。
最悪天地返しはやらなくても大丈夫ですが、こういう発酵食品は目をかけて気をかけることが肝要なのかなとも思っているので、1~2月に仕込んで半年間寝かせておいた味噌の様子を見る…ということも兼ねて、天地返しを行っています。
結局いつも滅多なことはないんだけど、もしも相当にひどいカビが来ていたり、味噌の間に空洞ができてカビが来ていたりしたらこの時点で気づいて対処することができます。

今年は周りに白いカビがふわっと来ていました。
スプーンでこそげるとほんの少量でホッとしました。
天地返しといってもざっくりとタライにカメの中身を全部出して、カメをキレイにしてまたザックリ戻して再び焼酎で表面を消毒してからラップでぴっちり覆っておく…という感じで大豆2キロ分の3つのカメがありますが、1時間もあればすっかり作業が終わってしまっています。

こちらは赤味噌!
愛知県に来て、今年はあぐりん村の講座のスタッフとしてお手伝いさせてもらい、地元のお母さん方と一緒に講座をさせてもらって覚えてきました。
愛知に来て赤味噌が大好きになりました。
今年から自家製の赤味噌食べれるなんてすごくウキウキします。
もう随分茶色くなっていますが、普通の米麹味噌の方はまだ黄金色で、豆麹を入れた方とは結構違うんだなーと思って見ていました。
…先週は味噌仕事と梅仕事と、夏休みの子どもたちの追われて毎日ドヤドヤしてましたが、日ごろ出たり入ったりしてゆっくり家で過ごせないので、子どもたちのことや家のことなどにいろいろと目が向いてきて、それはそれでいつもと違っていい部分もありますね。

さて!これからみっちょんに教えてもらったパンの復習がてら、1週間に一度くらいは子どもの昼食を兼ねてパンを焼けたらいいなあと思いさっそくやってみています。

粉が振ってあるのがジャムパンで、あとはチーズパンやチョコロールのちぎりパン、ちょっと素朴な感じのテーブルロールをつくりました。
5人家族で2回分の食事の戦力になってくれましたが、人さまにさしあげるにはもっともっと焼かなきゃ…!
質と量を上げて行けるように精進します!
あと、みっちょんみたいにロールパンの形成がうまくなりたいです!がんばります!

















 」となりました。
」となりました。

















































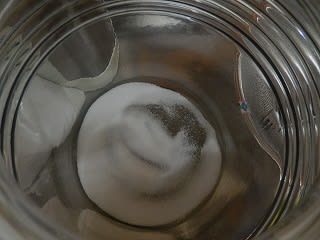
































 冷蔵庫にしまいましたが、冷蔵庫の中でもゆっくりと熟成が進んでいくと思います。
冷蔵庫にしまいましたが、冷蔵庫の中でもゆっくりと熟成が進んでいくと思います。










