
今日は、西郷どんで出てきた坂本竜馬が長崎で設立した(亀山社中)に絡めて、日本の造船技術がどうして
世界指おりの国となったのかを紹介しよう。それは、ペルーの来航の1853年にはじまる。この当時、徳川幕府は
世界の変化を長崎のオランダ人から知り、翌年蒸気軍艦を招き、いち早く、薩摩や佐賀藩などがその技術を理解した。
この技術を見て、日本では、すぐにこの蒸気船をつくることができないことから、西洋から購入することに専念し始め
1866年までの間に、輸入船の数は、110艘の内82艘が蒸気船であった。幕府が軍艦と輸送船を含めて27艘
他は、諸藩で、特に、薩摩が16艘、長州が6総であった。この薩摩と長州などへの売買をおこなったのが坂本竜馬である。
幕府は輸入に伴って、実施学習と輸入船の訓練教育を行うべく、いろいろの背策をおこなっている。
すなわち、運転の習熟を行うための船用機関の製造技術を習得するために、石川島に設置している。
これがのちの石川島播磨重工となるのである。1862年には、オランダへ16名を派遣留学生として、渡航させているが、
その中に、榎本武揚、中島兼吉などがおり、榎本は戊申戦争のあと北海道の開拓に一躍名をとどろかせ、中島は後の
中島飛行機のもとになるのだ。教育機関としては、徳川幕府は、神戸に1862年に付属、勝海舟に操練所を建設提案し、
その付属機関として長崎製鉄所を発足している。しかし、この操練所が解散したあと、その生徒であった坂本竜馬が
かの亀山社中を長崎に貿易商社とした設立していることは有名である。その後、勝海舟は再度、海軍伝習係となり
イギリス教師のもと英国式海軍伝習がはじまり、この後戊申戦争を経て、明治維新となるのである。この後は、輸入した
蒸気船には、老朽化に伴って故障もひんぱっしたが、これを自力で修理することが国として必要となり、国内各地に、
修理工場ができていった。これが、その後、日本の造船技術を完成させていくのである。














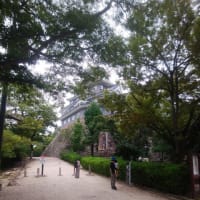





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます