
- 第13回 -
住友政友 ―住友家二人の創業物語―
https://www.blwisdom.com/vp/rekishi/13/

天正13年(1585)、越前(福井県)・丸岡に住友政行の二男として生まれる。
12歳の頃京へ上り、そのころ流行していた「涅槃宗ねはんしゅう」の僧・空源(くうげん)の弟子となる。「空禅(くうぜん)」と号して修行し、文殊院の称号を得るが、幕府の宗教政策によって僧籍を離れることとなり、寛永年間、45歳にして「冨士屋(ふじや)」の屋号で書物と薬の店を営むこととなる。「往生要集」おうじょうようしゅう、「御成敗式目」(鎌倉幕府が制定した法典)等の書物のほか、多くの書簡を残している。慶安5年(1652)68歳で亡くなる。

住友政友木像
「蜂の巣やけ」の発見

別子山中
別子銅山は愛媛県新居浜市の南に広大な地域を占めている。
このヤマを発見したのは阿波(徳島)生まれの「切上きりあがり長兵衛」という鉱夫であったと伝えられている。
あるとき、幕府の領地であった別子山中(別子山村)に分け入った長兵衛は「やけ」を発見した。
「やけ」とは酸化した銅鉱石が地表に露出した露頭を指すことばで、このことを長兵衛はただちに住友家が経営していた備中・吉岡の銅山支配人・田向重右衛門に報告した。
元禄3年(1690)秋、重右衛門は配下の者とともに別子に急行し、山の中を調査して「蜂の巣やけ」を発見した。
「蜂の巣やけ」とは品位の高い富鉱の露頭のことで、一同は狂喜した。このときの大きな喜びから翌元禄4年(1691)に別子銅山を開抗したときの坑口に「歓喜 間符まぶ(坑)」と命名したのである。
僧侶から商人への転身

賤しずヶ岳
賤しずヶ岳の合戦で秀吉に敗れた柴田勝家の家来に5000石を給されていた住友政行という武将がいた。
この政行の子供である政友は、勝家が秀吉にほろぼされた後、母親とともに京都に移り住んだといわれる。父・政行は合戦で命を落としたか、若くして病死したのかもしれない。
やがて成長した政友は、そのころ流行していた「涅槃宗ねはんしゅう」という新興宗教に入って主宰者である空源(くうげん)に見込まれて高弟になり、文殊院・空禅(くうぜん)と称した。
ところが、この涅槃宗は幕府に弾圧されて教団が衰弱してしまい、政友はやむなく薬や書籍を扱う商人に転じた。
万能薬といわれていた「反魂丹はんごんたん」を売ったり恵心僧都・源信の『往生要集』や馬の全集『全書』を出版したりしていたという。
そして、この政友の商売を支援したのが義兄・蘇我理右衛門(そがりえもん)であった。理右衛門は政友の姉を妻としており、涅槃宗に帰依していたため、宗門の高弟である政友を、自分より年少者ではあったけれども深く尊敬して心の拠り所にしていた。
住友の基礎をつくった「業祖」蘇我理右衛門の技術
理右衛門の本業は銅吹屋で、19歳のときに大坂から京都に出て小さな店を構えていた。
研究熱心な理右衛門は、堺で南蛮商人に銅から銀を抜く技術のヒントを聞き出した。
そしてさまざまな苦心の末に独自の「南蛮絞り」の技法を身につけたといわれる。
南蛮絞りは「南蛮吹き」とも呼ばれる。
南蛮炉の中に含銀粗銅と鉛の合金を木炭とともに入れ、銅の融点1084℃近くまで加熱する。そして、鉛が銀を含んで液状になったものを絞り出して灰の上に置き、徐々に加熱して鉛の融点まで温度を上げると、鉛は灰の中にしみこんで、銀だけが残るという方法である。
一説によると南蛮商人はハックスレー(白水)と称し、理右衛門は彼の名を取って店の名を「白」と「水」をくっつけて「泉屋」としたという。
当時の日本の主な輸出品は銅で、銅銭や銅製品として大量に海外に輸出されていたが、それらには銀が含まれたままだった。
銅から銀を抜く技術が日本になかったためで、ポルトガル人たちは日本から輸入した銅から抜いた銀を東南アジアで売りさばいて大きな利益をあげていた。
これに目をつけた理右衛門は新技術を開発し、銀を抜いてから銅を輸出するようになったのである。その証拠に当時のポルトガルの文書には日本の銅がある時期から銀を含まなくなったと記されており、理右衛門の技術が日本国にとって多大な貢献をしたことがわかる。

方広寺梵鐘
さらに理右衛門が偉大だったのは、苦労して得た「南蛮絞り」の新技術を、秘伝として独占しなかったことである。
技術を隠せば、それだけ多くの銅が銀を含んだまま国外に流出してしまう。これは国益に反することだと考えたのだ。
こうして新技術を大坂の銅吹き仲間に公開した「泉屋」は、大坂の銅吹き業の中心的存在として隆盛をきわめるようになり、多大な利益を手にすることになった。
「国家安康」の文字は自分を二つに切るものだと家康が難癖をつけて大坂の陣を引き起こした有名な京都・方広寺の梵鐘も、ほとんど泉屋から調達した銅でつくられた。
そして新技術を引っ下げた理右衛門は、大坂・夏の陣が徳川の勝利に終わると、商業の中心地として発展しはじめた大坂に進出した。
自分は京都の本店を取り仕切り、大坂店は長男の友以(とももち)に任せた。
友以は政友の婿養子であった。
つまり、ここに政友の宗教的な精神と理右衛門の先端技術を合体させ、次の世界への布石も考えた住友の基礎が固まったのである。
過酷な重労働が支えた住友の銅
開坑してわずか8年後の元禄11年(1698)には国内銅量の25%を算出するようになった別子銅山の存在は、当時の技術水準を考えると不思議な奇跡のように感じられるが、これを基底部で支えたのは無名の鉱夫と負夫と呼ばれた鉱石の運搬人である。
鉱夫はサザエの殻に鯨油を入れた「螺灯らとう」の芯に火をともして懸命に固い鉱石を採掘し、負夫はそれを「えぶ」という背負篭にのせて運んだ。
負夫は鉱石をかついで鉱山の坑の底から地上に運びあげたが、履物は踵までとどかない蹠あしうらの半分か三分の一くらいまでの短い足半あしなかといわれる草鞋わらじであったから、それはさぞ辛く重い仕事であったことと思われる。
また、仲持と呼ばれた銅や諸物資の運搬人は芋野、小箱峠、中宿を経て浦山までの6里弱(約23㎞)の急峻な細い山道を歩きつづけた。
そして、帰路は魚や日常生活に必要な品々をかついでヤマへ登っていったのである。

鉱石運び
女は8貫(約30㎏)の粗銅を背負い、男は12貫(約45㎏)を背負ったといわれる。
平坦な舗装路を歩くならまだしも、ゴロタ石の転がっている土の坂道を歩くことはよほど足腰をきたえてなければできるものではない。
とくに雪の積もる冬の辛さは言葉ではあらわせないほどの辛苦であったろう。現代のやわな都会生活者には不可能なことではないかと感じられる。
その証拠に屈強な青年が博物館に展示してある30㎏の粗銅を背負おうと試みても、容易に立ちあがることができなかった。
粗銅は浦山から天満浦(現在の宇摩郡土居町天満漁港)までの3里(12㎞)は馬に積んで運ばれ、天満浦で船に積みこまれて大坂・長堀(大阪市中央区島之内2丁目)の「住友銅吹所」(精製所)へ送られた。
やがては港を鉱山から天満浦へ行くより近い新居浜港に変えて積み出すようになり、近代になると、鉱山から港まで馬車や鉄道で輸送されるようになっていった。
それまではひたすら人力にたよらざるを得ず、最盛期には銅山人口一万人に至った。
住友家二代・友以が寛永のはじめに本拠地を京都から大坂・長堀に移して以来、粗銅は主にこの「住友銅吹所」で精製され、そのほとんどが海外に輸出されていった。
が、やがて次第に産銅量が下降し、岩盤が崩れやすく出水する危険も多くともなうということで、昭和48年(1973)には休山することになった。
鉱石を運び出していた端出場は、第三セクターのテーマパーク「マイントピア別子」に変貌し、観光客の訪れを待っている。
住友の家祖である政友は、経営理念を至極簡単明瞭にこう表現している。
一、商事は、 不及言候いうにおよばずとそうらへ共ども、万事、情ニ入可被候いれらるべくそうろう。
一、何ニ 而てもつね常のそうば相場よりやす安き物持来候共ものもちきたれとも、根本をしらぬ物ニ候ハヽものにそうらはば、少しもか買い申す間敷候まじくそうろう。左様之物さようのものハ盗物とうぶつと可心得候こころうべくそうろう。
一、人の くちあい口合(保証人)せらるましく候。
一、人何やうの 事申候共こともうしそうろうとも、気短く、言葉あらく、申もうすましく候。
(『文殊院旨意書』部分)
商売はいうまでもなく、何事にも心をこめてやらなければならない。
相場より安い品物でも、出所が定かでない物は買ってはならない。そのような物は盗品と心得るべきだ。
他人の保証人になってはいけない。
短気を起こしてぞんざいな口をきいてはいけない。

世のため人のために商売人は生きるべき
住友政友は、越前(福井県)丸岡城主・住友若狭守の子・政行の次男として生まれたが、父が賤ヶ岳の合戦で敗れて各地を転々とするなか、13歳のときに母とともに京都に出て出家して僧となった。
当時の京都では「涅槃宗」という新興宗教が急速に信者を集めており、時の天皇である後陽成天皇まで信者になるほどの勢いであった。「涅槃」とは死、寂滅、煩悩の火を消すことを意味する釈迦最後の教説であり、新興宗教ながら、他の教説を非難しない包容力があった。
その教祖・空源に見込まれて弟子となった政友(法名・空禅)は、布教活動に邁進。その布教途上で信者として出会ったのが、蘇我理右衛門である。
住友家は政行の6代前から住友姓を名のり、理右衛門の家系はその四代目から分かれたとされる。
つまり、さかのぼれば同じ住友の出ということになる。
巨大化する涅槃宗を幕府権力が見過ごすはずはなく、後陽成天皇が崩御すると、これを機に幕府は弾圧を強め、天台宗の執行天海僧正の手で涅槃宗を天台宗の一派に組み込んでしまう。
幕府の弾圧によって僧衣を脱いだ政友は、「反魂丹」の看板を掲げて「冨士屋嘉休」と称し、薬の販売と書物の出版をはじめた。
薬と書物を生業としたところに、世のため人のために働きたいという政友の社会性や公共性を読み解くことができる。
晩年の政友は、各宗派を紹介した遺文「法伝記」のなかで日蓮が『立正安国論』で他宗を攻撃する独善性について批判的見解を述べている。
冨士屋嘉休として、源信の『往生要集』の完本を出版したり、弘法大師の『即身成仏義』を刊行した政友は、天台・真言・浄土など数多くの宗教に通暁しながら、「人びとの幸せに貢献する」という商売哲学を自らの生き方によって示した、まさに住友家の「家祖」なのである。
時代の逆風を追い風に変えてしまう先見力
幕府は、元和2年(1616)に外国商船の寄港地を長崎の平戸に限定。
ついで寛永10年(1633)に奉書船以外の海外渡航を禁止した。
当時の輸入品は生糸、織物、薬品、書籍など。
輸出品は銀や銀製品が中心であった。恒常的に輸入超過の状態であり、そのため国外へ金銀が流出し、金銀の不足が幕府内の重要課題となっていた。
幕府は金銀の流出を防ぐために輸入品への支払いを金銀に代えて銅をあてていくように指示を出す。
この結果、銅が海外へ出るようになり、国内の精銅業者は活況を呈するようになったのである。
住友家の「業祖」である理右衛門が「南蛮吹き」の技術をある一定の基準をもって他の精銅業者に公開したのも、国益への寄与もさることながら、1社で独占するよりも、時代の追い風を受けて複数業者で展開したほうが精銅業界の発展の起爆剤になると判断したからだと推測できる。
天正18年(1590)の理右衛門による「南蛮吹き」の開始にはじまり、銅貿易商としての発展、さらに元和元年(1615)の第2代友以(とももち)による大坂進出によって住友家はさらなる飛躍を遂げる。
友以が京都から進出した当時の大坂は、慶長19年(1614)の大坂の陣による荒廃から復興しつつあった時期とちょうど重なる。
また、将来的な銅貿易の拡大を意識して、大坂という土地に、水運上の利便性を見出したことはいうまでもない。
大坂が「天下の台所」としての基礎を固めつつあったその時期に、友以は素早い経営判断を下したといえる。
そして、時代の流れを鋭くつかむことこそが住友流ビジネスの真骨頂である。
住友政友Photograph

丸岡城(福井県坂井市丸岡町)
福井平野丸岡市街地の東に位置する小高い丘陵に築かれた平山城。江戸時代に丸岡藩の藩庁となった

精錬され棒状・板状になった銅
銅の精錬はまず、人手によって選別された銅鉱石を乾燥・ばい焼き等の処理をし、炉に入れて粗銅をつくる。次に電気分解を行ない、不純物を取り除く。こうした一連の作業を経て銅がつくられるのである。

粗銅を入れた篭を背負い山道を運ぶ
この中に粗銅を入れ、女は8貫(約30㎏)、男は12貫(約45㎏)を背負い、一年中、細く険しい山道を歩き、運び続けた

えぶ(背負篭)
負夫は鉱石を「えぶ」に入れてかついで鉱山の坑の底から地上に運びあげたが、足半といわれる草鞋であったため、かなりの重労働だった

精錬夫
精錬夫の仕事とは、まず砕かれた鉱石を焼き、その焼鉱を一番吹き、更に二番吹きと「吹床」で吹きわけ、実に2ヶ月間もの時間をかけて「粗銅」をつくっていく、まさに重労働な仕事に従事していた

住友銅吹所跡(大阪市中央区)
住友財閥の祖といわれる2代目住友友似のとき、大坂で銅の精錬業に取り組み、その基礎を固めたといわれる。住友家一族の菩提寺は本来実相寺(浄土宗)であるが、友似などは法華信仰によってこの場所にある久本寺(本門法華宗)に墓碑がある。現在この場所は公園にもなっている
撮影:泉 秀樹
(2010年9月21日公開)













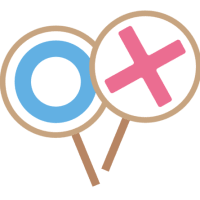






※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます