【李 商隱 の詩】
李 賀(791-817)小伝を記した 唐の
李 商隱(813-858)に
隆房卿(1148-1209)の 艶詞(つやことば)と よく似た詩がある
吉川 幸次郎 博士(1904-1980)の「この詩人については
この数編を以て もはや語らぬであろう」とされた 名訳を寫(うつ)す
他の いくつかの この詩人の作と ともに「無題」題しらず と題する
昨夜星辰昨夜風 昨夜の星辰(せいしん) 昨夜の風
畫樓西畔桂堂東 画楼(がろう)の西畔(せいはん) 桂堂(けいどう)の東
身無綵鳳双飛翼 身には 綵鳳(さいほう)の双(なら)び飛ぶ 翼 無く
心有靈犀一點通 心には 霊犀(れいさい)の一点 通ずる 有り
隔座送鉤春酒暖 座を隔(へだ)てて 送鉤(そうこう)は 春の酒 暖かに
分曹射覆蠟燈紅 曹(そう)を分ちての射覆(せきふ)は 蠟燈(ろうとう)の紅(あか)し
嗟余聽鼓應官去 嗟(なげ)く余(われ)は 鼓(つづみ)を聴きて 官(つかえ)に応じて去る
走馬蘭臺類斷蓬 馬を蘭台(らんだい)に走らせ 断蓬(だんぽう)に類(に)たり
事がらは 屈折した印象の かなたに ある けれども
遠い過去の時間の ことでは ない
ゆうべの星月夜のもと
そうして かすかに風の流れる ゆうべ
場所は 壁画のある 楼閣(ろうかく)の西がわ
木犀(もくせい)の植込(うえこみ)のある 座敷(ざしき)の東
そのとき そこで わたしは
はじめて あなたを見た
(おそらく大臣の邸宅(ていたく)である
詩人は 座敷(ざしき)の宴席(えんせき)を抜け出し
そこを 彷徨(さまよ)っていたようだ
彼(か)の女も また そこに いた)
はじめて あう あなた である
なかの よい恋人に たとえられる
綵(あやぎぬ)の はねを もつ 鳳凰(ほうおう)が
翼を さしかわしつつ 飛ぶ
という間柄は もとより そこに なかった
しかし 何か 通いあう ものが あった
神秘な犀(さい)の角(つの)には
すっと一本 筋が 突きとおっている というが
そのような 不思議な交流が あった
多くの言葉を かわしあった わけでは ない
あるいは ただ ほほえみ だけを
かわした のであった けれども
私は宴会の席に戻った あなたも そこに いた
やがて 余興(よきょう)が はじまった
はじめは 蔵鉤(ぞうこう)の遊びであった
手のひらに ちいさな鉤(かぎ)の
いくつかを 蔵(かく)しもち
相手に その数を あてさせる
人数が偶数ならば むこうと こちらと
「座を隔(へだ)てて」二組になり
奇数ならば 余った一人が 遊軍になり
双方の間を往來する
(と 周 処の『風土記』に見える)
あなたは 遊軍になって 私のところへ やって來
かわいい こぶしを つきつけた
数を あてそこねた私は 罰杯の酒を のんだ
あなたの ついでくれる 春の酒は 暖かだった
つぎには 盆の下に 覆(おお)いかくされた
ものの名を 射(い)あてる遊び
やはり 曹(くみ)を分けて ふた組になった
顔を近づけた二人のそばに
蠟燭(ろうそく)の ともしびが 紅(あか)かった
しかし 私は けっきょく
一介の 内閣事務官に すぎなかった
蘭台(らんだい) すなわち 内閣の記録局へと
馬を走らせねば ならなかった
風に ふきちぎられた 蓬(よもぎ)の まりが
沙漠の上を まろび ころんでゆく ように
たった ゆうべの星に きらめいた ひとみ
それも また 忘却の沙漠へと
ふきとばされねば ならない
(吉川 幸次郎『続 人間詩話』 その六十 李 商隱 一九五七年十月 岩波新書 278 b)
相見時難別亦難 相見(あいみ)るのときは 難(かた)く 別れも亦(ま)た 難(かた)し
東風無力百花殘 東風(はるかぜ)は力なく 百花 殘(くず)る
春蠶到死絲方盡 春の蚕(かいこ)は 死に到(いた)りて 糸 方(はじ)めて尽(つ)き
蠟炬成灰涙始乾 蠟(ろう)の炬(あかし)は 灰と成りて 涙 始めて乾(かわ)く
曉鏡但愁雲鬢改 曉(あかつき)の鏡に 雲なす鬢(びん)の改まらんことを 但(ひと)えに愁(うれ)え
蓬山此去無多路 蓬山(ほうざん)は 此(ここ)を去ること 多き路(みち)のり無し
青鳥殷勤爲探看 青き鳥よ 殷勤(いんぎん)に 爲(た)めに探り看(み)よ
(かつての恋人を 権力者に うばわれ
それを なげく歌のように 読める)
女性は 詩人の おいそれと 手の届かぬ場所に いまは いる
あうせ(逢瀬)は たいへん むつかしい
しのんで あった あとの 別れは 一そう たえがたい
季節は 晩春である
風さえも無力に けだるい
それは もはや 花を さかせる力を うしなった 風であり
すべての花が おもたく よどんだ空気の中で
むざんに くずれ散ってゆく
そして たちきりがたい 恋心の苦しさを うたう
蚕(かいこ)は 死ぬまで糸を はきつづけて死ぬ
「糸」は 同じ「シ」という音の 「思」に通ずる
また 蠟炬(ろうきょ) すなわち 蠟燭(ろうそく)というものは
もえて 灰となりつくすまで 涙を垂(た)れつづける
われわれの恋の心が おたがいの身を
やきつくす までは と もえさかる ように
わたしと へだてられた あなたは
朝の化粧の鏡に むかう とき
あなたの容貌の やつれを
雲なす わげ(=髷 まげ)に みとめる であろう
夜 そっと わたしの詩の句を くちずさむ とすれば
月の光の寒さを ひしひしと感ずる であろう
蓬山(ほうざん)とは 仙人の山 蓬莱(ほうらい)であり
彼(か)の女の いま いる場所に たとえる
それは 道のりと しては すぐ そこに ある
おなじ 長安(ちょうあん)の町の おなじ 町内に あった かも知れない
青鳥(せいちょう)とは 恋の使者となる 鳥である
青い鳥よ 殷勤(いんぎん)に こまかに
気を くばりつつ そこへ飛んで行って
彼(か)の女が どうしているか
わたしのために 探ってきておくれ
(吉川 幸次郎『続 人間詩話』 その六十一 李 商隱 一九五七年十一月 岩波新書 278 b)
來是空言去絶蹤 來る というは 是(こ)れ空(むな)しき言(ことば)にして 去りてより 蹤(あと)絶ゆ
月斜樓上五更鐘 月は楼(ろう)上に斜めなり 五更(ごこう:午前3~5時(夏) 4~6時(冬)頃)の鐘
夢爲遠別啼難喚 夢に 遠き別れを爲(な)せば 啼(な)くも 喚(こえ)となり難(がた)く
書被催成墨未濃 書は 成すを催(うなが)されて 墨も 未(い)まだ濃からず
蠟照半籠金翡翠 蠟(ろう)の照(ひか)りは 半(なか)ば 金の翡翠(ひすい)に籠(こ)もり
麝薫微度繍芙蓉 麝(じゃ)の薫(かお)りは 微(ほの)かに繍(ぬ)いし 芙蓉(はちす)を度(わた)る
劉郎已恨蓬山遠 劉郎(りゅうろう)は 已(すで)に 蓬山(ほうざん)の遠きを恨(うら)めるに
更隔蓬山一萬重 更に 蓬山(ほうざん)より隔(へだ)たること 一万重(ちょう)
おなじ女人を おもって の作と すれば
あうせ(逢瀬)は 一そう むつかしく なっている
劉郎(りゅうろう)とは いろ おとこ を呼ぶ語であって
(詩人 李 商隱)みずからの こと
(吉川 幸次郎『続 人間詩話』 その六十一 李 商隱 一九五七年十一月 岩波新書 278 b)
【李 賀 蘇小小(そしょうしょう)の歌】
若くして不遇のうちに病に斃(たお)れた
李 賀(791-817)の
原田 憲雄 大師(1919-)による 大研究 珠玉の名解説より 抜粋
不幸な恋に死んだ女性 蘇小小(そしょうしょう)の魂魄(こんぱく)が
來る筈(はず)のない恋人を 永遠に待ち続ける 歌
古代 無名氏の同名作「蘇小小(そしょうしょう)歌」によれば
蘇小小(そしょうしょう)は
南朝の斉(479-501)の頃の
銭塘(浙江)の名妓で 一説では 歌の作者だという その歌
我乘油壁車 あたしは 女車に乘って
郎乘青驄馬 あなたは 青馬に乘って
何處結同心 どこで 契りを結びましょう
西陵松柏下 西陵の あの松の下
李 賀 においても 蘇小小(そしょうしょう)は 初期の「七夕」などでは
名妓の代表に過ぎない 無性格な女人だった
ところが この「蘇小小(そしょうしょう)歌」における 蘇小小(そしょうしょう)は
名妓であれば 誰でもよい というような 代称では なく
中国の文学の中では いまだ かつて 取り上げられた ことも ない
女性の肖像であって 李 賀 の発見した人格としか 言いようが ない
余りにも 独自であり あまりにも 破天荒であるため
多くの読者は この作品から発する 鬼気を感じは しても
鬼気を生みだす 源の深義を理解する ものが ない
李 賀 蘇小小歌 蘇小小(そしょうしょう)の歌
幽蘭露 幽蘭(ゆうらん)の露(つゆ)
如啼眼 啼(な)く眼のよう
無物結同心 同じ心 結ぶものなく
煙花不堪剪 けむる花 切るに忍びぬ
草如茵 草は しとね
松如蓋 松は 傘
風爲裳 風が もすそ
水爲珮 水が 帯玉
油壁車 おんな車は
久相待 じいっと待つ
冷翠燭 冷い やり翠の
勞光彩 つかれた ともし灯
西陵下 西陵は
風吹雨 雨しぶく風
〔幽蘭(ゆうらん)の露〕 この句は 短いけれども
蘇小小(そしょうしょう)の「性格」を描いている
古辞や それまでの詩では 見いだせなかった ものである
「幽蘭(ゆうらん)」は 人に知られぬ ところで 咲く フジバカマ
孔子 家語に「
芝蘭(しらん:レイシ と フジバカマ)は 深林に生えるが
人が いないから といって 芳香を放たぬ ことは ない」と いい
「困窮によって 節操をかえぬ」とも いう
蘇小小(そしょうしょう)は 遊郭に住む 遊女である
遊女は もと 祭儀に奉仕する巫女に 起源を もつ
これが 専門の巫女と 娼妓とに分離し
巫女は 神宮で 神に仕え 娼妓は 遊郭で 生の歓楽を売った
表面は ずいぶん違った ものに みえようが
家庭から隔離され 恋愛も 結婚も 禁止されている点で 共通する
家庭で 生涯を送るべき もの とされた 女性が
一般社会から 隔絶した 遊郭に 住むのは
深林に生えるものに 類(たぐ)えることが できる
遊郭に住みながら 恋愛し 結婚し 家庭を営む
願いを持ち続ける と すれば「節操をかえぬ」もの
「深い林の中で 芳香を放つもの」と いうべきで あろう
遊郭は 性の歓楽を売る 市場で そこを訪(おとな)う 客は
彼女を 性の歓楽の道具としか見ず
ひとりの女性 ひとりの人間として 対等に付きあわない のが 常である
そのような場所での 蘇小小の ゆかしさは 場違いのもの
野暮な 田舎女のもの と 笑いものに されたかも知れぬ
しかし 多くの客の中には そのような ゆかしさに目を つけ
近づく者も いるだろう うぶな青年も いようが
誘いだして ほかへ売り飛ばそうとする 悪たれも いただろう
露は 涼しい眼もとの 暗喩(あんゆ)である
そのように 涼しい眼もとを褒めて 男は 逢引(あいびき)を求め
蘇小小(そしょうしょう)は 初めて恋をし ここで 男と逢ったのであろう
「君は この花のようだ」と 女に 幽蘭を 贈ったが
男は 結婚する気は なく あるいは 事情が許さず
それきり 女の前に現れない
しかし ここは 蘇小小(そしょうしょう)が 恋人と逢った場所であり
幽蘭は その ゆかりの花である
日が暮れても 受け入れてくれる ものも ない人が
佇(たたず)みつくす とき 手にした花が 幽蘭だった
「蘭を結ぶ ことには 離別の意が 含まれる かもしれぬ」という
清の 広群 芳譜は「およそ蘭には 一滴の 露の珠(たま)が
花蘂(かしん:しべ)の間に あって これを 蘭膏(らんこう)という……
多く取ると 花を傷(いた)める」と 説く
男は 蘇小小(そしょうしょう)から 取れるだけの 蘭膏(らんこう)を盗んで
消えてしまったのだ
〔啼眼(ていがん)の如し〕 「露しっとり」などと 愛想を いって 近づいた
男が去った あとの 蘇小小(そしょうしょう)の 涼しい眼もとが
どのように変わったかを この三字が語る
啼(な)くは 声を放って 泣くこと
啼眼(ていがん)は 放つべき声が禁圧されるために
目から涙となって滴(したた)り出た 感じを誘(いざな)い
「如(ごとし)」という 直喩(ちょくゆ)法で せき止められている ため
その効果が 一層 強まっている
〔物として同心を結ぶ無く〕 同心は 心を同じように 合わせる ことで
易経(えき きょう)に「二人 心を同じくすれば その利(するど)きこと 金を断(た)ち
同心の言は その臭(かお)り 蘭(らん)の如(ごと)し」という
そのような堅(かた)い交わりを願うところから
「結 同心」という言葉が成長し
やがて「男女の契りを結ぶ」「恋を遂げる」という意に定着した
契(ちぎ)りも また さまざまな人間世界の条件によって 引き裂かれる
ただ 引き裂かれても 同心を結び得ている のであれば
待って「老い」には 至(いた)り得る のであろう
かりに「老い」に至り得ぬ にしても
古辞(こじ:古謡)の「蘇小小(そしょうしょう)歌」のように
「どこかで 契りを結びましょう」というのなら
契りを結ぶ場所が いくつか ある わけであろう
その一つが 地下である にしても
けれども ここでは「無物 結 同心」という
同心を結び得る 頼りになる物が ない
まったく無いのだ 地上は もとより 地下にも
〔煙花(えんか) 剪(き)るに堪(た)えず〕 煙(けむり)は 烟(けむり)とも 表記し
霧や 靄(もや)や 霞(かすみ)のように ぼんやりした蒸気一般を さし
煙花(えんか)は その靄(もや)に包まれた花
古詩では 蓮(はす)の花を採(と)り 香りの よい草を採(と)り
なぜ採(と)るのか といえば 思う人に贈るため であった
楚辞に「素麻(そま)の 瑶華(ようか)を折って
離れている人に贈ろうと するが 老いは ずんずん極(きわ)まり
なかなか近づけず いよいよ遠ざかる」
「石蘭(せきらん)を着て 杜衡(とこう)を帯とし
芳馨(ほうけい)を折りとって 思うひとに おくろう」という
瑶華(ようか)は 宝玉の花 素麻(そま)は 神聖な麻
杜衡(とこう)は (オオ)カンアオイ 芳馨(ほうけい)は 匂いの よい花
芳馨(ほうけい)は 媚(こ)びて 相手の心を ひこう とする ための 贈り物
素麻(そま)は もはや帰ってこない であろう 遠くにいる人への 最後の贈り物
瑶華(ようか)も また「最後の」贈り物 いわば 別れを告げる「しるし」
「煙花(えんか) 剪(き)るに堪(た)えず」も
離別の しるしの 煙花(えんか)を切り取って
(帰ってきもせぬ)男に差し出すに
忍びない のである ことが 明白になる
求愛の花束が 突っ返される ことに よって 離別の花束と なる ように
違った花である 必要は ない けれども
芳馨(ほうけい)と 素麻(そま) 蘭(らん)の花と 瑶華(ようか)とは
求愛の花と 告別の花に 役割を分けている らしい
瑶華(ようか)も それが 離別のしるし である としても
遠くの人が 自分を思ってくれる ことは 歌う者には 確信されている
だから 明確 堅固な 宝玉の花「瑶華(ようか)」として 表現された
プラチナの台に 贈り手 贈り先の名を刻み込んだ
ダイヤの婚約指輪の ような もの
ところが 蘇小小(そしょうしょう)の 手にする花は 瑶華(ようか)では ない
霧や靄(もや)に つつまれると 幻のように消える
それが 煙花(えんか)であり 煙花(えんか)は 風が去り 雨が止めば
うつつ よりも 鮮やかに現れる それが 幽蘭(ゆうらん)なのである
蘇小小(そしょうしょう)の恋は 無物 結 同心で
完成の可能性は 現在にも 未来にも 無い
しかし 過去においては 愛 あるいは 愛に似た ものを 示され
それが 彼女を恋に導いた のであろう
愛 あるいは それに似た ものが消えても ゆかりの花は残っている
それが 幽蘭(ゆうらん)であり 煙花(えんか)である
幽蘭(ゆうらん)も 煙花(えんか)も また 同心を結ぶべき ものでは ない
死んでも死にきれずに さまよう 蘇小小(そしょうしょう)の
魂魄(こんぱく)で さえも が そうである ように
彼女は「深林」に住むにしても その深林は 遊郭という性の市場で
幽蘭といっても 身体を しごいて 生きる娼妓
無垢 無知な 処女では ない
醒(さ)めた理性は 女を夢中に させて 逃げた男が
彼を待つ 女のもとに 金輪際 帰ってこない ことを知り尽している
にもかかわらず 醒(さ)めた理性なんぞの忠告に 耳を傾けかねる 願いが
万に一つも ありえぬ 彼の やってくる時を待ち
彼の來ぬ のが 天命ならば むごい天に さからって
その理不尽な天命を 功(こう)無きものに させようと までに
物狂おしい 彼女の恋心は ふがいない つれない つまらない男 であっても
その ゆかりの花を切って 離別を示す には 忍びぬ のである
〔草は 茵(しとね)の如(ごと)く〕 草は 蘇小小(そしょうしょう)の乗る
幻の車の 中に敷く 布団(=クッション)のよう
〔松は 蓋(かさ)の如(ごと)し〕 松の木が 車につける 傘蓋の よう
〔風を 裳(しょう)と為(な)し〕 風が もすそ(裳裾=スカート)
〔水を 珮(はい)と為(な)す〕 河水の音が 帯を結んだ玉の触れあう音
〔油壁(辟)車〕 壁面を油漆(うるし)で彩色した 美しい車
元は 貴妃や夫人 日本で なら 女御(にょうご)や 更衣(こうい)に あたる
尊貴な女性 専用の車だった
〔久しく相待つ〕 待つ時間の 永遠といってもよい 久しさを 歌っている
相は 動詞が対象を持つことを示す接頭語
ここでは「互いに」という意味は持たない
〔冷たる 翠燭(すいしょく)〕 燐火(りんか)とも 鬼火(おにび)とも
現実を超えた火が、冷冷としている
〔勞たる 光彩〕 疲れきった光彩が やがて消える
〔風 雨を吹く(風雨吹)〕 煙花(えんか)の煙によって
雨の來ることが予想はされるが 勞 光彩 までは 雨は降っていない
幽蘭(ゆうらん)の露は 啼眼(ていがん)の如(ごと)く では あるが
啼眼(ていがん)では なく
蘇小小(そしょうしょう)の 心の内部を象徴する けれども
彼女は 泣いては いない
泣くことを堪(こら)えて 待ち尽(つく)すのである
雨が降るのは 勞たる光彩が消え
蘇小小(そしょうしょう)の姿が 見えなくなった
闇黒(あんこく)の 西陵(せいりょう)下に である
闇黒(あんこく)のうちに 蘇小小(そしょうしょう)のために
啼哭(ていこく)し 涕泣(ていきゅう)するものが あり
その啼哭(ていこく)するものが 風で
涕泣(ていきゅう)するものが 雨なのだ
李 賀 の詩では 闇黒(あんこく)の中で 風が吹き 雨が降る
闇黒(あんこく)は 蘇小小(そしょうしょう)の 沈黙 である
怨恨(えんこん)も 悲愁(ひしゅう)も すべて その内部に吸収する
ブラックホールが エネルギーを吸収する ように
風と雨とは 一つになって
蘇小小(そしょうしょう)の沈黙の中に 吹き込むのでは ない
すなわち「風雨吹」では ない
はげしく風が吹き はげしく雨が降るのである
雨が吹き 風が降る といっても よい
西陵(せいりょう)下の闇黒(あんこく)
蘇小小(そしょうしょう)の沈黙は
忍従でも あきらめでも おそらく ない
それは 永遠の女性の 永遠の たたかい なのだ
この句は 必ず「風吹雨」でなければ ならない
李 賀 は かつて「楞伽(りょうが) 案前に堆(うずたか)し」と うたった
楞伽(りょうが)とは 仏教経典の『
楞伽 経(りょうが きょう)』である
その楞伽(りょうが)に「大悲(だいひ)闡提(せんだい)」の説がある
闡提(せんだい)とは「
一闡提(いっせんだい)」のこと
梵語の icchantika を 漢字に写した音訳で
意味は「世間的な欲望に ひたって 法を求めない者」
従って
解脱(げだつ)や
涅槃(ねはん)を 得ることの できない者である
一は 一切の善根を焼きつくした もの
二は 一切衆生を憐愍(れんびん:あわれむ)する者
この 第二の者が 菩薩(ぼさつ)であり
方便(ほうべん:
衆生(しゅじょう)を導く巧みな手段)もて 願と なす
もし もろもろの
衆生(しゅじょう:一切の生きとし生けるもの)
つまり 菩薩は 一切の
衆生を
解脱(げだつ)させ
涅槃(ねはん)に入れる のを
自分の任務とするために すでに仏となる資格を持ちながら
すべての
衆生が
解脱(げだつ)せず
涅槃(ねはん)に入らない間は
自分も
解脱(げだつ)せず
涅槃(ねはん)に入らず 仏とならずに
世間の 欲望に満ちた人たちと同じ姿で 世間に とどまり続ける
これを「
大悲闡提(だいひ せんだい)」と称する のである
さて 蘇小小(そしょうしょう)は 「名妓」とはいえ
性の快楽を売るために 恋愛と結婚を禁じられた 娼婦である
彼女は そのような立場に置かれながら
禁じられた恋愛を成就させようとして
肉体の滅びた後にも 永遠に 人間界に さまよう者である
恋愛が禁じられることは 女性であることを 禁じられる ことであり
女性が 女性であることを 禁じられる ことは
人間が 人間であることを 禁じられる ことに 他ならない
性の快楽を売るために 恋愛を禁じられる ような
女性が存在する かぎり 人間の解放は ない
李 賀 の「蘇小小(そしょうしょう)の歌」は
すべての人間が解放されない かぎり
永遠に 自分一個の解放を拒否して さまよう
「娼婦の立場に おかれた 女性の魂魄(こんぱく)」としての
蘇小小(そしょうしょう)を 歌っている
これは
大悲闡提(だいひ せんだい)の すぐれた文学化 と いって よい
李 賀 の読んだ 十巻本の
楞伽 経(りょうが きょう)も
「諸仏品 第一」が終わると 仏を
楞伽(りょうが)城に招いた
主の 羅婆那 夜叉王は 姿を消す
楞伽 経(りょうが きょう)の主題は 多岐に わたる から
それは それで 差支えはない のかもしれぬ
しかし「
大悲闡提(だいひ せんだい)」に限って いえば
不徹底 と言わざるを得ない
法華経の「
提婆達多品(だいばだった ほん) 第一二」は
八歳の龍女が成仏するので 女性救済の経典として有名だが
その成仏は 実は「変成男子」
龍女が 女性の肉体を 男性の肉体に変化して 仏に なる
女性が 女性の ままで 仏に なる のでは ない
仏には 男性も女性も ない という論理は あろうが
それなら なおさら「変成男子」は
不可解 不徹底だと 言わざるを得ない
李 賀 の「蘇小小(そしょうしょう)」は 変化も 変成も せず
蘇小小(そしょうしょう)のまま 幽蘭(ゆうらん)を手に
永遠に さまよい つづける
大悲闡提(だいひ せんだい) の 趣旨から すれば これこそ
提婆達多品(だいばだった ほん)をも 突破したもの と いえようか
李 賀 の「蘇小小(そしょうしょう)歌」は 女性の尽きせぬ悲しみを
女性の立場にたって 歌おうとした もので
この詩の成立する 時間は 強いて名づけるなら
「鬼時」とでも 呼ぶべきもの であろう
蘇小小が 來ぬ人を待って 佇(た)ちつくした「西陵下」が
何処(どこ)であるかの 議論が 古來 幾たびか重ねられたが
それは たぶん 地理的空間では なく
鬼時と垂直に交叉する「鬼処」なのだ
鬼時と いい 鬼処と いう のは 生き残って 影のように さまよう
存在のほうから する言葉であって
「生は一瞬 死は永遠」という立場からすれば
鬼時と鬼処こそ 生き生きとして 手ごたえの ある
実存的時間 現実的空間 であるのかも しれぬ
(李 賀 歌詩編 1 蘇小小の歌 原田 憲雄 訳注 平凡社 東洋文庫 645)
26歳で亡くなった 李 賀 と 45歳まで生きた 李 商隱 は
百歳を迎えられる 原田 憲雄 大師と 亡き 吉川 幸次郎 博士によって
比類なき 邦訳と 解説を得た
李 賀 は 諱(いみな)事件という 亡くなった父の名と 進士の進が
音で通ずるとして 試験を受けることを差し止められ
王族出身者に与えられる 閑職を辞し 故郷に帰り
失意のまま 急な病を得て 亡くなる
李 商隱 は 進士試験に合格するも 派閥争いに巻き込まれ
庇護を受けた高官が亡くなると 対立する派閥の庇護を得たことから
執拗に非難され 中央を去ると 職を干され また全うできる職を得られず
故郷に戻り 病を得て 亡くなる
李 商隱は 李 賀 の人となりを伝える 李 賀 小伝 を書いている
臨終の場面の 不思議な出來事は 李 賀 の 嫁いだ姉から 聞いた とする
長吉(李 賀)が死にかけているとき
ふと日中に 一人の緋(ひ:やや黄みのある 鮮やかな赤
日本では 平安時代から用いられ『延喜式(えんぎしき)』では
茜(あかね)と紫根(しこん)で 染めた色を「深扱(こ)き緋」とし
紫に次ぐ 官位に用いた)の衣の人が
赤い
虬(みつち=みづち:想像上の動物 蛇に似て長く 角と四足があり
水中にすみ
毒気を吐いて 人を害する という)に乗って 現われた
一枚の書き付けを持っていて 太古の篆書(てんしょ:秦代以前の書体)か
霹靂(へきれき:雷)石文のようだ
「長吉を お召しに なっている」と いうのである
長吉には どうしても読めない
すぐ 寝台から 下り おじぎをして いう
「母さんは年よりで そのうえ病気です
わたしは 行きたくありません」
緋衣の人が笑って言う「天帝さまが 白玉楼を完成され
すぐにも君を召して 記念の文章を作らせよう と されるのだ
天上は まあ楽しい ところ 苦しくは ない」
長吉は ひとり泣いた
まわりの人は みな これを見ていた
しばらくして 長吉の息が絶えた
居間の窓から ぼうぼうと煙気が たち
車が動きはじめ 吹奏楽の調子の 早まるのが 聴こえる
老夫人が急に 人々の哭(な)くのを 制止した
五斗の黍(きび)が炊(た)きあがる ほどの 時間の のち
長吉は ついに死んだ
王氏に嫁いだ姉は 長吉のために
作り事を言うような ひとでは ない
じっさいに見たのが こうだったのである
(李 賀 歌詩編 1 蘇小小の歌 原田 憲雄 訳注 平凡社 東洋文庫 645)
かつての さまざまな勢力争いの 戦利品であり
いまは また 新たな 幼き無心の美貌に
取って代わられ 忘れ去られようとする 女人が
幼さの消え 傷つき疲れた 微笑で
自らを励まそうと 鏡の中を のぞき込む
しかたない わたしだって そうだったんだもの
ここに來たとき ただ そこに いるだけで
見知らぬ 年上の女の人を 泣かせたんだわ
知らなかったのよ ごめんなさいね
もう みんな いないわね
こんどは わたしが泣く番 ひとりぼっち で
みんな そうだったのね
鏡の奥を 昏(くら)く 風のすじが横切り
見憶えのある 館の露台 あるいは 城壁の屋上が 斜めに浮んで
そこに だれか 若い男のひとが 風に吹かれている
あの詩人さんだろか かなしい眼をして
幼い わたしが いまの わたし みたいになる って 詩を書いた
ちがう あの ひと じゃない もっと昔 もっと若くして死んでしまった
死んでも愛する人を待ち続けた 女のひとの詩を書いた 同じ姓(かばね)の
あっ いなくなってしまった どこへ行ったんだろう
雨が降ってる あの女のひとの ところへ行ったのかしら
土砂降りの中 それは みんな あの女のひとが 流さずに堪(こら)えた涙なの
風が 聲(こゑ)なく叫んでいるわ わたしは ひとりぼっち って
待たせてしまったね って言ってる
じゃあ あの女のひとは 彼女を嗤(わら)って捨てた ろくでなしを
待ってたんじゃなくて あの優しい詩人さんを待ってたのね
彼女を初めて よみがえらせた でも あんな ひどい雨の中
いつまでも ずっと立ち尽(つく)し 待ちつづける姿で
ああ やっと雨が上がる 少し靄(もや)が残っているだけ
そうか ふたりが 煙花なのね 虹色に耀いてみえる
詩人さんのほうが 年下みたいね
でも ほんとうは 逢えないくらい 年が離れているのよ
同い年でも たぶん会えないのは 同じだけど
天帝さまの 白玉楼へ 一緒に行こうね って言ってる
いいなぁ わたしも だれか 連れてって くれないかな
遠慮がち と言えなくもない 咳払いが聴こえた
えっ どこ 鏡の奥には 室内が戻っていた
鏡に 寄せかけられるように置かれていた ランプの
向う側 ずいぶん年取って見える 彼女が知っている詩人が
壁に凭(もた)れていた あら あなたも死んじゃったの
鋭いな 大人になったんだね
あら あなたより若いわよ まだ
そうだね でも そのうち追いつくんじゃないかな
ぼくは もう年を取らないから
やだ そんなに待てないわよ
おや そうなのかい
そりゃ そうよ あの二人を見た?
あの女のひと と あの女のひとの ことを書いた詩人さん
李 賀 って 言うんだよ ぼくは 李 商隱
知ってるわよ あの女のひとは?
蘇小小(そしょうしょう)
そうでした 良い名まえよね 良い詩
ぼくも きみのことを詩に書いたよ
知ってるわよ でも名まえは なかったでしょ
だって きみは 生きてる人だったし いまも 生きてる
でも 他の人には わからないわ
きみと ぼくの秘密さ
あら わたしは あの詩人さんの詩のほうが いいな
李 賀 かい
名まえが ついてたほうが いいな って思ったの
じゃあ そうしようか 何て名まえだっけ
いやな ひと 帰れば
真面目な話 ぼくが きみの名を呼んだら そうして きみが返事をしたら
そうして それを三度繰り返したら きみは こっちへ來なくちゃ いけない
あら いいじゃない 白玉楼?
言ってくれるね まぁ その離れ みたいな とこかな
あれも一応 僕が書いたって 知ってる?
あれって?
まぁ いいか ほんとに 呼んでいいんだね
いいわよ あっ ちょっと待ってね
最初に逢ったときのドレス まだ あるの
ほんとうかい だってまだ ほんの子どもだったろ
うるさいわね 背が伸びただけよ ほら どう
うん つんつるてん だな いまの ほうが よくないか
いやな ひと 絶対 これが いいと思ったのに
なんだって いいさ きみは きみで
いつも 清らで 耀いてる 心も 姿も
ふうん そうなのかしらね
わかったわ このままで行く
そう 來なくちゃ じゃあ 呼ぶよ
まちがえないでね 後生だから
緊張するなぁ
やめてよね
(続く)

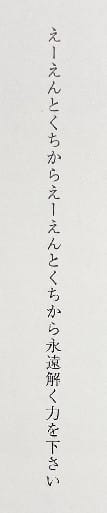
 石田 徹也 Tetsuya Ishida(1973-2005)体液 Fluids c. 2004 頃
石田 徹也 Tetsuya Ishida(1973-2005)体液 Fluids c. 2004 頃
 石田 徹也 Tetsuya Ishida 無題 Untitled c. 2000 頃
石田 徹也 Tetsuya Ishida 無題 Untitled c. 2000 頃

 フリーダ・カーロ Frida Khalo 愛は 宇宙を 地球と 私自身であるメキシコを ディエゴと 犬の
フリーダ・カーロ Frida Khalo 愛は 宇宙を 地球と 私自身であるメキシコを ディエゴと 犬の レオナルド・ダ・ヴィンチ Leonardo da Vinci(1452-1519)ベツレヘムの星(オオアマナ)と
レオナルド・ダ・ヴィンチ Leonardo da Vinci(1452-1519)ベツレヘムの星(オオアマナ)と








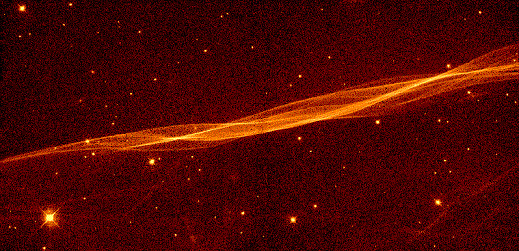













 フィンセント・ファン・ゴッホ
フィンセント・ファン・ゴッホ











 Potseluy Judah
Potseluy Judah 











