
こんなノム一色の世の中なのに…こんな記事で。
早く書かないと忘れてしまうので。
みんなすっかりチャンイに夢中でドンポ親分のこと・・・忘れてない?
かねてから読んでいた「ひとの子」
以前、リンクしていただいてる恭子さんのお宅でご紹介してくださいました。
いつもありがとうです~。
コチラCINE21 インタビュー
そうなんです。
トラン・アン・ユン監督がこの小説をモチーフにして「I come・・」を作るから出てくれないか?とのオファーがあった・・と彼がインタビューで答えています。
だのに珍しく読もうと思っていなかった私。
たぶん「冗談」に疲れ果てていたんだと思います。(笑)
お友達が「あれ?haruさんなら読んでると思った」とおっしゃるので。
挑戦しておりました~~。
まさしく「挑戦」(笑)
ひと月近くかかってやっと読み終わりました。
通勤電車の中でとっとと終わるかと思いきや、
パソ時間の激減を携帯で補ったので、
結局重い本を毎日持って歩きながら

一度も読まないなんてことを繰り返しておりました。
まあ、スラスラ読めてしまう代物ならまだしも、
これが「冗談」に続く冗談のような上段下段本。(爆)
しかも宗教。

しかもキリスト教。(カタカナに弱いの。)


がストーリーに組み込まれてます。
何だか読みこなせたのか不安なのですが。。。
なかなかこの本のレビューはないので、頑張ってご紹介することにします。
この本、殺人事件を軸にしたミステリーと
その被害者の殺される原因ともなった彼の思想に関わる宗教的哲学的な部分の二つの話が折り重なって出来ております。
ミステリーの部分はとても読みやすい。
推理小説を読み進めるようにぐんぐん読み進むのですが、
その事件の捜査官が捜査の足がかりとして被害者が書いたノートを読むという設定で語られる被害者、そして加害者の宗教観を投影した物語の部分が実に…読みにくい。
私は宗教とんと弱く。
常識以下のレベルだと思います。
ヤハウェって誰だっけ?
ユダ…聞いたことあるな。
丘?どこの丘だよ。
最後の晩餐?
なんだっけ…なんだっけ…
ずっとそんな調子。
あとがきからあらすじをざっと抜粋しますとですね・・。
ネタバレありなのでこれから読もうと思っている人は読まないほうが・・。
物語はテグ市で起きた殺人事件に端を発する。
被害者はかつて神学大学に籍をおきながらも、次第にキリスト教に懐疑的になったことから、退学処分を受け、彷徨を重ねていたと思われる男。
捜査本部が常識的な怨恨関係による犯行を疑い捜査を進める中、
担当捜査官 南警査は被害者の物の考え方や行動様式を理解することで犯人像を描き出そうと遺留品であった原稿などを見つけ出して読んでいく。
と同時に被害者の転居先を追跡し、被害者に師事していつも行動を共にしていた青年にたどり着く。
この青年を犯人と断定して追い詰めるまでのプロセスと殺害した動機を突き止める・・これが表向きのこの物語のあらすじ。
これは私が最初に言った「読みやすい部分」
そして私が「読みにくい」と表現した
被害者の信仰心の変化が殺人事件に発展した動機であったことを示すもうひとつの物語が仕込まれているわけです。
あとがきによればその物語とは
「旧約と新約の『聖書』の世界を舞台として被害者の信仰上の苦悩が産み落とした物語」と表現されております。
う~~ん。わかりにくいね。
では、被害者と加害者が求めていた真の「神」とはどんなものか。
彼らの思想についてすこし書いてみましょう。
被害者の遺留品の中から見つかった原稿にはアハシュ・フェルツという若者がキリストの父であるユダヤの神ヤハウェが現実の世界では無力であることに懐疑の念を抱き、真の神を求めて旅に出て紆余曲折の末、最終的に真の神に出会う話が書かれています。
アハシュフェルツは物語の主人公でありながら被害者が自己を投影している部分もあるように思います。
アハシュフェルツは旅先でイエスキリストに7度も対面し、議論を繰り返します。
キリストの教えを不審に思う理由を語り、キリストに説明を求めるも、サタン呼ばわりされ、相手にされない・・・・。
そんな中「真の神」に出会うわけです。
この真の神についてどう説明したらわかりやすいんだろうといろいろ考えたのですが・・この小説に書かれていることをすべて書くと複雑すぎてわかりにくい。
あえて書くとすればそれは限りなく社会主義に近い考え方といえると思います。
「この神は敬われて信仰の対象となることを拒否する。この神は人間はもはや神を求めるべきではなく、自らの力と自由な意志でもって地上の楽園の実現に全力をなげうつべきだと教えている。その際の人間の行為の基準が神の教えにではなく、人間の正義にあることはいうまでもない。」
現実社会の困窮と疲弊を日々目の当たりにして、既存のキリスト教的教義に不信感を募らせた被害者は放浪の旅を続けながらこのような神を理想として描くようになります。
そしてのちに加害者となる若者に出会う。
若者は被害者の信念に感銘を受け彼に心酔し、彼の教えをより明確に具現化しようとする。
それは富が集中している金持ちから富を奪い、貧しい人たちに分け与えるという行為だった。
その行いが自分の目指した神の教えに副ったものなのか・・・日ごと自信が持てなくなっていく被害者。
わが行いを正当化し、確信を手にするために犯罪を繰り返す若者。
二人の思いは食い違い・・・若者は自分が師と仰ぐ人物を手にかけることとなる。
こんなお話。
何回もおんなじこと書いている気がするな・・・。
これでわかっていただけるかどうかはわからないんですが・・ま、こんな内容のお話です。
では、簡単に感想を。
苦しい時の神頼み。
神様、仏様、キリスト様を同時に唱える私としては、ここに登場する被害者と加害者の宗教心というものは理解に苦しむところなのですが。
自分が信じているものを失うということ。
信じているものを疑わなければいけない事実を突きつけられること。
それは信じる気持ちが強いほど辛いことで、耐え難いことなのだろうと。
自分の生活に精一杯で世界の飢餓をほかの人の困窮を思う気持ちが薄いわが身では
ありますが、この本を読みながら、
神に祈ることも心の安寧としては必要かもしれないけれど、
祈ってもパンも水も届かないのだろう。
パンと水を必要としているひとに届けたいのであれば
やはりわが身の無駄をひとつでも削り、分けることも必要なのだろう。
そんな気持ちになったのでした。
本当はね。
もっと高尚な内容でもっと深いことが奥に潜んでいるような気がするんだけど・・・突き詰めていくと矛盾や疑問もいっぱいある・・・。
だから未だに宗教は研究され、哲学は学ばれるのだと思うのです。
こういう話は古くなると言うことはなく、さらに深遠に深められていくものなんだろうな・・・。
表現的にはアハシュ・フェルツの驚愕の冒険談はそれなりに面白く。
最後の最後、若者が捜査官に動機を語るシーンは胸に迫るものあり。
面白かったといえば面白かったような。(笑)
全文読むのは・・・という方はあとがきだけ読んでもだいたいの筋はわかるかと思います。
ただ、筋だけではない「情」みたいな部分はやっぱり本文読まないとわかりにくいでしょうか。
大学一年生の時この話を読んで感銘を受けた彼。
その当時のかの国の政治的背景なども絡んでいるのでしょうか・・。
さて。このお話。
いったいどうス・ドンポ親分と結びつくのか・・・
私にはまったくわかりませんからっ!
あの予告映像とこの話が結びつくとすれば・・・宗教とか哲学とかその辺かなぁ~。
ちなみに「ひとの子」というのはヤハウェの息子である「イエス・キリスト」を表した言葉で、この話の主人公たちの思想の中ではイエスは偽「ひとの子」アハシュフェルツが「ひとの子」だと表現されています。
こんな文章ですが・・・一応努力して何日もかけて書いてみました。
わかりにくいけどご勘弁を。
この苦労が報われる日は果たして来るのだろうか・・・。
「I come ・・」の公開が楽しみです。

早く書かないと忘れてしまうので。
みんなすっかりチャンイに夢中でドンポ親分のこと・・・忘れてない?

かねてから読んでいた「ひとの子」
以前、リンクしていただいてる恭子さんのお宅でご紹介してくださいました。

いつもありがとうです~。

コチラCINE21 インタビュー
そうなんです。
トラン・アン・ユン監督がこの小説をモチーフにして「I come・・」を作るから出てくれないか?とのオファーがあった・・と彼がインタビューで答えています。
だのに珍しく読もうと思っていなかった私。
たぶん「冗談」に疲れ果てていたんだと思います。(笑)
お友達が「あれ?haruさんなら読んでると思った」とおっしゃるので。
挑戦しておりました~~。
まさしく「挑戦」(笑)
ひと月近くかかってやっと読み終わりました。

通勤電車の中でとっとと終わるかと思いきや、

パソ時間の激減を携帯で補ったので、

結局重い本を毎日持って歩きながら


一度も読まないなんてことを繰り返しておりました。

まあ、スラスラ読めてしまう代物ならまだしも、
これが「冗談」に続く冗談のような上段下段本。(爆)

しかも宗教。


しかもキリスト教。(カタカナに弱いの。)



がストーリーに組み込まれてます。

何だか読みこなせたのか不安なのですが。。。

なかなかこの本のレビューはないので、頑張ってご紹介することにします。
この本、殺人事件を軸にしたミステリーと
その被害者の殺される原因ともなった彼の思想に関わる宗教的哲学的な部分の二つの話が折り重なって出来ております。
ミステリーの部分はとても読みやすい。
推理小説を読み進めるようにぐんぐん読み進むのですが、
その事件の捜査官が捜査の足がかりとして被害者が書いたノートを読むという設定で語られる被害者、そして加害者の宗教観を投影した物語の部分が実に…読みにくい。
私は宗教とんと弱く。
常識以下のレベルだと思います。

ヤハウェって誰だっけ?
ユダ…聞いたことあるな。
丘?どこの丘だよ。
最後の晩餐?

なんだっけ…なんだっけ…

ずっとそんな調子。

あとがきからあらすじをざっと抜粋しますとですね・・。
ネタバレありなのでこれから読もうと思っている人は読まないほうが・・。

物語はテグ市で起きた殺人事件に端を発する。
被害者はかつて神学大学に籍をおきながらも、次第にキリスト教に懐疑的になったことから、退学処分を受け、彷徨を重ねていたと思われる男。
捜査本部が常識的な怨恨関係による犯行を疑い捜査を進める中、
担当捜査官 南警査は被害者の物の考え方や行動様式を理解することで犯人像を描き出そうと遺留品であった原稿などを見つけ出して読んでいく。
と同時に被害者の転居先を追跡し、被害者に師事していつも行動を共にしていた青年にたどり着く。
この青年を犯人と断定して追い詰めるまでのプロセスと殺害した動機を突き止める・・これが表向きのこの物語のあらすじ。
これは私が最初に言った「読みやすい部分」
そして私が「読みにくい」と表現した
被害者の信仰心の変化が殺人事件に発展した動機であったことを示すもうひとつの物語が仕込まれているわけです。
あとがきによればその物語とは
「旧約と新約の『聖書』の世界を舞台として被害者の信仰上の苦悩が産み落とした物語」と表現されております。
う~~ん。わかりにくいね。
では、被害者と加害者が求めていた真の「神」とはどんなものか。
彼らの思想についてすこし書いてみましょう。
被害者の遺留品の中から見つかった原稿にはアハシュ・フェルツという若者がキリストの父であるユダヤの神ヤハウェが現実の世界では無力であることに懐疑の念を抱き、真の神を求めて旅に出て紆余曲折の末、最終的に真の神に出会う話が書かれています。
アハシュフェルツは物語の主人公でありながら被害者が自己を投影している部分もあるように思います。
アハシュフェルツは旅先でイエスキリストに7度も対面し、議論を繰り返します。
キリストの教えを不審に思う理由を語り、キリストに説明を求めるも、サタン呼ばわりされ、相手にされない・・・・。
そんな中「真の神」に出会うわけです。
この真の神についてどう説明したらわかりやすいんだろうといろいろ考えたのですが・・この小説に書かれていることをすべて書くと複雑すぎてわかりにくい。
あえて書くとすればそれは限りなく社会主義に近い考え方といえると思います。
「この神は敬われて信仰の対象となることを拒否する。この神は人間はもはや神を求めるべきではなく、自らの力と自由な意志でもって地上の楽園の実現に全力をなげうつべきだと教えている。その際の人間の行為の基準が神の教えにではなく、人間の正義にあることはいうまでもない。」
現実社会の困窮と疲弊を日々目の当たりにして、既存のキリスト教的教義に不信感を募らせた被害者は放浪の旅を続けながらこのような神を理想として描くようになります。
そしてのちに加害者となる若者に出会う。
若者は被害者の信念に感銘を受け彼に心酔し、彼の教えをより明確に具現化しようとする。
それは富が集中している金持ちから富を奪い、貧しい人たちに分け与えるという行為だった。
その行いが自分の目指した神の教えに副ったものなのか・・・日ごと自信が持てなくなっていく被害者。
わが行いを正当化し、確信を手にするために犯罪を繰り返す若者。
二人の思いは食い違い・・・若者は自分が師と仰ぐ人物を手にかけることとなる。
こんなお話。
何回もおんなじこと書いている気がするな・・・。

これでわかっていただけるかどうかはわからないんですが・・ま、こんな内容のお話です。
では、簡単に感想を。
苦しい時の神頼み。
神様、仏様、キリスト様を同時に唱える私としては、ここに登場する被害者と加害者の宗教心というものは理解に苦しむところなのですが。
自分が信じているものを失うということ。
信じているものを疑わなければいけない事実を突きつけられること。
それは信じる気持ちが強いほど辛いことで、耐え難いことなのだろうと。
自分の生活に精一杯で世界の飢餓をほかの人の困窮を思う気持ちが薄いわが身では
ありますが、この本を読みながら、
神に祈ることも心の安寧としては必要かもしれないけれど、
祈ってもパンも水も届かないのだろう。
パンと水を必要としているひとに届けたいのであれば
やはりわが身の無駄をひとつでも削り、分けることも必要なのだろう。
そんな気持ちになったのでした。
本当はね。
もっと高尚な内容でもっと深いことが奥に潜んでいるような気がするんだけど・・・突き詰めていくと矛盾や疑問もいっぱいある・・・。
だから未だに宗教は研究され、哲学は学ばれるのだと思うのです。
こういう話は古くなると言うことはなく、さらに深遠に深められていくものなんだろうな・・・。
表現的にはアハシュ・フェルツの驚愕の冒険談はそれなりに面白く。
最後の最後、若者が捜査官に動機を語るシーンは胸に迫るものあり。
面白かったといえば面白かったような。(笑)
全文読むのは・・・という方はあとがきだけ読んでもだいたいの筋はわかるかと思います。
ただ、筋だけではない「情」みたいな部分はやっぱり本文読まないとわかりにくいでしょうか。

大学一年生の時この話を読んで感銘を受けた彼。
その当時のかの国の政治的背景なども絡んでいるのでしょうか・・。
さて。このお話。
いったいどうス・ドンポ親分と結びつくのか・・・

私にはまったくわかりませんからっ!

あの予告映像とこの話が結びつくとすれば・・・宗教とか哲学とかその辺かなぁ~。
ちなみに「ひとの子」というのはヤハウェの息子である「イエス・キリスト」を表した言葉で、この話の主人公たちの思想の中ではイエスは偽「ひとの子」アハシュフェルツが「ひとの子」だと表現されています。
こんな文章ですが・・・一応努力して何日もかけて書いてみました。

わかりにくいけどご勘弁を。

この苦労が報われる日は果たして来るのだろうか・・・。
「I come ・・」の公開が楽しみです。



















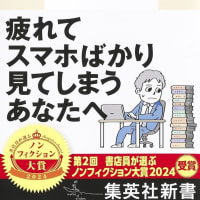






この間は、メールありがとうございます。
私がメールに気がついたのは、チャグチャグ馬コの馬を見ているときでした。とっても、遅くなってごめんなさいね。こちらには、その前に、メールしていたのでした。
ところで、私は、こういう本が好きなのだけれど、きっと、読まないでしょう。(笑い)
宗教はむずかしいですね。その人、その人の考え方があると思うからです。それで、何を信じればいいのか。これも、とても、むずかしいですね。信じているものが同じでも、感じ方が違えば、まるで方向が違うからです。
ダビィンチ・コード?の映画を見たときも(本は読んでいません。)同じようなことが起こりました。戦争の始まりは、きっと、宗教で、戦争の終わりも、きっと、宗教なのだと思います。
はっきり言えることは、いかに自分を信じるか。だと思います。ほかの人は、参考にしても、直接の原因ではなく、自分の心の揺れだと思うからです。自分を信じきることは、とても難しくて、やめたくなりますが、それでも、自分の信念を信じていく。これが、私の考え方です。
自分を信じきれず、相手も信じ切れないところに、悲劇は起きるのだと思います。自分を信じるように、相手を信じていれば、道は開かれていくと思います。
純粋できれいな心は、世の中をきれいにしていくと思います。
流石haruしゃん!
着々と宿題を片付ける秀才さんだわ。
私、彼とこの本の繋がりも良くわかんないまま・・・購入するのは至難の業と某所でちら見して、何気なくいつもの市立図書館で検索かけたら普通に書架に有り!(だぁれも借りてやしない)
で、予約入れました。取りに行かなきゃ!
難しそうだね
取り敢えず手にして、頬ずりして
読書に関しては凄い現役だから・・・
良かったよとか言ってくれたら母は嬉しい
毎日テレビからのたくさんの情報を目にし、被災された皆さんの姿を眺めて茫然とするばかり。
こういうときにこの本は生きるのか。
そんなことを考えたりもします。
1日も早い復興とまだ救助されていない方が早く見つかるよう祈っております。kazukoさんも、余震気をつけて。
さて。
コメありがとうです。
ダヴィンチコード…そうそう似たような感覚かもしれません。
私の中に宗教に関する思い入れがないので、正直なところカラダの中に話が入ってこない。
親近感が湧かないと言おうか…。
感情移入出来ないというのは、感情移入しながら本を楽しむタイプの私としてはなかなか話に乗れないわけで。
でも読みながら思ったんですけど、神様は自分の中にいて、外にいる偶像を崇めるものじゃないんじゃないかな…。
人にはそれぞれの神様がいて、その神様は当然みんな違う。同じ神様は2つといなくてもいいような気がする。
それはkazukoさんが言ってる自分を信じるという感覚に近い気がするんだけど…どうでしょう。
自分を信じなければ自分が信じるものさえ疑わしく思える…というのは当然ですものね。
うん。
宗教は本当に難しいです。
お付き合いありがとう。
何だか意味不明のレスでごめんなさい。(^_^;)
これ、絶版なの?
買えないという噂私も聞きました。
3000円近い値段にもびっくり(笑)
何の気なしに頼んだ図書館は無風でした。(冗談は借りてる人いた・笑)
実は読み切れなくて無断延滞してたんですけど、呼び出しされず。(^_^;)
ウリ地方では不人気らしいです。
物語の構成はとても変わっていて面白いと思いました。
発表された当時の社会情勢もあってか、ベストセラーだったらしい。
かの国の熱い国民性から想像するにウケるかも…と思いました。
今、小林多喜二の「蟹工船」
若者の間で流行ってるらしいですね。
ちょっと違うけど、歪んだ社会を考えるきっかけになりそうという点では同じ匂いがしなくもない。是非若者の意見を聞いてみたい~。
うちの宇宙人は日本語読めないんです~(号泣)
「ひとの子」難しいお話しですね(^_^;)
「I come・・・」の予告編を見た時、
ただの娯楽映画ではないな~と思っていたんです。
奇妙な映像がたくさんあって「?」が頭の中に渦巻いていました。
私も宗教関係は全くダメなので本は読めない気がします(+_+)
ですので、頑張ってご紹介いただいてとても嬉しかったです!
ありがとうございました(^0^)/
トランアンユン監督の映画3作見ましたが、どれも芸術作品の色彩が強く、娯楽作品とはちょっと違う気がします。
奇妙な映像も多いですよね。
I come・・は今までのどの作品ともちょっと違う気がしますが、怪しいには変わりなく。
それはそれで楽しみです。
ベネチアに出品するんでしたっけ?
彼は行かないんでしょうかね・・・。
これは日本公開間違いないので楽しみに待ちましょう。
つたない感想にお付き合いありがとうです~。
おぉ、『ひとの子』読み終わられたんですね!すご~い
なんだか難しそうなお話
映画とはどうつながるんでしょうね~。っていうより、トラン・アン・ユン監督は、どういうインスピレーション
また読んでみます
ところで、haruさん、ツアー行くんですよね~いいな~羨ましいわ
最近思うんですが、ビョンビョン、長期休暇に入ると、交際の話が出るじゃない?(出典:イ・ビョンホンの秘密)だから・・・もしかすると、今回が独身最後の生ビョンかもよ~!
彼が『IRIS』の後の長期休暇から、(独身で)生還しますように
では~!
勝手にお名前をお借りして申し訳ありませんでした。
ご挨拶に・・・と思っている間に書き込みそびれました。
何卒お許しを。
さて。
そうなんです。読み終わりました~。
恭子さんちでご紹介していただいた時から気になりながら、ハードル高そうだったので
自然と体がしらばっくれてた・・
のかもしれません。
ひょんなきっかけで読むことになり。
読んだら読んだでそれなりに面白かったです。
一言で言うと「斬新」な切り口でしょうか・・・。
私も宗教ものも外国ものも苦手。
宗教ものは価値観とか世界観とかを理解するのが
大変で正直恭子さんと同じように「そうなんだ・・」
って感じです。
お付き合いありがとうございました。
そして。
そうなんですよ。
ひょんなことからこれまた行くことになりまして。
これはやっぱりタイミングと勢いでしょうか・・。
で・・まだ決めてらっしゃらないのですか?
関西方面はチケット余ってると伺ってます。
よくよく考えて・・・ね。
あら、そうでしたっけ?
(秘密を知らない女です。
そっかぁ~。いよいよ年貢納めますかね・・・。
私は結婚奨励組なので心の準備は万全ですが。
どんな女の子を選ぶのかなぁ~。
エイミーちゃんなの?
そこは興味津々です。