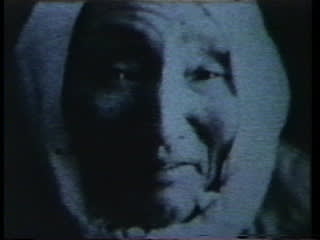詩というものを解説しようとすると、まるで健康食品の効能を説いているかのような気になってくる。理路整然とは対極にあるシロモノなのかもしれない。
ところで石井秀人の『小さな舟』は、もっぱら老人と老婆の顔を正面からとらえた写真を、さらに8ミリカメラで撮ることで成り立っている。
ぼおーっとこの作品を見ていた私は、ある瞬間、「おおっっ!!」と目が覚めるような思いをした。添付画像のような長めのショットで、ふいに画面の老人がウインクをしたように見えたからだ。
写真だから動くはずがない。なのにそこに表情が生まれた。表情が生まれたように錯覚した。
おお、これは魔術のひとつだな。しかし、その仕組みはわかるような気がする。
つまりこういうことなのだろう。
ざっくり言ってしまえば、いろんな揺れやボケが複合してこれを生み出しているのだ。
まず、カメラを手持ちしているから、手や身体の揺れがそのままある。
次に、あまり気づかないことだけれど、8ミリフィルムの映像は、けっこう縦揺れを起こしている。フィルムの横の穴にかぎ爪を引っ掛けて、物理的にフィルムを間欠的に動かしているため、つねに微細な縦揺れが起きている。それは物理的にもっとも小さい8ミリフィルムで、最も大きくなる。
さらに、石井秀人はきわめてゆっくりとピントが合った状態から、ピントがはずれた状態にピントリングを動かしている。
もひとつ言うと、石井秀人はわざと感度の高いフィルムを使用して、粒子の荒さによる、画面内の粒子の動きを見せている。
ね。これだけだとしても、種類のちがう4つの「揺れ」があるわけだ。
しかし、人間の視覚には「生体手ぶれ補正機能」があるので、そもそも「これは写真である」と認識されている映像を見ていると、そこから積極的に「揺れ」を排除して認識しようとする。なのに揺れやボケが何重にも重なってくるから、ふとその写真の顔に表情を感知してしまうのだろう。
ところで石井秀人の『小さな舟』は、もっぱら老人と老婆の顔を正面からとらえた写真を、さらに8ミリカメラで撮ることで成り立っている。
ぼおーっとこの作品を見ていた私は、ある瞬間、「おおっっ!!」と目が覚めるような思いをした。添付画像のような長めのショットで、ふいに画面の老人がウインクをしたように見えたからだ。
写真だから動くはずがない。なのにそこに表情が生まれた。表情が生まれたように錯覚した。
おお、これは魔術のひとつだな。しかし、その仕組みはわかるような気がする。
つまりこういうことなのだろう。
ざっくり言ってしまえば、いろんな揺れやボケが複合してこれを生み出しているのだ。
まず、カメラを手持ちしているから、手や身体の揺れがそのままある。
次に、あまり気づかないことだけれど、8ミリフィルムの映像は、けっこう縦揺れを起こしている。フィルムの横の穴にかぎ爪を引っ掛けて、物理的にフィルムを間欠的に動かしているため、つねに微細な縦揺れが起きている。それは物理的にもっとも小さい8ミリフィルムで、最も大きくなる。
さらに、石井秀人はきわめてゆっくりとピントが合った状態から、ピントがはずれた状態にピントリングを動かしている。
もひとつ言うと、石井秀人はわざと感度の高いフィルムを使用して、粒子の荒さによる、画面内の粒子の動きを見せている。
ね。これだけだとしても、種類のちがう4つの「揺れ」があるわけだ。
しかし、人間の視覚には「生体手ぶれ補正機能」があるので、そもそも「これは写真である」と認識されている映像を見ていると、そこから積極的に「揺れ」を排除して認識しようとする。なのに揺れやボケが何重にも重なってくるから、ふとその写真の顔に表情を感知してしまうのだろう。