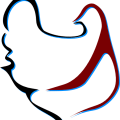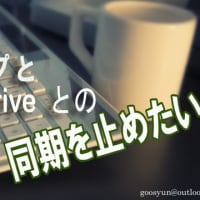それは、ある記事を書こうとしているのですが、何をどのように書けばよいのか、記事に盛り込むべき内容はどうするか、あれこれと苦悩しているからです。
書こうとしている、その「ある記事」とは、「高水準言語」に関する記事です。
高水準言語とは、コンピューターに対する計算処理の指示を、人間でも理解できる表現で書き表せるようにしたコンピューター言語(プログラミング言語)のことです。機械語に近い低水準言語に対する言葉です。
Amazonで購入した
ブライアン・カーニハン著
「教養としてのコンピューターサイエンス講義」
を読んで、その中の一つ「高水準言語」の解説が非常に分かりやすくて、感動したことは、前に書いたとおりです。
「高水準言語」の解説で感動したことは、
⇒ こちらの記事をご覧ください。
高水準言語の解説の中の、どのような説明に納得ができて、そしてどうして感動したのか、その辺のことを記事にまとめたい、と思っています。この私の感動を、他の人にも共感してもらいたいというのが、その記事の趣旨です。私が個人的に勝手に心が震えただけなので、「共感」といったって、それには限界があるかもしれません。
けれども、カーニハンの解説は、本当に分かりやすくて、「なるほどそういうことか。」と、大いに納得できるものでした。だから、自己満足でもいいので、記事にまとめたいという思いはあります。

ただし、ただしですよ・・・、
コンピューターサイエンス(コンピューター科学)のズブの素人が、高水準言語に関する記事を書くのは、やはりむつかしいものがあります。下手をすると、素人の誤解に基づく間違った記事を書いてしまう危険もあります。そういうわけで、どのように書くのがよいのか、どのようなことを記事の内容に取り込むのがよいか、と苦慮します。ブログに書く以上は、やはり、ウソや間違ったことは書きたくないですし。
このままでは、ずっと記事を書けないまま、時間だけが過ぎていきそうです。
それを避けるため、とりあえず、記事を書くとっかかりを作り、何らかの「着手」をする必要があります。そこで、書こうとしている記事のことであれこれ思いをめぐらせていることを、ただそれだけですが、こうして書いておくことにしました。
それでは、また次の記事で
■■■■ goosyun ■■■■