午前中は昨日の続きで総合通信の勉強を進めていこうと思っています
メインに進めている電気通信主任技術者試験の過去問と重複する分野もあるので、
近道せずそれぞれの参考書を読んで理解深めたいです
追記:午後一はお昼食べた後しばらくやる気が出なかったので、残りの問題の復習は夕方までかかってしまいました…
問5(1) p286~288 呼損率の定義→加わった呼に対して損失呼となる割合を示す(即時交換方式)
問5(2) p288 公衆電話交換網における 総合呼損率の定義→1-(1-B1)(1-B2)…(1-Bn)
問5(3) p289 出線能率を求める計算問題 求める公式の定義がサイトによって異なる?計算式を丸暗記した方がよいという意見もあり
問5(4) 参考ページなし?電気通信主任技術者 の令和3年2回目 問6(4)に類題が出ている
キューイングの種類について
IPパケットの転送遅延の原因は「距離による物理的な伝送遅延」または「ルータにおけるキューイングによる遅延」であるとの事
問5(5) p204(総合通信) L3スイッチの説明も含む、L3スイッチはVLANとして独立したネットワークをつなげる事ができる
p247~248 L2スイッチの説明のみ、L2スイッチのフレーム転送方式は現在 ストアアンドフォワード形式がメイン
参考:ストアアンドフォワード:フレーム全体をいったん受信し、メモリに蓄積してエラーチェックを行ってから転送する(転送速度は遅くなるが信頼性が高い)
問6(1) p299
システム領域型感染型ウィルスとは
.com、.exeなどの拡張しをつけたものから感染するのはファイル型
p300 ヒューリスティックスキャン方式に関する説明あり
問6(2)総合通信、主任技術者に参考ページなし?
EAPとは:PPPの認証機能を拡張した利用者認証プロトコルである
問6(3) p301の補足にプロービングの説明あり、スマーフ攻撃とブルートフォース攻撃は一覧表を参照
・リバースエンジニアリングとは何か
・グリッチとバグの違い
問6(4) p313(総合通信)
p343(主任技術者) の解説 暗号化によってパケットの秘匿や改ざん検知を実現するプロトコル
2つの参考書で解説に大きな違いはなし、AHプロトコルは暗号化でなく認証ヘッダにより認証と改ざん防止を行う
暗号化の役目をするのは暗号ペーロード(ESP)の方となる
問6(5) 参考ページなし?
・アンチパスバックに関しての解説
・ゾーニングに関する解説
問7(1) p322 強風によるダンシング対策として捻回を10mに1回程度の間隔で入れる
問7(2) テスター測定値の簡単な計算問題
問7(3) p329 セルラダクト配線方式、波型デッキプレートが出てきた場合の施工方法
問7(4) p336 デジタル式PBXの機能確認試験の一覧、内線キャンプオンの話
問7(5) p158 デジタル式PBXの解説、概略図を見ても問題の回答はわかりづらい
問8(1) p171 DSUの給電電圧について、TEに信号伝送する2線の電圧は34~42Vの範囲にある
問8(2) 選択Aについての解説は見つからず
p171 DSUのファントムモードはTR線を用いて行われる
問8(3) p338~339 ISDN短距離受動バス配線工事の制限について、DSUからTRまでは200m以内、接続コードは10m以下とする
問8(4) p359 光ファイバの接続方法毎の測定方法の一覧、プラグタイプラグ(光バッチコード)の場合、挿入法Bが正解だが選択しにないので挿入法Cを選ぶ事になる?
問8(5) p353 JISX5150の規格によるLAN配線のルール、固定水平ケーブルの物理長は90m以下とする、
分岐点はフロア配線版から少なくとも15m離れた位置にしなければいけない(参考書には記載なし?)
問9(1) p365~366 OTDR法に関する詳しい説明あり
問9(2) p361に解説あり、ただし抜粋
問9(3) p372 水平チャンネル長公式を求める、必ず1問は出る
問9(4) p205 問題文はオートネゴシエーション機能の説明、FLP信号でイーサネットに関する情報を送信する
問9(5) 参考ページなし?
挿入損失が3dbを超えた場合の考えはネット上でもすぐに見つけられず
問10(1) 参考ページなし?
切断配線クリートについて(実際に売られている製品)
問10(2) 問8(4)の類題、OTDR法について確認しておく事
問10(3) 参考ページなし?WBGTに関する設問が出た事がない
問10(4) p385~386 施工出来高に関する説明
問10(5) p390~392 アローダイアグラムに関する説明、クリティカルパスとは最長経路を示す
メインに進めている電気通信主任技術者試験の過去問と重複する分野もあるので、
近道せずそれぞれの参考書を読んで理解深めたいです
追記:午後一はお昼食べた後しばらくやる気が出なかったので、残りの問題の復習は夕方までかかってしまいました…
問5(1) p286~288 呼損率の定義→加わった呼に対して損失呼となる割合を示す(即時交換方式)
問5(2) p288 公衆電話交換網における 総合呼損率の定義→1-(1-B1)(1-B2)…(1-Bn)
問5(3) p289 出線能率を求める計算問題 求める公式の定義がサイトによって異なる?計算式を丸暗記した方がよいという意見もあり
問5(4) 参考ページなし?電気通信主任技術者 の令和3年2回目 問6(4)に類題が出ている
キューイングの種類について
IPパケットの転送遅延の原因は「距離による物理的な伝送遅延」または「ルータにおけるキューイングによる遅延」であるとの事
問5(5) p204(総合通信) L3スイッチの説明も含む、L3スイッチはVLANとして独立したネットワークをつなげる事ができる
p247~248 L2スイッチの説明のみ、L2スイッチのフレーム転送方式は現在 ストアアンドフォワード形式がメイン
参考:ストアアンドフォワード:フレーム全体をいったん受信し、メモリに蓄積してエラーチェックを行ってから転送する(転送速度は遅くなるが信頼性が高い)
問6(1) p299
システム領域型感染型ウィルスとは
.com、.exeなどの拡張しをつけたものから感染するのはファイル型
p300 ヒューリスティックスキャン方式に関する説明あり
問6(2)総合通信、主任技術者に参考ページなし?
EAPとは:PPPの認証機能を拡張した利用者認証プロトコルである
問6(3) p301の補足にプロービングの説明あり、スマーフ攻撃とブルートフォース攻撃は一覧表を参照
・リバースエンジニアリングとは何か
・グリッチとバグの違い
問6(4) p313(総合通信)
p343(主任技術者) の解説 暗号化によってパケットの秘匿や改ざん検知を実現するプロトコル
2つの参考書で解説に大きな違いはなし、AHプロトコルは暗号化でなく認証ヘッダにより認証と改ざん防止を行う
暗号化の役目をするのは暗号ペーロード(ESP)の方となる
問6(5) 参考ページなし?
・アンチパスバックに関しての解説
・ゾーニングに関する解説
問7(1) p322 強風によるダンシング対策として捻回を10mに1回程度の間隔で入れる
問7(2) テスター測定値の簡単な計算問題
問7(3) p329 セルラダクト配線方式、波型デッキプレートが出てきた場合の施工方法
問7(4) p336 デジタル式PBXの機能確認試験の一覧、内線キャンプオンの話
問7(5) p158 デジタル式PBXの解説、概略図を見ても問題の回答はわかりづらい
問8(1) p171 DSUの給電電圧について、TEに信号伝送する2線の電圧は34~42Vの範囲にある
問8(2) 選択Aについての解説は見つからず
p171 DSUのファントムモードはTR線を用いて行われる
問8(3) p338~339 ISDN短距離受動バス配線工事の制限について、DSUからTRまでは200m以内、接続コードは10m以下とする
問8(4) p359 光ファイバの接続方法毎の測定方法の一覧、プラグタイプラグ(光バッチコード)の場合、挿入法Bが正解だが選択しにないので挿入法Cを選ぶ事になる?
問8(5) p353 JISX5150の規格によるLAN配線のルール、固定水平ケーブルの物理長は90m以下とする、
分岐点はフロア配線版から少なくとも15m離れた位置にしなければいけない(参考書には記載なし?)
問9(1) p365~366 OTDR法に関する詳しい説明あり
問9(2) p361に解説あり、ただし抜粋
問9(3) p372 水平チャンネル長公式を求める、必ず1問は出る
問9(4) p205 問題文はオートネゴシエーション機能の説明、FLP信号でイーサネットに関する情報を送信する
問9(5) 参考ページなし?
挿入損失が3dbを超えた場合の考えはネット上でもすぐに見つけられず
問10(1) 参考ページなし?
切断配線クリートについて(実際に売られている製品)
問10(2) 問8(4)の類題、OTDR法について確認しておく事
問10(3) 参考ページなし?WBGTに関する設問が出た事がない
問10(4) p385~386 施工出来高に関する説明
問10(5) p390~392 アローダイアグラムに関する説明、クリティカルパスとは最長経路を示す

















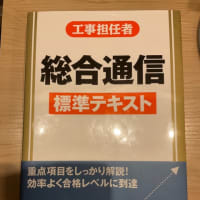


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます