私はパネットーネ(Panettone)よりパンドーロ(Pandoro)派です!!
「いきなりなに?」「クリスマス終わったのにまでクリスマスの話?」と思われてしまうかと思いますが、ちょっと気になったし、さすがに来年まで覚えていることは出来なそうなので、今日のネタにすることにしました。
パネットーネもパンドーロもイタリアのクリスマスの伝統的なお菓子です。
最近日本でも見かける機会が増えました。
昨日コストコに言ったら、定番の1キロサイズ(正確には1キロないんですけど)が1000円切る値段で売られていたし、珈琲ショップのKALDIや成城石井なんかでも売られていました。
イタリアでは、工場製品は2€から10€くらいの価格で売られているので、まぁそれほど高いという感じはしないです。
何度かこの話はしたかと思いますが、私が人生で一番初めにイタリアに行った時、同じツアーに参加されていた方が、帰りこの大きなパネットーネを手にしていたのが最初のパネットーネとの出会いでした。あの時は衝撃的でしたねぇ…
あれから20年、わざわざ買って帰らずとも日本で手に入るようになったんだから、すごいですよね。
ただ、イタリアでもパン屋やお菓子屋などで売られている手作りパネットーネ、パンドーロは結構なお値段なんです。
大体1キロいくらで表示してあるんですけど、パネットーネに関しては、見た目スーパーと同じ1キロくらいのサイズなのに中身によって結構重さが変わるので、値段を聞いてびっくり!なんて時も有るんです。
むかし、一度それをやってから、なかなか手作りパネットーネ、パンドーロに手が出なくなっていました。
ところが先日青葉台の方へ行った時、あるパン屋さんの窓越しに手作りのパネットーネを発見してしまいました。
この半身で850円。いいお値段です。だって、1キロサイズの半身ではないんですよ…
でもクリスマスだしどうしても食べたくて…
結果から申し上げますと、これは美味しかったです。個人的にはもう少し甘さ控えめでもいいかなとは思いますが。
で、この一緒に頂いた説明書きを見ていたんです。
普通の日本人にはこの説明書きとても役立つし、いいなと。
しかし、ふと気になることが…
あれ?パネットーネって「ミラノ銘菓」だったけ?
あそっか、そっか、パンドーロがヴェローナ(Verona)だったね。
確か昔パンドーロの事は調べた気がするのですが、ちょっとパネットーネのことも確認してみました。
パネットーネの誕生に関しては2つのいわれが有ります。
(他にも諸説有るみたいですが、この2つが一番信憑性があるようです。)
1つは
ミラノのGrazie地区に住んでいた鷹匠でもあったウリーボ・デッリ・アテラーニ(Ulivo degli Atellani)氏はアルジザ(Algisa)という美しいパン屋の娘に恋をしていました。ウリーボは彼女の父に見習いとして雇ってもらうために、お店の売り上げが伸びるような新しいお菓子を作ろうと努力しました。そのお菓子は風車で挽いた最上の小麦粉に卵とバター、はちみつとスルタン種(種なしぶどうの一品種)の干しぶどうを練り合わせて焼いたものでした。これが大当たり!!たくさんの人がこの新しい”パン”を食べたいとお店に押しかけ店は大繁盛。そしてその後若い恋人たちは結婚し幸せに暮らしました。
そしてもう1つは
ルドヴィーコ・マリーア・スフォルツァ、通称イル・モーロ(Ludovico il Moro)のコックは周辺地域の貴族が大勢招待される贅沢なクリスマスのお昼の準備を仰せつかりました。しかし、お菓子をオーブンに入れたことを忘れてしまい、真っ黒こげになってしまいました。コックの落胆や如何に…
すると小さな下働きのトーニ(Toni)は打開策を提案します。
「食器棚に僕が今朝、ちょっとの小麦粉、バター、卵、小さなシトロンの皮、いくつかの干しぶどうで作ったこのお菓子が残っています。もし他にお菓子が何もないのであれば、これをテーブルにお出ししたらいかがでしょうか」
コックは同意してテーブルにお菓子を出したあと、震えながらカーテンの後ろに隠れてお客たちの反応を伺っていました。
すると全員がこのお菓子に夢中になりました。
イル・モーロ侯爵はこの大変美味しいお菓子の名前が知りたいとコックを呼びました。
コックは事情を白状して「このお菓子は”トーニのパン(pan del Toni)です」と答えました。
こうして「トニのパン(パーネ・ディ・トーニ:pane di Toni)がパネット―二(panettone)となったわけです。
どちらの話もイタリアらしいなぁ、とちょっとほっこりする良いお話です。
500年以上の歴史を持つパネットーネですが、今のように全国的に食べられるようになったのは1900年代に入ってから。
ミラノの菓子職人、アンジェロ・モッタ(Angelo Motta)がパネットーネの工場生産に乗り出したから。
伝説には出てこなかったけど、パネットーネで一番重要なのは「酵母」。
黄金色の焼けた表面からは想像できないくらい中はふわっふわ。
このふわっふわは天然酵母を使い2,3日かけて何回も発酵させているかた出来る技で、発酵に適した温度、湿度を長時間管理するのは一般家庭では難しく、故にお店や工場で作るのに向いたお菓子というわけです。
Mottaのパネットーネは今でも大人気!スーパーでも安売りされていることが多いので私もよく食べていました。
あれ?今1つ気がついたけど、2大と言ってもいいパネットーネメーカーのBauliもMottaグループの傘下に入ってるじゃん。
知らなかった…
私が今回購入したパン屋さんでは、「ルヴァン種」という酵母を使っているようですが、「なんじゃこれ?」と思って調べたらなんとパネットーネ種という酵母が有るではないですか⁉
パネットーネ種とは
「生後すぐ初乳を飲んだ後の子牛の腸内から採集した物質と小麦粉を混合した発酵種」(Wikipediaより)とのことです。
正確にはこのパネットーネ酵母を使っていないものはパネットーネとは呼べないようですよ。
クリスマスの前後一ヵ月、大量消費されるパネットーネは大体夏の暑さが落ち着いたころから製造がはじまります。
昔から「なんでこんなに賞味期限が長いんだ?化学的なものいっぱい入ってるのか?」と思っていましたが、その辺りも解決!
実はこのパネットーネ種という酵母を長時間熟成発酵させることで、微生物が活動しにくい水分含有量が少なく、酸性度の高い生地が出来上がります。また熟成発酵の過程で、多くの「糖分」が変化し日持ちを助ける「糖アルコール」が増加するそうです。だからカビなどの微生物が育ちにくい状態になり、保存料を入れなくても長期保存が可能になるそうです。
更に焼成後も口どけが良く、長期間風味を保つ事もできるそうです。
いひひ、これで安心して食べられます。
ただし、パネットーネもパンドーロもカロリーが高いので気を付けましょう…ね。

ちなみにルヴァン種はフランスの酵母、とのこと。
料理に関しては門外漢なので、この辺で止めておきますが、何だか奥深くてはまりそうな予感です。














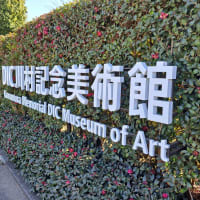





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます