三井記念美術館で開催中の
「日本の素朴絵」展を見に行く前に、ちょっとお勉強しようと思ってこちらの本を読んだ。
なかなか分かりやすくて面白い。
最終章に、ゆるカワではないことで横山大観にけなされた絵の話が出ていた。
そしてその作品、丁度最近横浜美術館で開催中の「原三渓」展で見たばかりだった。(現在は展示されていない)
大正9年院展に出展されたこの作品を見て横山大観は「悪写実」とこき下ろした。
この作品、畳の目まで細かく描写されている。
超リアリズムはこの時代受け入れられなかった、その対極に有るのが日本古来から脈々と続いてきた所謂「ゆるく」「かわいい」日本独特の文化だった。
実物を見たけど、確かに細かいし、ちょっと怖い。まるで今にも動き出しそうな日本人形のような雰囲気。
6月だったかな?
この本を読んだ。
直木賞候補にも挙がっていたこの作品、現在上野で開催中の「松方コレクション展」にぶつけて来たなと、商業主義的な裏事情はさておき、原田マハらしい面白い話だった。
そして主人公の1人、「田代雄一」に実際のモデルがいることを知った。
矢代幸雄、彼はアメリカ人美術史家バーナード・ベレンソンに師事しフィレンツェに滞在していた。海外の研究者も認めたボッティチェリの研究者だったが、師の勧めもあり、日本や東洋の美術研究者となる。
ベレンソンが所有していた、フィレンツェ郊外のヴィラには興味があって、一度一般に開かれた講演会が有った時に訪れたことがある。(講演は英語だったため、よく分からなかったけど…)
まさか戦前ここで日本人がいたとは…当然イタリアではそんな話聞いたことがなかった。
この辺りのことを色々詳しく知りたくて、様々な本を読んでいるところ。
この矢代氏こそ、原三渓を取り巻く様々な芸術家たちのことを記していた。
原三渓は、過去の傑作を収集するだけでなく、同時代の、新しい美術の振興にも助力した。
御舟の作品を酷評した大観や下村観山とも親しく、もた彼等より若い世代にも強い期待を抱いていた。
そんな若手の中でも最大のホープが速水御舟だった。御舟は三渓の期待通りの素晴らしい作品を残し、将来を嘱望されていたが、あまりにも早くこの世を去ってしまった。
矢代は、「御舟値段が他との比較を破って飛び上がっていることも、彼がいかに惜しまれているかを示す1つの証拠である。」と言っている。
参考:藝術のパトロン、矢代幸雄、中公文庫
そんなこんなでこの夏は、どちらかというと日本の方に傾いている私。
そして本って本当に面白い。
1冊の本から色々な方向へ興味が広がって行く…とめどなく。














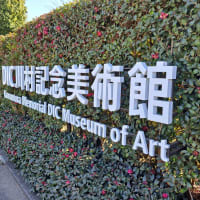





現在は、どうあつかわれているのか??ちょっと不安な感じもありますね。
コメント&いつも有益な情報をありがとうございます。
矢代氏に関する書籍で、I Tattiが優れた中国美術を所有していることを知りました。
私が訪れた時はそれらを確認することは出来ませんでしたが、ここ自体はハーバード大学の管理下に置かれ、今でも優れた研究機関で有ることは現地でも非常に有名でした。
先週、バーゼル美術館でボッティチェリ工房による作品を鑑賞する機会がありました。バーゼル訪問にあたって、以前読んだ『楽園のカンバス』を電子書籍で再読したところ、関連作品として矢代幸雄をモデルにした小説が紹介されており、興味を持って検索した際にまたお邪魔いたしました。
今年は記念年で、大和文華館でも企画展が開催されるのですね。
(学生時代、大和文華館から講師でいらした方が「矢代幸雄と話したことがある」とおっしゃっていたのを思い出しました。)
『イタリアの泉』さんのブログを通じてボッティチェリに興味を持ち、それがヴィラ・カジノ・アウローラを訪れるきっかけや、イタリアへ足を運ぶ原動力にもなりました。
gooブログが終了してしまうのはとても残念です。ブログはどこかに移行されるご予定でしょうか?
私事になりますが、ミュンヘン滞在も残りわずかとなりました。可能な限り、ボッティチェリの作品を追いかけ続けたいと思っています。
ご無沙汰しています。
バーゼルへは私も「楽園のカンバス」の影響で行きました。ボッティチェリ工房による作品を鑑賞という貴重な機会があったんですね。羨ましいです。検索かけたらMakiさんのインスタグラムと思われるページを見つけましたので、早速フォローさせていただきました。これからは私の方が楽しみに拝見させていただきます。是非、思い残すことなく見尽くしてください!!
先日テレビの番組で丸紅ギャラリーの「美しきシモネッタ」の特集を見て、また見に行こうかなぁ、と思っていたところでしたが、最近はすっかり西洋美術から離れてしまって、もっぱら日本美術ばかり追いかけています。
こちらのブログ、最近全然更新してないのですが、Hatenaブログの方へ現在移行中です。過去に書いたものは、私にとっても重要な記録なのでちゃんと残って欲しいと思っています。